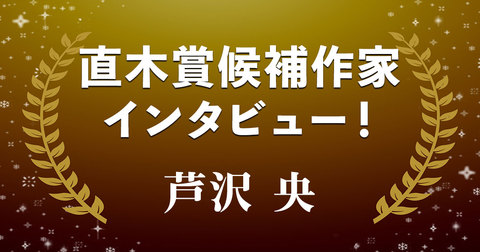覚めたくてもなかなか覚めることができない夢を渡り歩くような読み心地だった。一話、一話、嚙みつぶすたびにはっきりと、顔をしかめたくなるほど苦い。しかし咀嚼するにつれ、奇妙な甘さと後を引く香りが、苦みの奥から立ちのぼる。
『汚れた手をそこで拭かない』には五つの短編が収録されている。ジャンルとしてはミステリーに分類されるが、いわゆる密室トリックやアリバイトリックなど、派手な仕掛けとしての謎が出てくるわけではない。むしろこの本で描かれるのは日常で起こる小さな謎、その気になれば見ない振りだってできてしまう、調理中に指を刺す野菜の棘くらい些細な謎だ。
そんな些細な謎を巡る話が、幾重にも封鎖された密室や、逃げ道のない狡猾な殺人計画よりもよっぽど、怖い。追い詰められ、息苦しさに叫びたくなる。作中に監禁の描写は一度もないのに、視点人物とともに物語を追いながら、なんども「ここから出たい!」と強く思った。
第一話「ただ、運が悪かっただけ」では、ある夫婦が描かれる。妻は死に瀕しており、そんな自分の境遇を嘆いている。無口で人のいい夫は、過去の忌まわしい記憶に囚われている。妻は幼い頃からどんなものごとにも意味づけをしたくなる理屈っぽい性格で、五十代半ばで末期癌の診断を受けた自分の人生についても、こうすればよかったのだろうか、ああすればよかったのだろうかと思いを巡らせることをやめられない。そんな彼女が、残される夫にせめてできることはないかと持ちかけた提案により、夫の過去へと通じる扉が開く。
謎が解けて辿り着いた言葉により、罪悪感に囚われていた夫だけでなく、妻自身もまた、自らを苛む葛藤から出ざるを得なくなる物語の構成が、あまりに精緻で美しい。
第二話「埋め合わせ」は本書の中でも特にスリリングで恐怖をあおる話だ。職場や学校で大きなミスを犯し、それを隠したい、ごまかしたい、と一瞬でも思わなかった人が果たしているだろうか。プールの水を流しっぱなしにしてしまった学校関係者のニュースは毎年のように報道されるが、そんなニュースに接するたびに本作を思い出すほど、怖い。なんとか窮地から抜け出そうと様々な工作を試みる主人公・秀則の内面は、閉鎖空間に監禁されたデスゲームの参加者のような切迫感に満ちていて、読んでいるこちらまで不安で押しつぶされそうになる。また、過去の苦々しい失敗が次々と思い起こされ、冗談抜きに肝が冷える。
悪いことをした人間が最後に罰を食らって終わり、なんてありきたりな顚末ではなく、それまでの作中の窮地をまるで窮地だと認識しない、怪物じみた存在が突如現れることにもかえってリアリティを感じた。こういう不気味な他者はいる、他者からみた世界はまるで違う、と説得力を持って感じさせる、作者の人間を書く力の確かさがあって成立する、素晴らしいラストシーンだと思う。
第三話「忘却」は個人的にもっとも好きな話だ。隣人が亡くなる。隣人の郵便物が紛れ込む。どちらもそう珍しいことではない。それこそ指先をちょっと引っ搔く棘程度のできごとだ。忘れたっていい。しかし忘れずに思い続けてしまうことで、辿り着く真実がある。
軽やかな短い話だが、実は「埋め合わせ」よりも怖いのではないかと思う点がある。この小説の、不正を働く人間への解像度の高さだ。
――もったいない。
ただそれだけだったのだろう、と武雄は思う。その気持ちは、わからないでもなかった。
きっと、初めは電気工事代をもらっているくらいの気持ちだったのだろうし、その後は――忘れたのではないか。
不正を働くことは「わからないでもなかった」し、喉元を過ぎればそれすら「忘れたのではないか」。さりげない表現だ。さりげなさ過ぎて、とても怖い。生身の人間のいびつさ、不完全さへの鋭い理解と諦念、そして諦念から来る受容がある。
第四話「お蔵入り」はこのままの筋立てで映像作品として視聴したいくらい起伏に富んだ、本書でもっともドラマチックな話だ。次々と襲い来る深刻なトラブルに遭遇するたび、少しずつ主人公・大崎の「せめてこれだけは叶ってほしい」という望みがぶれ、目指すべき着地点を見失っていく姿が生々しい。また、物語が動く大きなトリガーとなる事件の描写において、その瞬間になにが起こったのか、主人公が全く知覚をしていないところに作者の技が光っている。人はきっと、もっとも直視したくない自分の姿は認識しないのだ。空白がある。空白が甘い夢を見せ、都合のいい期待を抱かせる。
人が認識したくないと願う自分の姿だけでなく、他者の目にはさらに醜さを感じさせる姿がある、と突きつける展開にも圧倒された。人は自分のことがわからない。その恐ろしさを煮詰めた一編だったと感じる。
第五話「ミモザ」は気弱でものごとに確信を持てない料理研究家の主人公が、狡猾で威圧に慣れた元恋人につきまとわれ、生活を脅かされる話だ。主人公の気弱さ、他者に断言をされると自分の思考がたやすく揺らぐ危うさに、終始ハラハラさせられる。物語が進むにつれ、脅迫者である男だけでなく、事態を解決する能力をまるで持たない主人公も、日常の形さえ整っていれば内側の問題には関与しようとしない夫も、みな等しく不気味に思えてくる。
「私は悪いことなんてしてないのに」なぜこんなにひどい目に遭わせるのか、と訴える主人公に対する、元彼の返答がとても明快で正直だ。恐らく唯一、彼が本心を語っている言葉だろう。
「悪いことをしたから悪いことが起きるとは限らないんだよ」
なんどもなんどもこじれた状況を解決しようと思考を巡らせ、言葉を選ぶのに、主人公は脅迫者を叩き出すことができない。主人公は確かに「悪いことなんてしてない」。けれど、彼女は彼女の性分から出られない。物語としてありがちな、なんらかの都合のいいきっかけや気づきをもって、彼女がそんな自分を変えていく――なんて展開には絶対にしないところに、人間のリアリティを追求する作者の凄みと恐ろしさを感じる。芦沢央さんは決して人間を美化しない。描かれるのはいつも弱く不完全で、容易に変わることのできない、醜さを抱えて生きていくしかない私のような、隣人のような、生々しい人たちだ。
汚れた手を、どこで拭けばよかったんだろう。本書を読み終えて、まずそんな問いが浮かんだ。
苦く出口のない五つの部屋。物語に出てくる人々の、頭の中の狭い部屋。罪悪感や恐怖、都合のいい忘却と期待、抜け出せない性分。それ以外にも様々な、読み手が思わず「わからないでもない」と感じてしまう汚れの部屋に囚われた人たちは、いったいどこで、汚れた手を拭けばよかったんだろう。衣服の背面になすりつけるでもなく、身近な他人になすりつけるでもないなら、どこで。
もちろん、手を洗えたら一番よかったのだろう。流し台に立って蛇口をひねり、流水に手を浸して、石鹼を使えたら。しかし彼らが囚われた部屋に流し台はない。そして「表沙汰にしたくない」と思った瞬間、部屋の出口は塗りつぶされる。彼らは自ら部屋の出口を塞いだのだ。
そもそも現実において、本書で描かれた汚れを洗い流せる流し台なんて、存在するんだろうか。生きている間に、ほんのわずかな不運で、油断で、過ちで、傲慢で、手に吸いつく汚れ。洗う場所のない汚れ。
自分の手を思わず見つめ、そして部屋の出口を確認したくなる。六つ目の物語がすでに始まっているのではないかと、恐れながら――。