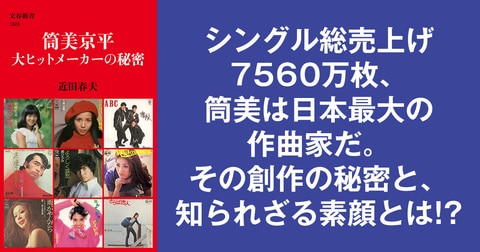小田和正の歌は、なぜ私たちの琴線に触れるのか。小田の誕生から2023年の現在までの人生を、小田本人はもとより、親族、友人、元オフコースメンバーや吉田拓郎、作家の川上弘美など、多くの証言から紡いだ物語が『空と風と時と 小田和正の世界』だ。
音楽の神様に導かれ、ストイックなまでに自分の音楽を追求してきた、決して器用とも順調ともいえなかった小田和正の音楽人生の記録の一部を、同書より抜粋して紹介する。
「ガキのころは、泳いだり、山登ったり、田んぼで遊んだり、そこらへん駆けずりまわっている毎日だったよ。金沢文庫のあたりって、昔は“神奈川で一番空気がきれいなところ”といわれた。蛍を捕ったりもした」
小田和正は、1947(昭和22)年9月20日、横浜市の金沢文庫駅近くで商売をしている「小田薬局」の次男として生まれた。

小田には、都会派のイメージがあるが、実際は少し違う。もっといえば、家の中には「都会人を自負する父」と「山深い田舎から出てきた母」の二つの文化があった。さらに、その母と同郷の若い人たちが数多く住み込みで働いており、いうなれば都会と田舎が混在する“疑似大家族”のような環境のなかで育った。
2005年に取材した際、私が「人生で大きな出来事と思うことを三つあげてください」と質問した時、小田はその一つに、「母親と出会ったこと」と言い、「あ、でも母親から生まれたんだから、それはアプリオリなことだから変だよな」と言い添えたことがある。
母とは、それほど大きな存在だった。子どものころから一貫して「自分の好きなことをやりなさい」と言い続け、暮らしのなかから得た知識や倫理を子どもに聞かせるような母親だった。この時の取材がすべて終わった年の暮れ、事務所の忘年会に招かれた際、小田から「母親の写真見たい?」と訊かれ、「見たいです」と答えると、ガラケーの携帯電話に収められた母きのえの写真を見せてくれた。それはモノクロ写真を携帯で撮影した画像だった。「小田さんに似ていますね」と言うと、「そうか」と少しうれしそうだったが、それは小田のお守りなんだと感じた。
今回、新たに取材を始めた時、この逸話を兄の小田兵馬にした。すると、兵馬も真顔でこう言った。
「俺たち兄弟さ、銀河のどこかから誰のところに生まれようかと言って、あの人を選んで生まれたんだよ」
他方、父に対しては強い調子で…
この話をどう思うかは、人それぞれだろうが、その母親が亡くなった年齢を超えてなお、息子がこのように話す母親とは、いったいどんな人物だったのだろうかと、私は興味をもった。
他方、2005年の取材時、父親は91歳でまだ健在だったが、小田は父に対しては強い調子で、「嫌悪」の言葉しか発しなかった。たとえば、音楽か建築かという選択のなかで、小田は大学院に進み、五年かけて修士論文を書くのだが、大学院をやめなかった理由の一つとして父親の縛りをあげ、「オヤジは学歴がないから、学歴にうるさかった」と冷たく言い放ったものだった。
この時の原稿に、私は、小田にとって「父は通俗の象徴、母は聖なる象徴」とし、「『俗』への嫌悪、『聖』への憧憬、これが小田をずっと縛ってきたように思われる」と書いた。そしてそのあまりに対照的な思いに対して、当時、いったい何があるのだろうかと、戸惑いと興味をもったものだった。その取材時から3年後の2008年、父は93歳で亡くなるが、そのしばらく後、兄兵馬は父の引き出しを初めて開け、父の姿をようやく少し知ることになる。

母・奥本きのえは、大正9(1920)年11月5日に和歌山県東牟婁郡北山村で生まれた。北山村は、奈良県と三重県に接し、和歌山県のどの市町村とも接していないという珍しい飛び地で、昔は本当に山深い土地だった。木の伐採や輸送、畑仕事が村の主な生業だった。兵馬は「おふくろにいわせると、平家の落人の集落で、血がどんどん濃くなっているんだと。血が濃いというと、僕らは、いろいろなことが腑に落ちるようでした」と話す。小田兄弟がまだ幼いころ、母のふるさとに遊びにいったことがある。
「昭和29年ごろです。その時、父が8ミリの映写機を持参して撮影し、その3、4年後にふたたび訪ねた時、前に撮った8ミリの映像を見せると事前に伝えると、村の人たちが、電気を使うからとわざわざ発電所に許可を求めに行ったらしいです。そのくらいの田舎でした」(兵馬)
きのえは9人兄弟姉妹で五番目の長女、上4人が男(四男はすぐ養子に)で、妹が2人、弟が2人いた。ちなみに、上4人の兄のうち、三男・龍三は絵も歌も上手く頭も良かったが25歳で夭折、それはいまなお小田家で伝説的に語られている。一番末っ子の弟、昭和5(1930)年生まれの奥本康は90歳を超えて健在、千葉市で薬局を営んでいる。2021年2月に私が訪ねた時、康はジーンズを穿き、Gジャンを着て、白髪を後ろで一つに結ぶという若々しいスタイルで店先にいた。
康は、「姉は末っ子の私を本当に大事にしてくれました」と何度も繰り返し、こう続けた。
「和正君は、私に輪をかけて愛情を受けたんじゃないですか」
きのえは小学校を出たあと、看護婦になりたくて、和歌山県・新宮の寺本医院、さらに松橋病院に勤め、その後、長兄を頼って上京した。この長兄・実雄が奥本家のキーパーソンだったようである。康が語る。
父は丁稚奉公の傍ら、薬種商の資格を
「本来家を継ぐはずの長兄は、小学校を出ると自分で丁稚奉公の口を見つけてさっさと東京に出ていったんです。このあたりは都会に出るなら大阪で、東京に行く人間はすごく珍しかった。長兄は働きながら勉強し、戦前のことですが、これからは英語を勉強しなければダメだと、カナをふった『リーダーズダイジェスト』なんかを田舎に送ってきました。クラシック音楽が好きでレコードをたくさんもっていましたね。
東京外語大学まで行ったけど、一時、共産主義に走り、大学をやめました。あの人は要領がよくて、兵隊にとられたが戦地には行かず、復員してきた時、軍の物資をトラックに積んでもってきました。もらってきたのか、かっぱらってきたのかな」
この長兄を頼って、戦前、きのえも上京したのである。
康が小学校6年生の夏休み、きのえが遊びにおいでと旅費を送ってくれ、上京した。太平洋戦争が始まった翌年のことである。この時、実雄と康のすぐ上の兄・五郎ときのえは三人で東京・本郷の下宿に住んでいたが、きのえはすでに世田谷の大蔵にあった第二陸軍病院で看護婦として働いていた。そしてそこで、衛生兵として働く小田信次と出会うのである。
父・小田信次は、大正3(1914)年6月12日に東京・本郷で生まれた。兵馬によれば、
「祖先は津軽藩の江戸詰の武士で江戸小石川に住んでいた。東大農学部のところに屋敷があって、うちの寺はいまも、東大近くの湯島にあります。父の実家は明治にたくさんできた小さな銀行の一つで役員をしており、別荘を持つなど裕福な暮らしをしていたと聞いています。父も旧制中学に通っていましたが、昭和2(1927)年、多くの銀行が倒産した金融恐慌の折り、父の実家が役員をしていた銀行も倒産し、父信次は旧制中学を中退せざるをえなかったようです」

信次は13歳の時、横浜・伊勢佐木町にある薬種問屋「桜井薬品」に丁稚奉公することになる。信次は昔の話をほとんどしなかったようだが、奉公していたころ、横浜の関内から逗子まで自転車で御用聞きに行っていた話は小田兄弟ともに聞いた覚えがあるという。
信次は丁稚奉公の傍ら、薬種商の資格を取ろうと、夜中、電灯がついているトイレの中で勉強し、睡魔に襲われると膝に針を刺して頑張ったというが、こういった逸話も、兵馬は父の死後、父が書いた文章から知るのである。
信次が薬種商の資格を得て薬舗開設許可が下りたのは昭和16(1941)年12月。丁稚になって14年目。太平洋戦争勃発の前日だったという。そして信次はすぐに、横浜のはずれである金沢文庫駅近くに薬局を開く準備を始めている。当時は、駅舎と畑とわずかな家があるだけの場所だったが、ちょうどこの直前、品川と横浜を繋ぐ京浜電気鉄道と横浜と三浦半島を結ぶ湘南電気鉄道が合併し、のちに京浜急行電鉄となり、金沢文庫駅は便利になると信次は見通していたのだろう。