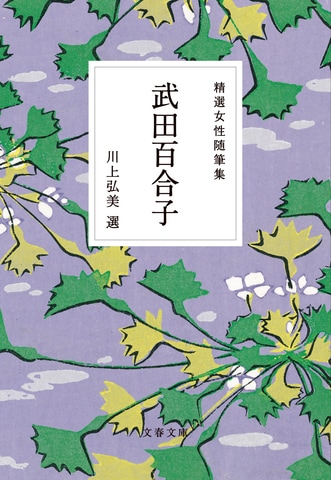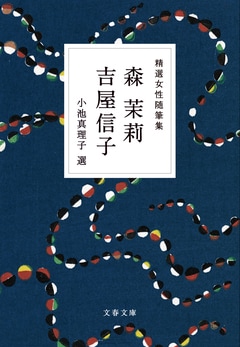武田百合子の著述がはじめて世に知られるようになったのは、一九七六年(昭和五十一年)、五十一歳のときのことだった。百合子は小説家・武田泰淳の妻としてすでに文壇にも知己が多かったが、それまで公の場で文章を発表したことはほとんどない。それが、この年の十月、泰淳が癌のために死去すると、夫妻が所有した富士山麓の山荘での生活ぶりを百合子がずっと日記につけていたことが明らかになり、泰淳と付き合いのあった中央公論社の編集者・塙嘉彦が通夜の席で、この日記を文芸誌「海」に掲載しないかと百合子に持ちかけたのである。それまで百合子は自分の書いたものを積極的に外に出すことはなかったが、このときは「供養の心持」でこの提案を受け入れた。
こうして「富士日記」が日の目を見ることになる。日記は「海」の一九七六年十二月号から連載され、翌年には単行本の上巻、おって下巻を刊行。これをきっかけに、それまで「作家の妻」だった百合子が、一人の文筆家として脚光を浴びることになった。
『富士日記』は驚くべきものだった。高名な作家の私生活の記録が注目を浴びるのはそれほど不思議なことではないが、『富士日記』にはそうした好奇心とは無関係に、読む者を虜にする魅力があった。この日記に登場すると、どんな人でもどんな出来事でも、かなりおもしろい、おかしい、変な感じになってしまうのである。元々個性的と言われているような人物でもおかまいなしだった。一例をあげると、深沢七郎。
三時ごろ、深沢七郎さんが、ひょっこり現われる。(中略)深沢さんは「ここは富士山の中ですか? 中じゃないでしょうねえ。やっぱり、中かな。裾野が下に見えるから。一合目かしら」とそのことばかり言っている。「なかでしょ。字富士山という番地だから」と言うと、心配そうな、いやそうな面持をする。深沢さんの一族は富士山に登ったり、富士山のなかに入ったりすると、必ず悪いことが起るのだそうだ。キチガイになった人とか、盲腸炎になって死んだ人とかあるそうなのだ。そのことを話して、深沢さんは飛ぶようにして帰ってしまった。そして、こんなことも言った。「富士山の見えるところに美人はいないですねえ」。いやだなあ。
夜、南條範夫のザンコク小説を花子と読み耽る。(二二~二三ページ)
富士山の呪いというと禍々しいはずなのだが、深沢の様子はどことなく素っ頓狂で、こちらがどう受け取ろうかと迷ううちに、話があれよあれよと進んでしまう。『富士日記』を読む最大の楽しみはおそらく、読者として、こうしてキョトンとすることにある。美辞麗句や皮肉めかした警句はないし、言葉はまっすぐなのだが、なぜか一寸先が闇。思いがけない人や出来事や表現(とくに科白!)が次々と連なって、おもしろおかしくて笑ってしまう一方、身体の変な部分が涼しくなっていくような、不安になっていくようなスリルもある。
百合子は楽しいことや心地良いことだけを見ていたわけではない。そうではない部分、恐いものや、嫌なものや、死をもいつも目の端でとらえている。だてに武田泰淳の妻ではなかったのである。泰淳という作家は、戦時中の人肉食事件を描いた「ひかりごけ」などにも見られるように、凄惨で深刻な状況をまっすぐにとらえる観念の屈強さを備える一方、そうしたのっぴきならない人間性の行き詰まりを、ふっと手品のように解放してしまうさばき方も知っていた。『富士日記』の世界もどこかそれに似ている。出てくるのは百合子や泰淳や娘の花をはじめ、近所の外川さん、大岡昇平、竹内好、工事の人、追突してきたトラックの運転手、スタンドの人、野次馬、ちんぴら、お医者、犬などいろいろだが、そういう中で人間の付き合っていかねばならないことのぴんからきりまでと接しながら、力で組み伏せるような語り口には決してならないのである。
日記はもともと泰淳の勧めでつけ始めたものだった。はじめは渋っていた百合子だが、「俺もつけるから。代る代るつけよう。な? それならつけるか?」と説得された。「どんな風につけてもいい。何も書くことがなかったら、その日に買ったものと天気だけでもいい。面白かったことやしたことがあったら書けばいい。日記の中で述懐や反省はしなくてもいい。反省の似合わない女なんだから。反省するときゃ、必ずずるいことを考えているんだからな。百合子が俺にしゃべったり、よくひとりごといってるだろ。あんな調子でいいんだ。自分が書き易いやり方で書けばいいんだ」(「絵葉書のように」)。
泰淳のこんな言葉を受けてはじめた日記を、夫の死後、百合子はぱったりやめてしまう。やはり想定読者は夫だったのだ。死期を悟った泰淳が「生きているということが体には毒なんだからなあ」と口にしたとき、「私は気がヘンになりそうなくらい、むらむらとして、それからベソをかきそうになった」とふだんの書きぶりに少しだけ負荷がかかっているのがとりわけ印象的だ。(一四四ページ)
『富士日記』以外でも、本書に収録された「枇杷」や「椎名さんのこと」「富士山麓の夏」など、泰淳のことを回想したものには佳品が多い。いずれも死の影が鮮明で、哀切感も苦しいほどだが、文章はすくっと立っている。
二、三日して私は肉まんをこしらえた。大岡と大岡の奥さんに二つずつやりたい、と武田がいうので、ふかしたてを持って行くと車がなく、玄関の前の凸凹した火山岩の石畳が、露でじっとり濡れていて、階下にも二階にも黒い雨戸がたてまわしてあった。その晩、「こんなに寒くてはバカバカしい。俺も帰る」と、武田はいいだした。そうして、東京に帰るとまもなく寝込んで、十月はじめに死んでしまった。(「富士山麓の夏」二五四ページ)
どうということのないようで、こんなふうにはなかなか書けない。晩年、脳血栓のために執筆に困難が生じた泰淳のために、百合子は口述筆記の役を務めた。それが文章修業になったと言う人もいるが、百合子の書くものに過剰に作家・泰淳の影を見るのは考えものだろう。弟の鈴木修も、百合子の「文学修業説」には否定的だ。「百合子の表現のしかたみたいなものは、昔から百合子がもっていたもののように思います。小さいときから百合子の話は意外性に富んでいました。(中略)文章のリズムみたいなものっていうのは、読んでいてなつかしい感じがします」(「文藝別冊・武田百合子」所収「インタビュー 姉・百合子の素顔」)。同じ「富士」を舞台にした泰淳の重厚な『富士』と、百合子の『富士日記』とを読み比べてみても、二人の資質の違いは明らかだ。
泰淳の短篇に「もの喰う女」(一九四八)というものがある。一方に男づきあいの多い、派手な顔立ちで神経質な弓子、他方にちょっとぼんやりしておとなしい、少女のような房子という二人の女性を配し、その間を主人公が揺れるという話である。この房子のモデルとなったのが百合子だった。作品の中で、神経が張りつめるような弓子との関係に疲れた主人公は、房子が「食べることが一番うれしいわ。おいしいものを食べるのがわたし一番好きよ」とあっけらかんと言う、その眩しいほどの明朗さに引きこまれていく。結末近く、酔っぱらって「オッパイに接吻したい!」と口走った主人公に対し、房子は一瞬のためらいもなく、乳房を露出する。それを「少し嚙むようにモガモガと吸」ってから、彼は果たしてこの素直さは何なのだ、愛なのか? トンカツを食わせたお礼か? と悩んだりする。
まさに二人の間柄を象徴する場面だ。百合子は泰淳に隷属していたわけではなかった。むしろ十二歳年上の泰淳が、「男に向ってバカとは何だ」などと叱ったり小言を言ったりしながらも、百合子の天真爛漫さに圧倒されていたフシがある。百合子をよく知る埴谷雄高は彼女を「生の全肯定者」と呼び、もともとニヒリストの気の強かった泰淳の世界が、百合子のおかげで広がりのある全体性を得たと言っている(「武田百合子さんのこと」)。「相思相愛でたいへんけっこう、なんて感じじゃなくて、人を愛するってこともあそこまでいくと、愛してるんだか戦ってるんだかわからない」という前記の鈴木修の回想からもわかるように、二人は人として拮抗していたのだ。
百合子は一九二五年(大正十四年)、横浜市に生まれた。旧姓鈴木。父は裕福な米問屋の入り婿だったが、妻が死んでから後妻をもらい、そこで百合子が生まれる。しかし、母親は百合子が小学生のときに死去。戦争末期、生家は米軍の爆撃で全焼し、戦後の農地改革もあって鈴木家は完全に没落した。百合子はすでに結婚していた兄の家に寄宿しながら、行商などするようになる。
文学には若い頃から縁があった。横浜の女学校時代には同人誌「かひがら」に所属し、「新女苑」に詩などを投稿、戦後の混乱期も、職を転々としながら同人誌「世代」に参加している。やがて、ひょんなことから作家たちが多く集まる文壇喫茶・酒場「らんぼお」で女給として働きはじめ、文士たちの間でアイドル的な存在となる。泰淳の熱烈なアプローチを受けたのもこの「らんぼお」でのことだった。当時の百合子は、「もの喰う女」に登場する房子と同じように、いつも同じスカートで、年中素足のまま同じ靴を履いていた。いかにも育ちの良さそうな、恥ずかしがりで奥ゆかしいところと、ぐいぐい行動に出る、犬のように野性的なところの両面を持っていた。猛スピードで車を乗り回し、ちんぴらと堂々とやりあうような人でありながら、しごく繊細で思いやり深い人でもあったのだ。だから、接した人はすぐファンになった――梅崎春生、堀田善衛、埴谷雄高、色川武大、吉行淳之介、加藤治子、赤瀬川原平、村松友視……みんなそうである。
本書の後半には、『富士日記』で人気の出た百合子が、自分のペースを守りながら書き綴った珠玉のエッセイが収められている。「草月」での連載をまとめた『ことばの食卓』(一九八四)は、食べ物を出発点にしつつ、例によって独特の視線でまわりの人間や社会をとらえたものだが、とくにオムレツ専門店でのひとこまが描かれる「夏の終り」は、「枇杷」とならぶ絶品。「挿花」の連載をまとめた『遊覧日記』(一九八七)は浅草の蚤の市から藪塚のヘビセンターまであやしげな場所への探索の様子が描かれ、出てくる人物たちもより賑やかで、小説の一歩手前の境地を思わせる。
周囲の勧めにもかかわらず武田百合子は最後まで“小説家”にはならなかったが、文章へのこだわりはプロのものだった。『富士日記』にしても、念入りな推敲をへて発表している。死後、書きかけのもの、未発表のものはすべて遺言に従い娘・花の手で処分された。人前に出るときには相応の覚悟を持つ、そんなたしなみを最後まで備えた人だったのだ。