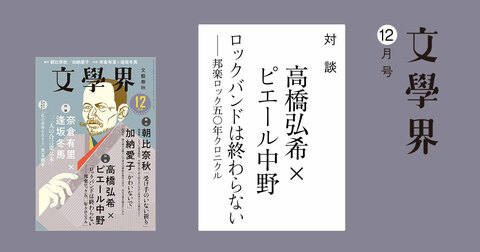「最近、太りの方はどうなの?」
祖母は時々、私の体型を見て心配そうに聞いてくる。その度にちょっとだけ腹が立つ。
「変わらないよ。ばあびもでしょ。」
ばあびというのは、私の祖母の呼び名だ。私はかなり太っているが、彼女もまたかなり太っている。50近く歳の差があるのに、周りから見たら私たちの身体の形はそっくりらしい。
「青嵐も私と同じ、渇きの病いなのかしら。困ったものね。」
時々こんなやり取りをしてお互いを少し心配し合うが、長続きしない。すぐにこれから何を食べようか? という話で盛り上がる。祖母は数年前にコロナに感染し、入院治療で奇跡的に回復した。しかし命と引き換えに、自力で起き上がるだけのパワーを失っていた。去年傘寿を迎え、在宅で介護サービスを受けながら都内のマンションで母と二人暮らしをしている。ベッドに寝ている祖母の身体は、とても太っているが、平べったい。年を重ねる度にどんどん溶けていっているように見える。
祖母は私と同様、食べることが大好きだ。身体が自由に動かなくなってからは、食事は家族が作っている。今やテーブル代わりになってしまった平たく広がったお腹の上に、お気に入りのウィリアム・モリス柄のナプキンを載せて食事を待つ祖母の姿がたまらなく愛おしい。私にとって祖母は、最愛の人であり、ミューズであり、親友でもある。同居はしていないが近所に住んでいるので、ほぼ毎日会いに行っている。
ところで、祖母の言う「渇きの病い」ってなんだろう。この言葉、なぜか妙に納得してしまう強さがある。祖母曰く、昔は食べても食べてもお腹が空くことをそう呼んだらしいが、説明を聞く前の方が腑に落ちる感じがする。なぜなら、私の場合はお腹が空いていることと、食べることが直接的に繋がっているわけではないからだ。確かに人よりは空腹感を感じやすいかもしれないが、お腹が空いていなくても食べたくなる時がよくある。空腹という言葉では補いきれない、ただ漠然とした渇きやすさを自覚している。
かつて都内で数店舗の飲食店の社長をしていた祖母は、「リサーチ」という体で東京中の美味しいものを全て食べ尽くしていたんじゃないか? と思うくらいにはグルメだった。私も幼い頃はよく外食に連れていってもらった記憶がある。家族経営だったため、父も母も調理師で、家でも「試作」という体で食べきれないほど大量の料理が出ていた。当然、家族全員太っていたし、食に対する感覚がみんなバグっていたように思う。家族で食事をした後も、父が部屋で一人こそこそキャンプ機材を広げて焼肉をしているのを目撃したことが何度かあり、子供ながらに引いていた。外食三昧の祖母と比べ、母は家で料理を作ることに強くこだわっていた。時々「餌作らなきゃ」とかいう言葉がぽろりと出るので、私たちは家畜扱いなのかよ……と悲しく思うこともあった。餌にしては豪華すぎるので、嬉しくていつも食べ尽くしてしまっていたけれど。人を太らせることが好きな人をフィーダーと呼ぶらしいが、母もちょっとその気があると思う。そんな家族のもとで育ったこともあって、私は20代前半頃まで平均的な一人前の量がわからなかったし、社会人になってからも食堂や定食屋で提供される食事が茶番のように感じてイライラしてしまうことがあった。シルバニアファミリーの食事会に、私だけ等身大サイズでお邪魔しているような、そんな感覚だ。
とにかく、私は子供の頃から太っていたので、太りに関しては妙なプライドのようなものがあった。明らかに痩せている人が語る「太っている」という話には、無駄に怒りを覚えてしまっていたし、贅沢な悩みだと思って、嫉妬していた。10代半ばから20代前半の頃、周りの友達はこぞって「痩せ」に取り掛かっていた。仲の良い友達が痩せ薬を使ったり、極端なダイエットを始めたりしている様子を見て、「すごいね」「私は諦めたけどね」なんて余裕そうに答えながら、悲しさを隠していた。お互い尊重しあっている関係だと思い込んでいたが、心のそこでは軽蔑されているんだとか、自分の存在を否定されているような気がしていたのだ。ボディポジティブだとか、どんな身体も美しいとか、そういう言葉を胡散臭く感じてしまうのは、その辺の感覚がいまだに残っているからだ。誰かが「太っている」ことは気にならないとしても、自分自身が「太る」ことに関してポジティブに捉えられる人は少ないだろう。私自身、自分の太った身体に対し、誰よりも否定的な言葉を使って捉えてきた。
時々、なぜそんなに太っているのか? という質問をされることがある。私は大抵「食べすぎてるからだよ」と答えてきた。多くの人は、そう答えたらスッキリ笑ってくれるので楽だ。たまに、聞いてもいないのにダイエットのアドバイスや健康に関する情報提供をしてくれる人もいる。この体型で生きていること自体、人に不安を与えてしまうらしい。気まずくて、いつも痩せたいと思っているふりをしている。
肥満ではなく「ファット」
私は今、大学院で「ファット」な身体との付き合い方を、衣服を作るという行為を通して発見するという研究をしている。やや複雑に聞こえるかもしれないが、私や祖母のように自分自身を「太っている」と感じている人が、どのような身体感覚を持っていて、どのように自分の身体と付き合っているのかを明らかにすることが一つの大きな目的だ。
今から約10年前に看護大学を卒業した私は、精神科病院や当事者コミュニティ等で看護師として働きながら、同時にアーティスト・ファッションデザイナーとしても活動してきた。好きで続けてきたそれらの仕事から、「身体との付き合い方」というテーマに行き着いたことは、必然に聞こえるかもしれないが、自分の中ではかなり意外なことでもあった。それは私が長い間、「自分の身体」について考えることを極端に避けていたからだ。幼い頃から太っていた私は、太っていながら生きていくことに、少なからず気まずさや恥ずかしさのようなものを感じていた。今振り返ると、成長するにつれて増強していくその感覚に対し、あらゆる方法で応じてきたと思う。それは、過激なダイエットで体重をコントロールすること、自虐漫画を描いて笑いの先手を打つこと、週末に白塗りメイクや仮装で別人のように変身することなど、多岐にわたる。
私が大学院に入学したのは、今から2年半ほど前のことだった。いわゆる社会人学生である。今は東京に戻ってきているが、当時は北海道にいた。森進一の名曲の印象が強すぎる、あの襟裳岬よりちょっとだけ西側にある、浦河町という海沿いの小さな街だ。そこで私は一応、看護師として働いていた。不思議な場所だった。愛着のある東京、大切な友達、そして何より最愛の祖母と離れ、一人で移住してしまうくらい、当時の私はその街に強く惹かれていたのだ。街には、「浦河べてるの家(1)」という、主に精神障害を持った人たちが生活や仕事、そして当事者活動をしている大きなコミュニティがあった。今から20年ほど前から、自分で自分に病名をつけたり、幻聴や妄想などの困りごとに名前をつけて仲間と研究したり、というようなとてもユニークな実践が行われている場所だった。ファッションデザイナーとしても活動してきた自分にとって、彼らが自分の「言葉」で自分を語り直していくプロセスは、まるで自分の手で自分が纏うための「服」を作っているように思えた。更なるファッションデザインの可能性を探しに……なんて高々とした目標を掲げて行ったものの、しかし、実際はそんな甘い期待を裏切られるような、常に胸がヒリヒリするような日々だった。
「こんな何もないところにわざわざくるなんて、あんた、よっぽど寂しいのかい?」
「えっ(笑)。いや、めっちゃ面白いことしてる! と思ってきたんですよ。」
「あんたも病気だね。」
そのコミュニティの重鎮たちは、時々ギクッとするような言葉を、挨拶がわりに投げかけてくるような、強烈な人たちだった。そんな彼らと一緒に過ごしていくうちに、私はまだ自分を語る言葉を持っていないことに気づかされていった。
自分を語る言葉。私が太っていることに困っているとはいえ、デブとか、肥満とかいう言葉で語りはじめるのは嫌だった。デブは呪いの言葉だし、肥満は健康診断で犯罪者として吊し上げられるような印象があって、どちらも私の被害妄想を盛り上げるキーワードでしかないからだ。そのヒントを得るため、私と同じように太っている人たちが、どのように生き、自分を語っているのか調べていたときに『「ファット」の民族誌(2)』という本に出会った。著者であり文化人類学者の碇陽子は、アメリカで1969年から始まった肥満当事者による差別廃絶運動について研究している。碇によると、運動の参加者たちは自分達を医学用語の「過体重」や「肥満」ではなく、「脂肪」や「デブ」という意味を持つ「ファット」という言葉を使ってお互いをエンパワメントしているというのだ。アメリカでは、侮蔑的なニュアンスを持っているこの「ファット」というワードを使うところに、自分の身体を自身の元へ取り戻していくような、主体的な態度を感じる。しかし、日本人の私にとっては侮蔑的なニュアンスもそれほど感じず、ただただ新鮮だ。その柔らかく軽やかな語感含め、とても気に入っている。私はこの「ファット」という言葉を用いて、自分や自分のような太った身体をもつ人について改めて捉え直し、自分の言葉を見つけていきたいと思っている。
寂しがりやの脂肪細胞
ところで、私の身体はどうしてこんなに「ファット」なのだろう。「食べすぎてるから」だとしたら、なぜなのだろう。自分の身体とうまく付き合うためのヒントになるような、しっくりくる答えはないだろうか。その答えを見つけるため、まずは「太る」ときに身体で起きていることを知ることから始めてみたい。
私は「今、太っている(ing)」というときの身体感覚がある。例えば、甘いケーキやお菓子、揚げ物を大量に食べてしまった時などに感じやすい。ちょうど肩や腕まわりと腰まわりが、ふわふわ、そわそわ、膨らんでいく感じがする。少しむず痒い感じだ。私はこれが、「脂肪」が増えるサインのように感じている。実際のところ、全く関係ないのかもしれないのだが、そう感じる部分には、身体のどこよりも脂肪がついているように見える。いわゆる、ぼこぼこした憎たらしく忌まわしいセルライト。Tシャツを着ると必ず袖からだらりと顔を出す、ぶよぶよのあいつだ。では、実際この脂肪はどのように増えていくのだろう。脂肪(組織)を構成する「脂肪細胞」について調べていく中で、思いがけない発見があった。
生きるために必要なエネルギー源となる栄養を蓄える役割を持つ脂肪細胞。太れば太るだけ増えていくのだろうと想像していたが、実はそうではなかった。その数は、幼児期から青年期にかけて増えていくが、成人期に入る頃には総数がほぼ一定となるらしい(3)。そのため、太り始めると脂肪細胞は増えるのではなく、まずは大きくなる。しかし、脂肪細胞には大きくなれるサイズ的な限界があり、それを超えるほど太ることでようやく「増殖」を始めるというのだ。一方、一度増えた脂肪細胞の数は減ることはない(4)。つまり、ダイエットなどで栄養の供給が減っていくと、脂肪細胞はただ小さくなっていくだけなのだ。面白いことに、脂肪細胞は脂肪組織として最大に増えた状態を覚えており、細胞のサイズが小さくなると、元の状態に戻すため、食欲を増進させ、もっと栄養を蓄えるように働きかける(5)。
……まるで、脂肪細胞は意志を持っているかのような話だ。若い頃に太ってしまった人が痩せにくいことや、リバウンドという現象も、このような脂肪細胞たちの性質を知ると納得してしまう。私が最高体重である125kgを超えたときの脂肪細胞たちは、きっと私の身体の中で大いに増殖し、盛り上がっていたことだろう。しかし、私は人生で3回ほど20~30kgの減量をしたことがある。食事制限ダイエットなのだが、その度に激しいリバウンドに悩まされていた。
そうなると、想像してしまうのが、私がダイエットをする度に小さくなっていった脂肪細胞たちの気持ちだ。仲間たちが次々に痩せほそり、お互いの距離が遠くなっていくにつれ、かつては密着し合っていた大勢の仲間との繋がりが失われ、孤立し、きっと寂しかったのかもしれない……(小さくなった脂肪組織を想像すると、確かにもの悲しさがある)。今思えば、私は彼らに随分と可哀想なことをしてしまっていたのだ。こう考えると、これまで司令塔だと思い込んでいた「私」よりも、身体の中にいる「脂肪細胞たち」の方が強い権力を持っているようだ。彼らは私の行動や身体全体を乗っ取ることで、仲間に囲まれ満たされていた過去の時間を、全力で取り戻しにかかってきていたということになる。
今まで私は、意志の弱さが太りの原因であると思い自分を責めてきたのだが、脂肪細胞たちに支配されていたことを発見してから、まるで免罪されたかのように肩の荷が降りたのだった。
それにしても、脂肪細胞はあまりにも寂しがりやすぎる。私の体重は4年ほど前の最後のダイエットによる減量後、いまだに右肩上がりに増え続けている(まだ最大の125kgは超えていないが、もしかして奴らは私をそこまで太らせるつもりなのだろうか)。無理に痩せなくてもいいが、せめて安定を願っている。とはいえ「なぜ太っているのか」「なぜ食べすぎてしまうのか」という問いに対する答えが、「脂肪細胞が寂しがりやすぎるから」というのでは、全く埒が明かない。そう、私が次に考えるべきなのは、その「寂しがりやの脂肪細胞たち」と、上手に付き合っていく方法なのだ。
脂肪細胞の「正体」
その方法については皆目見当もつかないので、実は最近、私を支配する脂肪細胞たちの姿をイメージしてみることからはじめてみた。きっと、ぶよっとしていて、柔らかい。身体の大部分をお腹が占めていて、手足は短そう。色はくすんだ薄ピンクや、黄ばんだ白色といったところだろう。できたら、寂しさで私を支配するのでなく、お互いを助け合っていってほしい。ならば大量に作ってみるか……。なんてことを考えながら、気づいたら小さな脂肪細胞の人形を30個ほど作っていた。思いのほか可愛いビジュアルに気分が上がり、いろんな人に見せびらかしていたのだが、祖母に見せた時に思いがけない発見があった。
「あら、これは私ね。そっくりね。」
びっくりした。私は全くその気が無かったのだが、確かに言われてみると、脂肪細胞の人形はベッドに溶けて広がっている祖母の身体の形とそっくりだったのだ。結局、全ての答えは祖母に行き着いてしまうのか? 私は少しだけ恐怖を感じた。同時に、自分でもなぜ今まで気づかなかったのかというくらい、腑に落ちるものがあった。祖母は続けた。
「かわいいわね、一つちょうだい。」
「いいけど、これはばあびのつもりじゃなくて、私の脂肪細胞を作ってみたんだよ。」
「あらやだ! 脂肪細胞だなんて! そんな変なもの作るのやめなさいよ!」
「ははは(笑)。確かに、ばあびにそっくりでかわいいね。私の身体の中に、小さなばあびが大勢いるってことだね。やばいね。」
「あらまあ! いやね。でもね、私はいつでも青嵐の近くにいたいのよ。」
そう言って、祖母は私の作った脂肪細胞の人形を、ベッド横の壁に貼り付けた。なんだかんだデザインがとても気に入っているらしい。祖母はとても寂しがりやで、いつでも私がそばにいることを望んでいる。そして私自身、身体をほとんど祖母に乗っ取られていると言ってもいいくらいに、生活が祖母中心になっているのも事実である。
「おつけものっ! おつけものっ! おつけものっ!」
隣の部屋で作業に集中する私に、容赦なく訴えてくる祖母の空腹アピール。朝も昼も夕食もしっかり食べているはずじゃないか? 私の都合なんて、祖母は全くお構いなしだ。塩分だってそんなに摂らせたくない。しかしそんな祖母にイライラしつつ、やっぱり愛おしさが勝ってしまうのだ。冷蔵庫からたくあんのお漬物を少しだけ切って、祖母の元に持って行く。
結局、「太り」とどのように付き合っていけば良いのか、まだはっきりとした答えは出ない。それを考えていく中で浮上したのは、憎たらしい存在だった脂肪細胞の正体が、最愛の祖母なのかもしれないという疑惑である。もしかしたら、祖母の寂しさと私がどう付き合っていくのかということに、私の求める答えがあるかもしれない。今は、日々祖母の身体をケアする時間を通して(介護と並行して服作りをしている)、そのヒントを探っているところだ。

註
1. 浦河べてるの家(2005)『べてるの家の「当事者研究」』医学書院
2. 碇陽子(2018)『「ファット」の民族誌――現代アメリカにおける肥満問題と生の多様性』明石書店
3. Salans, L.B. et al. (1971). Experimental obesity in man: cellular character of the adipose tissue. The Journal of Clinical Investigation. 50(5) :1005-1011.
4. Spalding, K.L. et al. (2008). Dynamics of fat cell turnover in humans. Nature. 453 (7196): 783-787.
5. マリエッタ・ボン、リーズベス・ファン・ロッサム(著)、ローリングホフ育未(訳)(2021)『痩せる脂肪――もっとも誤解されている器官の驚くべき事実』クロスメディア・パブリッシング
(初出 「文學界」2024年3月号)