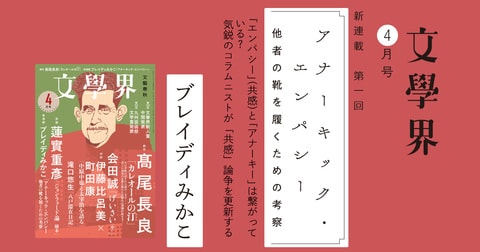「他者の靴を履く」ために出た旅が、「足元にブランケットを敷いて民主主義を立ち上げる」で終わった。特に足へのフェチがあるわけでもないのだが、自分がよく使って来た「地べた」という言葉を鑑みても、どうもわたしには人間が拠って立つ足元に戻って来てしまう習性があるようだ。
さて、最後に、取りこぼした一つの問題について書いておきたい。この本を担当してくださった編集者の山本浩貴さんからの質問にまだ答えていなかったからだ。
それは、「エンパシーを働かせる“範囲”の倫理的問題をどう考えたらよいのか」という問いだった。「誘拐事件の加害者、DV加害者はもちろん、例えばサイコキラー、性犯罪者や幼児性愛者、レイシスト、ミソジニスト……などにそもそもエンパシーを働かせてよいのだろうか」という疑問に答えてほしいというものだ。最近は「多様性の時代の落とし穴」について警鐘を鳴らす識者たちが存在し、例えばレイシストのような人々の考えを「尊重」するのは間違っているという批判もあるので、エンパシーの対象の倫理的線引きはあるのかどうかを書いたほうがいいのではないかという提案をいただいたのだった。
これでまず思ったのは、レイシストの考えを「尊重」するのはエンパシーではないだろうということだった。他者の靴を履いてみたところで尊重する気になれない他者の考えや行為はある。エンパシーを働かせる側に、わたしはわたしであって、わたし自身を生きるというアナーキーな軸が入っていれば、ニーチェの言った「自己の喪失」は起きないので、どんな考えでも尊ぶ気にはならないだろう。そもそも、エモーショナル・エンパシー(共感)ではない、コグニティヴ・エンパシー(他者の立場に立って想像してみる)のほうは(そして本書の大部分においてわたしはこちらについて語って来た)、その人に共感・共鳴しろという目標を掲げて他者の靴を履くわけではないから、その人の立場を想像してみたら(エンパシーを働かせてみたら)よけいに嫌いになったということも十分にあり得る。
しかし、それでも、誰かの靴を履いてみれば、つまり、その人がどうして自分には許せない行為をしたのか、どこから問題ある発言が出ているのかを想像してみれば、今後どうすればそのような行為が増えることを防げるか、または、どうすればその人自身の考えを少しでも変えることができるかを考案するための貴重な材料になる。これを怠ってずっと同じ批判の方法を取っていても(例えば、相手が間違っていることを示すデータを延々と突き付け続けるとか)あんまり効果は期待できないということは、近年の世界で生きている人なら誰しも気づいていることではなかろうか。
さらに、コグニティヴ・エンパシーに倫理的線引きが必要となると、物書きという職業の人間はたいへん困ることになる。今後、ドストエフスキーのような作家が登場しても、もうラスコリニコフは書けないということになるし、ノンフィクションの分野でも、危険な思想や性癖を持つ人のことは深く掘り下げて書かないほうがいいから単なるうすっぺらい邪悪な人物として仕上げてくれ、みたいな要求がまかり通るようになり、それこそ深みのない作品ばかりになってしまう。
また、コグニティヴ・エンパシーを使う対象に倫理的な線を引いたほうが良いのであれば、なぜ刑事裁判では、被告人がシリアルキラーであろうと幼児虐待者であろうと、情状証人(肉親や雇用主など)が法廷で証言し、被告人の生い立ちや境遇などの詳細を話して聞かせることが行われてきたのだろう。
それは、例えば、罪を憎んで人を憎まずとか、人間には贖罪と再生の可能性があるというような宗教的・道徳的な出処もあるだろう。が、それよりも重要なことがある。
人間はよく間違うからである。
人が人を裁くというのはそもそも無茶な設定であり、しょっちゅう間違える生物が判断を下しているのだから、できるだけ他者についてよく知ってからにしましょうねということなのだ。
裁判のようにある人の人生(国によっては人の生き死にさえ)を決定するような大きな判断でなくとも、わたしたちは日常的に他者を判断しながら生活している。英語では、「judge(裁判官)」という言葉が動詞としても使われ、「Donʼt judge me(決めつけないで)」という表現などは日常的に耳にする(ティーンがよく大人に向かって言う言葉だ)が、「いい人」だの「悪い人」だの「正しい」だの「間違っている」だのと勝手に他者を判断しながらわたしたちは生きている。人間である以上、それはやめられない。人間はよく間違うくせに他者を判断したがる生き物なのである。ならば、あまり間違えないようにする努力ぐらいはすべきなのである。
さらに、誰にでもエンパシーを使うことが「多様性の時代の落とし穴」で、その対象を制限するため倫理的線引きをしたほうがよいのだとすれば、その考え方の基盤には、世の中がカオスになってしまうのを防ぎたいという前提があるはずだ。しかし、実のところアナキストというのは困った人たちであり、カオスを拒否しない。
『改革か革命か──人間・経済・システムをめぐる対話』(三崎和志他訳、以文社)というトーマス・セドラチェクとの対談本の中で、デヴィッド・グレーバーは、セドラチェクから「カオスはとても危険」「しばしばとても危険な状況を生み出します」と言われて、こう答えている。
私が言いたいのは、カオスの際に脅威としてあらわれる害悪は、ある意味、下手につくられた自動システムの害悪よりも限定的だ、ということです。たとえば、どこかでアナーキーについて講義すると、「サイコパスはどうするんだ? そんなシステムでサイコパスが及ぼす危険をどうするんだ?」といった質問を受けます。私は次のように巧く答えます。「少なくともサイコパスは軍隊を率いたりはしないでしょう」と。単刀直入に言うと、個人は限られた害しか及ぼせないのです。
自動システムとして様々な線引きがすでになされている社会よりもカオスのほうが良いとグレーバーが言う理由は、彼が民主主義(=おおよそアナキズム)を信じるからだが、それはこれからの人間に必要なものについて彼が思っていたことと密接に関係している。
彼は、これについて従来のアナキストのイメージとはまったく違うことを言っていた。
これからの人間にとって重要なのは「穏当さ(reasonableness)」だと言ったのである。
「reasonable」には「道理をわきまえた」「分別のある」「極端でない」などの意味がある。アナキストがもっとも言いそうになかった言葉をグレーバーは堂々と使っていた。彼はその言葉についてこう説明している。
穏当さというのはどういうことでしょう? 穏当さというのは通約できない価値のあいだで折り合いをつける能力です。そう、それには共感〔筆者注:原文ではempathy〕、そして理解が含まれます。またそれには、理解できないことがあっても、どのみちそれを考慮に入れなくてはいけない、ということを受け入れることが含まれます。
グレーバーは、「合理性でなく穏当さ」が重要なのだとも言った。他者を「judge」してはじいていくことは秩序ある社会を作るために合理的ではあるだろう。しかし、それはグレーバーの言った「穏当さ」とは違う。むしろわたしたちは多様性というカオス(混沌)を恐れず、自分の靴を履いてその中を歩いていけと彼は言っているのだ。ときに自分の靴を脱いで他者の靴を履くことで自分の無知に気づき、これまで知らなかった視点を獲得しながら、足元にブランケットを広げて他者と話し合い、そのとき、そのときで困難な状況に折り合いをつけながら進む。「穏当さ」はその日常的実践の中でしか育まれないとグレーバーは考えていた。それは大きなシステムでいっせいに、自動的に行えるようなことではないのだと。
「理解できないことがあっても、どのみちそれを考慮に入れなくてはいけない、ということを受け入れること」
そこまでが「穏当さ」に含まれるとグレーバーは言った。ならばそれは、多様性の時代が提示する落とし穴ではないだろう。むしろ、それはすでに目の前に広がっているカオスから目を背けず、前に進むための叡智であり、覚悟のようにわたしには聞こえる。
「あとがき」より