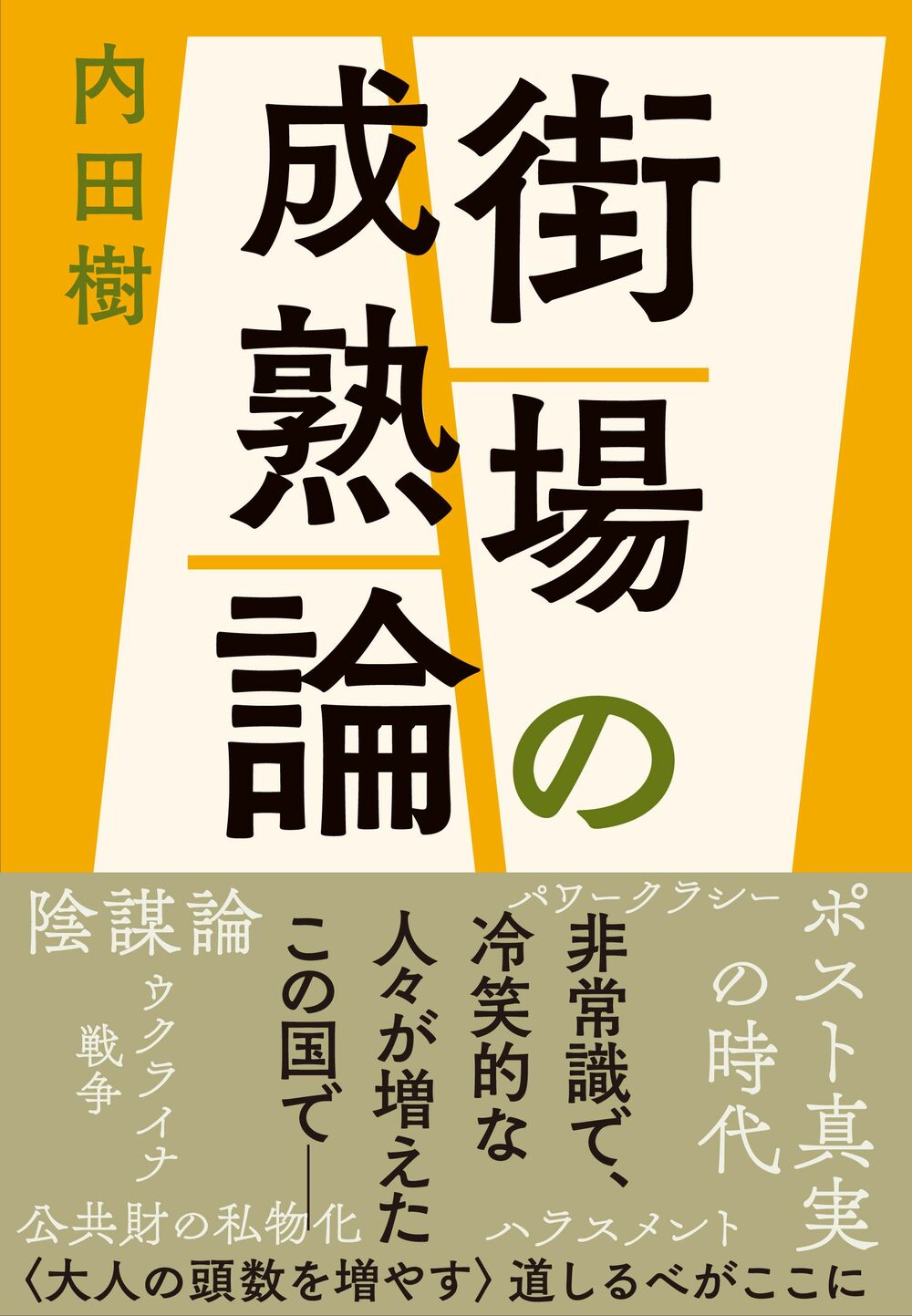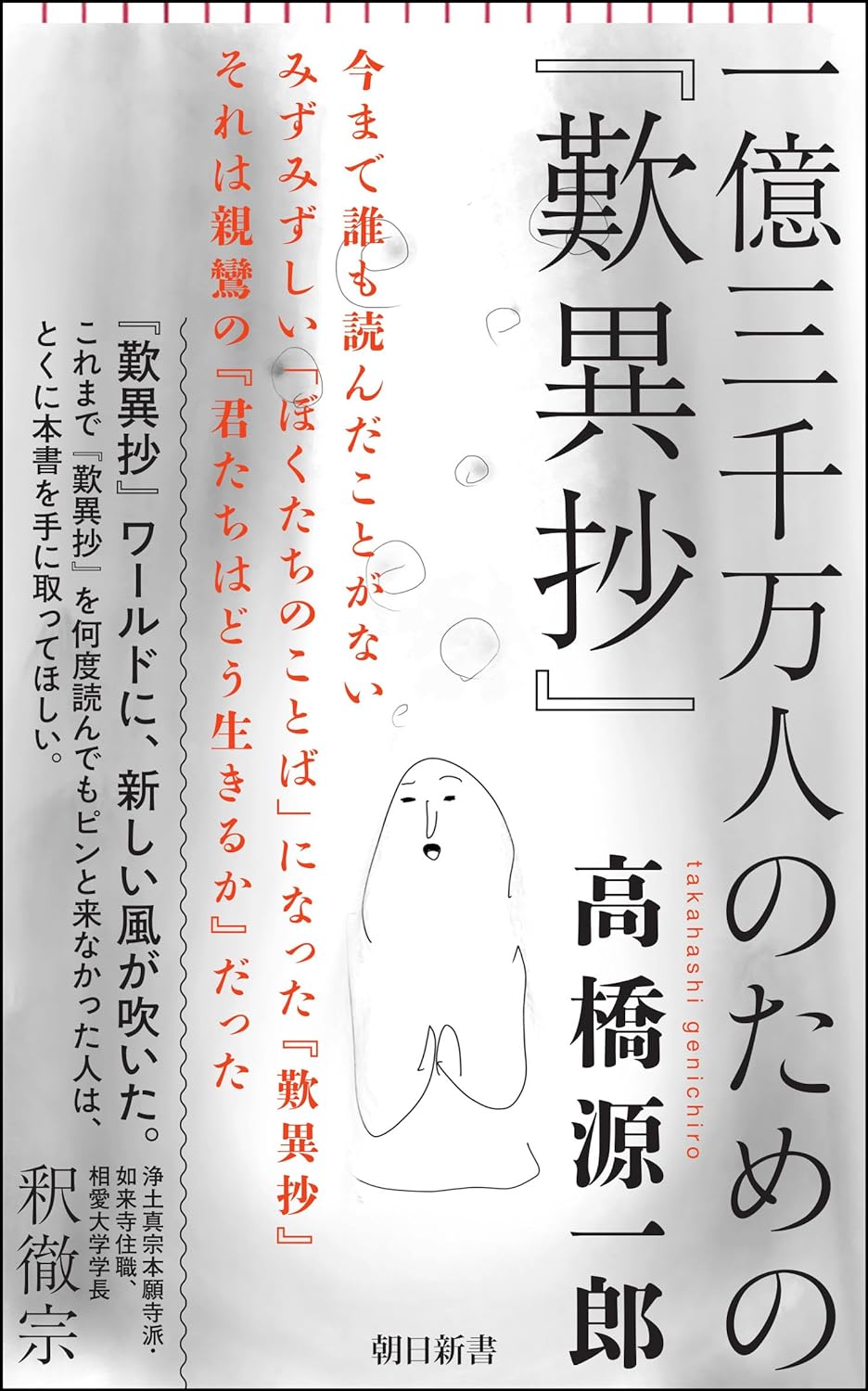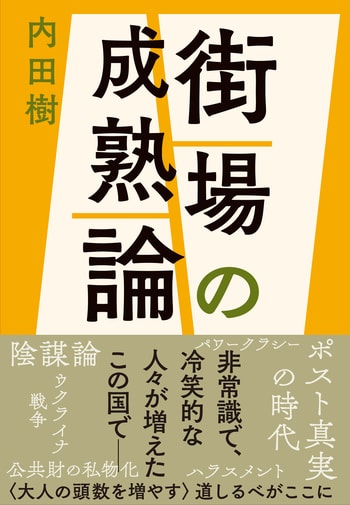『街場の成熟論』が話題を呼ぶ内田樹さんと、『一億三千万人のための「歎異抄」』を上梓した高橋源一郎さん。長年の盟友である二人が「成熟」をテーマに縦横無尽に語り合った。
◆◆◆
高橋 内田さんに会うのは数年ぶりですが、以前今や休刊になった『SIGHT』という雑誌で対談シリーズをずっと一緒にやっていました。そのときにはだいたい、まず僕から話して内田さんがレシーブする習慣でしたので、今日もそのスタイルでいきたいと思います。
内田 はい、よろしくお願いします。
高橋 僕も最近、『一億三千万人のための「歎異抄」』という本を出しました。「一億三千万人」という冠がついた本はこれで3冊目ですが、前の本の『論語』に続いて、親鸞の『歎異抄』を訳したんですね。本が出た後、そういえば、どちらも〈先生と弟子の話〉であることに気がついた。僕はいままで、いわゆる「翻訳」は3つくらいしか手掛けてなくて、『論語』の前は80年代にやった、アメリカの青春小説、ジェイ・マキナニーの『ブライト・ライツ、ビッグ・シティ』なんです。

内田 はいはい、当時読みました。すごく面白かったです。
高橋 あれは、すごく変わった小説で、二人称で書かれています。だから、文中ずっと「君は」って呼びかけているわけなんですが、そもそもそれを呼びかけているのは誰だろうと思ったんです。もちろん作者なんですが、その「語り手」は、主人公をずっと見守って成長を促そうとしている。つまり「先生」なんです。だから、僕は、「先生的な存在が誰かを成熟させる」物語を無意識で好んできたんじゃないか。そのことに、30年ぶりに気づきました。
でも、先生とはいっても孔子も親鸞もちょっと変わっていて、「教えない」先生なんですよね。例えば孔子は「仁とは何か」について『論語』で何十箇所も弟子たちから訊かれています。でも、弟子によって全部答えが違う。「君にとっての仁」を語るだけで、決して「正解」は教えない。
親鸞は親鸞で、弟子の唯円の質問に答えるけれど、さっぱり答えになっていない。親鸞になにか言われるたびに唯円が余計に混乱していくのがすごく面白い。
内田 教育ってそういうものじゃないですか。師は弟子を困らせる。徹底的に困らせる。「困る」のは、弟子が今使っている知的なスキームでは師の教えを処理できないからです。だから、それを手放すしかない。困った末にもう少し大きめの知の枠組みに切り替える。人間的成熟というのは連続的な自己刷新のことですから、自分の知的スキームに居着いたら成長できない。ですから、師匠というのは必ず弟子に答えの出ない難問を与えますね。
高橋 そう、だから師匠とか先生っていうのは、弟子を困らせるための存在なんだよね。そしてもうひとつ面白いのは、親鸞も孔子もやってることが実は「作家」と同じだと思うんですよ。
内田 どういうこと?
高橋 親鸞は、「称名念仏」といって、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば、あとは何もしなくてもいい、としています。でも、考えてみるとこれはかなりおかしな話で、当時から論争がありました。というか批判されていたんです。「念仏を唱えるだけで浄土に行ける? ただ言葉を呟くだけで、あとはなにもしなくていい? そんなのおかしいじゃないか」って。親鸞のやり方では、心の中では「アカンベー」していても念仏を唱えさえすれば救済されるなんてあり得ない、と。
しかし親鸞は「内心で何を考えていようと、ただ唱えるだけでいい」――つまり言葉だけでいいといったのです。これって作家の考え方なんですよね。僕たち作家には、そもそも、試験の問題に出てくるような「この作家の真意」なんてものはありません。出来上がった言葉が全てです。その言葉によって、作家がまるで何かを考えているように見えるそれが文学です。親鸞の考えでは、それは信仰も同じで、「南無阿弥陀仏」と唱えさえすれば「思った」ことになる。

内田 念仏だけ唱えていれば、心の中で信仰があろうとなかろうと構わない、極楽往生できますというのはやはり親鸞から弟子への極端な問題提起だと僕は思うんです。どう考えても「そんなこと」おかしいから。口先だけの念仏で宗教が成立していいはずがない。でも、師はそれでいいと言う。そこで弟子は悩むわけです。そして、最終的には「南無阿弥陀仏」という音声は確かに実在するけれど、自分の心の中に信仰が実在するかしないかは自分では検証できないという事実に行き当たってしまう。自分の信仰を自分で基礎づけることができない。たぶんその自覚が信仰のスタートラインなんじゃないかな。
高橋 そう、だから親鸞は弟子を一番根本的な問題で困らせてるわけなんですね(笑)。
内田 昔、僕の合気道の師である多田宏先生にロングインタビューしたことがあって、貴重な話をいっぱい伺って、テープレコーダーを片づけて、先生と並んで道場を出るとき、ふと「先生、最後にこんなところでなんですけど、武道修行の一番大事な心得はなんでしょう?」と聞いたことがあるんです。そしたら、先生が目の前の玄関口の看板に書かれていた「脚下照顧」という文字を指さして、「足元を見ろだよ、内田君」と答えたんです。僕はびっくりして、さすが武道の達人はすごいと感心したのです。
でも、それからずいぶん経ってから、ふと、僕がもしあの質問を吉祥寺サンロードを歩いている途中で口にしたら、そのとき先生はどう答えたか考えたんです。もしかしたら、「歳末大感謝」の看板を指して、「機を見る心だよ、内田君」と言ったかもしれない。吉祥寺駅まで着いていたら、JRの「そうだ。京都、行こう。」というポスターを指して、「直感に従えだよ、内田君」と言ったかも知れない(笑)。
たぶん、そうだと思うんです。多田先生はあらゆる場面で、弟子からの質問にそのつど即答しただろうな、と。孔子の「仁」もそうだと思うんです。弟子が「仁って何ですか?」と質問するたびに、そのとき手元にあったもので即答する。だから、そのつど言うことは違うんだけれど、すべてが繋がっている。それは、弟子により考えさせるということですね。
高橋 僕自身はリアルな師弟関係をもったことはないけれど、僕にとっての「先生」は先行する作家たちなんですね。トーマス・マンとか、カフカとか。
死んでいる人間はどうやって「先生」になるのか。まず本を開いて読むんです。テキストを読んでも、当たり前ですが、ほとんどの作家は死んだままです。ごくまれに生き返る作家がいる。「生き返る」とはどういう意味かというと、毎回違うことを言うんです。生きている人間のように。
死んでいる作家は何回読んでも同じことしか言わないけれど、カフカとか、マンのような作家は読むたびに前とは違うことを言ってるように、僕たちは感じる。どうしたらいいかわからないときに読むと、世界の掴み方を示唆してくれる。「こういうところ見たら?」と。「前回先生そんなことおっしゃらなかったでしょ」と言うと「あのときにはまだ君は、僕の言うことに気付いていなかったんだよ」と対話が生まれる。もちろん、それは、僕が成長した結果でもあるんですが、それがわかるためには、「先生」に出会う必要があるんだと思うのです。
何百年も前の人間でも、僕にとって生きている先生は雄弁に見える。僕は『歎異抄』を読んで、親鸞の750年後の弟子になった。孔子にいたっては亡くなって2000年もたって、弟子になった。弟子のニューフェイスというわけですね。

内田 今の話をうかがうと、僕とレヴィナスとの関係もそれとほぼ同じだと思いました。実際にレヴィナスに会ったのは1回だけで、あとは手紙のやり取りと、死せるレヴィナスの本をひたすら読んできただけです。最初の頃はレヴィナスが何を言いたいのか、まったく分からなかった。でも、「写経」するように翻訳をしてフランス語を日本語に置き換えているうちに、だんだんと言葉づかいが身体になじんできて、繰り返し読んでいるうちに、ああ先生がおっしゃりたいのはこういうことだったのか、と。少しずつ目が開いてきた。読解力というのは僕自身の人間的成長に相関していたんです。でも、すべての書物がそういう教化的な力を持っているわけじゃない。人間的な成長と読解力が相関関係にあったのは、僕にとってはレヴィナスだけです。
やはり文学でも哲学でも「カノン(正典)」と呼ばれるものは、無限の解釈・可能性に開かれている。ただ、たくさんの人の多様な解釈が水平にずらっと並んでいるわけじゃなく、一人の読者の解釈でも読者の人間的成長に応じて少しずつ深まってゆく。だから、解釈はどんどん変わるわけです。けれども、レヴィナスが「本当に言いたかったこと」を確定的に語ることは弟子には永遠にできない。
高橋 そういう仕方での成熟って確かにあると思います。先生という存在は、いわば鏡のように「前回気がつかなかったこと」を鮮明に映し出してくれる。その繰り返しを成熟と呼ぶのかもしれませんね。
今回『街場の成熟論』を読んであらためて思ったんですが、内田さんはあらゆることで本質的には同じことを言ってるじゃないですか。
内田 その通りです(笑)。
高橋 街場っていうのは実に便利な言葉で、これは「あらゆる場所」を指していますよね。“オン・ザ・ストリート”で、いわば“オール・オーバー・ザ・ワールド”。成熟ってどこかにこもってするものじゃなくて、いつでもどこでもどんな問題に関してもできる。だから、この本でもウクライナの話から安倍晋三の問題まで多岐にわたっていて、その都度言うことは異なるけれど、結局、みんな同じ地平にたどり着くのが面白いですね。

内田 「成熟/未熟」って、「真/偽」とか「善/悪」とか「正/否」というような二項対立じゃないんでしょう。未熟は成熟に至る途中の過程ですし、成熟だって「ここでおしまい」ということはない。成熟と未熟はアナログな連続体をなしている。だから、成熟した人間が未熟な人間に「屈辱感を与える」とか「処罰する」とか「排除する」ってことは本来あり得ないです。
僕は、人間世界のほとんどすべての事象はアナログな連続体であって、デジタルな二項対立で切りさばけるようなものって、実際にはほとんど存在しないと思うんです。だから、そのことを一生懸命説いているんです。だって、「こちらが完全な正義で、あちらが完全な悪だ」というタイプの二項対立的言説がどれほど世の中を不幸にしているか、日々思い知らされていますからね。
パレスチナ問題にしても、「内田さんはどっちが正しいと思いますか?」って聞かれるけれど、そんな問いにクリアカットに答えられる人の方がどうかしていると思う。どっちにも言い分があるに決まっているんですから。両方にいくぶんかの正義があり、いくぶんかの不正がある。僕らにできるのは、両者の言い分を聴き比べて、「こっちの方の言い分の方により説得力がある」というふうに判断するだけです。その「程度の差」を感知できる知性が大事だと思うんです。だって、世の中の対立って、全部「程度の差」の間で生じているわけじゃないですか。「五十歩百歩」と言いますけど、「五十歩」と「百歩」ではずいぶん違う。この五十歩の差が人の生き死にの境になることだってある。『成熟論』では、この程度の違いを感知して、判断できる計量的な知性がたいせつだということをあの手この手で書いているわけです。
高橋 まったくその通りで、あと内田さんはよく「大人がいない」という言い方をしますよね。僕が思う「大人」とは、正義を振り回すわけでもなく、何か決定的なことを言うわけでもなく、「ちょっと待って」と言える人。「それぞれに主張があるでしょうが、ここはちょっと一休みしませんか」と、“休戦”を提案できる人が成熟した大人だと、僕は思います。
内田 そうです。「ちょっと待って」ってすごく大事な呼びかけだと思います。昨今、生成AIテクノロジーが異常な勢いで進化していますけれど、今、これを一旦止めようという議論がアメリカで出てきています。techno-prudentialismというらしい。prudentialというのは「慎重な、細心の」という形容詞です。だから、これは「技術開発については慎重に主義」、ということになります。こういう考え方がアメリカでも出てきたことにちょっと驚きました。これはまさに「ちょっと待て主義」ですね。
業界はイノベーションだブレークスルーだと景気のいい話をしているけれど、それが雇用消失とか国民監視とかディープフェイクとか軍事転用だとかにどういう影響を及ぼすか、まだ分からない。それがもたらすベネフィットと比べてリスクがあまりに大きいテクノロジーについては、一度足を止めてその適否についてみんなで考えましょうということなんです。僕はすごく共感したんですよ。

高橋 いいですね。どんな技術もそうだけど、イケイケでやっていったあとの恐ろしさがあるから、減速が必要だと思います。
内田 「ちょっと待て主義」はこれまたアメリカはシリコンバレーで大流行している「加速主義」に対するカウンターだと思います。「加速主義(accelerationism)」というのは資本主義を加速して、その矛盾を限界まで先鋭化させて、それによって資本主義の「次のフェーズ」に突き抜けるという過激な思想なんです。これは非常に危険なものだと僕は思っています。加速主義によると、資本主義はもう限界に来ていて、命脈尽きかけているのだけれど、社会福祉制度や民主主義や人権思想のようなろくでもない制度があるせいで、むしろ資本主義は延命している。資本主義を終わらせるためには、そういう制度を全部廃止して、教育も医療も全部市場に丸投げして、金がないやつは野垂れ死にして、強い者だけが生き延びるという「生存競争」をするのがいい、と。ポスト資本主義の夜明けを迎えることができるのは、この「大洪水」を生き延びた強者だけで、制度にすがってかろうじて生きていた弱者たちは全部死に絶える。政治家でも学者でも、「日本なんていっぺん滅びればいい」みたいなことを言う人ってけっこういるじゃないですか。
高橋 ああ、わりといますね、左翼にも(笑)。
内田 右にも左にも、どちらにもいるんです。加速主義に対して、われわれもうろくしたおじいさんたちはついていけないから、「ちょっと待ってくださいよ」と。こちらは「減速主義」で対抗して、ブレーキを踏んで。
高橋 もごもごして何言ってるかわかんないし、僕らは足元もおぼつかないから、ゆっくりでお願いしますってね(笑)。
(その2へ続く)