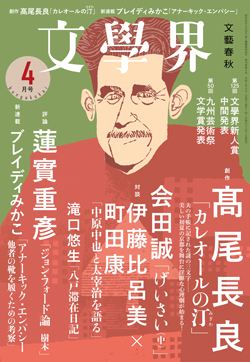
1.外して、広げる
エンパシーの日本語訳は「共感」でいいのか
いまから2年半前、わたしの息子が英国のブライトン&ホーヴ市にある公立中学校に通い始めた頃のことだ。
英国の中学校には「シティズンシップ教育」というカリキュラムがある。息子の学校では「ライフ・スキルズ」という授業の中にそれが組み込まれていて、議会政治についての基本的なことや自由の概念、法の本質、司法制度、市民活動などを学ぶのだが、その科目のテストで、「エンパシーとは何か」という問題が出たという。
息子は「誰かの靴をはいてみること」と答えたらしい。「To put yourself in someone’s shoes(誰かの靴をはいてみること)」は英語の定型表現である。もしかしたら、息子が思いついたわけではなく、先生が授業中にエンパシーという言葉を説明するのにこの表現を使ったのかもしれない。
「エンパシー」という言葉を聞いて、わたしが思い出したのは「シンパシー」だった。正確には、「エンパシーとシンパシーの違い」である。
わたしのように成人してから英国で語学学校に通って英語検定試験を受けた人はよく知っていると思うが、「エンパシーとシンパシーの意味の違い」は授業で必ず教えられることの一つだ。エンパシーとシンパシーは言葉の響きじたいが似ているし、英国人でも意味の違いをきちんと説明できる人は少ない(というか、みんな微妙に違うことを言ったりする)。だから、英語検定試験ではいわゆる「ひっかけ問題」の一つとして出題されることがあるのだ。

















