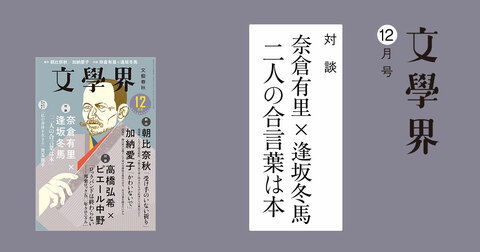戦争のさなかで文学を学ぶことになんの意味があるのか? 社会や愛をどう語れるというのか? 読者を作品世界にいざなう不思議な「体験型」授業を通じて、この戦争の時代を考えるよすがを教えてくれる青春小説にして異色のロシア文学入門。奈倉有里さん『ロシア文学の教室』を芥川賞作家で早稲田大学教授の小野正嗣さんが読み解く。

◆◆◆
文学を語るのは楽しいことだ。ところが授業や教科書という枠組みに入れられると、とたんにつまらなくなってしまう気がする。学問として教えることに向かないのではないか。文学の研究書・論文は、専門家たちの知見を広げ深めることには役立っていても、むしろ一般の読者を文学から遠ざけているのではないか。大学で文学を教えながら、そんな不安に駆られることがある。
そんなとき、興味深い授業が行なわれていることを知った。しかもロシア文学について。それが本書『ロシア文学の教室』である。どんな授業がなされているのか早速覗いてみた――。
ユニークな本だ。研究書とも文学エッセイとも違う。これは都内の大学でロシア文学を学ぶ学生たちの授業の様子を描いたフィクションである。授業では、主に十九世紀のロシア文学を対象に毎回一作品が取り上げられる。ゴーゴリの『ネフスキイ大通り』から始まって、トルストイの『復活』まで十二作品が扱われるラインナップ。授業は学生の積極的な参加が期待される少人数の演習形式である。
では授業を担当する二メートル近い巨漢の枚下先生は、学生たちに何を求めているのだろうか。課題作品を読んで内容をまとめ、関連する事実を調べて発表?
違うのだ。枚下先生が、湯浦、新名、入谷といったカタカナで表記すればロシア人の名前(ユーラ、ニーナ、イリヤ)に聞こえる学生たちに望むのは、作品を「体験」することなのだ。
では作品を「体験」するとはどういうことなのか。
たとえば、本作の主人公湯浦葵がチェーホフの短編を読むとき――「さて枚下先生が好きなのはどんな作品だろうとプリントを覗く。とたんにプリントの余白がすうっと陽の光に、文字が緑の葉になり、行間には川の清流が流れはじめる――」。湯浦は気づけばチェーホフの『コントラバス物語』の登場人物になっている。「僕はコントラバスを背負い、燕尾服にシルクハットをかぶって小川沿いの道を歩いている」。ゴーゴリの『ネフスキイ大通り』を開けば、夕暮れのネフスキイ大通り――「黄昏が家々や街路の上に降りてきて、点灯夫がはしごにのぼって街灯に火をともしていくころ、ネフスキイはふたたび活気づきはじめる」――に連れて行かれる。ネクラーソフの『ロシヤは誰に住みよいか』を読めば、すでにロシアの農民たちの暮らしのただなかにいる――「僕たちはだだっ広い田舎道にいた。踏み均された道沿いには距離を示す木の柱がぽつりぽつりと一定間隔で立っていて、道端にはごぼうのような草が茂っている」。
この「体験」とは、そう読書に夢中になっているときに私たちの誰もが経験していることだ。現実が遠景に退いていき、作品のなかに吸い込まれる。主人公に、あるいは脇役だろうが心惹かれる人物に感情移入し、その視点から世界を眺め、気づけばその人になりきっている。いや人だけではない。動物や植物や石にだってなりうる――ガルシンの植物たちが主人公となる短編を読んだときに、つる草として物語を「体験」した湯浦のように。物語を通じて、私たちは自分にあらざるものになる。本書は物語の持つこの魔法を、湯浦を通して私たちに追体験させてくれる。
この「体験」をするのは難しいことではない。ただ読めばよいだけだ。大学などで文学史や作品や作家についての先行研究が紹介されるのは、何はともあれ作品を読んでもらいたいからだ。ところが補助線であるべきものが抹消線になってしまう。ゴーリキーの『どん底』について学生たちがさまざまな解釈を示すのに耳を傾けながら、「どの解釈にしてもそれなりの背景があって、読みときながら『なぜそう言われているのか』を考えるのが大事になってきます」と枚下先生は言う。「おおよそ『イズム』なんてものは教科書的な分類か、政治的に肯定できるか否かを判断するための弁明のカテゴリにすぎませんので、そんなことは気にせず個々の事例をつぶさにみていくしかないんです」。
個々の作品をていねいに読む。枚下先生はもちろん作品の時代背景や受容や解釈の変遷についても話してくれる。しかしその案配が見事で、個々の作品との出会いを決して妨げはしない。学生たちの言葉を促し、それに答えながら各自の作品「体験」がより豊かになるよう言葉を添えていく。
そもそも、どうして私たちは物語を読むのか。枚下先生は「ロシア文学を素材として体験することによって、社会とは、愛とはなにかを考えます」とシラバスに書く。「社会」と「愛」を考えるとは、自分は一人ではないと認識することだ。社会は多数の個人からなり、愛は相手を必要とする。元来読書は個人的な営みである。現実世界でいやなことや苦しいことがあったときの逃避場所でもある。それがどうして私たちを他者と結びつける回路を開くのか。
二〇二二年二月二十四日にロシアがウクライナに侵攻し、その戦争がなおも続いているいま、ゲルツェンの『向こう岸から』を読みながら、湯浦はゲルツェンの苦悩に触れる。一八四八年の二月革命以降の社会的混乱のなかで起きたフランス軍による民衆の殺戮に衝撃を受けて、「どうしたら人の痛みを蔑ろにせずに思想を形成できるのか」と自問するゲルツェンに、自分自身の痛みを引き受けてもらったかのように支えられる。「噓みたいだ。ウクライナという文字を見ただけで思考が止まってしまいそうだった自分が、いままで目を背けなければ耐えられなかった多くのことを正面から考えられている」。
物語を深く「体験」することは現実からの単なる逃避ではない。かりに現在がすでに、「人間を愛情なしで扱ってもいい立場があると勘違いする」者たちが蔓延し、「暴力や虚偽や残虐が露呈し人間の尊厳の喪失が大多数の人々の一般的な行動規範となる恐ろしい時代」なのだとしたら、文学は、物語は、そして本書『ロシア文学の教室』はつねに私たちのそばにあって、解決策を与えるのとは異なるやり方で、私たちがそれぞれの現実に向きあい、生きつづける助けとなってくれる。