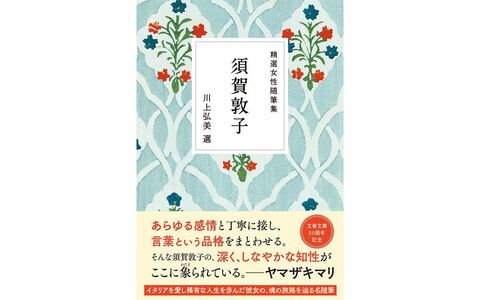長い時間をかけて作家になった須賀敦子は、らしくない作家ともいえる。
おそらく本人はみずからの作家というあり方を、肩書きや職業としてよりは、食べ、歩き、読むことと同じく本質的な「書くこと」の延長線上のごく自然な状態として意識していた。本や文章を書く、という行いは彼女にとって生きてゆくうえで自己確認のきわめて根本的な作業であり、人生における最大の命題であり続けたのだ。そして、本を読み、本を書くことをまっとうした人生の最終章で、彼女の生涯変わることのなかった書物への愛に目をとめた世界が作家という肩書きと、好きなようにものを書くチャンスを贈ったということなのだ、おそらく。
一九二九年、兵庫県に生まれた須賀はカトリック系の教育を受け、父親の転勤に伴って東京に移り住み、戦争でふたたび関西の学校に戻り、再度東京に赴いて大学を出ると五三年にはパリに留学、翌夏、イタリア語を学ぶために訪れたペルージャで忘れがたい印象を受ける。帰国後、働き始めるもこの思いは棄てきれず、五八年にローマ留学。ミラノのコルシア書店を中心としたカトリック左派の活動に共鳴し、六〇年にはミラノに移り、書店を動かしていたペッピーノと結婚、同時に日本文学の翻訳を始める。しかし夫は六七年に急逝し、七一年に帰国。大学で教鞭をとり、イタリア文学の翻訳を手がけながら、八五年に日本オリベッティの広報誌にイタリアを舞台にしたエッセイを載せ始め、九〇年『ミラノ 霧の風景』として上梓される。
例外的に遅咲きの新人作家、須賀敦子の第一作は、あらたに書き下ろされた「遠い霧の匂い」で幕を開ける。ミラノと霧と須賀敦子のイメージを決定づける文章だが、そこには実際に街をすっぽりと覆う霧と、須賀の追憶の中に宿命的に漂う霧と、とりわけミラノで過ごした、期待や熱意や驚き、出会いや失望や別れ、憂慮や充足や拠り所のなさに彩られた日々の果てに彼女が感じた死の影を孕む、いかにも文学的な霧がある。
「マリア・ボットーニの長い旅」は、人生を旅に見立てていた書き手が、自分を知らず知らずイタリアに導いた、裕福ながら常にごく自然体の女性の思いがけず数奇な人生と人物像を須賀一流の優しく皮肉なトーンで時間軸に沿って効果的に叙述した、読み応えのある一作だ。須賀の人物描写は力強い直観に根差し、痛快なほど主観的で、作品によっては当初の印象を時の経過とともに覆すことで鮮やかな効果を生むほどくっきりと、書き手の脳裏のイメージを具現化している。そして、通常は登場人物の多くが須賀流の口調で会話することで、家族や友人同士で話している時のような、ごく親密な雰囲気が醸し出される。だが、このマリア・ボットーニはくっきりと個性が際立ち、彼女に注がれた筆者の眼差しが変化してゆく様も、筆者が共感を覚えるイタリア人のあり方も自然に表れている。登場人物の死とともに筆が置かれることの多い結末を主人公が生き延びているのは書き手の気持ちの表れであり、自身とイタリアとの生きたままの関係を示唆しているのだろう。
五十代半ばから書き始められた作品集は、自身の才能に終始懐疑的だった須賀には予想外の反響と評価に遭遇する。作品の基盤には広範な読書で培われた世界観があり、それに沿って留学や海外生活や国際結婚がまだ稀だった年代に、優れて独創的な直観の赴くまま人生の旅の意味を求めながら個人的で、大いにロマン主義的な道を歩み続けた須賀の回想は多くの読者に受け入れられた。
『コルシア書店の仲間たち』で須賀は、前作のイタリア全般についての素描と考察から、自身の存在理由をかけたカトリック左派の活動拠点をめぐる群像劇へと照準を絞り込む。読者はそれまで伝えられることのなかった六〇年代ミラノの良心の一端を担っていた企業家や中・上流階級の人々の行動を、それとはまったく異なる、ごく貧しい人間たちの生態とあわせてうかがい知ることができるが、須賀の筆が冴えるのはやはり、包括的で年代記的な記述ではなく、個々の人物に光をあてるくだりだ。
『コルシア書店』はあの年代の、それもはっきりと限定されたミラノに向けられた筆者の目を反映して、作品全体が鎮魂歌のような翳りを帯びているが、“仲間”の一人であり、擁護者でもあった貴族の家柄のフェデリーチ夫人と、その家で開かれる夕食会での文化的なひとときを描く「夜の会話」の終盤では(“召使のサンティーナ”の闊達な人物像が味わい深い)、もっとも悲痛な時間帯が切りつめられた言葉で、しかしこの時も、そしてその後も決して直接的に踏み込むことなく語られる。その代わりそれは、特定の具体的な事実としてではなく、時も、場所も、主体も異なる死として、いくつもの作品の中でくり返し変奏されてゆく。
ミラノの物語を書き上げた須賀が次に取り組んだのは、自分をヨーロッパへと旅立たせた衝動と経緯、そしてみずからの魂の検証だった。『ヴェネツィアの宿』は、初めて日本を舞台にし、圧倒的な存在感を誇る父親や普段は物静かな母親を筆頭に、幼少期の須賀が深い感銘を受けた叔父や叔母ら、魅力的な人々が登場する作品を収め、そのまま私小説として読めるほど情緒的で淀みのない筆致で綴られているとともに、ヨーロッパ編と並行して読むことで、作家の心の歩みを確認できる教養小説のような骨格を有している。
「カラが咲く庭」は、不安や孤独とささやかな安堵が行き交う留学生たちの心模様を軽やかでメランコリックな語り口で表している。思いこみが激しく、しばしば突飛な行動力を発揮する若き日の須賀の姿が浮かび上がるが、学生寮を移る際にテルミニ駅で過ごした“宙ぶらりん”状態のユーモラスな描写はほほえましい。それは絶えず人との結びつきの中にあって、いつでも心の通いあう仲間たちを持ちながら、一定の環境に帰属することを潔しとしなかった須賀が生涯抱き続けた感覚に違いない。
『ヴェネツィアの宿』の終幕を飾るのは、父親へのオマージュ「オリエント・エクスプレス」である。わがままで自分勝手でぜいたく好きな性格に憤慨させられ、反発し続けたが、何よりも旅に焦がれ、異郷に惹かれる血を受け継いだ須賀が、列車にまつわる父の二つの指令を遂行する逸話だ。遠く離れた父のロマンとともに娘は娘なりのちょっとした心の震える冒険に出るが、その時、そして無事に約束を果たし、意識が遠のきつつある父親に旅の証を持ち帰る時の、父と娘の行き交う気持ちが静かな余韻を残す名品である。
続く『トリエステの坂道』では、それまで歩んできた軌跡を見つめていた目が現在から未来へとつながる道にも向けられ始める。須賀のエッセイではややとりとめなく話題が移行することがままあるが、ほのぼのと優しく軽妙で、それでいてしんみりとした味わいを持つ「電車道」は、庶民(書き手はあえて固有の共感をこめて“貧乏人”とも呼ぶ)のポートレートに秀でた手腕を見せる須賀の、どちらも母国語を忘れてしまった、市電病院に通うクロアチア人の神父と市営墓地をよちよちと歩くロシア人のおばあさん、そしてその孫娘の話である。根無し草のような、それでも飄々と人生を営み続けている人間たちに注がれる眼差しが温かい。
「マリアの結婚」は、モノクローム時代のイタリア式喜劇(ことによると書きながら念頭においていたかもしれない)を観るような懐かしさと可笑しさと奇妙な宿命観とともに語られる洒脱な一作だが、ここでも心情的距離が近すぎない人間について物語る時の絶妙にアイロニカルでなめらかな筆さばきが愉しい。
夫の家族を脅かし続け、ついには夫をも奪い去った暗い過去の影や、ミラノの“あまりにも一枚岩的な文化”の重みと対比させるように、須賀はフォルガリアの山村からやって来た義弟の妻シルヴァーナとその家族を、自由や開かれた未来の息吹を感じさせる存在として描く。「重い山仕事のあとみたいに」の寡黙で、しっかりと地面を踏みしめて生涯を送った生粋の山男として敬愛をこめて語られるグロブレクナー氏はその最高峰だ。いつもの如く物語は死で幕を閉じられるが、それはめずらしく晴れやかで誇らしげな死である。
須賀は『ユルスナールの靴』で新境地に踏み出す。いわゆるエッセイの枠にとどまらず(もっともそれは『ヴェネツィアの宿』ですでに凌駕していたが)、心酔する作家ユルスナールの文学世界や足跡と対峙して、作家としての自負と執筆力を奮い立たせようとした意欲作だ。“きっちり足に合った靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いていけるはずだ”の一行で始まる「プロローグ」では、多分にレトリカルになりつつ“靴”をめぐる連想がくり広げられる。それは世界を旅するための必需品であり、ヨーロッパそのものでもあり、方法論や手段であると同時に目標や憧憬でもあった。靴のメタファーは絶えず、自身の本来の居場所を問い続けた意識が必然的に生み出したもので、もとより一定の地に安住できる者には持ち得ない疑問であり、その意味で靴は幻想でもある。生来の“ノマッド”なら、たとえ靴を選べずとも歩いていってしまうはずだ。そして懐疑的な旅人は、行けなかった場所を、書けなかった文章を惜しむ。
続いて、“本を書く人は、わたしたちとは比べられないほどえらいのだ”と信じていた須賀は、一枚の「死んだ子供の肖像」から壮大なユルスナール宇宙への旅に読者を連れ出す。宗教、錬金術、ジョルダーノ・ブルーノ、求道、異端……たゆまざる想像力の翼は果てなき空を、魂の闇をぐいぐいかきわけてゆく。
“ちゃん”づけで呼ぶ幼友達に捧げられた深く抒情的な作品の中でも、心から人を愛おしむ才能に恵まれた語り手の静かで強い思いに胸動かされる「しげちゃんの昇天」。本人も折に触れて詳らかにしているように執筆活動において須賀が多大な影響を受けたナタリア・ギンズブルグの友人でもあり、彼女の文学を解き明かした評論家であるチェーザレ・ガルボリ邸を訪れた際の、文字通り夢のような体験をナイーヴに高揚した口調で伝える「チェザレの家」。幼き日々の記憶を淡々とふり返り、童謡のような情感を醸す「芦屋のころ」。人生のメタファーと物語の縦糸を求めて時を越える旅を続けた、いかにも須賀らしい独白のような「となり町の山車のように」。叔父叔母たちの大掃除の畳からイタリアへ、北伊の姑の田舎からユルスナールの北フランス、はてはオデュッセウスのギリシアへと軽々とタイムスリップしてゆく随想「大洗濯の日」。大阪のクズ屋さんたちの姿を物柔らかな光のもとに描き出した異色のレクイエムともいえる「ヤマモトさんの送別会」。“長年のイタリア生活を切り上げて帰国まもないころ”の情況を象徴する奇妙な体験談「なんともちぐはぐな贈り物」。人生の紀行文は、その時どきの心情を投影しながら書き続けられた。
ペッピーノ・リッカ宛書簡を読むと、それがまだ若い(が、若すぎるということはない)時期にいずれ夫となる相手にしたためられたことを差し引いても、須賀がまっすぐに人の心を摑む達人であったことがよくわかる。本質的にエッセイと変わらない読後感を抱かせるが、とりわけ夢のイメージは後年のいくつかの作品の原型となるものを髣髴とさせる。須賀は、現実の一場面や現実から触発されたイメージや“言葉の束”を意識の中に取り込み、その後もいく度となく回想し、その都度精製や再解析を加えるという、本人の言葉を借りれば“記憶の原石を絶望的なほどくりかえし磨きあげることで、燦々と光を放つものに仕立てあげ”るプロセスを飽くことなく続けた。そうした原風景ないし心象風景のインパクトに、現実を物語(あるいはその一節)として文学的(そう、多分にロマン主義的)に読みこなす破格の天分を備えていた須賀ならではの解釈が加味されて、あの独特の味わいを持つ文章が生まれたのだ。彼女にはみずからに与えられた物語の素材を、自身の解釈によって編纂し、自分の本としてもう一度書き直さなければならないという、おそらく誰もが持っているわけではない使命感があった。
須賀敦子が書こうとしたのは名文でも美文でもない、人の魂に寄り添う文章だった。もう一人の自分に、読み手ひとりひとりに語りかけるように、筆を進めた。だからしばしば、須賀の、聞いたことのある者なら思い出さずにはいられない深く、印象的な声で、自分だけに語りかけられているような心持ちになる。記憶の書棚があるとすれば、そこから一冊ずつ取り出して読み聞かせるようなかたちで、とっておきの思い出を紐解いてくれる。思い出の語りには時に綻びもあるが、須賀はさほど気にせず自分だけの言葉でかたくなな心を守りながら、大切に語り続けた――さながら小説の主人公がみずから自分探しの物語を追いかけつつ日記に書き綴るように。
彼女自身が常に学習者の姿勢でいたせいもあるかもしれないが、そんな須賀はまた、慕われる教師でもあった。少なからず(とりわけ現在形で思考する時)概念的な迷走に陥ることもあったが、長いあいだ胸中で推敲や編纂を重ねた遠い追想の物語は、おのずと作者の品格や人間性、試行錯誤を恐れず直観を信じて独自の世界を突き進んでいった人間の魅力をそのまま浮かび上がらせることになった。そこでは冷静さと温かさを併せ持った観察者の眼差しと情熱的で独断的な主観論者の言葉が霊妙に交錯していたが、その奥深くで力強い通奏低音を奏でていたのは、このひどく特異な語り手の数多くの人間的魅力の中でももっとも人を魅了してやまない、大きな愛だった。
これほどあからさまに様々なかたちの人間愛を、けれんみのかけらもなく表現できた作家は稀有なのではないだろうか――もちろん、そんなことはこれっぽっちも意識せずに。