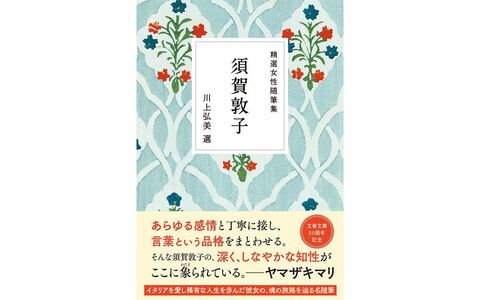「おていちゃん」の愛称で親しまれた沢村貞子は、平成元年(一九八九)に六十年に及ぶ女優生活に終止符を打った。引退の記者会見で「私は華のある女優ではないから引き際が肝腎。六十年もやったからもう十分。寂しくも悔いもありません」と語り、さらに記者の「ふつうのおばさんになるんですか」の質問に「私は、もともとふつうのおばさんです」と絶妙な答えをした。
『わたしの脇役人生』(新潮社、一九八七年)というエッセイ集があるように、長い女優人生を脇役に徹した。時代劇のスターだった兄の澤村國太郎を頼って映画界入りしたのは昭和九年(一九三四)。京都の日活太秦撮影所だった。
当初、二本立ての添えもので主役を演じたこともあったが、すぐに自分には才能もないし、スターとしての華もないと自覚し、脇役に徹しようと決意した。「齢をとっても、何とかひとりで食べてゆけるために……脇役になりたい、と望んでいた」(『わたしの脇役人生』)。
若い頃から脇役を望んだというのは女優として珍しい。何本か主役を演じたあと、撮影所の制作部長に、これからは主役ではなく脇役にしてほしいと言ったというから変わっている。
「齢をとっても、何とかひとりで食べてゆけるために」という決意に、現在でいう女性の自立の意識を見ることが出来る。女優という華やかな世界を夢見るのではなく、女優をひとつの職業として見ていた。
このあたりの醒めた意識は大女優でありながら女優であることにつねに冷静だった高峰秀子に似ている。二人がともに文章をよく書くエッセイストとして活躍したのは、この醒めた意識と関わるかもしれない。
以前、高峰秀子にインタヴューした際、話が沢村貞子に及んだ時、高峰秀子がこんなことをいったのをよく覚えている。
「あの人は賢いわよ。脇役に徹したでしょ。そのほうがずっと長続きするし、だいいちスターのように目立たなくていいのよ」
実際、沢村貞子の六十年という女優人生は長い。子役時代の長かった高峰秀子でも五十年。原節子は四十代はじめに引退したこともあって三十年足らず。田中絹代は五十年ほど。日本を代表するスターよりも脇役の沢村貞子のほうが長い。
明治四十一年(一九〇八)に浅草に生まれ、浅草で育った。純然たる下町っ子である。浅草がまだ東京の盛り場として随一のにぎわいを見せていた頃。
父親は小芝居で知られた宮戸座の座付作者。兄は前述のように若くして時代劇スターになった澤村國太郎。弟は戦後、映画界で活躍する加東大介。兄の二人の子供は長門裕之と津川雅彦。
「芝居もの」の一族に生まれているから生来の芝居好きと思いきや、『わたしの脇役人生』では「いつまでたってもこの社会に馴染めない」と言っている。
浅草は盛り場であるし、芸者の多い花街でもある。お祭りや行事が多い。確かにそういう華やかなところでありながら、他方で、地味で堅実な浅草がある。それを支えているのが「おかみさん」。
沢村貞子の母親も、「芝居もの」として派手に出歩く父親をつねに陰で支え、つましい家計をやりくりしながら四人の子供を育てあげた、浅草のおかみさん。沢村貞子は父親より、この母親に親しみを感じていたようだ。
小さい時から家事を仕込まれる。三つ年下の弟が子役として舞台に立つようになると、姉の貞子が小学生でいながら付け人のように弟の世話をする。家事の手伝いも厭わない。
沢村貞子は後年、『私の台所』(暮しの手帖社、一九八一年)など暮らし方の本を出すが、その下地は、堅実な母親によって子供の頃から作られていたといっていいだろう。
「芝居もの」の父親とは対照的に母親は地に足が着いた生活者だった。情にも厚く、近所のパン屋の女の子がお金を落して困っている時には、毎日のようにその子供の家でパンを買うようにする(本書所収「パン屋のしろちゃん」)。
大正十二年(一九二三)九月一日、沢村貞子が女学生の時、関東に震災が起きた。この時の母親は、いかにもしっかりもののおかみさんらしい。貞子をはじめ子供たちを先に逃がす。その時、貞子には小豆ご飯のはいったお櫃と三本の鰹節を、弟にはお湯のはいった鉄瓶を持たせた。とっさの的確な判断はまさに生活者の知恵だろう(「関東大震災のころ」)。
この母親が、ある時、自慢の丸髷をもうやめにしたと言い、「……もう、おつとめはすんだからさ」と呟くのは哀しい(「母の丸髷」)。無論、沢村貞子はその言葉の意味を大人になって知ることになるのだが。
沢村家の近所には、長唄の師匠という粋筋の女性が住んでいる一方、針仕事で女一人の暮しを立てている貞子の伯母のような地味な女性もいる(「長唄のお師匠さん」「お豆腐の針」)。貞子はその両方に目をやる。そして自分は「芝居もの」の家に生まれながらもっと知識が得たいと女学校進学を希望する。
大正十年(一九二一)、満十二歳で浅草に近い女学校、府立第一高等女学校(現在の都立白鷗高校)に入学。下町のエリート校である。父親は女に学問はいらないと反対したが、母親が支えた。ここでもおかみさんの力は強い。
入学試験にあたって小学校の先生は「兄弟が芝居の子役をしていることは絶対いわないように。府立はよい家庭の子どもしかとりませんからね」と注意した。役者が世間で卑しめられていた時代である。実際、女学校では同級生に「あの人の兄弟、河原乞食ですって……」と陰口を言われたこともあったという(「関東大震災のころ」)。
第一高女を卒業後、当時の女性としては珍しく女子大(日本女子大学師範家政学部)にも進学している。女学校の教師になることが夢だった。しかし、その頃から新劇に興味を持ち、昭和四年(一九二九)に、名優丸山定夫や山本安英らが立ち上げた新築地劇団に入団した。
昭和初年の日本は左翼運動が盛んになった時代。それに対し、大正十四年(一九二五)にはすでにそれを弾圧するために治安維持法が成立、昭和三年(一九二八)には最高刑が死刑になった。
新劇の世界は左翼運動が盛んで、若い沢村貞子は当時の夫の影響もありこれに加わり、治安維持法違反容疑で二度も逮捕されている。釈放後、離婚し、行き場のなくなった沢村貞子が選んだのが映画の世界で、京都にいる兄を頼った。俳優という「河原乞食」の世界はアウトサイダーが隠れやすい避難所だったとも言える。
左翼運動に関わったのは純粋に、社会の底辺にいる不幸な人たちを助けたい、働く人たちみんなが幸せに暮せる世の中を作りたいという若い正義感からだったが、当時はもうそれが通用する状況ではなかった。
映画界に入り、主役より脇役を演じたいと望んだのは結局は挫折してしまった左翼運動への思いがあったからかもしれない。
戦後、日本映画が黄金時代を迎えると脇役女優として引っぱりだこになった。本人は「便利重宝な女優」(「女優の仕事と献立日記」)と自嘲しているが、どんな小さな役でもきちんと打ち込む誠実さが多くの監督に評価されたのは間違いない。
出演作はあまりに数多く、代表作を選ぶのは困難だが、個人的には久松静児監督「警察日記」(一九五五年)の、捨てられた赤ん坊を引き取る田舎町の人情味あふれる料亭のおかみが忘れ難い。おそらく浅草のおかみさんだった母親のことを思い出しながら演じたのだろう。
私生活では戦前、俳優の藤原釜足と結婚したが十年ほどで離婚。戦後、新聞記者をしていた大橋恭彦(のち「映画芸術」を主宰)と結婚、添いとげた。結婚生活でも夫を立てて自分は脇役に徹している。「地味は粋の行きどまり」と言うが、地味の良さをよく知っている人だった。