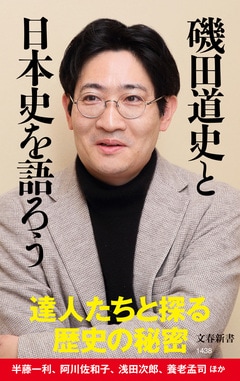二〇二二年(令和四年)一月九日から十二月十八日まで、三谷幸喜さん脚本のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』が放映され、たいへんな人気を博しました。本書『夜叉の都』は、それに先行して『別冊文藝春秋』に掲載されました(二〇二〇年七月号~二〇二一年七月号)。ドラマのタイトルにもなった鎌倉幕府の制度、「十三人の合議制」が成立してから後の幕府内外の激しい戦いを、北条政子を主人公として描いています。
日本で初めての武家の政権である鎌倉幕府を創始した源頼朝は、一一九九年(建久十年)の一月十三日に亡くなりました。あとを受けたのは頼朝と北条政子の長男である頼家でしたが、若い頼家の権力の暴走を抑えるという名目で、北条時政らは十三人の幕府重臣による合議組織を設置。それが幕府御家人の、すさまじいまでの権力争いの始まりでした。
梶原景時の失脚、比企能員の暗殺と比企一族の族滅、源頼家の暗殺、畠山重忠の誅伐、北条時政の幽閉、平賀朝雅の誅殺、和田義盛グループの敗亡、源実朝の横死と下手人公暁の殺害。そして朝廷軍との戦いである承久の乱での勝利。幕府を産み育てた経緯から御家人たちの忠節の対象となっていた北条政子は、弟の義時とともにこれらの争いを制し、肉親を次々に失いながらも、後代に引き継がれていく北条政権の基盤を構築しました。本書は政子の戦いを活写し、政争の相棒とも呼べる義時の死の真相までを語っていきます。
本書にも言及がありますが、鶴岡八幡宮で遭難した源実朝の遺体には、首がありませんでした。その首を葬ったとの伝承をもつのが神奈川県秦野市にある金剛寺です。言い伝えによると、三浦義村の郎党であった武常晴(武という地名は三浦半島に確認できます)は公暁の殺害を命じられた刺客の一人で、使命を果たす内に、公暁が肌身離さずもっていた実朝の首を取り戻しました。本来は主人・義村に届け出て恩賞を請うべきところ、常晴は世の無常を感じて鎌倉を離れ、秦野に人知れず葬ったというのです。
当時、秦野の領主だったのは波多野忠綱でした(本書にも少しだけ登場します)。波多野氏は源氏累代の有力家人で、頼朝のすぐ上の兄、朝長は同氏の女性を母にもち、この地で育っています。また「十三人の合議制」のメンバー、中原親能(大江広元の兄)とは密接な縁を結んでいました。ですので波多野氏がかりに金剛寺を整備して実朝の首を供養したとすると、その背後に広元あたりの存在を想定する(親能はすでに病没)ことができるかもしれません。
いま実朝のものという首塚を訪ねると、その近くに石碑が建っていて、実朝の和歌が刻まれています。「物いはぬ 四方のけだものすらだにも あはれなるかなや 親の子を思ふ」(『金槐和歌集』所収)。実朝の視線は、一心に我が子をグルーミングなどして世話する、イヌもしくはネコの姿にじっと注がれていたのでしょう。
母イヌや母ネコが幼子の面倒を見ている様は、慈愛に満ちています。それは現代でも中世でも同様だったはず。見る人すべての心は和み、癒やされる。ああ母の無償の愛情はなんと清らかで尊いものか、と。でも実朝はそうではなかった。言葉を話せぬ動物ですら、こうであるのに。それに比べてわが母は……。実朝が政子をどう見ていたか、この歌は何よりも雄弁に語っている気がしてなりません。
承久の乱への解釈として、いま学界では新しい説が台頭しています。従来は、後鳥羽上皇は鎌倉幕府の覆滅を切望していたと考え、疑ってもみませんでした。ところが上皇が「鎌倉を滅ぼせ」と呼びかける文書には、どこにも「幕府をつぶせ」とは書かれていない。「北条義時を討て」と書かれている。ということは、上皇が望んでいたことはあくまでも義時個人の追討であって、武家政権の否定ではない、というのです。
それに呼応するように、『承久記』という史料に描写される政子の姿は、実に弱々しく哀切です。彼女は参集した御家人たちに訴えます。「お前たちも知っての通り、わたしは次々に肉親を失ってきた。まずは長女、大姫を失った。最愛の夫、頼朝に死別した。次女の乙姫(三幡)、頼家、実朝の順に亡くなり、もう子どもは一人もいなくなってしまった。これで弟の義時にまで先立たれたら、わたしはどうやって生きていけばよいのか。みなみな、どうか憐れみをかけてほしい」。
歴史研究者の一人として、ぼくはこうした北条政子像に強い違和感を抱きます。彼女はめそめそと泣く女性なのだろうか、武士たちを泣き落とす女性なのだろうか、と。愛する夫・頼朝と産み育ててきた武家政権を守るため、あるいは実家である北条の権力を拡大するため。目的の解釈こそ色々あり得るだろうけれど、彼女は常に、戦いの渦中に凜然と立っていたはずです。勝利のためならば、わが子から「けだもの以下」と吐き捨てられてもやむなし。そうした覚悟をもって。
政子をそう捉えるからこそ、ぼくは『吾妻鏡』が描く政子に説得力を感じます。こちらでは、朝廷の挑戦に対して、彼女はまさに獅子吼します。「みなみな、今の生活があるのは誰のおかげであるか。すべて頼朝さまのおかげではないか。頼朝さまのご恩は山よりも高く、海よりも深い。しかしながら、このようやく得た安寧が、また再び朝廷によって破壊されようとしている。御家人たちよ、今こそ、戦うべき時である」。
こうした根本的なイメージの差異の提示に比べると、瑣末な指摘になってしまいますが、鎌倉時代には、「幕府をつぶせ」という表現はあり得ません。たとえば、後醍醐天皇は幕府を滅ぼすことに成功するわけですが、その思いを共有した大塔宮護良親王は、「朝廷を蔑如してきた伊豆の小役人の子孫、北条高時法師を討て」と呼びかける文書をたくさん作成しています。これを受け取った武士たちは、高時を討てとは幕府をつぶせということだな、と脳内で変換して、行動を起こしたわけです。さらに蛇足ですが、幕府という言葉自体が、当時はない。明治になって日本史という学問が始められ、便宜的に幕府の呼称が用いられました。ですから、「幕府をつぶせ」と言いたくても、直には言い表せなかった。そこで幕府の長である北条義時を名指しして、「義時を討て」という。「義時を討つ」ことが幕府を否定することと同義だったのです。
本のタイトル『夜叉の都』からして、答えは自明のようですが、解説の任を果たすため、ここはあえて問いましょう。本書の政子は、いったいどちらの政子なのか。めそめそ泣く政子でしょうか、獅子吼する政子でしょうか。
二者択一の大まかな指針は示しましたが、神が宿るのは細部です。政争の中で政子がどう変容していくか、とくに実家である北条家とどう関わっていくのか、そこに注意しながら読むことをおすすめします。政子の悲哀と決断を確認しながら読んでいくと、作者は最後に、もう一つ重大な仕掛けを用意しています。その中身を書いてしまっては台無しなので、拙い解説はここで筆を措きます。それにしても、伊東潤という方は、読者を飽きさせません。ストーリーテラーとしての力量、また歴史事象の読解力の深さに感嘆します。
味読に耐える名著です。つまらない歴史研究にまさる、骨太な仕事です。北条義時を主人公とする大河ドラマと比べてみると、一層の味わいがあるに違いありません。