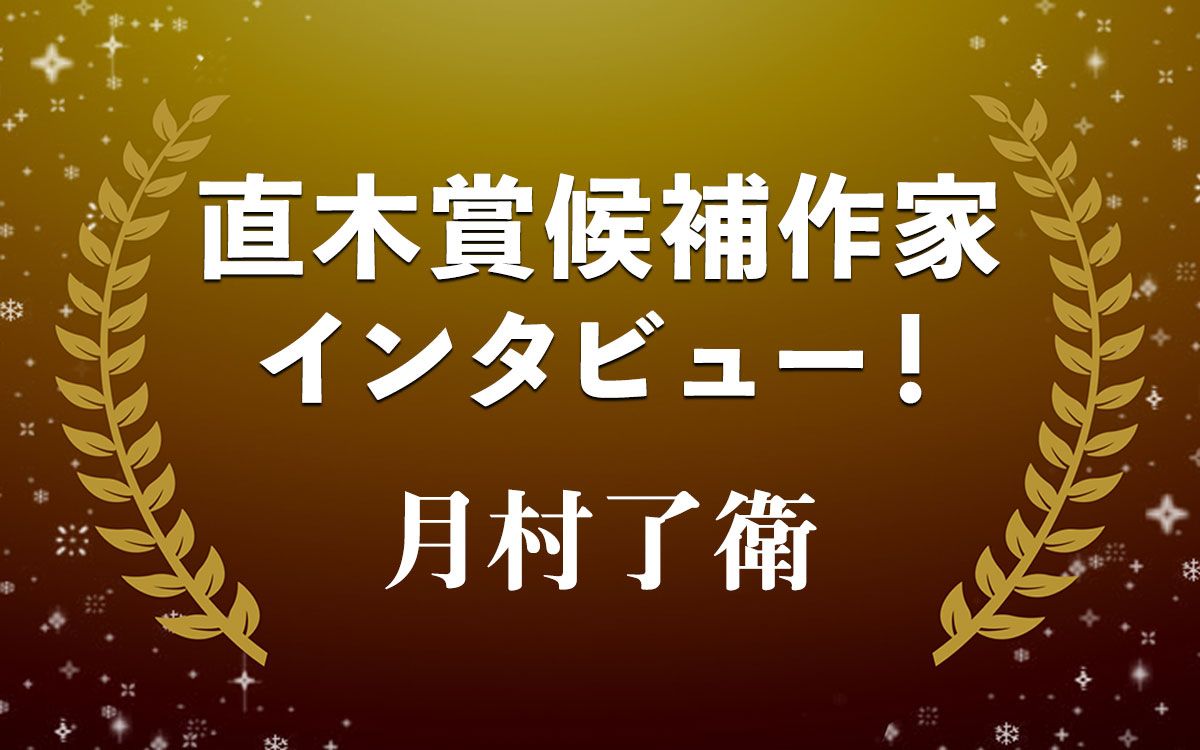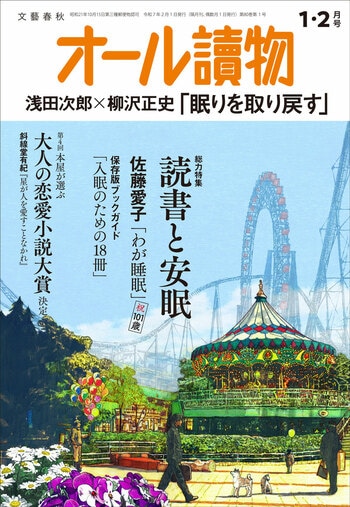〈この藩主「名君」か「暗君」か…直木賞候補作・木下昌輝『秘色の契り 阿波宝暦明和の変 顛末譚』〉から続く
きたる1月15日、東京築地の料亭・新喜楽にて第172回直木三十五賞の選考会が開かれる。作家・月村了衛氏に、候補作『虚の伽藍』(新潮社)について話を聞いた。(全5作の5作目/最初から読む)

◆◆◆
京都の闇を余すところなく描く
バブル期の京都。仏教最大宗派の一つである燈念寺派の宗務庁に勤める若き僧侶・凌玄は、仏堂がブルドーザーに潰される現場に立ち会ったことから、自宗の不動産取引の不正に気づいてしまう。糾すべきか、出世のために目をつぶるべきか。惑う凌玄の前にメフィストフェレスのように現れた、和久良という男。彼によって暴力団と引き合わされた凌玄は、金と利権渦巻く闇社会に身を投じていく。
「燈念寺派というのはもちろん架空です。仏教には大変多くの宗派が存在しますから、偶然にも実在のものに近づいてしまうことがないよう、用語や宗旨の扱いには苦労しました。しかし、燈念寺派の開祖や歴史などを、書かない部分まで作り込んだことは、凌玄は何を信じて何を大事にする人間なのかという肉付けにも役立ちました。寂れた寺の跡取りとして育った彼の生い立ちを考えた時に、小さな仏堂がある風景がふと浮かんだんです。冒頭の場面を書いた時にはまだ分かっていませんでしたが、凌玄の目の前で壊されたお堂と、彼の生家のお堂の景色とが重なりあった瞬間、宗派と個人、伽藍とお堂、という相似形がぱっと見えて、小説全体の構造が掴めたんです」
自宗に莫大な金をもたらす、地上げと表裏一体の再開発計画を進める中で、フィクサーとして暗躍する和久良の導きで際どい交渉や情報戦を制し、凌玄は燈念寺派の組織内でのし上がっていく。攻撃と懐柔を繰り返す上層部に囲まれ、清廉を好む同期僧・海照だけを相棒と恃む凌玄。同門の僧侶を信頼できない二人が、ヤクザに信を置いてゆく様が皮肉であり生々しい。
「他の作品でもヤクザを出すとなぜか評判がいい」と月村さんが笑う通り、利権に染まる教授と反目し京大を追われた学者肌の氷室、凌玄と接するうち得度を望むようになる紅林、にこやかだが得体の知れない和久良……と闇社会の個性がぶつかり合う様は圧巻。テンポ良い会話に引き込まれるうち、気づけば凌玄と共に荒涼たる境地へと至っている。特殊な舞台設定でありながら、実は人が誰しも抱えている業を抉り出す大作だ。
「信仰心ではなく、それぞれの信じるものを信じ、それに呑まれ、堕ちてゆく人間を描きたかった。凌玄にとっての仏教が、氷室の経済であり、和久良の出自なんです。自戒も込めてつくづく思うのは、人間には“見たいものしか見ない”愚かさがあるということ。人間関係でも、政治や社会でも、自分の欲や願望を投影して相手を見ているに過ぎない。そんな思いがタイトルの“虚”に繋がったのかもしれません」
月村了衛(つきむら・りょうえ)
1963年大阪府生まれ。早稲田大学第一文学部卒。2010年『機龍警察』で小説家としてデビュー。12年『機龍警察 自爆条項』で第33回日本SF大賞、13年『機龍警察 暗黒市場』で第34回吉川英治文学新人賞を受賞。15年『コルトM1851残月』で第17回大藪春彦賞を、『土漠の花』で第68回日本推理作家協会賞(長編および連作短編集部門)を受賞。19年『欺す衆生』で第10回山田風太郎賞を受賞。他著に『東京輪舞』『半暮刻』など多数。