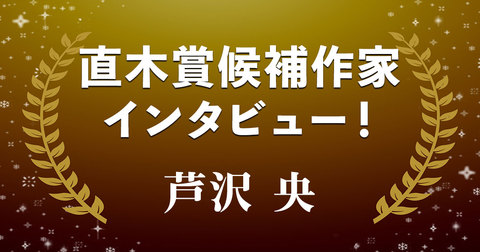『汚れた手をそこで拭かない』『火のないところに煙は』『夜の道標』など、近年のミステリ・ランキング常連でイヤミスの名手として知られる芦沢央さんによる待望の最新作『嘘と隣人』が2025年4月23日に発売になりました。
本作は、刑事の仕事を定年退職した平良正太郎が活躍する連作ミステリ。本作の魅力を皆さんにいち早く感じていただくべく、第2話「アイランドキッチン」冒頭を無料公開します。
思いついたのは、ホームセンターで種を見ていたときだった。
ミニトマト、バジル、チンゲン菜、きゅうり、こまつな、パセリ、枝豆、ししとう、アスパラ菜――棚にずらりと並んだ色鮮やかなパッケージの前で、さて、どれならベランダのプランターでも栽培できるだろう、と物色していると、後ろから軽く肩を叩かれたように唐突に、家を買おう、という考えが浮かんだのだった。
正太郎は、手にしていたチンゲン菜の種を棚に戻し、大股で店を出た。
定年退職したばかりの頃、ミニトマトの栽培を始めようと思いついたのも、この店にいるときだった。
なんとなく家でじっとしているのが落ち着かなくて、日曜大工用品でも見ようかとホームセンターに行ったはずなのに、気づけばミニトマトの種と土とプランターを買っていたのだ。
妻は、あら、と目をしばたたかせてから、懐かしいわねえ、と笑みをこぼした。家庭菜園だなんて孝則の小学校の宿題以来じゃないの、と。
そう言われて初めて、正太郎は自分がなぜミニトマトの種を買ったのかわかったような気がした。
もう二十年も昔のことだ。
息子が小学生だった頃は、正太郎の人生の中で最も忙しい時期だった。ほとんど家にも帰れず、たまに目にする息子の顔は寝顔ばかり。それでもたまたま、種を植える宿題の日が非番だった。息子が土の上にパラパラと種を落として水をかけようとしていたので、ちゃんと埋めないとダメだと声をかけ、隣にしゃがんで土に穴を開けてやった。
正太郎がやったのはそれだけだったが、ある日、いつものようにとっくに孝則が寝ているはずの時間に帰宅すると、息子は目をしょぼつかせながら起きていた。
どうしても、お父さんが食べてくれるところが見たいんですって、と妻にミニトマトが乗った小皿を差し出され、一瞬、なんだこれ、と思ったところで、ああ、あのときの種か、と気がついた。
息子にじっと見つめられながら口元に運び、わずかに萎んだ実に歯を立てた。ぷつりと皮が破れ、中から汁が溢れ出す。
酸味が強く、味に締まりがない。だが、うまいな、とつぶやいた言葉は本心だった。実際、ミニトマトをあれほど美味しいと感じたことは後にも先にもない――
そんな思い出をなぞる自覚さえないままに選んだ退職後の趣味だったが、いざプランター栽培を始めてみると、思いのほか性に合っていた。
毎朝ベランダに出て、新鮮な空気を胸に吸い込みながら様子を確かめ、水をあげたり雑草を抜いたりと世話を焼く。収穫したものを妻に渡すと、澄子は早速その日の食卓に並べてくれる。
いくつ種を植えて、いくつ収穫できたのかを記録して表にするのも楽しく、警備会社や自動車安全運転センターに再就職した同期たちからはせっかくの斡旋先を使わないなんてもったいないと口々に言われたが、これはこれで悪くない老後だと満足していた。
プランターは二つ、三つと増え、ベランダは手狭になってきている。
どちらにしても数カ月後には今の賃貸マンションの契約更新時期が来るから、次は庭がある物件を借りようとは漠然と考えていた。だが、考えてみれば、このタイミングで家を買うという選択肢もあったのだ。
退職金は手つかずで残っているし、貯金もそれなりにある。夫婦二人で暮らすくらいの大きさの家ならば、ローンを組まずとも買えるはずだ。妻にも長年迷惑をかけてきた。同じ神奈川県内とはいえ、異動のたびに引っ越さなければならない官舎暮らしは気苦労が多かったことだろう。労いを込めて、二人でのんびりした老後を過ごす家を贈るというのは妙案ではないか。
善は急げと、その足であざみ野駅前の不動産屋へ向かった。駅の東側に四軒、西側に三軒。記憶を探りながら駅前のコインパーキングに車を停め、東口を出てすぐ右にある売買専門のひまわり不動産を訪れる。
ガラスの全面窓に貼られた物件情報紙を順に眺めていくと、良さそうだと思うものが二つあった。庭付き一戸建ての中古物件と、〈ガーデニング好きにおすすめ!〉と書かれた分譲マンションの一階。どちらも値段は予算内で、娘夫婦の家へも行きやすく、間取りも2LDKと申し分ない。
ごめんください、と声をかけながら引き戸を開けた。文房具屋を営んでいた実家を思わせる、時代に取り残されたような空気を懐かしんでいると、はーい、どうぞーという間延びした声が返ってくる。
四つあるカウンター席の奥のパーテーションから、銀縁の眼鏡を首から下げた白髪の男性が顔を出した。
〈宅地建物取引士 山中昭弘〉という名札を胸につけた男には、見覚えがあった。名札ホルダーは少し左に傾いていて、それも記憶と重なる。
たしか十年ほど前、鑑取りで訪れた際に応対してくれた男性だ。当時は年配だと感じたが、印象がほとんど変わっておらず、未だに現役のところを見ると、正太郎よりも少し年上なくらいだったのかもしれない。
「気になる物件がありましたかね」
山中は十年も前に聞き込みに来た刑事の顔など覚えていないようで、のんびりと言った。
店内を見渡すと、いつから貼られているのかわからない横浜大洋ホエールズのポスターが目に入る。
正太郎にとって、不動産屋とはもっぱら聞き込みをするための場所だった。被害者や被疑者の金銭状況、近隣トラブル、人柄、生活習慣などの情報が集まっているからだ。
それ以外の目的で不動産屋を訪れたことは、一度もなかった。
警察学校を出た後は独身寮に入り、結婚してからはずっと官舎だった。引っ越しはもう嫌になるほどしているが、こうして不動産屋で物件を選んだことはない。退職と同時に今の賃貸マンションを選んだ際も、すべて妻に任せていた。
「夫婦で暮らす家を探しているんですが」
正太郎が切り出すと、山中は、心得たようにうなずいた。
「それじゃあ、とりあえずこれを書いてもらえますかな」と使い込まれたバインダーを差し出してくる。
正太郎はカウンター席に座りながら、〈受付票〉という紙を見下ろした。印刷したものを何度もコピーして使っているのか、線が粗く滲んでいる。
氏名や生年月日、現住所、職業、資金計画などの他、マンションか戸建か、新築か中古か、沿線、駅、駅徒歩分数、平米数、間取り、築年数、駐車場の有無などの希望を記入する欄があった。
一つ一つ考えながら書き込んでいくほどに、期待が膨らんでくるのを感じた。
それほど大きな家でなくてもいいが、とにかく広い庭が欲しい。庭仕事に疲れたら縁側に座って一服し――いや、防犯的には縁側ではなく、菜園を眺められる位置にベンチを置く方がいいだろうか。
できるだけ多めに物件を見せてもらおうと、心持ち幅を持たせて記入を終えると、山中は老眼鏡をかけながら向かいの席に座った。
「新築も中古もOK、マンションも戸建もアリ、と」
「どちらかと言えば戸建の方がいいが、築年数は二十年以内くらいなら問題ない。――もっと絞り込まないと、ものすごい数になりますかね」
「そんなことはないですよ」
山中は受付票に目を通しながら言う。
「見ていくうちに細かい条件を足していけば、あっという間に当てはまる物件は減っていくもんですからね。こだわらない部分は絞り込まない方がいいです」
「なるほど」
「逆に、絶対に譲れない、こだわりたいポイントはありますか」
山中が老眼鏡をずらして顔を上げた。
「野菜の地植えをやりたくてね。庭が広い方がいいんだが」
「だから戸建か、マンションでも一階が希望、と」
受付票に何かを書き込んでいく。
「外に貼ってあったやつなんかがイメージに近いなと」
正太郎が入り口を指さしながら言うと、どの物件のことを示しているか理解しているのか、他にもいろいろありますよ、と腰を上げた。
それまでのゆったりとした口調とは打って変わり、無駄のない動きで次々にキャビネットを開け、分厚いファイルから物件情報紙を取り出していく。
またたく間に机には物件情報紙が積み上がり、正太郎は感嘆した。
「大したもんですな。全部頭の中に入ってるんですか」
まあ、この稼業も長いですからねえ、と山中は目尻に皺を寄せる。
「今はこう、パソコンでね、不動産屋なら誰でも流通物件が検索できるようになってるんですよ。チェーンだろうが小さい街の不動産屋だろうが、それほど手に入れられる情報が変わるわけじゃない。でも、それだと検索条件にないものは取りこぼしちまうでしょう。そもそもパソコンはあまり得意じゃないですしね、アタシみたいなタイプには頭に入れておく方が楽なんですよ」
そうだ、あれもあった、とひとりごちながら机の引き出しからもファイルを取り、バサバサとめくって紙を取り出す。
「とりあえず庭というところ以外は緩めに条件を取って出してみました。ここから、これはないというものを外していきましょう」
物件情報を見始めると、なるほどたしかに駅徒歩分数が十一分だったり、予算を少しオーバーしていたり、築年数が二十年を超えていたりするものが混じっていた。
「おそらく、いろいろ見ていくうちに、庭以外にも譲れないところがはっきりしてくるはずですよ」
山中の言葉通り、最初は特に気にしていなかった条件も気になり始めた。ある物件でバリアフリーという言葉を目にすると、三階建ては歳を取った後使いにくいかもしれないと引っかかり出す。間取りは2LDKあれば十分だと思っていたが、3LDKの物件情報紙を見て、孝則や歩美が孫を連れて遊びに来たときに泊まっていってもらえるなと思ったら、部屋数は多いに越したことはない気がしてきた。
いまいちと思うものを脇へ除けていくうちに、あれほど大量にあると思っていた物件情報紙は六枚に減っていた。
「本当に減るものなんですな」
正太郎がつぶやくと、山中は、そういうもんです、と笑った。絞り込まれた物件情報紙を見比べ、ふむ、と顎を撫でる。
「意外にマンションもアリですか」
「いや、初めはなんとなく戸建の方がいい気がしたんだが、よく考えたら老後を過ごす家なんだし、階段がない方が楽でいいのかもなと」
「それは確実にそうですよ」
山中はきっぱりと言った。
「歳を食ってくると、どうしても足腰にきますからね。旦那さんは大丈夫でも、奥さんの方が先に弱っちまうこともある。ずっと戸建に住んできたけど、老後はマンションに住み替えたいって人も少なくないです」
「そうなんですか」
「実際、マンションってのは歳を取ってくるほどいいもんだと思いますよ。修繕とか清掃とかね、管理会社がやってくれるのは大きい。いちいち個人で業者を探して依頼するのは何かと面倒でしょう」
山中は、よし、それならまだ少しありますよ、と言って立ち上がった。再びキャビネットを開け、物件情報紙を引き抜いて机に置く。
正太郎は追加された二枚を手に取り、間取りと数枚の写真が載った方に目を落とし――あれ、と思った。
ここは、知っている。
焦げ茶色とクリーム色がスタイリッシュに組み合わされた外壁の八階建ての建物、エントランスの左右には小さな二体のシーサーが置かれている。
山中は正太郎の視線の先を確認し、「ここも人気の物件ですよ」と楽しそうに言った。
「築年数は少しいってますが、この部屋はフルリフォームしてますし――」
弾んだ声が遠ざかり、記憶が蘇ってくる。
たしか警部補に昇任する直前の頃だから、今から十一年前。
グランドシーサーあざみ野は、正太郎がこの街の所轄で刑事をしていた頃、捜査のために何度も訪れたマンションだった。
*
県警の通信指令室に一一〇番が入電したのは、二〇〇八年七月十日の深夜一時過ぎ。
通報者は、グランドシーサーあざみ野の二階に住む舟島洋平という三十四歳の男性だった。
寝付けずにテレビを見ていたら、外から何かが破裂するような大きな音が聞こえた。何事かと確認しに行ったところ、死体を発見することになったという。
死因は高所からの転落による脳挫傷と内臓破裂。即死だった。
亡くなったのは、同マンションの八階に住む豊原実来、二十八歳のOLで、初動捜査に当たった機捜が初めに下した判断は自殺だった。
遺書は見つからなかったが、現場の状況に事件性は見られなかった。彼女は二カ月前から心療内科に通院しており、鬱病との診断書を勤め先である三丸百貨店に提出して休職していたという。
この時点で問題になったのは事件性の有無ではなく、彼女が休職する前、ゴールデンウィーク明けの五月七日に、取引先の人間の家族から嫌がらせを受けているという相談のため生活安全課を訪れていた事実だった。被害届を受理しなかったことが自殺の原因だと遺族から糾弾されたのだ。
事の始まりは、二〇〇七年の十一月。
当時、豊原実来は三丸百貨店の子ども服売り場で仕入れ担当の仕事をしており、卒園・入学シーズンに向けてキッズフォーマルウェアのコーナーを拡充するために、有限会社トレインに発注をかけていた。
商品は期日までに届いたものの、サイズ間違いがあった。納品担当者である有吉勝吾に連絡を取ったところ、すぐに手持ちで正しい商品を納品すると言う。
だが、指定された時間になっても有吉は現れなかった。
会社に問い合わせたが、納品のために出発したはずだと言うばかりで埒が明かない。どうしてもその日に届かないと困るほど切羽詰まった状況ではないとはいえ、連絡がつかなければ帰るわけにもいかない。
ちょっとルーズすぎるのではないかと同僚に対して愚痴をこぼしていると、定時を過ぎた頃になって、有吉が納品に向かう途中の路上で脳卒中を起こして倒れ、死亡していたことがわかった。
有吉は連絡もせずに救急搬送されてしまうのはまずいと慌てたらしく、救急車を呼んでくれた人に、三丸百貨店の豊原さんに連絡してくれ、申し訳ない、後で必ず納品すると伝えてくれ、と繰り返していたという。
だが、残念ながら彼はそのまま命を落とし、結局、実来に対する伝言が最期の言葉になってしまった。
実来は後味の悪さを覚えた。
仕事のことなんて気にしなくてよかったのに。たしかに納品が遅れて自分は困ることになったけれど、命を落とすような緊急事態だったのなら仕方ない。自分なんかへの言伝てはいいから、亡くなる前にご家族と話せたらよかったのに、と。
もちろん、有吉自身、これで自分が死ぬなどとはつゆも思わなかったからこそ、仕事のことを気にしたのだろう。直近の約束のことしか頭になかったのだ。
三丸百貨店としても、そういう事情だったのならと咎めることはせず、弔意を示した。商品は翌日には別の担当者によって納品され、事なきを得たという。
だが、話はこれで終わらなかった。
亡くなった有吉勝吾の妻、希美が豊原実来に電話をかけてきて抗議を始めたのだ。
きっと夫は、倒れる前には具合が悪いのに気づいていたはずだ。あんたが急な仕事なんて寄越すから、夫は病院に行く時間が取れずに死んでしまったんだ、と。
実来はその場で上司に相談し、上司が代わりに電話口に出た。お悔やみの言葉を述べながらも、有吉が手持ちで納品することになったのはトレイン側が納品する商品のサイズを間違えたせいであったこと、有吉は具合が悪いのなら社の他の人間に頼めたはずだということ、脳卒中では前兆があるとは限らないことを丁寧に説明した。
上司は、婦人・子ども服売り場に配属される前、クレーマー対応の専門部署であるお客様相談室にいたこともあり、謝罪をする際の線引きを心得ていたらしい。
有吉希美は一旦引き下がり、以降は五日に一度ほどのペースで様々な偽名を使いながら電話をしてくるようになった。
実来が出ると、あんたは夫が死んだことを何とも思わないのか、とまくし立てる。実来は相手が有吉希美であるとわかった時点で、できるだけ電話を保留にして上司や同僚に代わってもらうようにしていたが、希美の長電話につき合い、謝ってしまったこともあった。
あんたさえいなければ、あたしは夫に最期の言葉を遺してもらえたはずだったのに、と言われたからだ。
それは実来自身も申し訳なさを感じていたことだったから、自分は関係ないと割り切ることができなかったのだという。
豊原実来は、善良な女性だったのだろう。
そして、時にそうした善良さは、困った人間の困った性質を増幅させてしまうことがある。
以来、有吉希美は毎日のように三丸百貨店を訪れては、実来が謝罪した一点に内容を絞り、あんたのせいだ、と泣きわめくようになった。
報告を受けた上司は、希美本人を説諭するだけでなく有限会社トレインに対しても、おたくの社員の家族がこれ以上こうした行為を続けるようなら、今後の取引は考えさせてもらう、と通告を出した。
この社としての対応も、特段誤りだったとは思えない。むしろ、一社員のためにきちんと対応する良心的な会社だと言えるだろう。
後から調べたところによれば、この段階でトレイン側も有吉希美に対し、注意を行っていた。お気持ちはわかりますが、取引先に責任はありません。こういうことをされるとあなたが業務妨害の罪に問われることにもなりかねませんよ、と。
有限会社トレインとしては、事は三丸百貨店との関係だけに留まらなかった。もし社員の家族による嫌がらせが原因で取引を切られでもしたら、他の百貨店でもブランド展開が難しくなるかもしれない。さらに悪評が広まれば、顧客の耳に入ってしまうことさえ考えられる。
ひとまずこの念押しが効いたのか、希美が三丸百貨店を訪れることはなくなった。
だが、代わりに希美は、実来個人をつけ回すようになった。
会社のそばで待ち伏せし、尾行して住所を特定し、マンションの前で声をかける。あんたのせいだと責め続け、謝罪をしても受け入れない。見かねた実来の恋人が通勤の行き帰りに同行するようになると、あたしからあの人を奪ったくせに、と逆上した。
この辺りから、希美の主張は妙な方向へと傾き始める。
希美自身、夫が仕事中に急死したこと、取引先の社員に納品について連絡することで頭がいっぱいで、自分への最期の言葉を遺さなかったことは、自分の言動を正当化する理由としては認められないと理解したのだろう。
希美は、「夫と豊原実来は不倫関係にあった」と主張し始めた。
だから夫も、最期に自分へではなく実来に電話しようとした。そもそも実来が有限会社トレインに発注をかけたのも、夫に対して好意があったからだ。百貨店での展開を望んでいた夫は、取引をちらつかされて応じてしまった。実来は夫への個人的な感情で取引を始めたから、夫が亡くなった途端、取引を切ると言い始めたのだ、と。
実来からすれば、まったくもって寝耳に水の話だった。
そんな事実は一切ない。そもそもトレインに出店を呼びかけたのはバイヤーであって、実来ではなかった。取引を切るというのも、実来の独断でどうこうできる話ではない。
実来は有吉勝吾とは発注と納品に関する連絡を取ったことしかなく、携帯の番号さえ知らなかった。
第一、希美だって、不倫などという話はそれまで一切していなかったのだ。
周囲から相手にされないことに不満を抱いた希美が、何とかして味方を増やすために虚言を吐き始めた――実来を含め、当初からの経緯を知っている人間からすれば、それは疑いようもないことだった。
「異常な人間だとはわかっていたけれど、あそこまでヤバいやつだったとは思わなかった」というのは、実来の恋人だった岡本春平が後に語った言葉だ。
だけどね、刑事さん、それよりヤバかったのは、そんな嘘を信じるやつがいたってことなんですよ――
希美はまず、岡本に「あんたも裏切られていたのよ」と言い聞かせようとし、彼が動じないと知ると、三丸百貨店の本社宛に匿名でクレームを入れ、実来の住むマンションのすべての郵便受けに豊原実来を告発する文書を投函した。
少し前から夫の様子がおかしかった。帰りが遅くなり、帰宅後も、仕事でトラブルがあったと言って家を出ることが増えた。夫を問い詰めて携帯を見せてもらうと、たしかに通話先は百貨店だったが、興信所を使って調べた結果、取引先の女である豊原実来が浮気相手だった。豊原実来は淫乱女である。夫をたぶらかした豊原実来を絶対に許さない――
実のところ、これをそのまま鵜吞みにした人はそれほどいなかった。
ノートの切れ端にひどく感情的な筆致で書き殴ったものをコピーしたらしく、一見して異常さを感じさせる怪文書だったからだ。
だが、それでも、豊原実来が面倒なトラブルに巻き込まれているということは伝わった。そして、詳細についてはともかく、不倫自体は本当の話なのだろうと考える人も少なくなかった。
実来と両親は慌てて近所に真実と経緯を説明して回ったが、後手に回った分弱かった。
なかったことを証明することは非常に困難だ。しかも、不倫相手だとされた有吉勝吾は既に亡くなっている。
何より、取引先の男性と不倫をした女というのは理解しやすくても、急死した夫が死の間際、仕事相手に連絡をしようとしただけでその相手をつけ回し、嘘まで言いふらして追い詰める人間は理解しづらい。
実来の置かれた状況は、あまりにも唐突で理不尽なものだった。自分の日常は平穏に続いていくのだと信じたい人間としては、豊原実来は人様の夫を寝取ったから、報いとして悪い噂を流されている、という筋書きの方が受け入れやすかったのだろう。
希美は常識では考えられない言動をしたからこそ、ありがちな嘘を信じさせることができたのだった。
実来が怪文書を手に恋人の岡本と署の生活安全課に相談に訪れたのは、この段階だった。
署員は時間をかけて被害状況を聞き、調書を取った。
対応した上田佳苗という女性警察官は、すぐに警察のデータベースで有吉希美の情報を調べた。そして、彼女が六年前、元夫へのストーカー行為で接近禁止命令を出され、それに違反して罰金刑を受けていたことを知った。
該当行為は裁判所の判決が出て以降収まったようだが、経歴から考えて、豊原実来の訴えに真実味があると感じたという。
けれど、当然のことながら、実来に対して有吉希美の前科を話すわけにはいかなかった。名誉毀損罪、業務妨害罪に該当するかを検討しなければならない以上、状況を正確に把握しなければならない。できるだけフラットに事実関係、出来事の日時を整理していったそうだ。
だが、警察に来るまでに疲弊しきっていた豊原実来は自分の訴えが疑われていると感じ、もういいです、と泣きながら話を打ち切ってしまった。
実来は心療内科に通い始め、鬱病との診断書をもらって休職した。
外に出るのが怖い、と引きこもるようになってしまった実来のところへ、岡本は足繁く通い続けた。
そんな時期がひと月ほど続いたある日、岡本は、いっそこのまま仕事を辞めて結婚するのはどうだろうと提案した。
ひどい災難に巻き込まれてしまったけれど、職場の同じ部署の人たちは実来が完全なる被害者であることを知っているし、転職するとなれば応援してくれるだろう。こんなことのために退職するのは不本意だろうが、いつまでもあの女にかかずらっていたのでは人生がもったいない。ちょうど自分には大阪本社への転勤の話が来ていたところだから、それを受けて二人であちらに新居を構え、新しい勤務先を探してはどうか。物理的に距離ができてしまえば、あの女もさすがにあきらめるだろう、と。
実来は提案を受け入れた。そこから少しずつ精神状態が上向いてきていたという。夫の転勤に合わせて転職するというのは珍しくない話だ。周囲に残された誤解も、ほとぼりが冷めれば時間をかけて解いていくことはできる。
何より自分には、信じて支えてくれる恋人や家族がいる。何もすべてを壊されてしまったわけではない――岡本に対してそんな言葉を口にし、岡本も、やっと前向きな彼女に戻ってくれたと安堵していたそうだ。
それから二週間後、二人で宮崎県にある岡本の実家を訪れた。新居はどんな間取りがいいかと話しながら帰宅し――けれど、その三日後、豊原実来は自宅マンションの八階の外階段から転落して死亡した。
自殺のわけがない、と岡本は主張した。
実来は新しい生活に対して希望を持っていた、こんなタイミングで自ら命を断つわけがない、と。
ただ、実来の両親の話では、岡本の実家から戻って以降、実来は様子がおかしかったという。疲れた、と言って部屋に閉じこもり、食事もろくに取っていなかったそうだ。
両親としては、不安を抱きつつも、本当に疲れているのだろうと考えていた。久しぶりの外出で飛行機にまで乗ったのだし、そうでなくとも婚約者の両親に会いに行くというのは緊張するものだ。帰宅した途端にどっと疲れが出たのだろう、と。
しかし、その後に転落死したとなれば、話は変わってくる。
いくら精神状態が回復傾向にあったとしても、揺り戻しというものはある、というのが、実来を診察していた心療内科医の見解だった。
新生活への期待が芽生えたからこそ、もし引っ越し先にも有吉希美が現れたら、という不安はかき消せないものになったのではないか。どうせまたどん底に突き落とされるくらいならば、幸せな可能性が残っているうちに人生を終わらせてしまいたい――鬱病の患者の中にはそうした考え方をする者も少なくないらしく、起き上がることもままならない急性期よりも、多少動けるようになった回復期の方が要注意なのだと心療内科医は語った。
実来の両親は、聞き取りを行った機捜隊員に対し、どうして被害届を受理してくれなかったのか、もっと真摯に対応してくれていたら、娘はここまで追い詰められることもなかったのに、と訴えた。
捜査員個人としては、不憫に思う気持ちもあっただろう。けれど警察官として、ここで、謝罪することはできなかった。それは公的機関である警察の判断を否定することだからだ。非があったと一度認めてしまえば、取り消すことはできなくなる。生活安全課の対応について不適切な点はなかった旨を説明し、弔意を示す以外に、一捜査員にできることはなかった。
実来の両親も、本当に警察にすべての責任があるとは思っていなかったようだ。どうしてちゃんと娘の話を聞いてやらなかったのか、ずっとそばについていれば、夜中に家を出たのにも気づけたはずなのに、と自分たちを責め、捜査員たちも、これ以上警察にできることはないと判断して豊原家を辞去した。
だが、翌日、「マンションの外階段で人影を見た」という女性の声の通報が入ったことで状況が一変する。
目撃者は名乗らず、証言の信憑性も不明だったが、何やら二人の女性が揉めている様子だった、会話の内容は聞き取れなかったものの、片方は中年のように見えた、という情報を受け流すわけにはいかなかった。
飛び降り自殺だと断定したところから一転、殺人事件である可能性が浮上したのだ。
真っ先に挙がった被疑者は、当然のことながら有吉希美だった。
機捜から捜査を引き継ぐことになった所轄署の刑事課強行犯係は、有吉希美に任意同行を求め、改めてマンション住民への聞き込みを開始した。