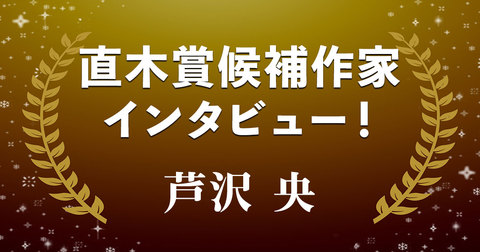『汚れた手をそこで拭かない』『火のないところに煙は』『夜の道標』など、近年のミステリ・ランキング常連でイヤミスの名手として知られる芦沢央さんによる待望の最新作『嘘と隣人』が2025年4月23日に発売になりました。
本作は、刑事の仕事を定年退職した平良正太郎が活躍する連作ミステリ。本作の魅力を皆さんにいち早く感じていただくべく、第1話「かくれんぼ」冒頭を無料公開します。
歯が痛いことには、五日前から気づいていた。
そのうち治まるだろうと市販の鎮痛剤でごまかしていたものの、これは無理だと認めざるをえなくなったのが、昨日の就寝前。氷枕で冷やしながら眠りにつき、今朝歯医者に電話をする頃には、元々どの歯が痛かったのかもわからなくなるほど右顎全体に波打つ痛みが広がっていた。
十一時からなら診察できると言われ、十時半に家を出た。十分ほどで歯医者が入っているたまプラーザ駅ビルの駐輪場に着いたが、空いているラックが見当たらない。二列ほど確認してようやく空きを見つけ、自転車を担ぐようにして押し込んだ。
ビルの入り口へと足早に向かいながら、二十七番、二十七番、と頭の中で唱える。
それは正太郎にとって、一種の確認のようなものだった。帰りまで番号を覚えていられるかどうか。
現役時代には意識せずともできていた。見聞きしたものをとりあえず覚えておくのは、刑事の習性だったからだ。現場検証や聴取で得た情報は、リアルタイムでは使えないことがほとんどで、街中を歩いているときに目に入った光景が後々意味を持ってくることもある。新たな情報が入ったときに結びつけられるよう、できるだけ取捨選択せずに映像のまま頭の引き出しに入れておかなければならない。
何十年も習慣づけているうちに、自分は元々記憶をするのが得意な人間なのだと思うようになっていた。だが定年退職して一年半が経ち、そうではなかったのだと思い知らされている。今や、意識を向けなければ認識すらできないし、覚えておこうとしなければ忘れてしまう。
歯医者に着いて受付を済ませると、十一時を五分過ぎたところで診察室に呼ばれた。
口の中を検められ、レントゲンを撮られた結果下された診断は、やはり虫歯だった。
「かなり深くまでいってますし、痛みの出方からしても神経に達していると思います」
若い男性の歯科医師はレントゲン写真を指さしながら言う。
「加齢に応じて歯のエナメル質が減っていくので、どうしても虫歯になりやすくなるんですよ。あと多いのは歯周病ですね」
歯科医師はもう一度正太郎の口の中を確認して言い、カルテに何かを書き込んでいった。
「歯の状態からすると神経を抜いた方がよさそうではありますが、できるだけ神経を残したいというようなご希望はありますか」
「痛みが取れればなんでもいいです」
正太郎は、白い天井を見上げたまま答える。
「それでは麻酔して根の治療をしていきますね」
歯科医師はさらりと言うと、背後にいたスタッフに専門用語らしき言葉で指示を出し始めた。椅子がゆっくりと倒れていき、正太郎は遅れてヘッドレストに頭を委ねる。
――おまえ、虫歯一本もないんだろ。
ふいに、柴崎の言葉が蘇った。
若い頃からずっと目標にしてきた先輩でもあった柴崎が顎をさすりながら言ったのは、もう何十年も前、正太郎が被疑者の聞き込みを担当しながら重要な手がかりを見過ごしていたことが判明して課長から大目玉を食らった後だった。
柴崎は正太郎を昼食に誘い、ラーメンを口の左側だけで咀嚼しながら「この仕事は食うのも寝るのも不規則だろ」と言った。風邪くらいなら気合いで何とかなるけど歯が痛いのはどうにもなんねえんだよなあ、と。
柴崎は銀歯だらけの歯を見せて笑い、正太郎の背中を叩いた。
――おまえは刑事に向いてるよ。
治療が終わり、会計を済ませて歯医者を後にしたときには、十一時半を回っていた。
正太郎はゴムのような感触になった顎を指でつつきながら、駐輪場へ向かう。精算機の前まで来たところで動きを止めた。
一拍置いて、二十七番という響きが浮かび、詰めていた息を吐く。操作を終えてラックから自転車を引き出した瞬間。
「あ」
背後から高い声がした。
首だけで振り向くと、大きな紙袋を抱えた若い女性がこちらを見て立っている。
正太郎は自転車の向きを変え、改めて女性を見た。年頃は二十代半ば、身長は百六十センチくらいで緩いパーマのかかった茶色い髪を左耳の下でまとめている。グレーのオーバーサイズのパーカーに細身のブラックジーンズというラフな服装だが、化粧が華やかで爪に鮮やかな黄色いネイルが施されているためか、あえてカジュアルな印象に寄せているような美意識の高さがうかがえる。
「司くんのおじいちゃんですよね?」
見覚えのない顔だった。だが「きりん組のリョウマの母です」と続けられて、「ああ」という声が漏れる。
隣の鷺沼駅に住む娘の歩美から、孫の保育園の迎えを頼まれたことが何度かあった。祖父母が行く家庭は少ないから、目立って覚えられていたとしても不思議はない。
「リョウマ、家でもよく司くんの話をするんです」
女性は柔らかく微笑んで言った。
「困ってることがあると、いつもすぐ気づいて声をかけてくれるって」
「そうですか」
正太郎も顔をほころばせる。
孫の話を聞けるのは嬉しいものだ。だが、こちらはリョウマという名前を聞いたことがなく、返せるエピソードのないことが少し申し訳なくもなる。
「うちの孫こそ、仲良くしてもらっているみたいで」
ひとまず曖昧に会釈を返した。考えてみれば、お迎え時にも他の保護者とはすれ違いざまに軽い挨拶を交わすだけの距離感で、こんなふうに話しかけられたのは初めてだった。自分の子どものときにも保護者同士の付き合いはしたことがなく、どうも勝手がわからない。
正太郎が自転車のグリップを握り直し、では、と切り上げようとすると、先に女性が「あの」と口を開いた。
「ちょっとその自転車貸してもらえませんか」
「え?」
女性は「変なことをお願いしてごめんなさい」と身を縮める。
「自転車の鍵をどこかで落としちゃったみたいで……家にスペアキーはあるんですけど、あの、とにかく早く戻らないといけなくて」
あまりに突拍子もない話に思えた。こんな知り合いと言えるかどうかも微妙な相手から自転車を借りるくらいならば、駅前でタクシーでも拾う方が早いはずだ。
反射的に、素性を確かめるための問いがいくつか浮かんだ。だが、それを口にすれば疑っていることは明らかで、本当に歩美のママ友なのかもしれない以上、下手なことは言えない。
女性は長いまつげを伏せた。
「早く戻らないとリョウマが……」
正太郎は女性の顔へ視線を向ける。
「お子さんを留守番させてるんですか?」
「留守番というか、その」
女性は紙袋を抱えた腕に力を込めた。
「ほんのちょっとのつもりだったんです。でも思ったより時間がかかっちゃって、早く戻らなきゃいけないのに鍵がないし、歩いて戻ったら遅くなっちゃうし、どうしようって私……」
正太郎は、麻酔で感覚が戻らない顎に拳を当てる。
疑念が消えたわけではなかった。けれど本当に五歳の子どもが一人でいるのだとしたら、こうしている間にも転落、誤飲、感電――様々な事故が起こりうる。
「わかりました」
女性が弾かれたように顔を上げた。正太郎は、壁に貼られた館内の案内図を指さす。
「そしたら私はこの喫茶店で待ってますんで、戻ったら声をかけてください」
正太郎は自転車を渡し、「何かあったら娘――司の母親に連絡してもらえますか」と言い添えた。女性は何度も礼を言いながら自転車を駐輪場の出口まで押していき、「すみません、すぐに戻ります」と言ってサドルに跨る。
正太郎は、駅とは反対側へ走り始めた後ろ姿を見送ってから、スマートフォンを取り出した。歩美の番号を呼び出してかけたものの繫がらず、LINEで簡単に経緯を説明する。三十秒ほどで既読がつき、折り返しの電話が来た。
『もしもし、お父さん?』
「ああ、LINE読んだか」
『なんでそんなことになってんの?』
歩美の声が裏返る。
「それより、リョウマって子は本当にきりん組にいるんだよな?」
『あ、それは大丈夫。リョウマくんは二カ月くらい前に転園してきた子』
念のため女性の外見についても伝えてたぶん本人で合ってると思うと言われ、正太郎は息を吐いた。
歩美のママ友で間違いないのなら、そのうち子どもを連れて戻ってくるだろう。
だが、歩美は『私リョウマくんママの連絡先知らないんだよね』と続けた。
正太郎は、ほんの少し嫌な感じを覚える。
――だとすれば、彼女も歩美の連絡先は知らないことになる。
そして、こちらが何かあったら歩美に連絡するようにと言った時点で、彼女も連絡先がわからないことには気づいたはずだ。
「まあ、コーヒーでも飲みながら戻るのを待つよ」
とりあえず正太郎が言うと、歩美はなんか迷惑かけちゃってごめん、と声を沈ませた。正太郎は、彼女が戻ってきたら連絡すると約束して電話を切る。
引っかかる点はあったものの、正太郎としては、この時点で問題はほとんど解決したつもりでいた。相手の身元が確かならば、トラブルになるようなこともあるまい、と。
だが、彼女はその後二時間経っても戻ってこなかった。
「これまた大きな持ち物を減らしてきたわねえ」
二十分かけて徒歩で帰宅すると、呆れ顔の妻に出迎えられた。
「いつも、出かけるたびに荷物を減らして帰ってくる人だとは思ってたけど」
「いつもってほどじゃないだろう」
正太郎はバツの悪さを感じながら靴を脱ぐ。
「あら、傘だってハンカチだって、どんどんあげてきちゃうじゃないの。困ってる人がいたからって」
「……今回のは貸しただけだ」
妻の澄子は「毎回そう言ってるけど」と面白がっている口調で言い、正太郎の上着を受け取った。
部屋着に着替えてリビングへ向かい、ソファでひと息ついたところで、玄関チャイムが鳴った。澄子が応対しに行くよりも早く鍵が開けられる音が続き、ただいまー、という歩美の声がリビングのドア越しに漏れ聞こえる。
歩美は正太郎と顔を合わせるなり、「信じられない」と連発した。
「お父さんから自転車借りたってのも驚いたけど、そのまま借りパクするとかある?」
眉を吊り上げて声を尖らせる歩美に、澄子が「ちょっと落ち着きなさいよ」とお茶を出した。正太郎も「まだ決まったわけじゃないだろう」とたしなめる。
歩美はお茶をひと口飲むと、湯吞を音を立ててテーブルに置いた。
「だってすぐ戻ってくるって言ってたんでしょ? それなのにこんな時間まで連絡もしてこないって非常識にも程があるじゃない。もう夕方だよ?」
「何かあったのかもしれないだろう」
正太郎が案じているのはそこだった。
元々、子どもの身に何かあったらという懸念から自転車を貸したのだ。懸念が現実になって、自転車を返しに行くどころではなくなってしまった可能性もある。
「それでも連絡くらいはすべきでしょ」
歩美は語気を荒くして言った。
「てかマキちゃんママから聞いたんだけど、リョウマくんママってLINEが使えないとかで誰とも連絡先交換してないらしいんだよね」
あら、と妻が言葉を挟む。
「今時そんな人いるのね。ガラケーとか?」
歩美は「さあ」と肩をすくめてみせた。
「一応マキちゃんママの電話番号は知ってるらしいから、何かあったんならマキちゃんママに連絡が来ると思うんだけど」
スマートフォンを操作しながら、顔をしかめる。
「しかもさ、お父さんには子どもをひとりで留守番させてるって言ってたみたいだけど、どうもそうじゃなかったらしいんだよ」
「違ったのか?」
正太郎は口につけていた湯吞を下ろし、差し出されたスマートフォンを受け取った。文字がぼやけて読めず、首から提げていた老眼鏡をかけようとしたところで歩美がスマートフォンを引き取る。
「今日はリョウマくんとタケルくんとマキちゃんの三人でくじら公園で遊んでたんだって」
「くじら公園?」
「ほら、保育園の近くの」
「ああ」
くじらの滑り台がある公園には、正太郎も司にせがまれて連れて行ったことがあった。
――歩いて戻ったら遅くなっちゃうし、どうしようって私……
たしかに、あの公園は鷺沼駅からも離れた場所にあるから、たまプラーザ駅から行こうとしたら電車を使ってもそれなりに時間がかかる。
「リョウマくんママが途中でクリスマスプレゼントの買い出しに行くことになって、マキちゃんママとタケルくんママでリョウマくんを預かってたんだって。で、十一時くらいにマキちゃんとマキちゃんママは帰ったんだけど、タケルくんたちはお昼まで遊ぶって話になってたみたい」
いささか名前が多くてややこしいが、三組の母子が公園で遊んでいたところ、一人の母親が途中で席を外し、次にもうひと組の母子も帰ったため、残った母親が子ども二人を見ることになった、という話だろう。
つまり、リョウマくんという子は家でひとりで待っていたわけではなく、他の母親に預かられていたということになる。
「だったら、どうしてあんなに慌ててたんだ?」
正太郎は首をひねった。けれど歩美は、「そりゃ慌てるでしょ」とお茶をあおる。
「子ども同士を公園で遊ばせてて、ちょっと席を外す間子どもを見ててもらうってのはよくあるけど、あんまり遅くなると感じ悪いじゃん。お昼時だったし、子どもがお腹すいたって言い出したら見ててもらうだけじゃ済まなくなるし」
「そういうのって難しいわよねえ」
澄子が相槌を打った。歩美が顔を上げて澄子を見る。
「お母さんの頃も陰口を叩く人とかいた?」
澄子は、どうだったかしらねえ、と曖昧に答えた。
「官舎のママ友付き合いなんて、夫の職場での上下関係も絡んでくるんじゃないの? グループの中心人物みたいな人の機嫌を損ねると大変とか」
「そうねえ」
正太郎はお茶をすすりながら、二人を眺める。育児にろくに参加してこなかった身としては、こういう話になると居心地が悪い。
「要するに、私が舐められてるってことだよね」
歩美がふてくされた声音で言った。正太郎は、思いもよらぬ強い言葉に少し驚く。
「だってリョウマくんママは、タケルくんママと私のどっちに迷惑をかけるか天秤にかけたってことじゃない」
「いや、それは」
正太郎は咄嗟に否定しようとしたが、言葉が続かなかった。
そういうことになるのかもしれないと思ったからだ。ママ友に迷惑をかけないために他のママ友に迷惑をかける――一見本末転倒に思えるが、相手の重要度に差があるとなれば話は違ってくる。
「まあでも、怖がられるよりは舐められる方がいいじゃないの」
澄子がのんびりとした口調で宥めた。
「別にタケルくんママは怖がられてるわけじゃないよ」
歩美がため息混じりに言う。
「タケルくんママ、いい人だし」
「そうなの?」
「うん。おおらかで頼りになる人。保育士だから子どもの扱いも上手いし、面倒見もいいし」
正太郎は意外な思いで歩美を見た。そこは素直に褒めるのか。
「よくお迎えの後に一緒に子どもたちを公園で遊ばせるんだけど、誰かがちょっと席を外していい? って言うと、いつもタケルくんママはいいよいいよ行っといでって快く送り出すんだよね。それで陰口言うのとかも見たことない」
「へえ、本当にいい人じゃない」
澄子が言うと、歩美は「そうなんだって」と複雑そうな顔をした。
「タケルくんママは、自分も気軽に子どもを預けてくの。だからみんなもタケルくんママには子どもを任せやすいっていうか、お互い様だよね、助け合いって大事だよね、みたいな空気に自然になるっていうか」
「今もそういう人いるのねえ」
「でしょ? 私も司を保育園に通わせるまでは今時の育児ってもっとギスギスしてて、全部家族だけでなんとかしなきゃいけない感じなのかと思ってたもん」
歩美はダイニングテーブルにだらりと腕を伸ばす。
「正直私は人様の子どもを預かるのは怖いし、貸し借り的なのは苦手なんだけど」
「でも、そういう人って貸し借りみたいには考えないんじゃないの?」
そうなんだよー、と今度は背もたれに首を反らせる歩美を、正太郎は微笑ましい気持ちで眺めた。
「まあ、どちらにしても週明けになれば保育園があるわけだし、このまま連絡が取れないってこともないだろう」
澄子も「そうよ」と取りなす声音で言う。
「自転車が戻ってくるまではお迎え代わってあげられないけどね」
茶化すように続けた澄子に、ようやく歩美も「えーそれは困る」と声をやわらげた。
そのまま澄子が「今日は夕飯はどうするの」と話を切り替え、二人は献立の話題で盛り上がり始めた。正太郎はそっと席を立ち、ベランダへ出る。
煙草に火をつけ、煙を深く吸い込んだ。ニコチンが身体に行き渡っていく感覚を味わいながら、ゆっくりと吐き出していく。
箱を見ると、残り二本だった。
そろそろ煙草もやめ時かな、とぼんやり思う。元々、やめることにはそれほど抵抗はなかった。これまでにも、捜査中で吸う暇がないときには吸わずにいられたし、年単位で禁煙していたことも何度かある。
それでもまた喫煙するようになったのは、単に煙草を吸っている時間が好きだからだった。一人で煙を眺めていると感情がなだらかになるし、喫煙所で人と他愛もない話をしながら灰を落とすのも楽しい。美味しいものを食べるような感覚だから、吸うなと言われればやめることもできるが、これから一生吸ってはいけないと言われたら寂しい気もする。
だが、退職してから明らかに本数が増えていた。手持ち無沙汰でつい手を伸ばしてしまい、気づけば一日一箱以上吸ってしまっている。一箱六百円としてもひと月一万八千円――退職金は出たとはいえ、まだ年金をもらっていない身には分不相応な嗜好品なのかもしれない。
歯医者にも金がかかるしな、と顎をさすりながらリビングに戻ったときだった。
「お父さん」
キッチンカウンターの前にいる歩美が、妙に慌てた声を出した。
顔を向けると、澄子も歩美の隣で難しい表情をしている。
「どうした」
「今、マキちゃんママから連絡があって」
歩美がスマートフォンを差し出してきた。正太郎は老眼鏡をかけて目を凝らす。
画面には、ネットニュースの記事が表示されていた。
〈離婚調停中の妻を刺傷 ストーカー夫を殺人未遂容疑で逮捕
11月24日正午前、川崎市宮前区鷺沼の公園で離婚調停中の妻(26)の右腕を包丁で刺したとして、神奈川県警が日浦陽平容疑者(27)を殺人未遂容疑で逮捕した。妻は昨年6月、容疑者からのDV被害を緑南署に訴え、当時4歳だった子どもを連れて目黒区の知人宅へ避難していた。日浦容疑者は今年2月、妻の知人宅へ押し入り、住居侵入とストーカー規制法違反の罪で有罪判決を受け、執行猶予中だった〉
文章の合間にある写真には、くじらの滑り台が写っている。
――まさか。
正太郎の思考にかぶせるように、歩美が言った。
「これ、リョウマくんママのことなんじゃないかって」