教育格差や体験格差を埋める。それ自体は善意だ。
しかし、公平な競争を実現することが果たして子どもたちのしあわせにつながるのか。
『子どもの体験 学びと格差』(文春新書)を上梓した教育ジャーナリストのおおたとしまさ氏と『学歴社会は誰のため』(PHP新書)で話題の勅使川原真衣氏が語る。
(本対談は、5月29日に紀伊國屋書店新宿本店で開催されたトークイベントをもとに加筆・再構成してお届けします)
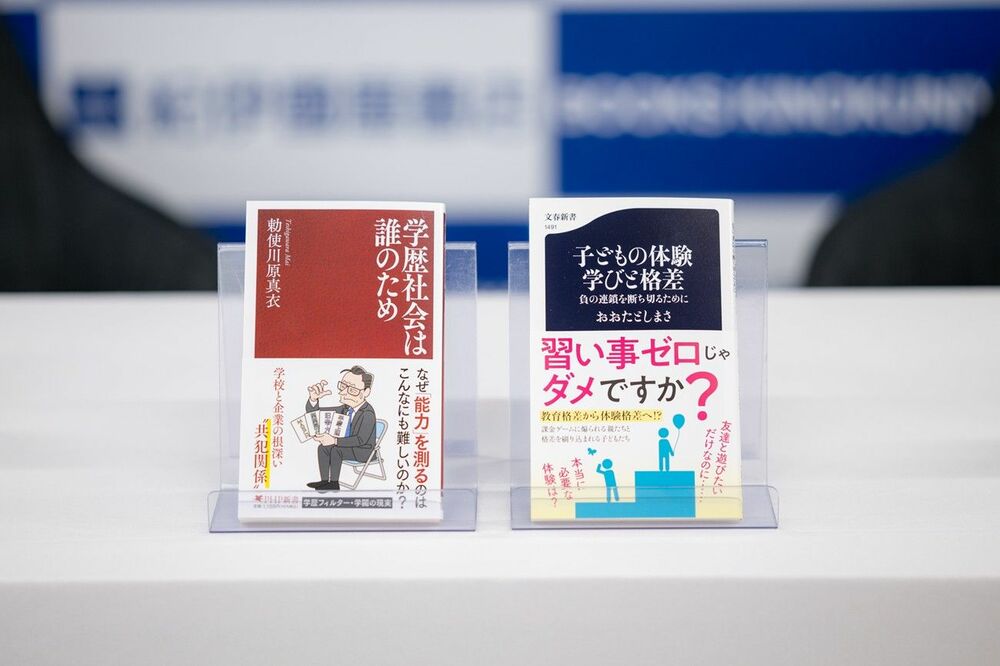
◆◆◆
公平な競争が実現すればしあわせになれるのか?
勅使川原 「本来的に変えなければならないのは、教育の結果得られた“能力”のように見えるもので大人になってからの収入や社会的地位が決定づけられてしまうしくみではないか」と、おおたさんの『子どもの体験 学びと格差』には書かれています。本当にそうですよね。
おおた そんなの理想論だというひとがいると思いますけど、教育格差とか体験格差とかをなくすことよりも、学歴社会を変えるほうが現実的だと僕は思うんですよ。
だって、生まれはコントロールできないですよ。どこに生まれるかとかね、遺伝のこととかも含めたら。それは人智を超えたこと。遺伝の影響まで遡って教育格差をなくそうとしたら、たぶん、頭が良い子の学習権を奪うとかしかできないですよ。「君はもうこれ以上勉強しちゃダメだから」って。

だけど、会社の人事システムとか、賃金形態とかは、人間が決めていることじゃないですか。だったら変えられるはず。そっちのほうが現実的だと思うんだけど、「それは変えられません。社会はそういうしくみですから」っていうフレームワークに閉じたまま教育格差や体験格差が議論されちゃっているのが、僕はものすごく気持ち悪いんですよね。
勅使川原 いまあるフレームワークの中で議論している限り、いま優位な立場にいるひとの権威性みたいなものが温存されますからね。
おおた 教育格差を無くせと言っているひとたちが何を求めているかっていったら、結局のところ、公平な競争を実現しようということです。でも「それでいいんだっけ?」って僕は思う。
勅使川原さんも『学歴社会は誰のため』で、ある就職コンサルタントがその著書で書いていることを、痛烈批判しています。そのコンサルタントは、「教育機会の実質的な平等が実現されれば、学業成績が低いことのほぼ唯一の原因は当人の努力不足(自己責任)になる」みたいな論理を展開しているんですけれど、勅使川原さんは「私が描く方向性とは真逆のベクトル」と一刀両断しちゃう(笑)。
いくら教育格差がなくなったとしても、本来ひとそれぞれであるはずの学びが競争の具にされて、勝ち負けがはっきりして、「お前が努力しないで負け組になったのは言い訳できないよね」って言われちゃうような逃げ場のない能力主義的競争社会をつくって「僕たちしあわせなんだっけ?」ってところを考えないと。
貧困の連鎖からの脱却は自己責任!?
おおた 「学歴が異様な威力をもってしまっているから、教育段階での差が人生を大きく左右するように思われてしまって、教育格差はけしからんという話になる。だったら学歴を無力化する方法を考えればいいじゃん」という点で、僕たちふたりはもともと一致していました。その対談が、2023年の拙著『ルポ 無料塾』の最終章に収録されています。
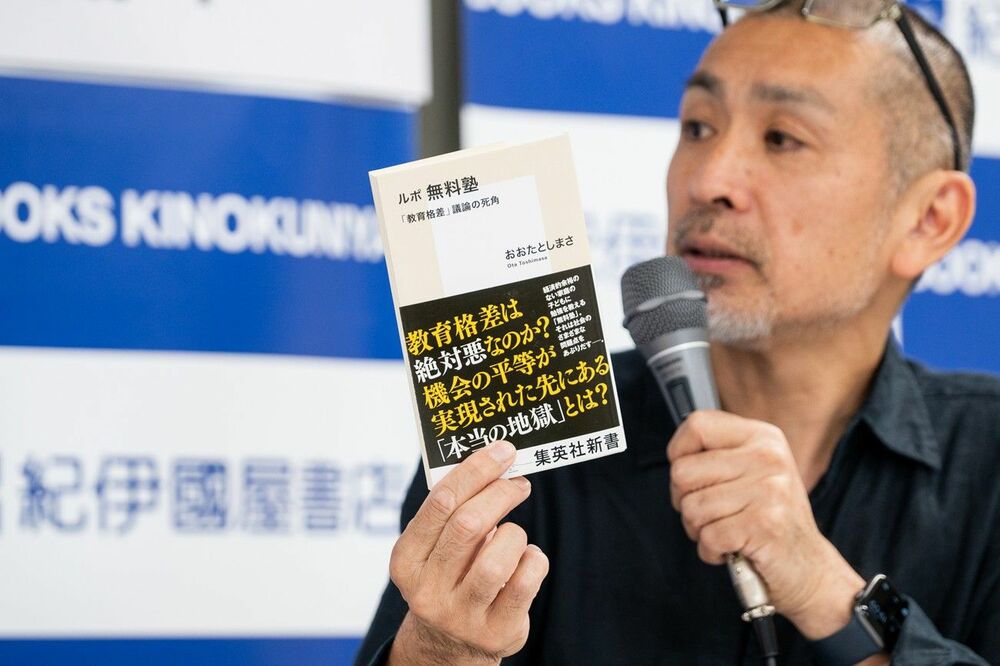
勅使川原 でしたよね。そこからそれぞれに活動して今回、2冊の本がほぼ同時に出ました。
おおた 今回の勅使川原さんの『学歴社会は誰のため』の前半では、学歴によって将来の経済的成功が決定づけられてしまうことのナンセンスさを一つ一つ丁寧に、勅使川原理論で説いていくわけです。「働くということは、お互いの持ち味の組み合わせでパフォーマンスを最大化することだって言ってるのに、ペーパーテストの結果みたいなもので、その職場に必要な持ち味の組み合わせって判断できるんだっけ? わかるわけないよねぇ……」という理屈で、就活で学歴を問うことの合理性を木っ端微塵にしていく。
勅使川原 うんうん、ありがとうございます!
おおた そして今回の僕の本では、「学歴だけじゃなくって非認知能力も必要だっていわれてきたぞ。そのためには体験しなくちゃいけない。体験にはお金が必要だ!」ということまで言われ始めたぞってことで、「ちょ、待てよ」って話を書いている。
勅使川原 有利、不利の話ってみんなすごい好きなんですよ。みんな自分に関わるので。少しでも有利でいたい、不利でいるのは嫌だって。そういう話が好きなんだけれども、有利か不利かを考え続ける限りにおいては、競争とかそのゲームを、内面化しちゃっているんですよね。
おおた 競争している限り、どこまでいっても……、仮に有利であったとしても、いつ抜かれるかわからないと思ったら、ずーっと頑張り続けなければいけない。てことは、ひとの世話をしている余裕がないですよね、ずっとね。だから格差が生まれるわけですよね。
勅使川原 はい、これは特に痛快かつ重要なご指摘でした。教育がコンプレックス産業化していますよねってことは私も言っているし、誰でも言える。でもおおたさんの本はその先を行っているんです。特に二つの意味で。一つは、家庭に教育を任せっきりにする前提に疑問を呈している。もう一つ。いい学校に行って、いい仕事に就いて、いっぱいお金をもらえたらしあわせだということを多くのひとは当たり前のこととしているなかで、その職業を媒介した能力主義的配分こそを変えようと訴えている。
おおた 競争社会ということは、要するにライバルに差をつけろという社会なんです。その差の代名詞が「偏差値」だったわけじゃないですか。それが「生まれ」に相関していることを教育格差と呼んでいた。こんどは体験格差。偏差値だけじゃなくて、子どもの体験の「差」にまで社会的な注目が集まってしまった。
親ガチャのハズレを引いた子がいますよと。そこにお金を与えて、機会を与えるから、そのチャンスをものにして、能力を高めなさいと。そして貧困の連鎖から抜け出してねって。これ、自己責任化ですよね。社会の歪みのせいでできちゃった格差を埋める責任を、苦しんでいるひとたちの努力に押しつけていいの? しかも、それで負の連鎖が止まるとしたら、その子どもが大きくなったときだから、20年後、30年後じゃないですか。
格差はいまの政治課題です。教育で格差を解消しようっていうのは問題のすり替えです。教育社会学でよく使われる言葉だと……。
勅使川原 「社会課題の教育化」ですね。
おおた 論点のすり替え、問題の先送り。それにみんなで加担しちゃっているんじゃないの? ……というのが私の『子どもの体験 学びと格差』の主旨ですね。

いちばんの罪は子どもから学びの喜びを奪うこと
勅使川原 いやー、よく言っちゃいましたよね、それ。教育社会学は公平(equity)の観点からはいっぱい考えてきましたけれど、公正(justice)についての議論はあまりされていない。それをこんなに説得性をもちながら展開できるのは、現場取材がベースにあるからだと思います。
私自身、『格差の“格”ってなんですか?』という本の中で、「格差格差っていうけれども、格の違いっていうこと自体がちょっと特権的じゃないか」という指摘を恐る恐るやっていますけれど、私の論理だとそれぐらいしか言えなかったなという反省もあるんですよ。だけどおおたさんは今回の本の中で、行動遺伝学者の安藤寿康さんにまで話を聞いて、格差そのものをなくすことはできないんだって言い切っちゃった。
おおた 行動遺伝学の威を借りて(笑)。
勅使川原 職業によって収入に大きな差をつけて競わせるのではなくて、誰でも尊厳をもってしあわせに暮らすのに十分な稼ぎが得られる社会にしていけばいいじゃないかと。仰る通りですよね。
おおた わざわざ「格差」なんて言葉で構造化しなくても、やりたいことができない子がいたら、それは普通に助けてあげればいいじゃないですか。
勅使川原 そうだ!
おおた 格差っていった瞬間に、もう「子育ては競争だ」って意味を含んでますよね。
勅使川原 格の違いって言っているんですからね。
おおた そうしたら親としては、「格の上のほうにしてあげなきゃ。少しでもお金があるんだったら課金しなきゃ」と考えて、中流層であったってギリギリまで家計を削って、子どもの習い事や体験学習にお金をかける方向に行っちゃう。そうしたら結果、金額的な差はますます広がりますよね。「何やってるの?」って感じ。
勅使川原 でも難しいですよね。「格差をなくすためにお金を集めよう!」っていうほうがわかりやすくて、賛同を得やすい。そこに対して、私たちの論をどうやって盛り立てていこうかなって。お金にならないことってこの世の中で流行らないから。
おおた 流行らせようとか盛り立てていこうとか思うと続かないですよね。
勅使川原 ぐさり。そうだ……。
おおた 大きな成果を焦ると、大衆の耳目を集めやすい強引なロジックを声高に喧伝しちゃうことになる。だけど、「たくさん体験をして非認知能力を高めないと将来困っちゃうから、だから助けてあげなければいけない」みたいな理屈をくっつけた瞬間に、支援対象の子どもたちは「自分はみんなよりも能力が低いまま大人にならなければいけないんだ。不利な人生なんだ」と思ってしまうでしょ。それって子どもからしてみたら、めちゃめちゃ怖いですよね。
勅使川原 呪われている。
おおた でも僕が個人的にいちばん罪だと思っているのは、こういうロジックが流布することで、子どもたちから学びの喜びを奪ってしまう可能性が高いってことです。
子どもって「いいこと思いついた!」って瞬間に、自ら体験を始めますよね。そのときがいちばん楽しいし、学べるわけじゃないですか。だけど、「この体験にはこういう目的があるんですよ。しっかり非認知能力を伸ばしてくださいね」って言われた瞬間に、やる気なんて失せますよね。
学校で目的を設定された勉強をやらされているからこそ、学校の外で何かを体験することが輝いて見えていたわけです。だけど、そこにも目的を設定されちゃったら、「子どもはどこで喜びを感じればいいの?」って。

勅使川原 日常の営為すべてに「効用」や「合理性」「意味」のお墨付きを用意して、タイパよき活動をお膳立てしないとろくな大人になれない……なんて言説がまことしやかに喧伝されていますが、おとといきやがれですよね。教育経済学者がROI(投資収益率)で子育てを語って、かつそれを「科学的」子育てなどと呼んだりしますが、「いつまでパイの奪い合いをさせる気なんだ?」ともやもやします。
初期値の違いは、遺伝学をはじめとする個体差としても、経済的にも、たしかにあります。でもその違いは、いつもいつも個人単位で埋めなければいけない由々しき「格の違い」という問題ではない。違いがあっても、競争ではなく共創によって埋め合えればいい。ごく限られたひとしか「豊かに」「しあわせに」暮らせないとの前提に立つような「生き抜く」社会ではなく、「生き合い」をしたって何も罰は当たらないよね? ……という話を我々はしています。奪うだけが能じゃないですよね。パイを増やすことに叡智を持ち寄りたいです。



















