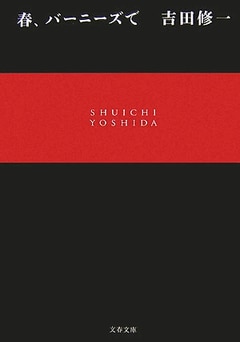『国宝』が社会現象級の大ベストセラーになっている吉田修一さんの最新文庫『ミス・サンシャイン』が2025年8月5日に発売になりました。
本作は、伝説の映画女優・和楽京子こと石田鈴の波乱万丈な映画人生を描き、島清恋愛文学賞を受賞した傑作長篇です。
本作の魅力を皆さんにいち早く感じていただくべく、冒頭の章「梅とおんな」を無料公開します。
梅とおんな
立派な石垣だった。ちょっとした城壁の構えで、門の両脇に鎮座する厳しいソテツなど、金剛力士の阿形像と吽形像のようである。
この奥に、目指す「パレスマンション」があるのは間違いないのだが、往生際悪く、「本当にここかなぁ」と、岡田一心は石垣のまえを行ったり来たりしている。
一心などと聞くと、実家が浄土真宗の寺かなにかで、将来は坊さんにでもなるのだろうかと思われそうだが、父は中堅電機メーカーの営業マン、母は手の込んだ料理を作るのが趣味の専業主婦であり、ちなみに実家の隣は寺ではなく小さな教会である。
ならばこの一心という名前がどこから来たかといえば、ちょっとロマンティックな話になる。結婚まえに父が母へ書き送ったらしいラブレターのなかに、「一心に」という言葉があったそうで、どういう文脈だったのかはさすがに息子からは照れ臭くて聞けないが、母によれば、とても心を動かされる文章だったらしい。
さて、金剛力士像のようなソテツのまえに突っ立ち、その一心が手に握りしめているのは、ここパレスマンションの住所が書かれたメモと、ゼミの担当教授からもらった紹介状なのだが、いつもの癖でメモのほうはすでに紙飛行機に折ってしまっている。
やっぱりここだよな……。
一心は諦めるように呟くと、「よし」と、腹を決めて門をくぐった。
この門構えなので、くぐったところで、親しみの持てるフツーのマンションが建っているわけもないのだが、門から奥へは茶室へでも繋がっているような石畳が伸び、広々とした敷地内には樹齢の古そうな樹々が生い茂っている。
一見、ちょっとした公園である。いや、公園というか、すぐ近所にある皇居や北の丸公園や千鳥ヶ淵の深い森の一部が、台風かなにかでここまで飛ばされて来てしまったようだった。
このちょっとした森の先に、煉瓦造りの小ぶりなマンションが建っている。いわゆるヴィンテージマンションというやつで、近辺に林立している高層マンションとは一線を画している。
マンション内のエントランスは薄暗かったが、掃除は行き届いていた。青々とした観葉植物の葉やプランターの色とりどりな花、そしてピカピカに磨かれた床のタイルなんかを見ると、おそらく管理人さんが楽しんで仕事をしているのが伝わってくる。
一心は紙飛行機のメモを開いて部屋番号を確かめる。
最上階の401。
一つ深呼吸してオートロックのボタンを押すと、数回ほど呼び出し音が鳴ったあと、「はい」と聞こえてきた声は予想していたよりもずいぶん若々しい。
「おはようございます!」
緊張もあって、部活の新入部員のような大声を張り上げてしまった。
「……あ、すいません。あの、岡田一心と申します。五十嵐先生からご紹介いただいて」
自分の大声に自分でドギマギしながら続けると、「あら、もうそんな時間?」と、なぜかインターホンの向こうで相手も慌て出す。
「すいません、ちょっと早かったですか?」
「いえ、あたしが勘違いしてたのよ。……それよりあなた、お庭の梅、きれいだったでしょ?」
「え?」
「だから、おにわのうめ」
「え? 鬼は能面?」
「え? ……だから、外のお庭に咲いてたでしょ、梅のお花が」
緊張もここまでくると自分でも笑ってしまうが、「ああ、庭かぁ」と振り返った目に飛び込んできたのが、満開の白梅であった。瀟洒なマンションの造りばかりに気をとられ、真横を通ったのに気づかなかったらしい。
「どうぞ、入ってらして」
インターホンが切られ、オートロックのドアが開く。
一心は、「失礼します」と、切れたインターホンに応え、自動ドアのレールをなぜか踏まないように跨いだ。
正面の大きなガラスの向こうに中庭があった。今は使われていないらしい噴水に枯葉が溜まっている。
エレベーターの横にはメールボックスが並んでいる。全部で十世帯ほどだろうか。
401号室に「石田鈴」とある。ずいぶん薄れているけれども、元はいい万年筆のインクで書かれていたのだろう。
ここ数日、ずっと耳にしていた「和楽京子」という名前と違っていたので一瞬戸惑ったが、昭和の大女優が芸名を表札に出すはずもない。
「いしだすず」と読むのか「いしだりん」と読むのか。どちらにしても、本名は少し地味だった。
ゼミの担当教授である五十嵐先生に声をかけられたのは、一心が学食でミックスフライのAランチにするか、五十円安い麻婆豆腐のBランチにするか、本気で悩んでいるときだった。
すでに食べ終えて学食を出て行こうとした先生が、「あ、そうだ、岡田くん」と立ち止まり、「……君、今、バイトしてるんだっけ?」と尋ねる。
「やってないです。やってたら、Aランチに即決します」
一心の返事を先生はさほど気にすることもなく、「君に紹介したいバイトがあるんだけど、興味ある?」と訊く。
「あります」
ずっと居心地よくバイトしていた書店がビルの建て替えで閉店となり、店長からは他店舗を紹介してもらったのだが、自宅から電車を乗り継いで一時間かかる場所で断念したばかりだった。
「私も、どういう仕事になるか、まだよく分からないんだけどね」
元々、呑気な先生だが、さすがに心もとない。
「家庭教師とか? 引越しとか? カフェとか?」
「いや、そういうんじゃないんだよ。ちょっとした家政婦さんというか……」
「そりゃ無理ですよ。料理、洗濯、掃除、全部苦手ですもん」
「いや、そういうのをやってくれる人はもういるから。じゃなくて、ちょっとした家のなかの力仕事なんかをね、頼める若い人がいないかって相談されてね」
「ああ」
それなら一心にもイメージが湧く。引越しの準備か何かで、短期のバイトになるのであろう。
「君くらいの世代でも、和楽京子って知っている?」
先生に訊かれ、「知ってますよ。時代劇の『隠密道中 月影一座』に出てた女優さんでしょ。翡翠の玉を使って悪人を殺す旅役者の女座長」と一心は答えた。
父が好きで、子供のころによく再放送で見ていた人気時代劇のドラマだった。
「その和楽さんの家なんだよ。君に紹介したいバイト先」
もちろん悪と戦いながら地方巡業する旅役者の一員になれと言われているわけではないのだが、さすがに一介の大学院生である自分と昭和の大女優はそう簡単には結びつかない。
四階でエレベーターを降りると、廊下は二手に分かれていた。ワンフロアに二世帯だけのようで、和楽京子の部屋は右手にあった。玄関先は少し手狭な感じだが、マンションの規模を考えれば、この先に広がる室内は相当の平米数だろうし、全戸のベランダからは前庭を見渡せるはずである。
ポーチの門扉を開けてチャイムを押そうとすると、先に玄関ドアが開いた。
「壊れてるのよ、そのチャイム」
顔を出したその人は、当然だがあの和楽京子である。
『隠密道中 月影一座』のように銀杏返しのかつらではないし、ほとんどノーメイクに近いその顔はたった今、風呂から上がったように血色がよく、印象より少しだけ薄くなっている髪を一つにまとめて、なにより薄手のセーターを柔らかく盛り上げているふくよかな胸元が、とても八十代の女性とは思えないほど艶かしい。
実はここへ来るまで、一心はあることを恐れていた。昭和を代表する大女優とはいえ、ここ十年ほどはほとんど表舞台に出ていない。もしもドアの向こうから、質の悪い整形手術を繰り返した結果、顔が無残に壊れた老女が出てきたら、自分は動揺を隠していられるだろうか。はたまた、相手は昭和の大女優である。一介の大学院生との対面など、それこそ御簾の向こうからで、顔も見せてもらえないのではないだろうか。などなどである。
しかし出てきたのは、風呂上がりのような血色の良い女性で、実際にはおばあちゃんではあるが、おばあちゃんと呼んでしまうのもはばかられる。
「初めまして。岡田と申します。よろしくお願いします」と一心は頭を下げた。
「こちらこそ、よろしくね。まあ、とにかくお入りになって。すぐにどうこうってお仕事じゃないのよ。ゆっくりやってもらえればいいんだから」
玄関に招き入れられると、和楽京子がスリッパを出してくれる。薔薇模様のフリル付きスリッパは、明らかに一心の大きな足を拒んでいたが、出されたものは仕方がない。
「あの、石田さん、これを」と、一心は五十嵐先生からの紹介状をまず渡した。
和楽京子がその場で封を切りながら、「『鈴さん』でいいわよ。みんな、そう呼ぶから」と言う。
「あ、はあ」と、一心も頷きはするが、だからと言って、「じゃあ、鈴さん」とすぐに呼びかける勇気もない。
「ほら、呼んでみなさいよ。こういうのは一回、声に出しちゃえばそうなるんだから」
少しせっかちな人らしい。
「じゃあ、あの、鈴さん、よろしくお願いします」
「はい。こちらこそ」
そう答えながら紹介状にさっと目を通したその鈴さんが、「それにしても、あなた、庭の梅に気づかないなんて、どこ見て歩いてるのよ」と、インターホンでのやり取りに戻りながら廊下を奥へ向かう。
一心もあとを追うと、日当たりのいいリビングに出た。スタイリッシュというよりは、花柄の椅子やソファのせいで、ちょっとした花壇のようである。実際、生花も多く、いい匂いがする。
リビングの奥には、やはり日当たりのいいベランダがある。一心が暮らすアパートのベランダが手漕ぎのボートなら、こちらはちょっとしたクルーザーである。
ベランダに出た鈴さんが手招くので、一心は香りのいいリビングを横切った。高価そうなソファにクッションが置いてあると思っていたら猫が寝息を立てている。まったく人見知りしないらしい。
「ちょっと見てごらんなさいよ」
鈴さんがベランダで見せてくれたのは、見事な梅の盆栽だった。前庭にあった梅の一枝が、こちらも台風かなにかで飛ばされてきたみたいである。
「きれいですね」
「そうでしょ」
「盆栽にはまったく詳しくないですけど」
「あたしだって詳しくないのよ。でも、きれいなものはきれいじゃない」
梅に鼻を寄せた鈴さんが、「ちょっと、ほら」と、一心にも嗅ぐようにと場所を譲ってくれる。
改めて近くに立つと、鈴さんはかなり小柄である。一心の肩くらいしかない。その代わりに驚くほど目が大きい。黒目が澄んでいて、よく吸い込まれるような目という言い方をするが、こういう目のことなのだろう。
一心はフリルのスリッパからゴム草履に履き替え、鈴さんを真似して梅に鼻を寄せた。たしかに甘い香りだった。
周辺には殺風景なビルが多いせいで、ベランダからの眺めが良いとは言えなかったが、それでも前庭が広いので青空が抜けている。
「この梅ね、下の梅の木から盗んできたのよ」
鈴さんが小さく舌を出す。
「盗んできたって、枝を折ってきたんですか?」
「枝を折ったら、あなた、すぐに枯れちゃうじゃない。庭師の大将にグルになってもらってね、こっそりと取り木したの」
「取り木?」
「取り木って、そうね、なんて説明すればいいのかしら。たとえばきれいな形をした枝があるとするじゃない。その枝の根元の樹皮をまず剥がすのよ。そこに、土を巻きつけるの」
「土を?」
「そう。ビニールの小さな鉢植えあるでしょ。あれを買ってきて、樹皮を剥いだところを包んで、そこに土を入れるの。そうすると、その鉢に新しい根が伸びてくるでしょ。伸びてきたら、その枝を切って、新しい根と一緒にこうやって別の鉢に移すわけ」
なんとなくイメージはつくが、そう簡単に根なんて生えるものなのだろうか。
「庭師の大将と、夜中にこっそりと作業してね。半年よ。根が出るまで、半年もかかったんだから。……とにかく、管理人さんやここの住人の人たちにバレやしないかってヒヤヒヤよ。だから、半年後にちゃんと新しい根が出てるのを見たときなんてもう、庭師の大将に抱きついて喜んだわよ」
一心はベランダから前庭の梅の木を見下ろした。夜中にこっそりと取り木している鈴さんと半纏姿の庭師の大将が見えるようである。
改めて視線をベランダに戻す。置かれているのはわりと大きな鉢植えである。そこからうねるように垂れ下がった梅の枝は、華奢な女の人の手首ほどの太さがある。もしもこんな太い枝がとつぜん切られていれば、あれだけエントランスの観葉植物やプランターを愛でている管理人さんなのだから気がつきそうなものだ。
「でも、こんな大きな枝を切ってきたら、誰か気づくんじゃないですか?」
一心は鉢からこぼれ落ちそうな枝を下から覗き込んだ。
「取り木したときは、こんなに大きくないもの。切ってきたときは、こんなものよ」
鈴さんが両人差し指を自分の肩幅くらいに広げてみせる。
「それがこんな太くなったんですか?」
「そうよ。すごいでしょ」
「あの、いつ切ってきたんですか?」
「いつって……、もう十年以上にはなるかしらね。庭師の大将だって、もう亡くなっちゃって。お葬式のとき、ちょうど咲いてたもんだから、棺にこの梅の花入れさせてもらったのよ、あたし」
一心はまたベランダから庭の梅を見下ろした。まるでいたずらでもするように隠れて取り木している二人の姿はやはり見えるが、まさかそれが十年もまえの姿だとは思いもしなかった。
十年まえといえば、一心はまだ中学生である。初デートで乗った観覧車で、その高さに目を回して吐いたのがそのころだが、遠い記憶の彼方のことだ。
一心は改めて鈴さんに目を向けた。
この人は十年もまえのことをまるで昨日のことみたいに話す、というか、きっとこの人には十年まえのことなど本当に昨日のことなのかもしれない。
休日の多摩川河川敷の青空に、金属バットの快音が響いている。大きな歓声につられるように、一心は隣のグラウンドへ目を向けた。青空に伸びた球が飛んでいく。
隣のグラウンドで行われている草野球チームの試合も、こちらと同時刻に始まったはずだが、一心が所属する「市が尾エンジンズ」のほうは、すでにデザイン会社のチームである「多摩川レイカーズ」に六回コールドで負けていた。
ちなみに弱小チーム「市が尾エンジンズ」は、神奈川の港北地区に展開する中古車チェーン店が作る草野球チームなのだが、この「たまプラーザ店」に一心の幼馴染である山下が勤務しており、人数合わせで呼ばれたのが最初だった。ほぼ野球初心者の一心が6番ショートでレギュラー獲得できる程度のチームである。
顔の汗をタオルで拭いながら、隣の試合経過をぼんやりと眺めていると、やはり横で着替えていた山下が、
「それで? バイト代はいくらもらえんの?」と訊いてくる。
早々にコールド負けした敗者チームのベンチでは、余ったおにぎりを持って帰れと、チェーン店社長の奥さんがチームメイトに分けて回っている。一心もおかかのはみ出したおにぎりを一つもらうと、「時間にもよるけど、だいたい日給一万円」と教えた。
「そんなにもらえんの? そのばあさんの梅の話を聞いてやるだけで」
山下はもらったおにぎりを早速頬張っている。
「まあ、初日はたまたまそうだったけど、近所に借りてる倉庫の整理をしてほしいみたいだから、結構な力仕事になるんじゃないかな」
「終活ってやつ?」
山下に言われ、「ああ」と一心も今ごろ気づく。
「なあなあ、若い女優とか遊びに来ないのかな? 元女優なら付き合いあるんじゃないの?」
「もう引退して十年以上だから、そういうのないと思うよ」
「じゃあ、ばあさんと二人っきりで荷物整理かぁ。まあ、一日数時間で一万なら悪くないけど。俺なら時給安くても、可愛い女の子がバイトしてるカフェとかで働くけどな。だってさ、もったいなくない? 時間が」
着替え終えた山下がバッグを担ぎ上げる。
「車、乗ってく?」
「いや、いいや。歩いて帰る」
一心は最寄り駅へ続く土手へ向かった。青々とした土手の緑と、どこまでも広がる河川敷の青空である。
幸い、寄り道したカフェはさほど混んでいなかった。いつもの豆でアメリカンを頼み、窓際のカウンター席に着く。
駅からは少し離れているが、ノルウェーに本店のあるカフェらしく、大きなガラス窓の青い木枠と内装の白木がのんびりとした気分にさせてくれる。
一心はアメリカンを一口飲むと、パソコンを開いた。昨夜、探しておいた映画を再生し、イヤホンを耳に突っ込む。
一九四九年製作の白黒映画である。始まった途端、フィルム映像が乱れ、そこに筆書きで『梅とおんな』というタイトルが大写しになる。
これが和楽京子のデビュー作である。
物語は終戦後、山陰地方に復員してきた若い僧侶と、その地を訪れたサーカス団の踊り子との束の間の恋を描いたものだが、和楽京子はこの純朴な僧侶の妹役として、数シーンにだけ登場する。
映像が粗い上にセリフも少なく、アップもない彼女の顔は、あまりはっきりとは映っていないのだが、それでも十代の少女らしい溌剌とした白い笑顔が梅の花のようで、一心は思わず見入ってしまった。白黒映像を見ているはずなのに、彼女の頬だけがほんのりと色づいていたような印象まで残る。
「古い映画ですよね?」
ふいに声をかけられ、一心は慌ててイヤホンを抜いた。振り返ると、店の女の子が立っている。
「あ、はい……。古いです」
あまりにも急だったので、一心は鸚鵡返ししかできなかった。このカフェに通い始めて三ヶ月以上になるが、初めて注文以外で彼女と言葉を交わした。
彼女はしばらくパソコンの映画を眺めると、手にしたダスターで隣のカウンターを拭き始めた。少し日に灼けたそのほっそりとした顎の線を、真横から見るのも今日が初めてだった。
「あの……、古い映画、好きなんですか?」
カウンターを拭きながら離れていく彼女に、一心は思い切って声をかけた。
「それ、成田三善監督の作品ですよね?」
彼女に訊かれ、「そ、そう」と一心は頷く。
「好きなんですよ。その監督の作品」
彼女は口の端だけで微笑むと、汚れたダスターをたたみ、レジへ戻る。一心はその後ろ姿が映るガラス窓をいつものように眺めた。
鈴さんの家で梅の盆栽を見せてもらったあと、一心は紅茶をご馳走になった。近所にあるという洋菓子店のフィナンシェも頂いたが、しっとりとした食感でバターが濃く、最後は思わず指まで舐めてしまった。
近くに物置にしている小さな部屋があるから見に行こうと鈴さんに言われ、「そこの荷物を片付けるんですか?」と尋ねると、「そこもそうだし、こっちの家のものも徐々にお願いしたいのよ」と、鈴さんは花壇のようなリビングを見回す。
「さあ、プク。お散歩よ」
鈴さんがソファで寝ていた猫に声をかける。猫は無反応だったが、セーラー服がついた散歩用のリードを見ると、ソファを飛び降りてくる。尻尾がピンと立っているので、よほど嬉しいらしい。
「猫って、散歩するんですか?」と思わず一心は尋ねた。
鈴さんは慣れた手つきでプクにセーラー服を着せながら、「ねえ、珍しい猫よねえ」と自分でも呆れている。
外へ出ると、プクは慣れた様子で前庭の低い石垣に飛び乗り、優雅な足取りで渡っていく。いつものコースらしく、そのまま高くなる石垣から途中で降りると、今度は鈴さんの足に体をこすりつけながら歩き出す。
「猫の散歩って初めて見ました」
ガードレールの上を器用に歩いていくプクを追いながら一心は声をかけた。
鈴さんとプクの距離感は完璧で、リードがピンと張りそうになるとプクが待つ。
「大きな犬にも物怖じしないのよ。たまにシャーッなんて威嚇して。きっと、飼い主に似たんでしょ」
機嫌よく笑う鈴さんは健脚で、街並みを眺めながらのんびり歩く一心はときどき駆け足で追いかけなければならない。
「いつもは和歌山県か鳥取県まで歩くのよ」
「え?」
意味が分からず一心は訊き返した。
「皇居の周りの道に、全国の都道府県の花を紹介するプレートが百メートルおきに埋めてあるの。千鳥ヶ淵の交差点に滋賀と京都があって、反時計回りに半蔵門まで歩くと和歌山県。一人でウォーキングするときはそれこそ長崎まで行って帰ってくることもあるんだから」
「長崎ってどこの辺ですか?」
「桜田門。警視庁のまえ」
「僕、長崎出身なんですよ」
「あら、そうなの? 市内?」
「はい。鈴さんも出身は長崎ですよね」
「……あら、そう。……あなたも長崎の人か」
やはり猫の散歩は珍しいようで、行き交う人が好奇の目を向ける。ただ、鈴さんとプクは慣れたもので気にもしない。
プクがとつぜんリードを強く引いて先を急ぎ出したのは、その皇居のお濠へ出る少し手前、新しくマンションが建つらしい工事現場のまえだった。すでに古い建物は解体されており、建築会社の名前が大きく書かれた高い養生壁の向こうには、ぽっかりと青空が広がっている。
「プクちゃん、今日も、警備のお姉さん、いるねえ」
鈴さんもプクに引かれて少し足早になる。何ごとかと一心もあとをついていくと、養生壁のまえに女性警備員が一人ポツンと立っていた。特にトラックや作業員たちの出入りもないようで、退屈そうである。
女性警備員もすぐにプクに気づいたらしく、「プクちゃん、今日もお散歩してもらってるの」としゃがみこむ。プクはその足元で体を地面にこすりつけながら、撫でてくれとばかりにその白い腹を見せる。
女性警備員は六十代だろうか。日に灼けた顔に化粧っ気はなく、長くこの仕事をしているらしい貫禄がある。
「今日はちょっとあったかいから楽ね」
鈴さんがプクの腹を撫でる彼女に声をかけ、「……あ、そうそう。今日はあなたにプレゼントがあるのよ」とトートバッグから小さな箱を出す。
プクを抱いて立ち上がった彼女に、鈴さんが渡したのは小さな雛人形だった。手のひらサイズのガラスケースに入った磁器の人形で、古そうだが高価そうである。
「このまえ生まれたお孫さんにと思って」
とつぜんのプレゼントによほど驚いたらしく、彼女はおでこに下がってくる大きめのヘルメットを何度も押し上げながら、その目にはうっすらと涙を浮かべている。
「……ここの工事が始まってから、ずっとプクがあなたに会うのを楽しみにしてるでしょ。こうやってプクを散歩させるようになってずいぶん経つけど、プクがこんなに懐いたの、あなただけなんだもの」
「でも、こんな立派なもの、いただけないです」
「立派なんてもんじゃないのよ。でも、きれいでしょ? 有田焼だと思うけど、ずいぶんまえにね、知り合いから頂いたの。遠慮せずにもらってよ。その方がこのお人形さんも喜ぶんだから」
一心は二人のやりとりを少し離れた場所で眺めていた。東京を歩いていれば、工事現場などどこにもあり、必ずそこには警備員が立っている。ただ、そんな彼らと交流を持っている人を見たのは、これが初めてだった。
彼らと交流を持ったからどうということではない。逆に交流を持たなくたってどうということではない。ただ、鈴さんはこういう警備員の孫の誕生を祝ってあげる人なのだと思っただけだ。