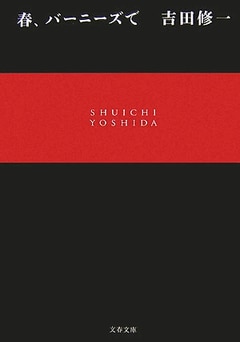『橋を渡る』が「週刊文春」に連載されたのは二〇一四年から二〇一五年にかけてのことだった。この時期、毎週のような特大スクープで「週刊文春」は他誌を圧倒していた。連載終了後のことだが、不倫報道の餌食になったベッキーの発した「センテンス スプリング」(「文春」の珍訳)は流行語にまでなる。
「文春」にはすでに「どぎつい物語」があふれていたのである。そこにどうフィクションの居場所を見つけるか、当然、作家は考えただろう。
吉田修一の答えは、まずはニュースそのものに飛びこんでいくことだった。『橋を渡る』を読み進めるとわかるように、作中には「セウォル号沈没事件」や「ワールドカップ」から「都議会セクハラヤジ問題」「iPS細胞」など、実際にメディアを賑わしたニュースが溢れている。
これはなかなかの冒険だ。現実のニュースはとにかく刺激が強い。新しさ、珍しさ、感情的な盛り上がり、そしてもちろん実在の人物たち。通常、フィクションではこうした刺激から距離をおき、現実をひと味ちがう視点から切り取る。そうしないと、「どぎつい物語」の刺激に押し流されてしまう危険があるから。