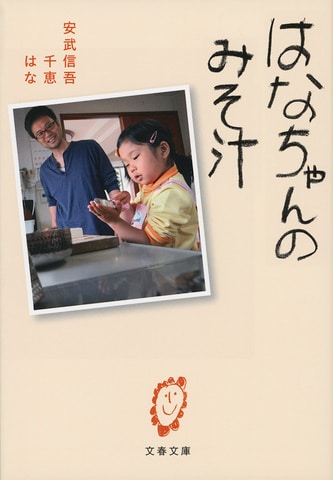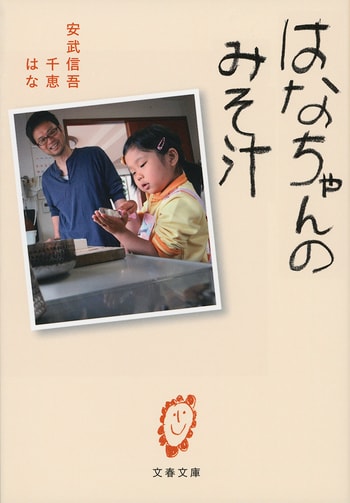最愛の千恵さんの命を救えなかった信吾さんの失意の深さは、私には想像することさえできない。半ば廃人のようになった信吾さんを気遣っている人たちの話も聞こえてきた。しかし何よりも、父子家庭の育児の不安と絶望感の淵にいた信吾さんを再生させたのは、はなちゃん手作りのみそ汁だった。千恵さんは亡きあとも、みそ汁を使って信吾さんの命を立ち直らせた。
信吾さんは千恵さんよりも手料理ができる人だった。そのことは本書でも、結婚する前に千恵さんの手料理を初めて食べたときのエピソードとして紹介されている。千恵さんが亡くなったあと、信吾さんがみそ汁を作ることはわけなかっただろうが、はなちゃんとの約束は千恵さんの“遺言”であった。そして信吾さんにとって、五歳のはなちゃんが台所に立つことは「自分が料理したほうが早い」という苛立ちの時間ではなく、千恵さんとの約束を守って、はなちゃんが成長していくために必要な大切で楽しい時間であったのだ。
「はな、上手に作ったな、このみそ汁。お母さんの作ったみそ汁とおんなじ味がする。おいしいよ」
はなちゃんはお父さんのこの言葉が聞きたくて、台所でみそ汁を作り続けた。
一方で、私は、実は信吾・はな父子家庭に危慎していたことがある。はなちゃんがあまりにも「いい母親」になっていたことだ。
はなちゃんは五歳から母親役を務めることでお父さんを支え、お父さんに喜んでもらうことに充実感を得ていたが、子どもという生き物は本来、わがままを言い、親に甘えながら育つ一面がある。
私は千恵さんの遺したブログに「竹うどん」というハンドルネームで、信吾さんに注意を促すコメントを書き込んだ――子どもには、子どもとして無条件の親の愛の庇護に置かれる権利がある。千恵さんの代役を立派に果たそうとするはなちゃんに意図的に「子どもの時間」を与えてほしい、と。
人は繰り返される日常を「普通」と認識して適応し、社会性をはぐくんでいく。これは、進化の過程で脳に仕組まれた生き残り戦術なのだ。「小さい時から台所に立たされた、父子家庭のかわいそうな子」という自覚は、はなちゃんにはない。はなちゃんが小学一年生の時、「お母さんがいなくて寂しくない?」と友だちに問われて「ううん。お父さんがいるから大丈夫」と答えたという。
私は三十八年間の教師経験があるから、周りの大人たちが無遠慮に注ぐ「かわいそうな子」という視線が、両親がそろっていない(最近は両親の離婚も多くなった)子どもたちを、非行に走らせるケースが少なくないことを知っている。
だからこそ、大人たちは「あなたはかわいそうじゃない。この世に生を受けて、そして今、誰かのおかげで生きている。その人への感謝の気持ちを忘れないで。その人を悲しませないように生きること。その力をつけて生きなさい。過去はたった一日でもやり直しはできないけれど、未来は自分の意志でつくっていけるから」と言い切ったほうがいい。
みそ汁を作り続け、信吾さんにほめられ続け、はなちゃんには「お父さんのために料理を作ることは楽しい」という心が根付いた。それが千恵さんからプレゼントされた宝だった。私が子どもだけで作る“弁当の日”で目指した「子どもが育つ環境」づくりが、千恵さんの「余命」の数か月に凝縮されていた。まさに命がけで千恵さんははなちゃんに一生の宝をプレゼントしたのだ。
だから、はなちゃんはお母さんの亡くなった後も、お父さんに喜んでもらうために料理のレパートリーを増やしていった。たまごやき、オムライス、肉じゃが、カレー…。そして最近は野菜作りを始めていて、採れたての新鮮野菜をてんぷらに揚げる楽しさを身につけた。私も福岡県で講演した折には、よく、はなちゃんと「しりとり」に興じ(だから、一時期、はなちゃんは私のことを「しりとりおじさん」と呼んでいた)、お家に泊まった翌日には、「はなちゃんのみそ汁」をいただいた。私ははなちゃんを通して、千恵さんのいのちもいただいたことになる。