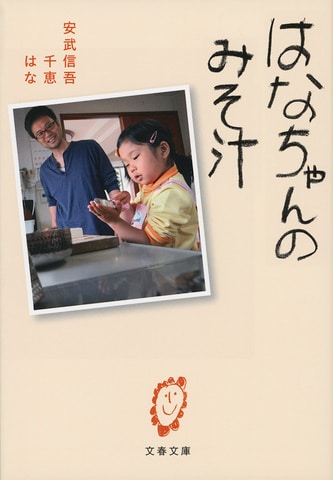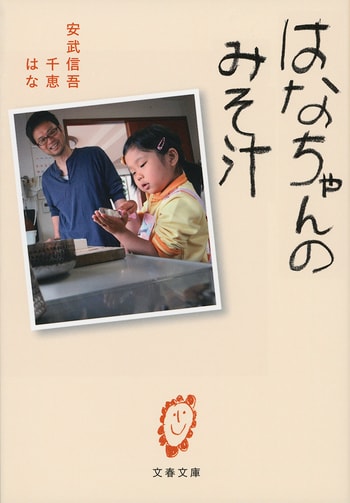千恵さんは「心を鬼にして」はなちゃんを台所に立たせ始めた。五歳前の子どもに食事を作らせるのはかわいそうだと思っていたからだ。だが子どもは子どもで、幼いころから台所にやって来ては「やらせて」「できることある?」「何か手伝おうか」と言うものだ。その度合いは五歳がピークで、十歳になると、もう言ってこなくなる。これは味覚の発達プログラムともリンクしており、極めて自然な現象なのだ。多くの親が子どものけがを恐れたり、忙しさから余裕が持てなかったりで子どもを台所から遠ざけてしまうが、「心を鬼にして」はなちゃんを台所に立たせたことがいかに素晴らしい親の仕事であったか。そのことを、私の講演のスライドショーで涙した大人たちは学んでいる。
「今日の講演を聞いて、今日からわが子に人生にとって最も大切なものを伝えにかかろうと思っても、不慮の事故で帰宅前に亡くなることもありますよ。もし、そうなったとしても死ぬ間際に“今日までの自分の子育てに悔いはない。伝えるべきことは伝えてきた”と言い切れる方、手をあげてください」
講演会でこの質問をするのは幼稚園・保育所などの保護者を対象にしていることが多い。会場は一気に重い空気に包まれ、参加者は手が上がる人を探そうともしない。誰一人手が上がらなかった会場の方が多く、これまでの講演で挙手された方は合計で十人に満たない。そしてその方たちは二つのグループに分けられる。高齢出産の方と余命を宣告された経験のある方。つまり、自分亡き後のわが子を切実な想いでイメージした方たちなのだ。
東日本を大きく震わせた二〇一一年の「3・11」は明日という近未来でさえ誰にも約束されていないことを教えてくれた。そして家族そろっての日常の団欒だけで「かけがえのない幸福」であったことを痛感した被災者が大勢いらっしゃる。
幼いうちから子どもを台所に立たせることは、子どもの成長を考えると、とっても大切なことなのだ。残された時間の長短こそあれ、すべての親は、子どもに対して、余命というタイムリミットを持っているのだから。
すべての親にとって子育てはいつも手探りなのだ。手探りだから真剣になり、真剣だから伝わる。できれば明るく伝えたい。それを千恵さんが実践した。信吾さんがつないだ。そしてはなちゃんの成長が全国の親を育てている。
心の底から湧いてくる衝動を受けて、失敗にもくじけないで次々と新しい事柄にチャレンジしていく力を「生きる力」という。