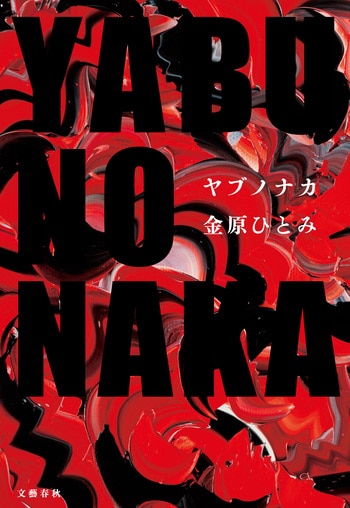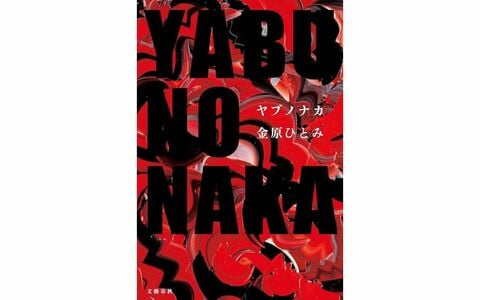〈「離婚ゼクシィ」があればいいのに! 手探りだらけの離婚で大変だったこと――小説家・金原ひとみ×千早茜「私たちの離婚と再婚」〉から続く
千早茜さんが「珍しく、この小説には自分の体験も入っています」と語る“離婚”小説の『マリエ』。金原ひとみさんも、「私も離婚が成立してそこまで時間が経っていないので、一気に親近感が湧きました」と話が弾んだ初対談。
とても一言では語れない実際の離婚体験から、体験を描く際の流儀まで、作家の本音満載でお届けします。(前後編の後編/前編を読む)
◆◆◆
コロナが結婚へのハードルを下げた?
千早 金原さんは二〇二四年に離婚されたんですね。いつぐらいから、どれぐらいの時間をかけて離婚問題と向き合っていらしたか、聞いても大丈夫ですか。
金原 私はもうけっこうずっと離婚したかったんです。ある時向こうが決定的な一言を口にして、その日のうちに別れてくれと言いました。それから濃淡はあったんですけど、ずっと離婚はしたかった。もう一生許せないだろうと分かっていたので。でもそこからけっこう時間がかかりましたね。
その間は、周りのみんなの離婚話が助けになっていました。あちこちで「離婚経験ありますか?」と聞いて、どんな離婚だったかをヒアリングして。だから私、出版業界の人たちの離婚話を業界一網羅しているかもしれません(笑)。

千早 離婚率が高い業界ですもんね。私も誰かに離婚経験を聞きたかったんですけど、私の友達、そもそも結婚してる人が少なかったんです。
でも世の中がコロナ一色になった時期に、結婚は自分の人生に必要ないと言っていた友達たちが、「このままだと孤独死するのかな」とか言いだしたんですよ。コロナでこんなに価値観が変わるんだってビックリしました。結婚相談所もやっぱり、コロナ禍以降で登録者数がすごく増えたらしいんですよね。
金原 へえー、そうなんですね。
千早 私はふだん、小説には時代性を出さないように気を付けているんですが、そういう背景があったから、『マリエ』にはコロナの描写を入れました。今の離婚をテーマにするのであれば、社会現象としてコロナを登場させる必要があると思って。多分コロナじゃなかったら、独身だからといって孤独死まで考える人は多くなかったと思うんですよね。

金原 きっとそうですね。『マリエ』では、新しい恋人とコロナに罹って二人で部屋に閉じこもるシーンがありますけど、私も同じ状況になったんですよ。まったく匂いを感じなくなって。
千早 あ、罹っちゃったんですか。
金原 療養してる最中に匂いも味も完全になくなって、あの時の奇妙な感覚と苦しみが、この本を読んで蘇ってきました。お話を聞いているとこの本は、千早さんがこれまでやってこなかったことに挑戦した一冊なんですね。
千早 そうなんです。挑戦というには地味ですけどね。
離婚の瞬間、その人が溢れ出す
金原 料理のシーンがめちゃくちゃよかったです。聞いたこともない料理がたくさん出てきて。由井君と一緒に生地を練って作る料理とか。私、料理は好きなんですけど、凝ったものは全然作らないのですごく面白かった。
千早 でも、最近の金原さんの小説でもわりと凝った料理が出てきましたよね。あ、あれだ。『マザーアウトロウ』で、彼氏の蹴人君が家で作ってた……。
金原 あ、エンパナーダ。
千早 それです! 何だこの料理はと思って調べました。
金原 エンパナーダ、実際に生地から作ってみたんですけど、マジで時間がかかり過ぎて(笑)。バカみたいな思いをして作ったので、この経験を何かに使わないとと思って小説に書きました。

千早 エンパナーダってどこかで食べられますか。
金原 フランスにいた頃に、レバノン系とかメキシコ系の料理屋さんではよくメニューにあったんです。スパイシーで、生地がちょっと独特な、サクッ、ほろっとした、クッキーに近いような食感で。
千早 食べてみたい。私、『わるい食べもの』という食エッセイも書いてるんですけど、そこでは食に関する呪いみたいなものを外していきたいという野望があって。私は、いわゆる「ていねいな暮らし」が好きなんです。
金原 はい。伝わってきます。
千早 でも、「ていねいな暮らし」って、世間では「(笑)」がつけられるような扱いを受けるときがあって。そのことにずっとカチンときてたんですけど、コロナ中ってそれがちょっと変わったんですよね。
金原 みんな、料理道具とかを調え始めて、ホットケーキミックスとかベーキングパウダーが売り切れましたよね。
千早 そうそう。家にいることが増えたからか、「こんな手のかかる料理作っちゃった」とか、「ワイングラス揃えちゃった」とか、みんな家でできることを楽しみだした。
金原 あとコロナって、人の内面をかなり浮き彫りにしたと思いませんか? 「この人、そういう人だったんだ」って。
千早 なりました、なりました!
金原 ウイルスをどれくらい気にするかも人それぞれで、「え、あなたがそんなに気にするの?」とか、意外な側面がたくさん見えた時期だったなと。
千早 あまりコロナ対策をしてない人に対して、対策してる人が怒るとか。
金原 ありましたね。逆に「絶対にマスクはつけない!」と言い張る人もいたし。
そういう意味で、コロナも離婚も、どちらも人をむき出しにさせる点で似ていると思うんです。「自分はこう思う」をどうしても押し付けなきゃいけない状況なんでしょうね。
千早 なるほどー! その見方はすごく面白いです。
金原 たくさんの人から話を聞いたので、いろいろな離婚の形があることもわかった。別れた今でも仲良しっていう人もいれば、相手のことを「死ね」と言ってる人もいる。親権とかお金とかメンツとか、気にするところもまちまち。個人の結婚観の違いが、離婚によって明らかになる、みたいな瞬間があると思いました。
千早 逆に結婚はただただめでたいものという側面が強くて、あまり差がでてこないんですかね。
金原 そうですね。結婚しただけなら、まあまあ楽しい結婚生活を送ってるんだろうと思うだけなんですけど、別れる段階になると、「そこが許せなかったのか」とか、「離婚条件で競り合ったのそこか」とか、エピソードのディテールが人によって全然違う。離婚の話ってその人のパーソナリティが溢れ出すので、結婚より全然面白いですね、ネタとしては。
エッセイは本当の話じゃなきゃダメ?
千早 金原さんの『パリの砂漠、東京の蜃気楼』というエッセイ集も読んだんですけど、金原さんのエッセイって小説みたいだなって、思っていたんですよ。
金原 ありがとうございます。おっしゃる通り、この十年くらいエッセイは小説と同じだと思って書いてます。
千早 あ、やっぱり。
金原 デビューした頃はエッセイがすごく苦手だったんです。変におどけた感じのエッセイとかを書いたりもしてたんですけど、小説に比べてなんでこんなに心地が悪いんだろうって不思議でした。でも、『パリの砂漠』は、掌編小説を書くつもりで書いたらすっごくスムーズに書けた。「なんだ、こっちのほうが書きやすいじゃん」って。この辺りからエッセイと小説の境目を気にしなくなりました。最近はエッセイの依頼が来ても、お構いなしにフィクションにしちゃっています(笑)。だってそもそも、現実をそのまま書くなんて不可能ですし。
千早 そうなんですよね。でも、エッセイって本当の話じゃなきゃいけないっていう圧が世間的にはあるじゃないですか。私はそれを意識してしまうから、エッセイが嫌で嫌で。『わるい食べもの』みたいに「食」という切り口があればなんとかなるんですけど、自分の日常を書く場合、噓を書いちゃダメということに縛られて、何が言いたいのかわかんなくなるんです。

金原 でも私、千早さんの私生活が垣間見える『胃が合うふたり』をすごく楽しく読みました。
千早 ああ、読んでくださったんですね。その本の共著者の新井見枝香さんはエッセイに噓をばんばん書けるんですよ。一緒に食事に行って書くというテーマだったのに、まったく関係のないことから書きだすし、それでいて面白い。書きながら「この人とはメンタルが全然違う」と思っていました。
金原 その違いがすごく興味深かったです。同じものを見ていても、全然違うメンタリティーでそれと向き合ってる。
千早 金原さんは小説には作家自身のことが書かれているみたいな読み方をされるのはどう思いますか。例えば『YABUNONAKA』だったら、この主人公の女性作家は金原さん自身っていう読み方をする人もいるじゃないですか。
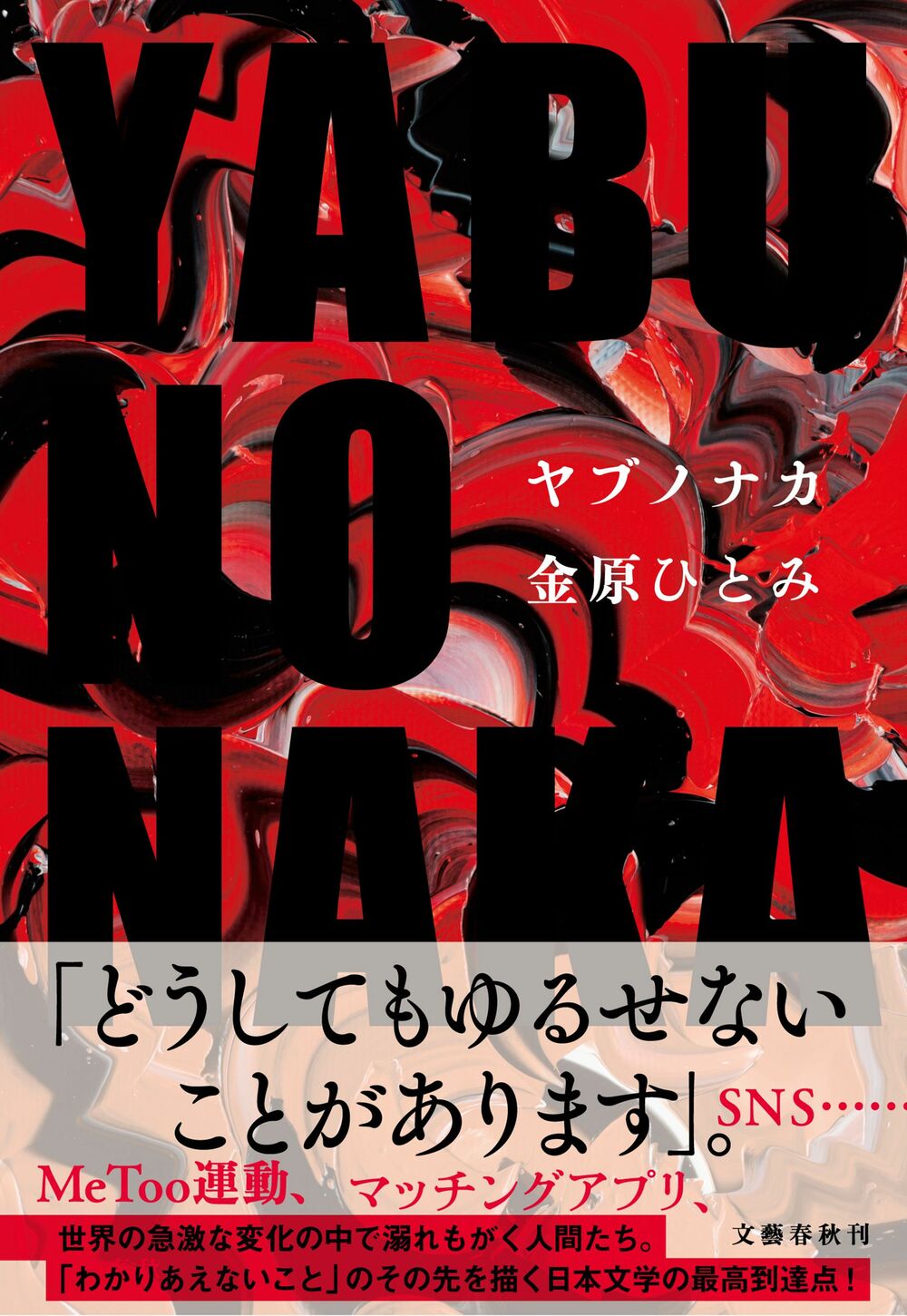
金原 それはそれで全然構わないです。デビューした頃から、「主人公と自分を混同されることをどう思いますか」ってよく聞かれるんですけど、本当にどうでもよくて(笑)。どう読むかは読者の感受性によって決まるもので、受け取る側のフィールドだから、好きに読んでもらってかまわない。自分も誰かの書いた小説を読むときに、「もしかして実体験なのかな」とか考えますし。

千早 金原さんは河出文庫から出ている『私小説 作家は真実の言葉で噓をつく』という企画の編集もされていますよね。
金原 そうですね。私小説って言うと、みんな身構えちゃうじゃないですか。いわゆる昔の無頼な文豪たちが露悪的に酒や女にまつわる私生活を書いているのが私小説みたいな(笑)。「ドロドロしてるもの=私小説」みたいなイメージが古くさくて嫌だったんです。というのは私、私小説的な要素が入った作品がすごく好きなんですよね。モラヴィアやオルハン・パムク、ミシェル・ウエルベックとか、日本だと滝口悠生さんとか。なのでそろそろアップデートして皆にガンガン私小説を書いてもらいたいなと、そういう企画意図を伝えて作家のみなさんに依頼したんですけど、それでもやっぱり「いや、私小説はちょっと」みたいな反応は多かったです。
千早 確かに私にその依頼が来ていたら、「私小説とは何だ」ってなって一週間ぐらいフリーズしてそう(笑)。
金原 でも、自分にとって真実の言葉で書けば、それは私小説なんじゃないかなって思うんですよね。
千早 すごい素敵な言葉。
金原 ずっと私はそう思っているんです。実際にあったことかどうかというのは問題じゃなく、真実の言葉で書いているかどうかを意識して書いてくれれば全て私小説なんじゃないかな、と。
再び結婚を決めた理由
千早 私は再婚するときもけっこう迷ったんですよ。恋愛は二人で新しい関係性を作っていく建設的で楽しい行為と思えるけど、結婚は制度としか思えなくて。向こうは初婚でしたし。でもずっと「結婚しよう」って言われていて、こちらのネガティブな結婚観を押しつけるみたいなのもどうかと思うようになりました。金原さんはそこの迷いはなかったですか。
金原 なかったですね。
千早 結婚したかった?
金原 どうなんだろう……? 結婚したいとかしたくないとか、あんまり考えたことがなくて。私はわりと、結婚のことを愛情表現の一種だと思ってるんです。
千早 あ、「結婚したいぐらい好きだよ!」っていう。
金原 そうそう!
千早 最上級ってことですか。
金原 いや、もっと上はあるんじゃないですか、「臓器提供できるよ」とか(笑)。ただ、そういう愛情表現の中の一つだとは思っています。
千早 へえー。考えたこともなかった。初めて聞く意見です。
金原 結婚のことを、社会的なものというより、かなり個人的なものだと思ってるんですよね。
千早 面白ーい。制度を使って愛情表現をするみたいなことですか。
金原 ちょっと制度を利用してるぐらいの感覚ですね。
そういえば、結婚についてはすごくいい言葉があって、江國香織さんの小説に出てきたんですけど、「結婚って、基本的に子どもがすることでしょ?」
千早 それ、私も読んだかも。
金原 『シェニール織とか黄肉のメロンとか』という小説で、五十代後半の女性三人の話なんですけど、その中の一番遊んでいるタイプの女性がそう言うんですよ。まあ、言われてみればそうですよね。だいたいみんな二十代とか三十代で結婚するわけじゃないですか。間違えて当然、うまくいかなくて当然だよねっていう。
千早 いい言葉ですよね。
金原 それくらいのテンションでいれば、制度としての結婚にとらわれずに済むのかなと思いますね。
千早 バツがついても別にいいよねって。ただ経験者としては、離婚しようと思ってもなかなかすぐにできるものではないので、結婚するときはそのへんは慎重にと思いますね(笑)。

金原 はい。私も離婚のときにいろいろと揉めたので、人が結婚するって話を聞くと、「婚前契約書、交わしといたほうがいいよ」とアドバイスしますね。お金のこととか。
千早 それは良いかも。関係がうまくいってるときなら建設的に条件交渉もできますもんね。
金原 ただ、みんなあんまり真剣には受け取ってくれないんです。「旦那のほうが稼いでいるから」とか言って。
千早 ああ……。でも状況って変わりますからね。結婚生活のあいだに、時代も変わるし人間も変わっていくから。
金原 そうそう。でも結婚するときって、絶対に自分たちは変わらないと思ってる。
千早 むしろ「変えないように」結婚するんだと思います。
金原 だからこそ、このアドバイスができるのは離婚経験者だけなんですけど、やっぱり初婚の人には届かないんですよね。
離婚は幸せになるための選択肢
金原 離婚できなかったときに慰めになっていたのが、ニコール・キッドマンが離婚問題が片付いて弁護士事務所から出てきたところとされているネットミームの写真で。
千早 え、見たい。
金原 解放感にあふれていて、すごくいいんですよ。この写真なんですけど……(スマホで画像を見せる)。
千早 すごい(笑)。喜びが爆発してますね。
金原 悩んでいた時に「早くこれになってね」ってこの画像を見せてくれた友達がいて、ずっと心の支えになってました。「私もいつかはこうなれる」って信じて頑張ってきたところがあって。だから私、ようやく離婚が成立したときは、「あれになれたんだ!」ってワックワクで日比谷公園を歩きました(笑)。もう足が宙に浮いてるみたいで、本当に世界が輝き始めた瞬間でした。
千早 私も、離婚届を出しに行った日に面白いことがあったんですよ。最後に離婚届は二人で出しに行ったんですけど、役所の窓口に立った瞬間に私が「渡辺淳一文学賞」を受賞したことがネットニュースに流れたんです。それを見た友人たちから「おめでとう」ってめっちゃLINEが来て(笑)。離婚届をちょうど出してるときに、「おめでとう」「おめでとう」っていう通知でスマホ画面がいっぱいになって二人で笑ってしまいました。

金原 すごいエピソードですね! 最高の偶然の一致。でも離婚って本来めちゃくちゃポジティブなものですよね。みんな離婚して幸せになってるなって、周りを見ても思うんです。
千早 そうそう。「離婚したんだ」って言うと、「大変だったね」とか「大丈夫?」とか心配されることが多いんですけど、私としては「今、どんな気持ち?」とか「幸せ?」とか、そういうふうに聞いてほしいんですよね。「めっちゃ幸せ!」と私は言いたいので。
金原 うんうん。私も離婚してからずっと幸せです。
千早 お互いに幸せになるための選択肢として離婚があると私は思うし、実際自分はそうでした。悩んでいる人に、離婚がひとつのポジティブな選択肢になればいいなと思っています。
【プロフィール】
金原ひとみ(かねはら・ひとみ)
1983年東京都生まれ。2003年に『蛇にピアス』でデビュー。04年に同作で芥川賞を、21年『アンソーシャル ディスタンス』で谷崎潤一郎賞を、25年『YABUNONAKA―ヤブノナカ―』で毎日出版文化賞(文学・芸術部門)を受賞。
千早茜(ちはや・あかね)
1979年北海道生まれ。2008年に、小説すばる新人賞を受賞した『魚神』(「魚」から改題)でデビュー。09年、同作にて泉鏡花文学賞、13年『あとかた』で島清恋愛文学賞、21年『透明な夜の香り』で渡辺淳一文学賞、23年『しろがねの葉』で直木賞受賞。他に『男ともだち』『正しい女たち』『神様の暇つぶし』『赤い月の香り』『マリエ』『雷と走る』など著書多数。