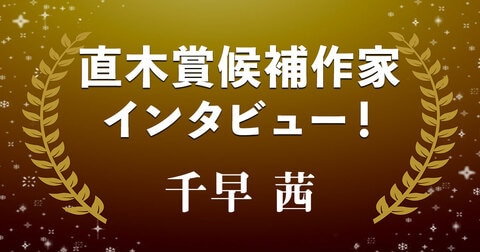新人賞受賞時の選考委員だった「ダディ」が新・直木賞作家へ贈る、厳しくも愛あふれる言葉とは。
北方 今回の直木賞受賞作『しろがねの葉』を読んで、ものすごく小説がうまくなったのを感じました。
千早 ありがとうございます。北方先生は、私がデビューした「小説すばる新人賞」の選考委員で、「小説すばる新人賞」の出身者はみんな、北方先生のことをダディと呼んでいるので、今日もそうお呼びしますね。
北方 最初の印象はもっとかわいい女の子だった。
千早 ちょっと待って(笑)。
北方 プロの作家を前にして、どうしていいか分からないという感じの、初々しい可愛さだよ。『魚神(いおがみ)』(受賞作「魚」を改題)については「これは泉鏡花賞もの」「鏡花賞風」とか言ったら、そのまま泉鏡花文学賞も取ったんだよな。
千早 ちょうど矢野隆さんの『蛇衆』と同時受賞だったんですけど、ダディは我々のことを「ヘビとサカナ」って呼んでましたよね(笑)。授賞式の二次会の時に、「矢野、お前は一年に5冊書け」「千早、お前は2~3冊でいいよ」と。手加減されたと思いました。
北方 矢野は書かなきゃ駄目でしょう。数を書いて、いっぱいの中から傑作が出てくるかもしれないという作家で、想像力のダイナミズムのとっかかりがいっぱいあるから。あなたは想像力のダイナミズムがまだできてないから、数書いたらつぶれちゃうよ。
千早 じゃあ、まだかわいらしい女の子?
北方 変わったのは外見だけ。
千早 ひどい(笑)。

水の冷たさ、闇の怖さといった無限の広さ
北方 ずっと、イメージを大事にして書いてきたでしょう。小説ってイメージの芸術なんですよ。説明の芸術じゃない。それをきちんと分かって書いてるから。今回、うまくなったと感じたのは、いわゆる描写的なところ。描写的とは小説的ということです。その描写の力が明確にあって、それは書き続けている間にどこかで無意識に身についちゃったんじゃないかな。『魚神』にはなかったものが、いっぱいありますよ。
千早 ほんとですか?
北方 たとえば、細かい描写。『魚神』はおどろおどろしいとか、イメージ的だったところが、『しろがねの葉』の中では、水の冷たさ、闇の深さがあった。この小説の中の世界の狭さについて問う選考委員もいたけど、小説の広さに関して論議する時に、ただ単に地面の広さを、場所の広さを言うのはナンセンス。上限はたかが地球で、どんなに広くしても地球以上に広くなれない。
千早 SFでもない限り、宇宙まで行けませんからね。
北方 ところが、闇の広さとか、小説家の世界の広さは、無限の広さとなり得るものでしょう。地面が狭くても無限の広さがあるのが小説で、闇というのは潜って中に入ったら、無限の広さがある。その闇が書けているから、俺は全然狭いと思わなかった。そういう、無限の広さを無意識に出せるようになってるよね。間歩の中も、においがあり、毒があり、空気があり、あそこで働いているやつの手が冷たかったりする。それらが全部総合されて描写になっているから、闇の怖さが分かる。見える。そこが「ああ、力を付けたんだな」と思った。
千早 ほんとに? うれしいです。
北方 それだけの作品であったと思います。でも、褒めるのはここまでで。
千早 はい(笑)。
北方 終盤で時間が飛ぶ意味がどれだけあるのかと考えた。トントントンと時間が飛んで、それまで筒であったものが輪切りになっている。その必然性は、はっきり言ってよく分からなかったね。
千早 ラストがちょっと飛びすぎたかなというのは、自分でも懸念点でした。
北方 時代も時間もスーッと筒で来たものが、ストンストンストンと輪切りになって最後まで書いてるから、女の一代記だという評も選考会ではありました。主人公のウメにとって、間歩は恐怖とか地獄であると同時に歓喜だったんじゃないか。その歓喜を書くのが小説でしょう。
千早 連載を終えてから直した部分もありましたが、歓喜ですか、そこには行きつきませんでした。
北方 単行本にする時に、書き直そうと思うのも駄目なんです。連載の時に、最後のところにあらゆるエネルギーを集中して書いていたら、次元が違う小説になった。
千早 体力をもう少しつけたいです。
北方 いや、気力ですよ。普段は持ち上がらないものが、持ち上がるというのは潜在能力。それが途中から出て、最後の二ページで、さらにものすごい飛躍できる。その飛躍が小説の結末だと思うこともあります。ただ説明して終わって、主人公の一生が閉じればそれでいいというものじゃない。あなたの場合は、どこかで最終的に小説のダイナミズムを何か心の中で収束してしまうというのが『魚神』の時からあります。ごめんね。今日はお祝いの対談なのに、期待が大きい分、いろいろと欲張って注文してしまいました。
千早 いえ、今日は問題点を聞こうと思ってきたので、すごくありがたいです。
北方 小説はイメージの芸術だから。『しろがねの葉』はそのイメージをちゃんと書いている。吐いてる血の毒々しさもちゃんと描写で書かれているし、思いがイメージとして存在している。女たちが抱く思いはいつもあてどのないもので、男が次々と死んでいくから、三人ぐらい亭主をもらわなきゃ駄目なんだと言うけど、ちゃんと生きている証を作るやつも居る。それを作者は書こうと思っていて、きちんとできています。だからといって、ものすごい傑作というわけじゃない。改革の余地はいっぱいある。
千早 私は、整合性を考えて作るタイプなので、ウメも、この時代に女であの穴の中に入りたいと思う子というのは、やっぱり、気が強くて、養ってくれる喜兵衛も呼び捨てにするような、したたかな、ふてぶてしい子かなというイメージで作りました。不思議の国のアリスみたいに女の子が自分から穴に入るってどんな性格だろうと考えたんですよね。

北方 それが森の中にある小っちゃな穴倉の闇の中で、そこにかわいい動物が居るとかじゃなくて、銀山の中の間歩でよかったな。間歩の中が地獄だったから、無限の広さが出たんだよ。
千早 石見の女が3人の夫を持ったという伝承を現地のガイドさんに聞いて、好きな男を3回も看送っていく女の一生を書きたいと思ったんです。銀山を描くならば、間歩を書かなきゃいけない。女が入れないなら、入れるしかないという感じで。
北方 山師の喜兵衛とウメの人間関係は、ずいぶん苦労しただろうし、工夫もしただろうけど、完璧にうまくいったかどうかも疑問だったね。それでも、よく書いた。特に間歩。どこにでもある暗さではなく、間歩の暗さとして書けているし、水の冷たさや、怖さも。ウメが集団に襲われてバージンを失う時の、恐怖と痛みが同時に来るところは強烈でした。「くそーっ」と思って生きていく、したたかなウメという人間をきちんと書く力量がある。だから、あなたが今後どういうものを書けばいいかというのは分かりません。
千早 ええっ。
北方 それは自分で決めるんです。もう少し高みの世界を狙えるだけの実力が充分にあると認められたし、今回自分でも自覚できたと思う。賞をもらうことによってできる自覚がね。だから、次の作品というのはものすごい期待してる。
千早 怖いな。
北方 もうあなたは堂々たる作家なんだから、俺に反論して「バカ野郎」とか言ってよ。
千早 言えない(笑)。昔、小説の駄目なところをダディが指摘してくれた時、私が「でも」と言い返そうとしたら「でも、は作品で聞く」とぴしゃりと仰ったじゃないですか。
北方 今日は好き勝手に話しているから、横で編集者がハラハラしているけれど、小説の話なんだから自由でいいんだ。自由に語っているうちに何か出てくるんだよ。それが一番本物。「構造(プロツト)はどうやって立てるんですか?」とか聞いたってしょうがない。ウメを書いた時にいろいろ考えたことで、この人が生きていくわけだ。少しずつ少しずつ考えたウメっていうのは変わってきているはずなんだ。この小説の中でウメは生きる。生きるために変わっていくんだ。それは充分に感じたから、もちろん全部設計図通りに書いたと思ってない。生きてる人は作者がどうにもできないようなこともあるんだよ。

千早 確かに、今までは設計図どおりに書くタイプだったんですけど、今回はどうにもならないところがありました。最初に考えたウメから変化していった。
北方 だからよかったんだよ、千早。小説の人物が、設計図の中で生きてるというのは、生命がない状態なんだ。それが、生命を持っちゃった瞬間に、その人物が感覚や思想とか、いろんなものを持つ。その感覚にしたがえば、作者が思った通りには行ってくれなかったりする。それが小説の中で人が生きるということ。
千早 ちょっとだけつかめた気がしました。
北方 小説って最終的には人を書くから。いろんな事象があったとしても。小説の中では自分が作る人間じゃなくて、できあがってくれる人間だと。そう思っていれば、その人は生きるよ。
千早 「小説すばる」は、いつも授賞式の二次会があるじゃないですか。私が賞の候補に挙がると、必ずダディが反省点とか言ってくれて。『男ともだち』の後に、「お前、もう1回ぐらい俺に作品を読ませろよ」と言ってくれたんですよ。その時、新人賞から出直してこいという意味だと思って、「ごめんなさい」と謝ったら、村山由佳さんが「違うよ。千早、察しが悪いんだから。もう1回、直木賞の候補まで上がってこいということだよ」と笑いながら教えてくれて。
北方 そう。もう1回、直木賞の選考会で読みたいと言ったんだ。
千早 ダディが居なくなった後に気づいて、また頑張らなきゃと思いました。北方先生もですけれど、宮部みゆき先生も私がデビューした時の選考委員でしたから、お二人に本を読んでもらうには直木の候補にならないといけない。だから、今回は本当にうれしかったんです。
北方 いい性格してるな。いい性格してるから、小説を書くんだ。
千早 以前、直木賞の候補作になった『男ともだち』は体の関係のない男女の話なんですけど、「リアリティがない」、「男は下心のない女に優しくしない」という意見が選考委員の方からも読者の方からも上がっていました。
北方 いや、下心のない女には優しくする。下心がある女には優しくしないよ。どこかでその下心をくじいてやろうとか、いろんなことを考える(笑)。
千早 ダディはそうなんですね(笑)。ダディは「これは純愛小説だ」「こういう関係性もある」と言ってくれたんですけど。特殊な関係性をずっと書いていきたい気持ちがあっても、それを納得させるだけの文章の力が、私にはまだないというのはすごく反省しました。
北方 あの時は私も言いたいことはいろいろありました。これは純愛小説だけど、あなたに純愛小説を書く資格があるのかい、と。恋愛小説はいくらでも書けるけど、純愛となるとものすごく難しい。石原慎太郎さんが都知事の時に、銀座の寿司屋を予約してもらってご飯を一緒に食べたことがあったんだ。慎太郎さんが先に来て酒飲んでて、バーッと「お前の文体で純愛小説を書け」と話し出した。そこそこ力を付けてきたから、中河与一の『天の夕顔』みたいなのが書けると。『天の夕顔』は、ちょっと歪んだ純愛小説なんだけど、石原さんの考える純愛というのが、聞いてもよく分からなかった。とにかく何回も「お前の文体で書け、お前の文体で書け」と。最後に、やっと口が閉じたから、「石原さんだって作家じゃないですか」と言ったら、頭をひっぱたかれて、「俺は都知事なんだよ」と(笑)。
千早 作家じゃないんだ(笑)。
北方 「俺は都知事だ。忙しいんだ」。
千早 ダディに言われて『天の夕顔』は読みました。美しかった。『男ともだち』以降、「その関係はあり得ない」という人を納得させるだけの関係性を書けるようになるのが課題ではありました。
北方 どれだけ納得させられるかというのは相当作品をいっぱい書かなきゃいけないかもしれない。その中で傑作が生まれてくるんだよ。だから、恐れずに駄作をいっぱい書いてよ。
千早 駄作ですか(笑)。
北方 いま、笑ったけど、傑作がどうやって出てくるか分かるか? 無数の駄作の中から出てくるんだよ。傑作を書こうなんて思ってたら書けないんだよ。
「小説の言葉」を探せ
千早 今回で直木賞の選考委員をお辞めになると聞いて、本当にびっくりしています。ダディが選考されている時に受賞がかなってほっともしていますけど。
北方 俺にとっては直木賞の選考というのはいつも本当につらかったよ。
千早 どうつらかったんですか?
北方 自分と違ういろいろな才能と向かい合わなきゃいけない。しかも、若い。俺は圧倒された。負けるとは思わなかったけど、圧倒された。その日々だった。俺が持ってない、あるいは持っていたけどなくしてしまった若さがあるなと思ったら、たまらなかったね。だけど、それを通り過ぎて、選考で刺激を受けることができるようになったんですよ。この選考を23年間やっていたおかげで、自分が鈍磨しなかった。選考するたびに新しい才能と格闘するから、研ぎ澄まされるところがあったんだよ。
千早 どうして辞めるんですか?
北方 最後に、長い長編をもう一本書きたいんですよ。選考委員をやりながらでも書けるかもしれない。でも、書けないかもしれない。直木賞って本当に不思議なことに、その選考委員は文壇的な権威じゃないかと思われるんですよ。直木賞は社会的な波及性の大きさゆえに、選考委員が社会的な権威を持っちゃう。俺はそれが嫌。書いてないのにそれにしがみつくのは最悪だと思った。もしかしたら書けないかもしれないから、今やめておこうと。もちろん『チンギス紀』の次の長編は書くつもりだし、その前に、文体を整えるために、「オール讀物」で十五枚の短編も書きます。
千早 図々しいことを言っていいですか? 私も、今それをやってます。今回の長編を書いて疲れて、文章を練り直したいから、二十枚ぐらいの短編を純文学誌の「すばる」で毎月書いています。
北方 すごくいいことだと思う。もう一つ言っておくと、二十枚ぐらいと言ったでしょう。そうではなくて、カッチリ20枚。君は手書きじゃないだろうけど、俺の場合は15枚。気持ちとして、15枚目の原稿用紙の最後のマスに丸を書いてから始めるから。
千早 うわぁ、すごい。
北方 そうすると、言葉を選ぶ。選んで選んで選ぶわけよ。本当の言葉が出てくる。小説の言葉。小説の言葉ってどういうのか分かる? どう認識してる?
千早 エッ、小説の言葉? 時間をください。
北方 いやいや。何も認識してないんだと思う。たとえば赤というのを描写する時にどういう描写をする? 赤だったとして、「美しい赤」。これはよく分かるよね。それから「きれいな赤」。
千早 「キラリとした赤」。
北方 あと、「いい赤」。「いい赤」と書くのは非常に主観的だけど、そこに普遍性を持たせるのが小説だと思う。矛盾してるけど、「いい赤」と書いてきちんと普遍性を持って説得力があるのが小説の言葉だから、「いい」という言葉をいつも小説家は探すべきなんだよ。俺が中学の頃に、教科書に載っていた志賀直哉の『城の崎にて』には、「向う側の斜めに水から出ている半畳敷程の石に黒い小さいものがいた。蠑螈(いもり)だ。まだぬれていて、それはいい色をしていた。」という描写がある。
千早 ほんとに? 気づかなかった。文章への意識が違う。
北方 その「いい」というのがすごい気になって、「『いい』というのはどういうことでしょうか」と学校の先生――のちに日本で3本の指に入る上田秋成の研究者になった方に聞いたんだ。それで、続けざまに先生に休み時間に呼び出されるようになった。他人からは何を怒られてるんだと言われたけど、「いい」の解説だったんだよ。先生もそこで解析してた。「いい」という主観的な言葉にどれだけ客観性を持たせられるかが小説の言葉なんだというのは、本当に古典的だけど、志賀直哉に学んだんですよ。だから、とりあえず短いのをお互いに頑張って書こうぜ。20枚にしろよ。きっちり。
千早 はい。今は、どうしても24とか25とかになっちゃって。
北方 20枚と思った時に、24枚書いたら、無駄じゃなくても、4枚分を切って、どこかに押し込めなきゃいけない。どこかというのは、行間なんだ。それで、行間というものを考える書き方になる。だから、君は20枚以上使っちゃいけない。
千早 そこで打ち止め。
北方 それで見えてくるものがある。言葉の選び方がそれまでと違ってくるよ。最近の直木賞の候補作は、分厚いのが多いんだけど、読むと、描写が同じ場所で行ったり来たりしてる。「足踏み」と言ってもいい。たぶんパソコンのせいだね。
千早 ああ、そうですね。いっぱい書けちゃいますもんね。いっぱい消しちゃえるし。そういえば『魚神』の前半は手書きでした。
北方 俺は今まで500冊ぐらい本を書いたけど、全部手書きですから。
千早 エッ、本当ですか? 今も?
北方 今も手書きだよ。手書きって本当に不思議なことが分かるよ。
千早 手、疲れますね。
北方 それより心が疲れる。手ぐらいどうってことないんだよ。グチャグチャになっても担当編集者が読んでくれる。
千早 鉛筆ですか? ペン?
北方 万年筆。だから直せない。しかも、今書いている長編は1冊500枚。501枚でも駄目、499枚でも駄目と決めてるわけ。原稿用紙をきっちり500枚使う。500枚の最後か1行余るぐらいのところまで書く。僕は原稿用紙を捨てないんだよ。ケチだからかもしれないけど。捨てたのは、ずっと前に一枚だけ。寝ちゃったんだよ。それでよだれが(笑)。だから、万年筆が壊れたりすると本当にショック。書いてる最中に、悲鳴を上げたような感じになって、手がインクだらけになってるけど、どこも漏れてない。きれいに拭いてまた書いても、しばらくすると、またインクだらけ。ルーペでこうやって見ると、軸に縦に細かい亀裂が入ってた。モンブランだったんだけど、もう使えない。新しいのを探して、ペン先の柔らかいペリカンの限定品を買ったら、万年筆業界が大騒ぎになって。ペリカンに転んだからペリコロと言われた。
千早 モンブラン派が怒ったんですね。
北方 柴田錬三郎が最後に『眠狂四郎』を書いた万年筆が、なぜか俺のところに来たんだよ。他人の万年筆だから、自分が書くのは合わないんだけど、どこか不思議な気配があると思っていて、小説のタイトルを書かなきゃいけないという時に、その万年筆を出して、『破軍の星』と書いた。そうしたら、この作品で柴田錬三郎賞を受賞したんです。
千早 すごい。怖い。
北方 俺は思わず授賞式にそのペンを持っていって、「皆さん、これを見てください。この作品はこれで書いたわけじゃないけど、タイトルはこの柴田錬三郎さんの万年筆で書きました」と。君もそういうことは小説の中にいろいろと書くといいよ。そういう感性があるんだよな。何かよく分からないけど。
千早 怖い感性?
北方 というより、予知能力……というととんでもないけど、俺なんかには全然ないようなものがある気がする。
千早 何だろう。ごく普通の人間だと思いますが……。
北方 それは探してください。俺はないんだから言えない。これからは好きなものを書けるよ。だからこそ難しいと思う。あんまり簡単なものを選ばないようにするんだな。これはきついと思うものを選んで書いてよ。
千早 自分のために。
北方 そうすると、自分が知らなかった自分が出てきたりすると思う。ものを作る行為というのは、楽なところでやっちゃ駄目なんだ。
千早 負荷をかけるということ?
北方 負荷をかけるって、どうしてそう単純に言葉化するの?
千早 駄目ですか。
北方 単純に言葉化をしたりしちゃ駄目だよ。小説の言葉というのは。
直木賞のその先へ
千早 最後なので聞いてもいいですか? 直木賞をとっても作家の人生はこれからだとは思っていますが、大きい賞ではありますよね。デビューの頃から知ってる人が受賞するのはどんな気持ちなんでしょう。でも、デビュー作もいっぱい読んでるから覚えてないですかね。
北方 いや、『魚神』は覚えてるよ。自分が選考してデビューした作家の作品は覚えてる。角田光代が、彩河杏(さいかわあんず)という名前でコバルト・ノベル大賞に応募した時に俺が選考委員だったの。そのあと、別の賞の選考委員で「角田光代」の作品を読むことになった。
千早 え~、すごい。名前を変えてたのに、気づいたんですか?
北方 気づいた。最初の時に角田に、「お前、俺は選考委員だから親とも思え」と言ったんだ。彼女も素直に「はい、お父さま」と言ってたんだ(笑)。それが、直木賞の時に、角田が来て……。
千早 「お父さま」って?
北方 いや、「2回目だからおじいちゃんですね」って言いやがったんだよ(笑)。
千早 さすが角田さん。
北方 でも、受賞してくれるんなら、おじいちゃんでもいいです。
千早 でも、小説すばるの出身者は、みんなダディと呼びますから。お父さんですよね。村山由佳さんもそうだし。
北方 尾崎世界観が君に「明日、北方さんと会う」と連絡した時に、君が「ダディによろしくね」と返したんで、尾崎は目が点になってた。男どもはみんな「おやじ」とか「おじき」。天野(純希)は「うちのおやじが」って。
千早 確かに、歴史小説系の方はそうかも。関口(尚)兄さまもダディって言いますよ。私は関口さんのことは「兄さま」で、矢野さんのことは「兄貴」と呼んでます。
北方 小説すばるの二次会が有名になってるけど、あれはふるさとなんだ。みんな、日頃の作家生活で殺し合いをやってる。誰かが生き延び、誰かが斃れる。ただ、1年に1回だけ、お前ら、ふるさとに戻ってこいと。そこで、生存を確かめるというか、お互いに顔見ようよ、俺は何でもやるからと、司会をやってる。
千早 そしてダディの指揮のもとに三本締めをしてそれぞれの戦場に戻る。ダディは、いっぱいいる受賞者みんなにちゃんと声をかけてくれる。すごい優しいんですよね。
北方 いい賞です。選考委員のわれわれも何となく誇りですよ。
千早 だから、今回、北方先生の最後の直木賞の選考で、もう1回読んでいただけて、受賞できて本当に良かったです。ありがとうございました。
写真◎石川啓次
(「オール讀物」3・4月合併号より転載)