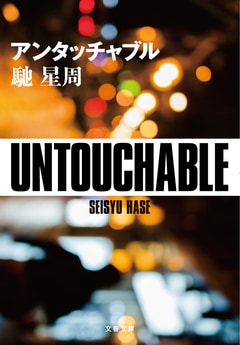かくして、わたしは第一七回大藪春彦賞選考会に臨み、『残月』の受賞を強く推した。
候補作の中に、頭ひとつ抜けた傑作があり、その作品の受賞はすんなり決まったのだが、『残月』は少々手こずった。
その詳細は書かないが、しかし、わたしは粘りに粘った。
だって、『残月』はわたしが書いていたかもしれない物語なのだ。これを受賞させずに、選考委員をやっている意味などあるものか。
結局、わたしの熱弁が功を奏し、『残月』も受賞することに決まった。もちろん、力のある作品であることは他の選考委員も認めていたからだ。
他人の小説について、あれほど熱く語ったのは久しぶりのことだった。
後日、また月村と話す機会があった。選考会でわたしが粘りまくったことをどこかで耳にしたらしい。
「いやあ、馳さんがぼくの小説を気に入ってくれたってことが嬉しいなあ。ぼくの作品、他にはどれが好きですか?」
「知らない」
わたしは答えた。月村は鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしていた。
「あなたの小説を読むのは『残月』が初めて。他の作品は読んだことがない。申し訳ないけど」
それで小説の話は終わりだ。あとは酒を飲み、馬鹿話に興じた。
それから数日後、とある出版社から数冊の本が送られてきた。中身は月村の『機龍警察』シリーズ全巻だった。
送ってきた編集者の手紙にはこう記されていた。
「馳さんがまだ『機龍警察』を読んでないらしいので、すぐに全巻送ってくれと月村さんに言われましたので、とりあえずお送りいたします」
なんだ、月村。『機龍警察』を読んでいないのはけしからんとでも言いたいのか。自信があるのはいいが、本を送りつけてくるのはやりすぎだろう。
そうは思ったのだが、とりあえず作者がわざわざ送ってきたものを放置するのも気が引ける。
というわけで、『機龍警察』の一巻目を開いた。気がつけば、たった数日で全巻を読破していた。
まんまとしてやられてしまったのだ。
月村了衛は凄腕である。いろんな意味で。