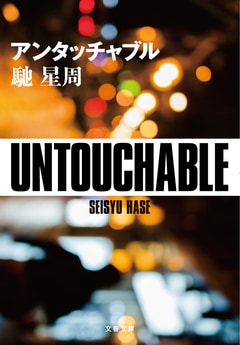そのため、郎次は腕利きの侍でも瞬時に殺せる武器を持ちながら、しかし、装弾のための時間を稼ぐことにあくせくし、なおかつ、自分の持っている残弾を常に気にしていなければならない。
そう。郎次は西部劇に登場する無敵のガンマンではないのだ。銃がなければただ殺されるのを待つしかできない無力な男でもある。
この辺りの設定には唸った。
銃だけが頼りの弱い男。弱いが故に、惑い、奢り、絶望し、破滅へ向かって疾走するしかなくなっていく。
『残月』は時代背景こそ江戸時代だが、徹頭徹尾、ノワールなのだ。
わたしが書きたかった物語なのだ。
『残月』が第一七回大藪春彦賞を受賞したとき(わたしは選考委員のひとりでもある)、月村と少しばかり話をした。
なぜ、郎次にコルトM1851という特異な銃を持たせることにしたのか。
わたしの問いに、月村は微笑みながら答えた。
「最初にコルトM1851という銃があって、それに沿って物語を綴っていったのです」
なるほど。
実際にはもっと複雑なあれこれがあるのだが、とりあえずここではそれは割愛する。とにかく、同じノワールの書き手でも、出発点はまるで違う。
わたしは人からはじめる。どのような人間を主人公に据えるか。考えに考えて考え抜く。考え抜いた人間像が必要とするのがコルトM1851であるという状況下で物語を書きはじめる。
だが、月村はまずコルトM1851ありきであったのだ。この時代にコルトM1851を所持していてもおかしくない人物として郎次を設定し、性格に肉付けしていく。
どちらがいい、悪いという話ではない。作家としての資質の違いだ。
作家としての資質はまったく違うのに、しかし、お互いが書く物語は同じベクトルを向く。なぜなら、それがノワールだからだ。
欲望と執着に雁字搦(がんじがら)めにされた人間は遅かれ早かれ破滅する。その姿を描くのがノワールなのだ。
その破滅していく姿をいかにリアルに、いかに激しく、そして疾走感を持って描けるかどうか。
ノワールを描こうとする者は、内に抱えた暗い情念とともに、その技量も問われることになる。
月村の技量は見事だ。
このラインを越えると自分は破滅する。それがわかっていてなお、ラインを越えようとする郎次の心情には疑念を挟む余地がない。
郎次にはその道しかないのだ。生まれてからこの方、その道だけを歩いてきたのだ。だから、歩き続けるしかない。
読む者を納得させるだけの力が『残月』にはある。
脱帽だ。