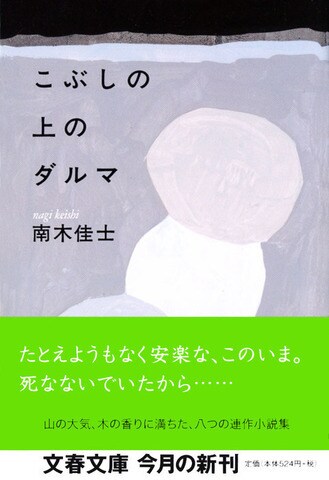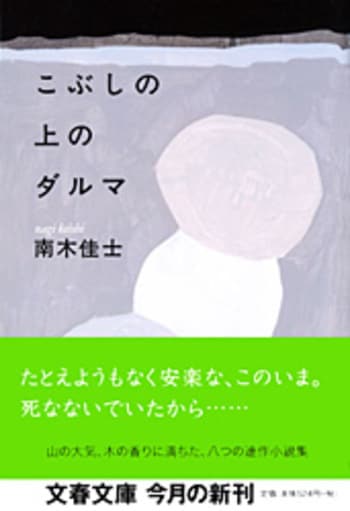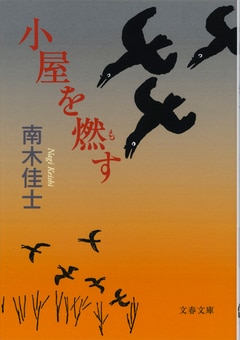人は時とともに変容する。それも、無責任なまでに。
こういう実感を得ると、言葉に置き換えたくなる。少なくともわたしにとって、書くという行為は、この、からだを通して得た実感を他者に伝えようと試みる作業にほかならないのだから。
総合病院の呼吸器内科病棟の責任者として末期がんの患者さんたちを看取る日々をおくっていたころ、目の前で呼吸を止めてゆく人たちの呼気に含まれる独特の臭気、肌の冷え、残される者たちのすすり泣きの声。これらがわたしのからだに沁みこみ、悲観を醸成し、確たる実感となっていった。
いわゆる医者物小説にはエリート医師と美人看護婦の恋愛はよくでてくるが、医者なら当然感じているはずのこの種の実感がきちんと表現されていないではないか。もしかしたら、この悲観はわたしだけのものなのか。ならば、わたしなりの言葉で表現してみるしかない。
こんな感じで医者と作家の兼業生活は始まったのだった。
文學界新人賞を得て作家の末席に加わってからすでに四半世紀近くが過ぎた。歳とともに医者の仕事が多忙になり、気力、体力の衰えも甚だしく、小説を書けるのは休日にかぎられてきた。結果として家族旅行など話題にものぼらない家庭しか築けなかった。
狭い勉強部屋で机に向かううしろ姿と、厄年の前後でパニック障害に苦しめられて鬱々と楽しまぬ父親しか知らない二人の息子たちはそれぞれに、背伸びしすぎた果てに心身を病んだ父を反面教師として育ち、みずからの身の丈に合った仕事に就いて静かにこの家を出て行った。
妻と、老いたトラ猫だけが残された。
老いるというのはそれまで若さの力わざで隠しおおせてきた本来グロテスクな生存本能が、力が失せるとともにあらわになってくるという事態だから、妻も猫も、もとよりわたしも、みな自分のことしか考えなくなり、家のなかはすさまじい様相を呈してきている。
居間のコタツに寝そべって妻とテレビを観ている。あいだに猫が寝ている。
「あっ、あのお団子うまそう」
食べ物の映像にのみ反応して、妻が高い声をだす。
猫が、妻をにらむ。明らかに、うるせえなー、という表情をしている。
「いいじゃないの。おこらないでよお」
妻の猫なで声を無視し、トラは再び不機嫌な眠り顔になる。
それを見ながら手枕でうとうとし、気がつけば一時間近く眠っていて、口角によだれが付着している。
「うわっ、きたない」
との妻の声をまったく気にせず、カーディガンの袖でよだれを拭いつつ冷えた茶をすする。
こういうふうに人生は終わってゆくのだな。むなしいとかさみしいというのは若いときのたわごとで、実際は多色が単色に、そして単色がさらに薄れて淡色に、どこでなにが輝いていたのかも分からないようになって終わってゆくのだな、と実感しつつある。