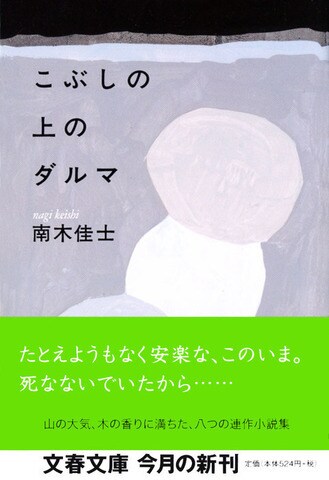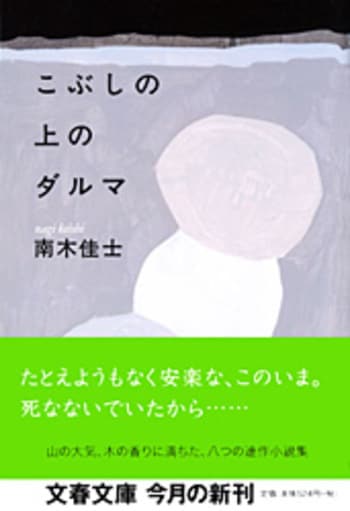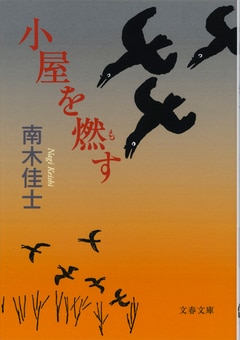甦る原色の過去
今回上梓する連作短篇集『こぶしの上のダルマ』にはこのあたりの感慨の細部が描いてある。本来は書き下ろしたものなのだが、章ごとに読み直してみると短篇としても成立していそうで、ならば「文學界」に分割連載して完成度を高めれば、とのアドバイスもあり、実際、そうしてみたら最初のものよりずっと作品世界が広がり、深まった気がする。
この本はわたしの二十冊目の著作になる。数を目標に書いてきたわけではないのだが、なんとなく、ああ、医者をやりながらこんなに書いたのだなあ、とのため息のでる数ではある。
これまで出した本を、文庫本も含めて狭い本棚に並べてみると、あと一冊でちょうど一段が埋まるところだったから、『こぶしの上のダルマ』を収めると区切りがつく。この棚はあまり長くながめていると気がふれてくるため、新たな本を追加するときのみ、ほんの三十秒ばかり見る。
「かたちのある生の記録が、しかもお仕事として残せるのですからうらやましいですね」
と言ってくれる方がいるが、亡くなった作家たちの忘れられ方の早さはここ二十年でも恐ろしいものがあるので、ええ、まあ、とか答えながら、はなから相手の世辞を信じていない。
本棚の前を素早く立ち去るのは、自著の列を見ていると、その背後に、これらを書かなかった際の自分の人生を探してしまう愚行を犯すからでもある。
たら、ればの話ができるのは若いうちの特権で、老いてからのそれはみっともないばかりなのだが、それでも、最初に新人賞に応募して、これで反応がなかったら才能がないのだから小説はあきらめ、才能がなくても地道に努力すればむくわれるはずの医学の道に邁進(まいしん)しよう、と原稿用紙二十数枚の「処女作」を入れた封筒を田舎町の郵便局の窓口に提出したときの高揚感。一次選考にも残らなかった作品の感想を電話で伝え、さらなる精進をうながしてくれた編集者の声。そういう原色の過去が一気に想い出されて、いまある偶然の足場がひどくもろく感じられ、大いなるめまいを覚えてしまうのだ。
信州の厳しい冬にも終わりの気配がただよってきたころ、とりあえず記念すべき二十冊目の本の校正を終えたあたりから、急にのどが痛くなった。
今年はインフルエンザの流行が遅れ気味で、二月の末からにわかに患者が増えてきたが、まあ、予防接種も受けていることだし、とマスクもせずに診療にあたっていた。だから、のどの痛みもふつうの軽い風邪と判断したが、そこは自分だけが大事な身、きちんと鼻腔のぬぐい液を検査に出し、インフルエンザ抗原陰性は確認した。
しかし、症状は日ごとに悪化し、熱はないのにからだがだるく、鼻水はでる、鼻の粘膜はひりひりする、咳はでるで、ついに耳鼻科医の診察をあおぎ、やはりインフルエンザによる広範な粘膜の炎症らしく、副鼻腔炎も起こしている、と診断された。
予防接種は打ってから五ヶ月くらいで効果が半減するらしいが、昨年十月、職員のなかでは我先にといちばん早いほうの接種を受けたゆえ、ちょうど効かなくなる時期にさしかかっていたのだった。早く受けないとあぶないぞ、とわたしにおどされながらも、効果持続期間を考慮して冷静に接種を一ヶ月遅らせた妻のほうがうわてだった。
コタツにもぐりこんで咳をしていると、いつものように老猫が腹の上に載ってきた。そのとぼけた顔が体調不良のときにはたまらなく憎らしくて、こいつに風邪をうつしてやれば早くよくなるのでは、とたくらみ、わざと咳を吐きかけた。
三日後、わたしはよくなり、猫の声が出なくなった。冬場に好むぬるい湯を飲むとき痛そうに顔をしかめる。その痛みはまさに数日前に経験したものだから、猫の咽頭痛がわがこととしてのどに沁みる。
「猫に風邪をうつして自分だけよくなるなんて、最低」
妻に言われるまでもなく、わたしのなかの残存良心が責める。
おろおろしながら猫の体温を測り、背をなでてやる。
その横で、あたしものどが変だから、と妻がビタミンCの顆粒をあわてて飲み足している。
いまはただ、終わってゆく生活の細かな実感のみを、書く。