歌野 笠井さんの新作『魔』のゲラを読ませていただきました。僕はいままで飛鳥井シリーズは読んでいなくて、今回が初めてだったのですが、矢吹(やぶき)駆(かける)のシリーズともまた違って、新鮮な驚きがありました。なかでも一番強く思ったのは、一般に、現実的な社会問題は本格ミステリにそぐわないと言われていますが、必ずしもそうではないということです。
たとえば「痩身の魔」という作品では拒食症が扱われていますが、たんに物語の題材として扱われているのではなく、ある本格ミステリ的な展開にも大きく寄与しています。摂食障害という現代的な社会問題と、現実離れしていると思われがちな本格のトリックとが、自然な形で融合しています。

笠井 『魔』の収録作は心理学シリーズにしようと思ってストーカーや摂食障害をテーマに選んだのですが、以前の飛鳥井シリーズでは、外国人労働者や「ジャパゆきさん」、あるいはリストラやホームレスなど、一九九〇年代以降に起こった社会問題を扱ってきました。
考えてみると、本格ミステリがはやらなかった時期は、だいたい日本が平和で豊かな時代なんですね。戦争直後の混乱期は本格ミステリはすごく人気があった。それが六〇年代の高度成長時代に入ると失速していく。九〇年代になって、日本の社会がこれまでにない混乱に見舞われるようになった時期に、また本格ミステリが復活した。たぶん九〇年代以降に問題になってきた新しい社会病理に関心をもつことと、本格ミステリを書くことには何か関係あるのではないかと思うんです。
綾辻(行人)君の『十角館の殺人』も、学生が酒を飲めない人に無理やり飲ませて死なせてしまうという出来事が事件の発端になるわけで、これも八〇年代後半ぐらいに社会問題化したことですね。だから、いわゆる社会派的社会性とは異質の、本格的社会性というのがあるんじゃないかと思うんです。矢吹シリーズは、二十年から二十五年ぐらい前の外国が舞台だから、そういうことを書くわけにもいかないし、別の設定で書いてみようと思ったわけですね。
歌野君も最近の作品では、そういった本格的社会性をめぐって話をつくっているわけですよね。
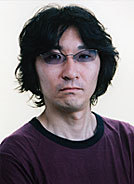
歌野 前作(『世界の終わり、あるいは始まり』)ではそういう部分をかなり意識しましたけど、今回(『葉桜の季節に君を想うということ』)はそうでもないんですよ。
笠井 いや、今回も老人問題という社会問題を扱っているし(笑)。『葉桜――』は、これまでの本格ミステリ・マスターズの中でも一番評判がいいですね。
歌野 僕としてはちょっと意外だったというか、やはり本格のシリーズということで、ガチガチの本格ものを書かなければいけないんじゃないかと思っていたんですよ。それが、刊行が始まる前にパーティーがあって、綾辻さんが「自分の本格を書けばいい」とおっしゃっていたので、踏ん切りがついたんです。それでも本が出たら、「これは本格ではない」ととらえられるかなと心配に思っていた。ところがそういう人は意外と少なくて、しかも本格の濃度が高いと言う人までいて、本格とは何なのか逆にわからなくなったところがあります。『葉桜――』の場合、本格ミステリのガジェットは意識して排除してあるし、登場人物が論理的に謎を解くということもないわけです。
笠井 江戸川乱歩の本格の定義がありますよね。冒頭の謎、中段のサスペンス、最後の論理的解決という。これも別に間違いじゃないと思うんですが、正統本格という場合は、プラス、犯人が完全犯罪のためにトリックを仕掛けて謎が生じ、探偵がそのトリックを解くことによって犯人を特定するという、つまり犯人役と探偵役が対立的に出てきてトリックをめぐって知の争いを繰り広げるというのが、おそらくもっとも基本的なパターンだと思います。一九二〇年代、三〇年代の英米本格は大体このパターンだし、日本の戦後本格も大体そうですよね。
ところが、たぶん第三の波が始まったときから、この正統的なパターンはそのままでは通用しない、という意識がそれぞれの書き手に生じていたんじゃないかと思うんです。自分のことを考えてみると、ヴァン・ダインやエラリイ・クイーンを手本にして『バイバイ、エンジェル』を書いた、その時点ではそれほど深く考えていなかったんですが、犯人がアリバイ・トリックを仕掛けるのに、偶然が重なってそれが成り立たない状況に陥ってしまい、しかたないから首を切るというプロットを立てた。つまり、首なし死体という謎は犯人の計画が崩れることによって生じた謎です。その点で、単純に犯人がトリックを仕掛けて、探偵がそれを解くというパターンからはズレている。『哲学者の密室』の三重密室もそうだし、今度の『オイディプス症候群』もそうで、犯人の計画が崩れることによって生じる謎というものを、自分でははっきりと意識しないままに書き続けてきたような気がします。これも一つのズラし方で、状況設定は非常に正統的な本格だけれど、そこに内在しながらズラすという方法ですね。
折原一の叙述ものなんかは、名探偵が出てこない場合が多いし、見るからに正統的なパターンからはズレている。綾辻君の『十角館の殺人』も叙述トリックですが、彼らの試みと僕がやろうと思ったこととは、根本的にはあまり違わないと思っています。
歌野 『十角館の殺人』の場合、本格ミステリを全く読んだことがない人が読むと、あまり驚かないという面がありますよね。『バイバイ、エンジェル』の首切り殺人も、それまでに本格ミステリをある程度読んだことがあって、入れ替わりトリックを知っている人が読むと、あっ、これはまた例のパターンだろうと思ってしまうという、読者の本格に対する素養を前提としたトリックでもあります。新本格以降、本格ミステリに精通した人が書き手になるようになって、そういう読み手を選ぶタイプの小説が増えましたね。
笠井 『十角館の殺人』を読んで本格だとまず思った人は、孤島のクローズド・サークルという本格の典型的なパターンで、おまけに変な館が出てきて、登場人物がミステリ研ということもあって、延々と本格談義が繰り広げられる、というようなところで喜んだと思うのですが、ちゃんと見ていくと、必ずしもクイーンの国名シリーズや横溝正史的な本格にピッタリはまるものではなかったわけです。
あと、そことのつながりで言うと、八七年に『十角館の殺人』が出て以降、法月(綸太郎)君や歌野君など、大戦間の英米本格とか、日本の戦後本格の形をかなり忠実に踏襲した、名探偵が活躍する本格探偵小説がかなり出てきたわけですね。ところが、九二年あたりを転機にして、第三の波初期の名探偵シリーズが中断された例がとても多いんです。
名探偵たちが消えた
歌野 九二年というのはどういう年ですか。
笠井 綾辻君の『黒猫館の殺人』や法月君の『ふたたび赤い悪夢』、北村薫さんの(春桜亭)円紫ものの『六の宮の姫君』、有栖川(有栖)君の『双頭の悪魔』などが出た年です。僕の『哲学者の密室』もこの年で、島田荘司さんの『アトポス』は九三年かな。八〇年代の末から九〇年代の初めにかけて活躍した、第三の波の花形探偵が、この時期を最後に次々と姿を消していく。後でまた復活したりもするけれど、いったん空白期に入っていったわけです。歌野君の最初の三作も、信濃譲二という名探偵が登場する、正統的な本格の枠を踏襲したものです。歌野君の場合はほかの人たちよりもちょっと早くて、九二年まで行かないでやめたにしても、そういう流れの中で捉えることができると思うんです。ある意味で名探偵システムの危機みたいなものが九二、三年ぐらいに表面化してきた。
歌野 確かに気になる偶然ですね。みんなそれぞれ中断させた理由は違うんでしょうけど。
笠井 僕の場合は次作の『オイディプス症候群』の書き直しに手間取り、結局七年ぐらいかかってしまったというのが中断の理由です(笑)。『オイディプス症候群』は孤島のクローズド・サークルものなのですが、雑誌連載の段階では探偵役のカケルは最後に登場して謎解きをするだけだったんです。なぜそうしたかというと、クローズド・サークルの中にシリーズ・キャラクターがいると、サスペンス性が失われると思ったんですね。探偵役とワトソン役はどうせ死なないだろうから、アガサ・クリスティの『そして誰もいなくなった』と違って、必ず二人は生き残ると読者に思われてしまう。だから、ワトソン役のナディアも、どうせ死なないだろうと読者は思うかもしれないが、探偵役同伴よりはハラハラするだろうということでそうしたつもりだったんだけど、後でよくよく考えてみると、さっきから言っている、正統本格の枠組みがどこか失効してきているということへの無意識の対応でそうなったのかなあという感じもするんです。
もう一つ偶然の一致があって、僕が『オイディプス症候群』を連載していたのとちょうど同じ頃に書かれていたはずの『アトポス』でも、探偵役は一番最後に馬に乗ってやってきて謎を解くだけで(笑)、それまでは出てこない。期せずして同じような構成をとっているんですね。
歌野君が信濃シリーズをいったん三作で打ち止めにして、九〇年代に入ってからは正統的な本格からズレていくような方向性になったのはなぜですか。
歌野 僕が信濃を退場させたのは、正義の側にあるはずの探偵がマリファナを吸うというのはまずいから退場させてくれと、版元の部長さんに言われたからで(笑)、なにも言われなかったらその後も書いていたかもしれないんですが、あれだけの数の名探偵が同じような時期にいなくなったというのは、やっぱりなにかあるんでしょうね。
笠井 それぞれの作家自身は名探偵システムの危機を自覚して引っ込めたというふうに思っている人はいなくて、綾辻君なんかは不用意にゲームの仕事を引き受けてしまって、小説を書いている暇がなくなっちゃったわけだし、それぞれ理由があると思うんだけど、十年たって俯瞰(ふかん)して見ると、諸個人の都合とはまた別に、なにか時代的な意味を読み取ってもいいんじゃないかと思うんです。
歌野 僕の場合は信濃シリーズをやめたことによって次に何を書くかということを一から考えなきゃいけなくなったというのはありますね。自分の本格は何かという問題も含めて。
笠井 その後、名探偵ものから離れて、『死体を買う男』とか『ブードゥー・チャイルド』『安達ヶ原の鬼密室』『世界の終わり、あるいは始まり』といった、コアな本格読者から注目される問題作を二年に一冊ぐらい書き継いできたわけですね。ただし、歌野君の場合、そのつど違うことを試みるから、例えば折原さんみたいに叙述トリック一本というわけではないので、歌野作品を継続して読んできた読者でないと、なにを考えてやっているのかよく分からないところがあったかもしれません。
歌野 それは自分でもずっと気にしていることで、やっぱり職業として作家をやるにはスタイルというのは絶対大事だと思うんですが、どうも自分は飽きてしまうというか、気持ちが保てないんですね。言い訳になっちゃうんですけど、僕は本格ミステリは二つの部分から成り立っていると思うんです。一つは昔からのものを守ろうとする方向性。本格のガジェットであるとか、名探偵システムであるとか、そういうものを守ろうという方向です。その一方で、新しいものを求めようという方向性もあって、それはトリックですね。トリックに関してはどんなに保守的な読者でも、以前の焼き直しよりは新しいトリックのほうを喜ぶわけです。
僕は読者としてはどちらも好きなんですが、書き手となると、どうしても新しいものを求めるほうにばかり目が向いてしまって、古いものを大事にしようという気持ちが起きないんですね。ああ、また似たようなものを書くのかといったん思ってしまうと、気分が乗らなくなってしまう。そのあたりのバランスをうまくとって書ければいいんですけど、つい新しいことばかり考えちゃうんですよ。こういうのってよくないなあ、と思うんですけど。
笠井 しかし、それは読者にとってはいいことだと思うけど。
歌野 いや、年間何冊も本を出していればそれでいいと思うんですけど、たまにしか出さないのにいつも違うというのは、どうもよくないみたいです。たまに出して同じというのは読者に安心感を与えられるけど、たまに出して違うのだったら、別人が書いてるのと一緒ですから。
笠井 シリーズ名探偵ものの本格の場合には、型の踏襲を楽しむというところもありますね。類型的キャラクターが類型的なふるまいをするのがうれしいという。でも、それと同時に思いもよらない形で完璧に騙されたいという、その二つがないと正統本格にはならない。
歌野 だから、前の作品と完全に同じだったらダメなんですが、トリックが新しかったら、シチュエーションとかが似ていても文句は言われないんですよね。そういうのが正統的な本格だと思うし、書きたいなあと思うんだけど、なかなか自分ではできないんです。
本格ミステリの論理性
笠井 正統的な枠組みの中で新しいことをやろうと思うと、やっぱり新しいトリックの一点に絞られてくるね。枠組みをはずしてしまえば、またいろいろなことが可能になってくるけど。読者を騙すという点では、いろいろとやり方があるわけだから。
僕は新しいトリックを思いつかなくて苦労するといったことは、あまりないんです。最初に本格のパターン、クローズド・サークルでもいいし、首なし死体でもいいけど、今回はこれでいこうと決めたら、後はそのパターンの代表的なものを頭の中で思い浮かべる。それを幾つか組み合わせたり、ちょっと変えたりしてみるわけです。だから、真に独創的なトリックを考えたことがあるのか? と言われると、あんまりないんじゃないかな。
『葉桜――』のインタビューで、歌野君はトリックの意外性が第一で論理性にはさほど関心がないと言っていたけど、僕の場合は逆に論理のほうに凝るので、トリックはまあ水準だったらいい、謎を解体する論理のところに笠井にしか書けないものを込めようというスタンスです。だから、長くなる(苦笑)。謎を解体する手続きのほうで独自性を出そうとすると、ああじゃない、こうじゃないと延々と書かなければならないので。
歌野 僕は論理のほうは読むのも苦手で、やっぱり一発トリックを見せられて、オーッ! ていう感じなんで。たぶん推理小説が嫌いな人っていうのは、論理を読むのが嫌いなんじゃないかなと思うんですよ。なぜかというと、人間の考えというのは、やっぱり直感的だと思うんです。答えが出るときは一瞬のうちに分かるのであって、それは恐らく無意識のうちに、いろいろな経験をもとに頭の中で論理的に組み立てているんだろうけど、人間はその過程を意識しませんよね。本格における論理というのは、それを一々言葉にして書いていくわけで、推理小説に興味がない人は、きっとそういう手続きにまどろっこしさを覚えるのではないでしょうか。
笠井 矢吹駆の言う本質直観というのはそういうことなんだけど、ワトソン役に迫られて、しょうがないから七面倒な議論をするというふうにしてあるわけ(笑)。
僕は本格の論理性には二つパターンがあると思っていて、簡単に言えば短編型と長編型なんですけど、短編型はG・K・チェスタトンのブラウン神父ものが一番分かりやすい。要するに騙し絵ですね。ルービンの壺っていうのがあるでしょう。最初どう見ても壺に見えていた絵が、見続けているうちに突然、女の横顔になるという、あの驚きが短編の論理性で、その場合の論理というのは発想を変えるというか、視点を変えるというか、そういうものなわけです。
一方の長編型は、初期クイーンの国名シリーズみたいに、ひとつの謎をめぐって、ああじゃない、こうじゃないと推理を重ねていく。これは連立方程式の解を発見するような論理性だと思うんです。方程式にいろいろな数を代入していって、完全に割り切れる数字を見つけていく。こちらがなぜ長編型かというと、いろんな数字を代入していく手続きを取るために必然的に長くなる傾向があるわけです。
ですが短編型、長編型というのはちょっと表現が正確じゃなくて、短編作品で長編型の論理が使われることもあるし、その逆もある。鮎川哲也みたいに長編の傑作も多いけど、むしろ短編のほうで割り切れる論理を徹底追求している人もいるし、島田荘司の場合は大長編を次々に書いた時期があるけれど、基本的には短編型の論理だと思うんです。おそらく歌野君はその分類でいくと短編型の論理性のほうに惹かれるタイプなんでしょう。
歌野 そうですね。確かに自分でも短編と長編だと、短編のほうを書きたいという欲求がありますね。ただ、どうしてもミステリは長編じゃないと認められないようなところがあるし、短編だからと言って短時間で書けるわけでもないので、長編を中心に書いています。
笠井 最近の作品で言うと、有栖川君の『スイス時計の謎』が長編型論理を使った短編としては、久しぶりの傑作だったと思います。
長編型の論理というのは数学を理想にしているけど、数学みたいにはいかないわけです。というのは、数学で扱われる点とか線とかというのは抽象理念ですよね。紙の上に点を打ったって、顕微鏡で見れば面積があるわけだから、位置だけあって面積がないような点なんて現実には存在しないわけです。そういう架空の理念を組み合わせるから完璧な論理性が可能になるわけで、それを現実の場所に当てはめたら、無限に多様な可能性の中から一つの蓋然的な解釈を選んでいくという手続きの連鎖になる。そうなると、結局は全く恣意的になってしまうのかというとそんなことはなくて、蓋然的なんだけど唯一の結論を探偵が提示し、読者が納得すれば、それはやっぱり割り切れているわけですね。
本格の歴史の中で、そういう論理性はクイーンの国名シリーズ以降、だんだん緩んできている。時どき鮎川哲也のような中興の祖が現れたりするんだけど、今度の『スイス時計の謎』は久々に、これしかないという論理を提出しているような感じを読者に与える作品です。
歌野 そうですか。それは読んでおかないといけないな。
笠井 一読に値すると思いますね。僕が読んだ範囲だと、今年の前半は、正統本格が『スイス時計の謎』で、正統本格からズレたところでは『葉桜――』が二大傑作という評価です。
本格的社会性とは
歌野 谺(こだま)健二さんの『赫い月照』は読まれましたか?
笠井 読みました。
歌野 僕はこの作品を読んで、ものすごいエネルギーを感じたのですが、一方でどう解釈していいかよく分からない部分もある。どこで自分が戸惑っているかというと、これでもかと出てくるトリックのほとんどが、別にこんなトリックなくてもいいじゃないかというようなものなんです。山田正紀さんの『ミステリ・オペラ』にも、そういうトリックがたくさん出てきますが、あの作品にはそんなことを許してしまえる全体的な世界観があって、読み終わったときには、全部が素晴らしいという気持ちになりました。
ところが、『赫い月照』の場合はそういう気持ちになれなくて、何が違うんだといったら、もちろん作者が違うし、書いていることが違うわけですが、一番違うのは扱っている題材だと思うんです。『ミステリ・オペラ』における満州国というのは歴史的な事実だけど、僕にとってみればお伽話のようなものです。一方『赫い月照』の酒鬼薔薇事件の場合、実際に自分が知っている。リアルタイムでニュースで見たようなことを、トリッキーな本格ミステリとして展開されるとどうしても違和感が残るんです。本格として社会問題を扱うことの難しさを感じました。
笠井 さっき社会派的社会性と本格的社会性は違うという話をしましたが、例えば横溝正史の『獄門島』は、復員兵問題という、当時、最もホットな社会問題がベースにあるわけです。ただし、こんなひどい目にあった人が帰ってきて、悲惨だ、戦争はよくないといったメッセージは背景に沈んでいて、根本的にはトリックを成り立たせるために復員兵問題を使っている。
社会派的社会性というか、一般小説でもいいんだけど、戦争の悲惨さを訴えるような小説は、復員兵問題を含めて戦争という現実を通過した人間にはリアルに響かないところがあっただろうと、僕は思うんです。人間にはあんまり悲惨なことを体験すると笑っちゃうしかないというところがあって、深刻な顔をして弾劾したりするというのは、弾劾するエネルギーが残っているぶん、本当にひどい目にあっていないのではないかという疑いを、僕は社会派的社会性にたいして持ちますね。
谺君は自身が体験した阪神・淡路大震災をトリックにしたところから出発しているんだけど、これこそ本格に固有の社会性というもので、そういう行き方自体はなかなかいいと思うんです。ただ、その延長で書き続けてきて、作品にトラウマ(心的外傷)問題を繰り込んでいくに従って、社会派的社会性のほうに寄っていっているような節もあって、そのあたりが微妙ですね。
歌野 だからこの先どうなっちゃうのか。一つはもう神戸の地震から離れて全く違うものを書くのか、もしくはミステリから離れるかのどっちかだと思ったんです。だけど、あの生々しさというか、読んでいてすごいエネルギーが伝わってくる。僕の中では名作と駄作の境界線にあるような印象なんですよ。中途半端な佳作ではなく。
笠井 たぶん谺君も参考文献にしていると思うんだけど、一九九二年にジュディス・L・ハーマンというアメリカの精神医学者が書いた『心的外傷と回復』という本があります。トラウマの問題、特に女性のPTSD(心的外傷後ストレス障害)を取り上げて非常に話題になったんですが、これがものすごく問題がある本なんです。
七〇年代から、ベトナム帰還兵たちの戦争神経症が社会問題になっていたのですが、ハーマンは、男のPTSDが戦争神経症だとすると、女のPTSDは幼少期の性的虐待であるというわけです。それがフェミニズムの影響などもあって、八〇年代のアメリカで大きな影響力を持った。アメリカの心理療法家や精神医たちが、神経症的な症状を訴えてくる女性患者に対して、性的虐待の隠された記憶を掘り起こすということをやり始めたんです。その結果、たくさんの患者たちが忘却していた記憶を思い出して、自分の父親や家族をレイプや虐待の罪で告訴するという事態になった。
ところが、九〇年代の後半に入って、そうした裁判の多くが原告側の敗訴に終わってきます。もちろん、勝訴の例もあったわけですが、訴えた女性たちが思い出したと思い込んでいた記憶が、じつは心理療法家や精神医たちが暗示や誘導によって植え付けた偽りの記憶だったというケースも多かったんですね。それで、今度は逆襲が始まって、偽の記憶を思い出させた精神医や心理療法家が逆に告訴されるようになった。
トラウマ問題をミステリに組み込むとき、谺健二はまだハーマン的水準で捉えているところがあるように思うんです。トラウマやPTSDは、それほど無条件には前提にならないんじゃないかという疑いが、まだあの人の捉え方にはないような気がします。だけど、谺君の場合、荒唐無稽で笑うしかないような物理的トリックが外傷体験と抱き合わせになっている限りは、バランスがとれているとも思うんですが。
歌野 あと、最近の作品で言うと、昨年、法月さんが出した『法月綸太郎の功績』を読んだときに、これは料理にたとえると非常に出来のいいスープストックだなと感じたんです。つまり、コックであれば作れなくてはいけないスープの基本があるように、本格の実作者が本来、達成していなくてはならない基本を、高いレベルで示してくれたと。
笠井 法月君も、別にスープストックだけでいいと思っているわけではないだろうから、今度、長編を出すみたいだけど(笑)。
歌野 いや、逆に短編だからこそ味つけや盛りつけでごまかせないから、本当に基本的なところだけを純粋な形で見せつけられたと思うんです。あれを読んで目が覚めた思いです。
それと、最近の若い書き手では乙一さんはとにかくすごいと思いました。ほかの若い人はまだあまり読んでないのですが、総じて感じることは、みなさん達者で、文章力なんかは僕がデビューしたときよりも随分あるなと。
笠井 いや、それは歌野君がちゃんと小説を書こうと思っていたからぎこちなかったんであって、彼らは小説書こうと思うほど大量に系統的に小説を読んでいないから。マンガとかゲームとかアニメを、言葉を主とする形式で書いたらどうなるか、という発想ですから、逆にこなれているんです。もともと近代小説作家として伝統的にあるべきものとされてきたような、いまとなっては余分で無駄な悩みなどもたない。これってやっぱり無視できない流れだね。
歌野 そうですね。僕はこれまでそういう流れを気に留めていなかったのですが、笠井さんの『魔』の巻末のインタビューを読むと、あえてライバル視するというか、そういう感じで捉えていますよね。六十歳が六十歳に向けて書いてもしょうがない、作者が何歳になっても若い人たちに向けて書かなきゃいけない、というのを読んだときに目から鱗(うろこ)が落ちたというか、全くそういうことを考えてなかったんで……。
笠井 僕は清涼院流水評価を間違えたと反省しているところがあって、作品の評価については別に間違っていないんですが、僕はあれは一代雑種だと思ったわけ。簡単に言えば本格とゲームの一代雑種だと。レオポンは子孫は作れないんだから、京大ミステリ研の先輩たちのように血相を変えて批難する必要はないと思っていた。ところがその後、続々と清涼院チルドレンが生まれてしまった。これはもう判断の間違いであって、今、なぜそういうことになったのかということを「ミステリ・マガジン」の連載で考えているんです。
歌野 最近、鳴りをひそめてますね、清涼院(笑)。
笠井 清涼院は清涼院チルドレンに乗り越えられてしまったのかな。とにかく今後に注目しましょう。
















