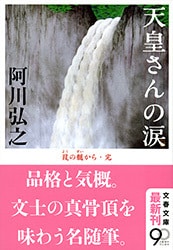だから僕は書いた。二十世紀まるごとを、僕は書いた。それは戦争の世紀で、そしてイヌの世紀だ。そして僕の解釈するところ、ロシア革命ではじまり、ソビエト連邦の解体で終わった世紀だった。一九九一年には、なかば終わっていた世紀だった。その一九九一年、僕は当たり前の二十代の若者にして、馬鹿者で、だから前年まではいま・ここにある歴史をリアルタイムで感じたりはしなかった。する必要なんかないのだと、不遜にも思っていた。それが一九九一年の一月、突然変わった。湾岸戦争が勃発した。僕は衛星放送のニュースに齧(かじ)りついた。そして唐突に終わった。八月、ソ連でクーデターがあった。情報が錯綜して、しかし呆気なく終わった。それから十二月、信じられないことにソ連が消えた。あまりにも簡単に、それこそ八年後のノストラダムスの予言の“不発”の衝撃にも及ばない、なんだか茫然自失するしかない感触で。
その時、僕は真剣に怒った。
いままで叩き込まれてきた価値観、世界観、教え込まれてきた歴史観、そんなの、全部、書き割りじゃないのかって。
完全に洗脳されてたんじゃないのかって。
誰が洗脳していたのか? もちろん、世の中だ。世間だ。
そして二十代の若者(にして、馬鹿者)は思った、僕が生きてきた二十世紀、この二十世紀、そこに投げかけられたベールは、いつか残らず僕が剥いでやる。いいか? お前たちを直視して、ざまあみろ、と言ってやる。
そういう挑発的な態度は、結局、あれから十四年が経っても変わっていない。僕は二十代の青臭さから、全然脱却していない。それどころか作家となって、僕が編みつづけ/語りつづける小説は一作ごとに攻撃性を増している。いうなれば確実に実戦的なツールに育ちはじめている。
万歳、と僕は思う。
そしてこの小説だ。この九冊めの、『ベルカ、吠えないのか?』だ。僕は無限の頭数のイヌを伴走者に、ついに二十世紀を語りだす。実際には、僕が彼らの伴走者になって、歴史が翻弄してきたイヌたちの物語を、ここに吐きだす。
イヌたちは吠える。愛し、憎み、だから吠える。合い言葉は――その吠え声は、うぉん、だ。この小説内で、イヌたちはどこにいる? アリューシャン列島に、ハワイ諸島に、朝鮮半島に、インドシナ半島に、アメリカに、メキシコに、アフガニスタンに、もちろん旧ソ連邦内に、だからどこにでも、いる。
それがこの小説だ。イヌが、吠える。