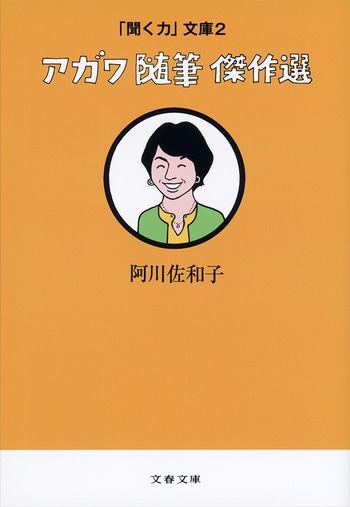本書は阿川佐和子さんの「謎の赤ん坊時代」から現在に至るまでの随筆集。一編が短いので、佐和子さんのスナップアルバムを眺めるようにあっという間に読み終えてしまった。そしてしみじみと思う。「恐るべき記憶力!」
しかし赤ん坊時代のエッセイには「この記憶はウソかもしれない」とご本人は記している。大人に内緒でマッチをいじって遊ぶ自分の映像が思い浮かぶというのはおかしい、この視線は第三者のものではないか、と。
たしかに記憶は年月を重ねるうちに改ざんされてしまうことはありうる。しかしご本人が怪しげだとおっしゃっても、それがウソだとはわたしには思えない。記憶とはその持ち主だけのもので、内容を誰かに伝えるときには言葉を使って説明するしかないが、語るにもそれなりの技術が必要だ。
佐和子さんは小説家でもあるが、ご自身の身に起こったことを物語として綴るのは当然と言えば当然。つまり本書は佐和子さん自身の物語と言える。阿川佐和子さんの人生を檸檬のようにギュッと絞り、その果汁を味わえる一冊かもしれない。
そして本書は、佐和子さんが育った阿川家の物語でもある。他人の家の常識は実に面白い。お味噌汁に梅干しを入れるというのは初めて聞いた(今度試してみたい)。志賀直哉氏にもらった黒ランドセルの章は、さすが作家の娘らしい話。お父様の阿川弘之氏が娘の佐和子さんに大きな影響をもたらしたことは承知していたが、一つ一つのエピソードを通して、父娘の関係が立体的になってきた。
お父様のカミナリは思わぬところから落ち、突然機嫌が悪くなったりする。
「父は基本的には私にとって怖ろしい存在であった」と書かれているが「予知不能火山」たるお父様を描く佐和子さんの筆致は軽快でどことなく楽しげだ。
特にハワイ旅行の話は印象的。お父様の身の回りの世話係兼食事をともにする相手として、ハワイに行くことになった佐和子さん。現地で不機嫌になったお父様にタイ料理屋へ連れられて、料理の辛さと格闘しながら食べ続けている。そんな二人に対するアメリカ人の紳士のにこやかな視線に、仲よさそうな父娘を演じざるを得なくなった……父娘の心境が「うんうん、なんだかわかる」とうなずいてしまうこのエッセイ、冒頭の「謎の赤ん坊時代」と同じく、第三者の視点から綴った文章である。お父様に叱られる自分を客観的にとらえつつ、さらにアメリカ人の視線を借りて、汗をかきながらタイ料理をほおばる父娘を描く。どんどん俯瞰していくハワイ旅行中の父娘物語の一コマとして楽しい。