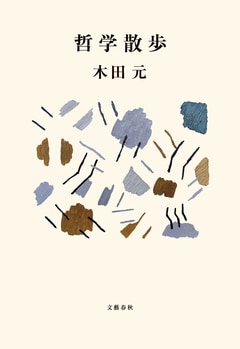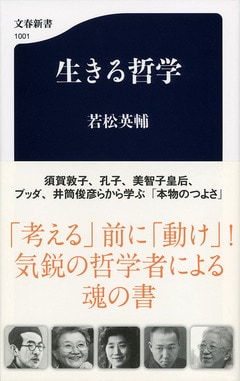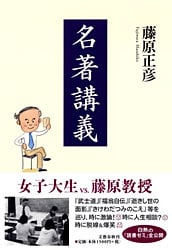言ってみればひとつの戦後精神の記録だが、同時に、ドストエフスキー、キルケゴール、ハイデガーと読み進んでいった、それら思想家たちへの単刀直入な道案内にもなっている。ハイデガーを読みたい一心で大学に進み、英独仏はもちろん、ギリシア語、ラテン語を数カ月でものにしてゆくその様子は、シュリーマンが『古代への情熱』で披瀝(ひれき)した外国語学習法さながらで、外国語習得に悩んでいる人間にはじつに適切なアドバイスになるだろう。もっとも、一言語一日十時間三カ月というのは並みの人間には不可能、やはり木田先生は並みではないと思ってしまうのだけれど。
とはいえ、新著の面白さの白眉(はくび)はやはり小林秀雄とハイデガーの対比。ドイツ本国でも特異にして晦渋(かいじゅう)と評されるハイデガーの思想にそれほどの違和感を持たずに入り込めたのは、小林の文章に若い頃から親しんでいたからだと述べておられるが、その体験から出発して両者の類似点を次々に指摘されてゆく。言語観において両者の類似は頂点に達するが、その間に、ハイデガーの限界は近代の超克をきわめて近代主義的に行おうとしたところにあったという指摘をさりげなく挟んでもおられる。
ちなみに、小林秀雄とハイデガーが類似しているのはニーチェ体験が共通しているからではないかと指摘されるところで、突然、小生の名が登場するのには驚いてしまった。というか、恐縮してしまった。小林のニーチェ体験には和辻哲郎二十四歳の著作『ニイチエ研究』が与(あずか)ったという小生の説を紹介してくださっているのである。「人は行為を目的や動機から説明しようとするが、目的は活動の蒼白なる記号に過ぎない」というような『ニイチエ研究』の文体が、たとえば『様々なる意匠』の、バルザックの『人間喜劇』には作者自身も含まれざるをえないことを考えれば、バルザックの「人間理解の根本規定は蒼然として光りを失う概念に過ぎまい」というような小林の文体へと展開していったのではないか、という説である。思想を文体にまで高めたのは和辻ではなく小林だった。二十年前に書いた文章だが、いまもそう思う。
読書回想録と述べたが、新著は最終章「小林秀雄と保田與重郎」にいたって、回想録ではなくなる。ハイデガーに似ているのはむしろ保田與重郎ではないか、若い頃にもっと読んでおけばよかったと述懐するわけだが、先生にとって保田與重郎は現在の問題にほかならないのである。当然のことだろう。保田だけではない。ハイデガーも小林秀雄も現在の問題なのだ。
木田先生は日本の哲学者の文章を日本語として分かりやすいものにしてくれたわけだが、その秘訣は文章以上に若々しい思考にあったのだと思う。
あらためて感謝の念を覚える。