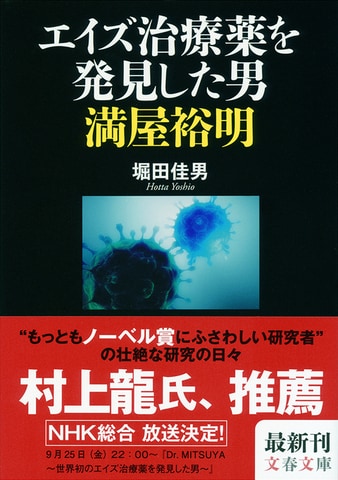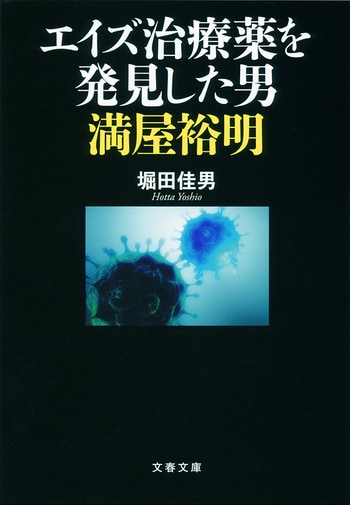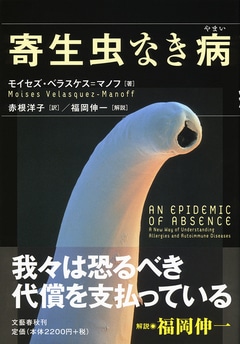別の解決策として、ワクチンの完成が期待された時期があった。だがワクチンは一五年になっても完成されていない。完成どころか、研究をしている人たちの間では「エイズワクチンは不可能に近い」との考え方が主流になっている。それほどエイズに対するワクチンの開発は難しい。
満屋が「長生きのくすり」を開発しはじめた八〇年代、日本の医学部には研究者が治療薬を開発することを軽視する傾向が残っていた。ドイツ医学への偏重傾向が色濃く残り、基礎医学に重きが置かれていたからだ。
「治療薬に結びつくような研究はサイエンスではないという風潮がありました。でも治療薬をつくることがどれほど大変なことか、多くの人は理解していなかったかもしれない」
満屋が最初の三薬を発見していなければ、エイズの抗ウイルス薬の研究は最低でも二年は遅れていた。その間に世界中のエイズ患者がどれほど亡くなっていたかは計り知れない。
ただ「新薬の発見」と一言で述べても、一般人にとっては想像の枠を越えている。これまでになかったものを探しだしてくる作業は、研究者であっても並大抵のことではない。ましてや特許を申請できるような発見は生涯に一度あるかないかのことだ。ITの分野でも世界中の人がハッと息を飲むような発明は極めて少ない。それほど新しいものを見つけることは難しい。
そうしたなか、一人の日本人科学者が世界で最初にエイズの治療薬を開発した経緯を書き記せたことは幸運と呼んでいい。
さらに単行本を書いている最中にAZTの訴訟が起きた。当初、AZTの開発をストーリーの主軸に据え、物語としては本文で述べたddIとddCの認可がでたところで終わる予定だった。だが特許訴訟を追うことで、製薬会社の行状を公の眼にさらすと同時に、アメリカの司法の汚点を突けたことは何よりだった。
「なぜなんだろうと思わないといけない。おいしいものを食べた時も、『おいしいね』で終わっていてはいけない。つねになぜおいしいのかと思わないといけない」
満屋は自分に強制的にこの「なぜ」を課している。さらに満屋が日頃から気にとめていることがある。
「研究者は不必要なことをやるべきではない。研究者は新しいことだけをやるべきなのです。いわゆるルーティンワークはやるべきではない」
科学者としての成功の基盤がここに見える。多くの人と同じことをしていては世紀の発見はない。ましてや事務業務に時間をとられていてはいけない。そう思っていても実践できない人が多いなか、満屋は自分を律するようにして、いまも研究に勤しむ。
九九年に単行本をだした直後、出版関係者からいくつかの厳しい意見を頂いた。本書の内容が「エイズを治した男」ではないというのだ。さらに「伝記本としては満屋の年齢が若い」という声もあった。
当時はいまのように「慢性の感染症」と言えるまでエイズを抑えこめていなかったし、満屋もまだ四〇代で伝記にするには確かに若かった。
けれども一五年夏、両点は克服されたのではないか。感染すると全員が死ぬと言われた病気は三十年もたたないうちに治療可能になった。さらに六五歳を迎えた満屋は、実績・名声共に伝記の対象者として十分な科学者になった。
書き手として、長きに渡ってノンフィクションの主人公と寄り添えたことは僥倖と呼んで差し支えないだろう。今後のさらなる治療薬の発展とエイズ患者が本当に、そして早いうちに地球上からいなくなることを願っている。
二〇一五年夏
(「あとがき」より)