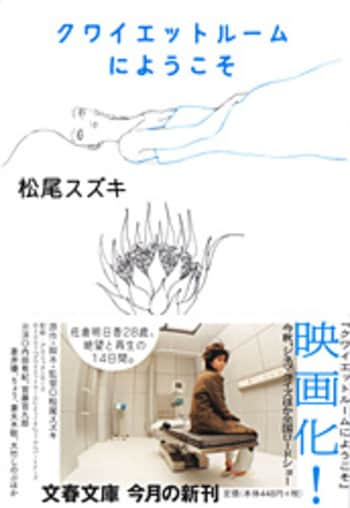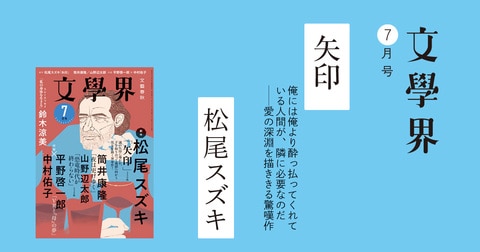――今回の小説『クワイエットルームにようこそ』は、『文學界』二〇〇五年七月号に一挙掲載され話題になりました。精神病院の閉鎖病棟を舞台とされていますが、以前からこうした分野には関心があったのですか。
松尾 もともと精神病院や閉鎖病棟のルポなどには興味がありました。映画『カッコーの巣の上で』とか、病識がないのに、病人と位置づけられて隔離されてしまう恐怖にサスペンスを感じます。何故か狂気にひかれてしまうところが自分にはあるんですね。狂気というのは、人から見た感じと、自分が感じているものとは決定的に違います。その温度差が不気味ですね。
――まず印象的なのは冒頭部分です。エンジン全開で、読者はこれから一体何が始まるのだろうと混乱すると同時に、期待をしてしまいます。
松尾 やはり最初はパニックだと思うんですね。自分では何が起こったのかわからないし、周りもそれに巻き込まれてしまう。ここでは胃洗浄という肉体的な苦しさのパニックを、夢の中で映像的に置き換えてみたらこうなるだろうということで書いてみました。鬱々とした人生があって、そこにパニックが起きて、嵐が過ぎ去った後に、孤独な静けさがあるというところから始めたいなと考えていました。
――この小説は主人公の明日香が体験した閉鎖病棟での十四日間が、一人称の視点で饒舌に語られていきます。一方、たくさんの登場人物が出てきて、それぞれにキャラクターが立っている。読者は主人公に思いを寄せると同時に、ある種演劇を観ているような気分も味わえます。作者である松尾さんの視点はどこにあるのでしょうか。
松尾 今回の場合は、自分が二十八歳の女性になりきって書いているというところがありますね。演じながら書いているという感じでしょうか。
――明日香は、不用意とはいえ、オーバードーズ(薬の過剰摂取)で閉鎖病棟に強制入院させられてしまいます。そんな切迫した状況で最初に心配するのが締め切りのこと。ある意味、松尾さんの意識とも重なる部分があるのでしょうか。

松尾 主人公をライターにしたのは、ひとつは文章を書くことができるということ。もうひとつは、フリーランスの人間が逃げ場のない状況に追い詰められたときに、締め切りなど小さなことがひとつひとつサスペンスになっていくということです。会社勤めのOLであれば、有給とってちょっと一息ということもあり得るかもしれませんが、生活がかかっているフリーの人間にとっては休業イコール、サバイバルなわけです。
――この作品では、小説的空間の中に演劇的空間が溶け込んでいるかのような印象を受けます。作者として、両者を融合させるというような意図はあるのでしょうか。
松尾 小説と演劇では全然違いますね。人物設定の仕方やキャラクターの作り方は同じなのですが、演劇というのは、一人称で語られるものではないし、一人の主観で語りきれるものでもないと思います。今回の小説では情報としてはいろいろなことが語られているのですが、それはあくまでも明日香を通した視線でしかないわけです。
――明日香が意識を回復した後に最初に出会う人物、ナース江口。彼女の事務的で無機質な感じは非常に印象的ですね。
松尾 日常生活の様々な場面から、このキャラクターは生かせそうだなと感じることは多々あります。ナース江口に関してもモデルがいて、ナースではないのですが、その鉄仮面ぶりは彼女のキャラクターにぴったりだろうと思ったわけです。そういった部分では、この役者にあの役柄を演じてもらいたいと考えているのと、共通するところがありますね。
リアルと笑い
――閉鎖病棟に漂う重苦しい空気と、それを笑い飛ばしてしまうある種の軽さのようなものとのバランスは、シビアな空間なだけに難しかったかと思います。
松尾 人間って、二十四時間ずっと深刻にはなれないというところに、ぼくはリアルを感じるんです。本人の中にもそういう状態をギャグにしてしまう気持ちはどこかにあるだろうし。何となく自分の意識に逃げ場をつくっていくのが、人間のリアルな部分だと考えています。ぼくの書く作品というのはすべて、リアルなことがあった次の瞬間に笑いがくる。それが現実なんじゃないかなと思います。
――あまり笑ってはいけないところだとか、そういう状況だからこそ、小さなことが笑いや可笑しさにつながることは確かにありますね。
松尾 あるいは、本人はいたって深刻なんだけれども、客観的に見ると笑うしかないというような。
――閉鎖病棟の中には種類の違う病名の患者が出てきます。実際に取材などされたりしたのですか。
松尾 資料を読んだり、実際に閉鎖病棟に入っていた人の何人かに話を聞いたりして、自分で病院の見取り図を作ってみました。
――登場する人物の中には、少し変だけれども、一般の社会にもいるような人々が出てきます。ここで描かれた閉鎖病棟というのは世間とは全く別の空間ではなく、社会生活の一部を切り取ったもののようにも感じられるのですが。
松尾 メタファーというか、一つの社会、もっと言ってしまえば地球の縮図です。複数の人間が、逃げ場のない場所に入れられたとき、どんなことが起こるかということです。
――明日香の葛藤というのは、ある意味当然であり、普通のことであるとも言えます。結局、正常か異常かというのは、絶対的なものではなく、相対的なものだということですから。
松尾 例えば、ぼくもときどき自分は変だなと思うことがあります。ひとりで音楽を聴いているときに、気がついたら一生懸命、指揮をしていたりだとか。これだって、ひとりだからいいものの、公衆の面前でやっていたら変な人ですよ。そう考えると、所詮同じ人間が狭い空間の中で社会ごっこをやっているに過ぎないということも言えますよね。普通に服を着て、帽子をかぶって、人と話したりしているけど、自分が着ているものだって洋服ごっこだし、自分が書いた本を人が読んでいるのも、ある意味ごっこではないのかと。
――そのために締め切りを守って、あるいはそれを急き立てる編集者もごっこといえばごっこかもしれません(笑)。では、ごっこの外の世界には何があるのでしょう。
松尾 それはぼくらが感じている宇宙というものだと思います。つまり宇宙的な視野に立てば、ほとんどのことはごっこに過ぎないとも言えますよね。
――ところで、タイトルにもある「クワイエットルーム」とは一体どんな空間なのでしょうか。
松尾 明日香の日常が、対人関係のどたばた続きだったので、そこから飛んで静かな世界に行きなさいよ、といって行ってみた。そこからまたさらなるどたばたが始まるのですが、一瞬正気に返る場所ということでしょうか。ある空間と別の空間を結ぶ隔絶された場所、出口であり入り口であるような、現実の手が及ばない空間。そこだけなんです、明日香が一人でものを考えられるのは。
――つまり、その中で彼女はようやく『クワイエットルームにようこそ』という作品を書き上げたということですね。
松尾 そうですね。
――閉鎖病棟に入っている人の入退院を決める権限は、保護者に握られているというのがひとつの鍵になっていますね。結局、病気と診断されて入るのではなく、保護者の判断次第という言い方もできます。
松尾 入院には任意と強制の二種類があって、任意の患者には病識があるのだけど、強制の場合はそれがない場合が多く、あるのは被害者意識です。例えば拒食症の場合も、自分がやせ過ぎていて、このままだとまずいなと思う人と、やせていることに美意識を感じ続けていて、さらにやせなければと思う人がいるわけです。当然、後者の方が危険度が高いわけですが、根が深い方を書きたいという思いはありました。
――映画『イン・ザ・プール』ではトンデモ精神科医・伊良部の役で主演されました。この小説を作り上げる上で、何か影響を受けたことはありますか。
松尾 うーん、特にはないかもしれませんね。『イン・ザ・プール』の場合はもう少しのん気に笑える話だと思うんです。今回の小説は、それよりはギリギリの話ですよね。閉鎖病棟に叩き込まれているという被害者的な状況だからこそ書けるヒリヒリした笑いというものがあると思うんです。これが第三者の立場に立ってしまうと笑えない話です。あくまでも本人がどうしようもなく追い込まれているからこそ、自虐的に笑うしかないというような。
――最後のシーンは冒頭とは対照的に静かではありますが、心地よい余韻があります。
松尾 あそこで、明日香は唯一の仲間であると信じていた栗田さんも実は危ういかもしれない、ということを悟り、はっと我に返るんですね。
――それをどう解釈するかは読者にも委ねられているという気がします。ところで、松尾さんは、演劇、映画、雑誌など様々なジャンルで、作る側としても、演じる側としてもご活躍されています。その中で小説というのは、どのような位置にあるのでしょうか。
松尾 自分のやっている表現の中では究極の手段であるという意識はあります。今は舞台に立って動いているという状態ですが、そこからどんどん不自由になって、人との関わりを断って無人島に一人残っても、書けるわけじゃないですか。そういう手段としては有効だなと考えています。最後の砦というか、すべてを奪われても残るものというか。
映画や芝居を作ったりして、ストレスを感じたときにも、俺にはまだ小説があるわい、というような奥の手という感じはありますね。