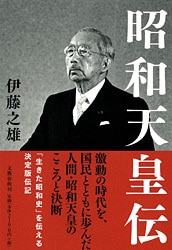本書のタイトルにある「卑怯」という表現は、太平洋戦争終結直前の一九四五年八月に米陸軍が刊行した「対日戦用マニュアル」から採られている。本書『米軍が恐れた「卑怯な日本軍」』の著者である一ノ瀬俊也氏の直訳によると、新兵教育のために作成されたこのマニュアル本の題名は「卑怯な一発 日本軍の策略、欺騙戦術、対人攻撃法」と名付けられているという。
米軍の言う「卑怯」とは、日本軍の多様なゲリラ戦術のことを指している。確かに、日本軍は対米戦における各地の戦場において、「待ち伏せ」「夜襲」「仕掛け爆弾」といった様々な戦法や武器を駆使して戦った。
米軍はそれらの戦術を心底から恐れ、その結果として「卑怯」なる言葉を導き出した。即ち、「卑怯」という単語の選択は、「恐怖心」「畏怖」といった心理の裏返しであると考えられる。実際、一九四五年三月末から始まった沖縄戦では、米軍内において多数の兵士が精神に異常をきたす事態にまで及んでいた。
本書によれば、「対日戦用マニュアル」には次のような一文が記されているという。
〈日本軍は卑怯な手を好む。戦争の歴史上、背信とずる賢さにおいて日本軍にかなう軍隊は存在しない。真珠湾のだまし討ち以来、アジアや太平洋の島での作戦を通じて、日本軍はあらゆるトリック、優勢を獲得するためのまやかしを使った〉
この「対日戦用マニュアル」という刊行物が、日本への蔑視的な敵意に充ちた内容であったことは、この引用文を一読しただけでも充分に察せられる。但し、一ノ瀬氏はこのような一方的な内容に彩られたマニュアル本への批判にのみ重点を置くのではなく、なぜ米軍側がかかる心理状態に陥ったのかという背景について、丁寧に焦点を合わせて考察している。
即ち、日本軍の攻撃と言うと「バンザイ突撃」や「特攻」などがすぐに思い浮かぶが、それだけではない側面が実際の戦場には存在したのだという史実への着目である。日本軍には世界の他の軍に類を見ない独特の「潔さ」「勇敢さ」があったことは事実だが、それ以外にも多様な表情を有していたことを本書は教えてくれる。
私自身、「米軍が抱いた日本軍への恐怖心」について、実際に肌で感じた取材があった。それは、二〇一五年四月、天皇皇后両陛下の訪問に合わせ、パラオ共和国のペリリュー島を取材した時のことである。
ペリリュー島は一九四四年九月から十一月にかけて、日米両軍が激しく干戈(かんか)を交えた地である。日本軍の戦死者は一万人以上、米軍側にも千八百人ほどの犠牲者が出た。
殺到する米軍の上陸部隊に対し、日本軍は島中に洞窟陣地を張り巡らせて迎撃した。ちなみに、このような洞窟戦法は、ペリリュー島の戦いを嚆矢として、後の硫黄島や沖縄での戦い方に受け継がれていくことになる。
ペリリュー島の中心部に向かって密林の中を歩いていた私は、米軍側が「死の谷」と呼称したという一帯に出た。両側を鬱蒼とした木々に挟まれた薄暗い一本道である。
戦時中、米兵がこの道を進むと、両脇の洞窟や岩の裂け目から無数に銃弾が飛んで来たという。敵の姿が見えない中、静かな谷にヒュンヒュンと弾丸のみが飛び交う局面は、確かに強烈なる恐怖心を呼び起こしたに違いないと容易に想像できた。
幾つかの洞窟内部への出入口付近を確認すると、その多くの部分が黒く焼け焦げた状態となっていた。その黒々とした焼け跡は、米軍が使用した火炎放射器の威力を如実に示していた。米軍が火炎放射器を実戦に初めて導入したのがペリリュー島であった。新兵器である火炎放射器は、洞窟内に潜む日本兵の身体を一挙に焼き払った。私は洞窟内を這って進みながら、「そこまでする必要があったのだろうか」との率直なる疑念を感じた。
しかし、本書を読み進めれば、この残酷なる燃焼の意味が腑に落ちる。米軍が抱いた日本軍への「深刻なる恐怖」が、一種のヒステリックとも言うべき戦い方に繋がったことが理解できる。
ペリリューの戦いから帰還できた日本兵は僅かに三十四名のみと言われるが、その中の一人の方にお話を伺う機会があった。土田喜代一さん(取材時・九十五歳)は、米軍の上陸後、上官から「棒地雷」なる武器を手渡されたという。
「海軍の私は棒地雷というのをこの時に初めて見ましたが、陸軍には前からあったようですね。ちょうど刀の鞘を少し大きくしたようなもので、先端に爆薬筒が付いているんです。この棒地雷を持ったまま『戦車のキャタピラに体もろとも突っ込め』ということでした」
結局、土田さんの多くの戦友たちが、この棒地雷を使って戦車と共に肉弾と散ったという。
本書では、日本軍が生み出した様々な地雷や手榴弾についても事細かに述べられている。「棒地雷」のような「対戦車肉迫攻撃」が生まれた背景について、一ノ瀬氏は日本軍が作成した戦車攻撃教育用のマニュアル本の内容を引用しながら次のようにまとめている。
〈対戦車肉迫攻撃は本当に万能の戦法だとか「皇軍独特」だと信じられていたのではなく、当時の軍人としても出来ることなら戦車には戦車や火砲で対抗したいが国力の格差はそれを許さないという苦い認識に基づき、仕方なく持ち出された戦法に過ぎないということがわかる。肉弾は別に神聖視されるべきものではなく、あくまで「創意工夫」「希望」、すなわち現実との妥協の産物であった。それを単なる狂気とか精神論で片付けてしまうことは、過去の日本人を理解する正しい態度ではない〉
物量で明らかに格差のある相手を前にして、軍隊として如何に戦うべきか。陸軍の計り知れない苦悩に思いを馳せなければ、先の大戦の悲劇性を理解することはできない。
その他、日本軍は「死んだふり」「民間人へのなりすまし」といった手法も対米戦において用いていたという。本書はこのような戦い方の原点を、日中戦争下に求めている。
つまり、中国軍が日本軍に対して得意としていたゲリラ戦術を、後に日本軍が取り入れるようになったという歴史的経緯への視点である。確かに、一九三七年の南京攻略戦の際にも、日本軍は中国軍の「便衣兵」(民間人へのなりすまし)の脅威に大いに悩まされた。このような「卑怯」な戦い方を中国軍から教訓として学んだ日本軍が、対米戦にこれを応用したという史実の断面は、昭和史の実相を考える上で非常に興味深い。
無論、米軍の言う「卑怯」には、差別的な側面が濃厚に含まれていた。当時の欧米諸国に定着していた「黄禍思想」は、先の大戦の本質を理解するためには見逃してはならない重要な要素の一つである。
戦前戦中に欧米社会で描かれた風刺画などを見ると、日本人はキツネやアリ、猿、蛇といった姿で描かれている。そこには「狡猾」「野蛮」といった日本人観が色濃く滲む。更に、真珠湾攻撃が「だまし討ち」と認識されたことによって、このような日本人観は否応なく強化され、その結果、「卑怯」という言葉が「対日戦用マニュアル」のタイトルに冠されるにまで至った。
付言すると、このような日本人に対するイメージは、実は今でも大して変わっていないのかもしれない。以前、アメリカで「日本人を動物に喩えると何か」というアンケート調査が行なわれた際、最も多かった答えは「fox」(キツネ)であった。
この「fox」には多様な意味合いが含まれるが、例えばチェスを指している際に「foxyな手」と言われれば、それは「賢い手」という肯定的なニュアンスと共に「狡猾な手」といった語感も内包されることになる。
米軍が日本軍を「卑怯」と指弾する一方、戦時下の日本軍では「米兵は精神的に軟弱」といった言葉が頻繁に使われた。銃後において「鬼畜米英」という言葉が広く流布したこともよく知られる通りである。
他方、中国人は日本人を「日本鬼子」と蔑み、日本人は中国人を「チャンコロ」と笑った。差別や敵意といった感情の構図は、基本的に双方向性のものであるという峻厳な事実が浮かび上がる。
そう考えれば「卑怯」もお互い様であったとも言えるし、世界中の軍隊は全て「卑怯」であったとも言い得るであろう。