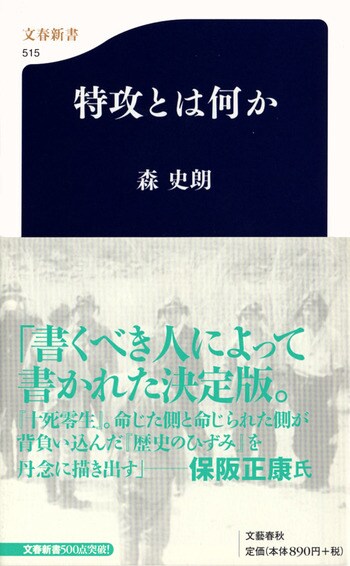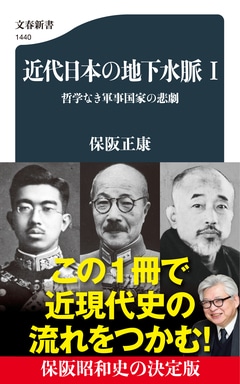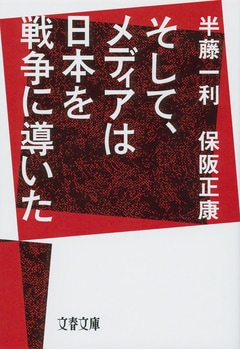――まず、『特攻とは何か』の本題に入る前に、プロローグにも書かれているように特攻と、九・一一同時多発テロやロンドン地下鉄爆破事件などのテロ行為とのちがいについて、お話しいただけないでしょうか。
保阪 それは簡単なことでしょう。戦時下であるか、そうでないか。戦時下の戦闘行為としての特攻と、平時におけるテロとは根本的にちがっているでしょう。
森 テロリズムとは、辞書的な意味でいえば単に暴力主義、反政府的暴力行為ということになります。一般市民をまき込んだ無差別な破壊的行為ともいえるでしょうね。
特攻は戦闘行為ですが、しかしそれが「決死」ではなく「必死」の戦法、すなわち特攻=体当たり攻撃を発意した日本海軍の最高指揮官大西瀧治郎中将がいみじくも語ったように、それが正常な戦闘行為でなく、「統率の外道」というべきものであったことはまちがいありません。
特攻を語る場合に、この大西中将が自嘲して言った言葉の重味を、まず踏まえておく必要がありますね。
“命じた側”はどう生きたか

保阪 では、本題に入りましょうか。
私は森さんの『特攻とは何か』をゲラ刷りで読んで、こんな感想を持ちました。私も特攻については昨年、『「特攻」と日本人』(講談社現代新書)で、隊員たちの遺書を通して特攻作戦をたどるという作業をした。以前から、特攻隊に大変関心を持っていたけれども、彼らの遺書を読むと涙が出る世代なんですね。どうしても、今まで書けなかった。特攻というのはやはり人為的なことですから、命令した人がいる。その責任はきちんと問うべきです。そのため、書くのに何か構えというものがいる。去年、その構えがいちおうできて、ようやくこのテーマに取り組むことができたというのが正直な気持ですね。
森 私が特攻隊に関する本を書き上げたのは一九八六年(昭和六十一年)の『敷島隊の五人』(文春文庫)が最初です。

これは昭和十九年十月二十五日、比島最前線のマバラカット基地を飛び立った最初の神風特別攻撃隊敷島隊の五人の隊員たち、それぞれの最後の五日間をたどるというテーマで書いたものでしたが、これは特攻を命じられた側に視点をおいているために、命じた側、つまり当時の在比第一航空艦隊(一航艦)司令長官大西瀧治郎中将の立場が充分に描かれていない、という指摘があったんですね。
特攻とは、米軍艦船に飛行機もろとも体当たりせよ、という非情な命令です。志願を募るという形式をとるけれども、実質的には上官が部下に参加をうながす半強制的な意味あいが強いものだった。そのことは、前著に充分に書きました。では、命令する側がなぜこんな非道な命令を下したのか。
新書の編集部から最初にその問いかけをされたときに、なるほどその視点で書かれたものはないと気づいたんです。命じられた側の悲劇は数多く書かれて個々の悲劇性は大いに語られるけれども、命じた側は大西瀧治郎一人が“特攻の創始者”と評されているだけです。その配下に一航艦参謀長、首席参謀、各航空隊司令、飛行長、飛行隊長たちがいたはずだ。彼らは、そのときどういう対応をしたのか。何を考え、その渦中をどう生きたのか。そのことは、今までまったく書かれていない。
これは、命令系統のあり方、上司と部下の関係において今日的テーマとなりうると考えた。つまり、日本人論としてのテーマですね。結果的に、その試みが成功したかどうかはわかりませんが……。
保阪 おっしゃる意味に賛成です。たとえば、海軍作戦の中枢部にいた軍令部第一部長中沢佑少将という人がいる。
その人は特攻作戦について、大西中将がフィリピンに進出するさい、軍令部総長(及川古志郎大将)にはじめて「体当たり必死戦法」を説き、列席した軍令部首脳(伊藤整一軍令部次長、中沢第一部長)が寝耳に水のおどろきであったように、回想録に書いている。
ところが、その頃中沢少将は前線視察に出かけていて彼の記述とは日程的につじつまが合わない。その後のことですが、この点を戦史家妹尾作太男氏に指摘されて、中沢さんが海軍関係者の会合で絶句する、という場面があったりした。
森 そうですね。大西中将がレイテ決戦の前に前線進出するのは十九年十月初旬のことで、この頃すでに特攻兵器である人間魚雷「回天」の製作がはじまり、搭乗員の養成がおこなわれていたから、海軍首脳は部内でひそかに特攻の実施を決定していたわけですね。こういうデタラメが戦後も永くまかり通ってきた。
保阪 その大西瀧治郎ですが、彼は中沢証言や当時の現地指揮官たちが書いた『神風特別攻撃隊』(猪口力平・中島正共著、日本出版協同=昭和二十六年刊)などによって“特攻の創始者”とされた。敗戦後、彼はその責任を負って自決するわけなんだけれども、彼の個性や軌跡をたどってみると、過分にそれを背負い込んでいるような事実がある。
同時に、大西は最後には内地にもどって海軍の軍令部次長という要職につくんだけれども、彼のなかにはものすごい危険な部分がある。つまり、特攻という、「統率の外道」をあくまでもつづける狂気の部分ですね。これが大西が責任を押しつけられた理由のひとつですよ。
ただ一人の反対者
森 大西中将についていえば、敗戦直後の八月十六日午前二時四十五分、「特攻隊の英霊に曰(もう)す/善く戦ひたり深謝す」の有名な遺書を残して割腹自決した。先年、その遺書全文が石碑となり、五十五回忌のさいに菩提寺であるJR東海道線鶴見駅近くの鶴見総持寺に納められて、その除幕式に私も招かれて出席しました。
いままでの定説でいえば、この大西長官が敗戦直前にフィリピンに派遣されてレイテ湾に米陸軍マッカーサー部隊二〇万の上陸をむかえ撃つ。そのために特攻隊を編成して、海軍兵学校出身の関行男大尉に指揮官として白羽の矢を立てる。隊長の関大尉はみずから志願して、「ぜひ、私にやらせて下さい」と申し出て、新婚まもない妻を遺して米空母に体当たりをし大戦果をあげる、というのが海軍関係者の証言だったんです。
しかし、事実はそんな単純な話じゃない。まず、大西中将は突然の人事異動で内地からフィリピンに出されたもので、前任者は「ダバオ事件」といって、海岸の白波を米陸軍の上陸部隊と錯覚して司令部ごと山中に逃れるという大失態をやった。まるで『平家物語』の富士川の惨敗みたいなんですね(笑)。この混乱のさなかに在比航空兵力の大半を失った。そのため、前長官が赴任してわずか二カ月後に、あわただしく大西中将が現地入りする。
そこで、手もとのわずかな航空兵力でひねり出した窮余の一策が体当たり攻撃なんです。事前に、内地から出発前に準備していた戦術じゃない。
保阪 その点についていえば、大西は「特攻に狎(な)れるな」という言い方をくり返ししますね。狎れるなという意味は、こういう非道な戦法を無限に日常化することの恐ろしさ、ある意味での人間の感性や理性を超えていくことに恐怖感をもっていたんだと思う。
森 大西中将は特攻を、後に陸軍や戦艦大和をも沖縄に突っ込ませるような、全軍特攻を最初から企図していたわけじゃないんですね。あくまでもレイテ湾のマッカーサー部隊の上陸を阻止する。そのために、戦艦大和、武蔵を中心とした連合艦隊総力でレイテ湾の上陸船団に突入する。その一時期だけに、米海上航空兵力を飛び立たせないように航空母艦の飛行甲板を使用不能にするという、限定的な戦法だった。
それが、最初の敷島隊の戦果が「米空母一隻撃沈、一隻中破」という過大なものであったために、部隊を拡大し、さらに全軍特攻へとエスカレートして行く。この特攻戦拡大が数多くの悲劇を生んで行くわけです。
保阪 僕は自分の本には書かなかったんだけれども、沖縄戦の最後の頃、失禁したり、腰が抜けて立てなくなったりする特攻隊員がいたりした。茫然自失しているのを抱え込んで乗せ、そして飛ばしていった、と学徒の整備兵が言うんですね。で、彼らはその乗せた罪というのをやっぱり今でも背負って生きている、と何人かから直接聞いている。
森さんはこの本に書かれているように、遺族を訪ねる旅をしているんですが、実際に彼らと会ったときの感じというのはどうでしたか。
森 遺族を訪ねる旅ですか。いやあ、あれはつらかったですねえ……(苦笑)。
特攻隊員の遺族といえば当時の軍神ブームのなかですから、大騒ぎでしたね。家の前で拝んで行く人がいたり、神社まがいに鳥居を建ててくれたり、家族は狂熱のるつぼに放り込まれた。それが敗戦とともに一転して戦争犯罪人あつかいでしょう。両親とも、失意のうちに亡くなった人がほとんどでしたね。
ある特攻隊員の妹さんに、「戦後は一家が不幸つづき。それも、兄が体当たりで大勢の人を殺したからでしょうか。もう、そっとしておいて下さい」と、頭を下げられたこともありました。一方、長男を特攻で亡くした母親は、「もう、だれも恨んどりゃあしません。責任者が責任をとってくれましたから……」と、大西長官が敗戦後自決してくれたことで気持が癒(い)やされる、という意味のことを言っていましたね。
保阪 それは、本心ですか。本当に癒やされたと思っているのかなあ。
森 いやァ、それはどうかなあ……。時間の経過という問題がありますね。私が遺族を訪ねたのは戦後四半世紀もたってのことですからねえ。
保阪 森さんの本には、実際に隊員の人選に当たった飛行隊長のインタビューが載っていますね。命じた側の責任者は、特攻というものをどう考えていたのですか。
森 最初の神風特別攻撃隊の隊長は健在でした。私のインタビューが戦後はじめてだ、と言っていました。とくに取材を避けている、というわけではなく、これも戦後三十年という時間の経過のおかげでしょう。
その隊長氏は、「私は未熟だった。こんな危急の事態にどう対応して良いか、わからなかった」と言っています。飛行隊長といっても三十歳そこそこの若さですからねえ、正直な感想だと思います。ただ茫然と、最高指揮官の言いなりになっていた、というのが本当のところじゃないか。その分だけ、戦後は部下を死地に追いやった自分の責任について己を責めつづけていたようですよ。
保阪 大西の部下で、美濃部正少佐という人物が登場しますね。大西と二人、朝まで話しあって特攻隊を自分の部下から出さなかったという。
森 美濃部正少佐はただ一人、現地部隊の指揮官として特攻に反対した人物ですね。レイテ湾の米上陸軍を阻止するのが日本海軍最後の作戦というなら、大西長官と兵学校同期生の福留繁二航艦長官も一緒になって、もちろん自分自身もふくめて指揮官先頭で米軍艦船に突っ込むべきだったと、戦後も主張している人です。
保阪 私も彼になんどか会いましたが、こういう軍人がいたということが、私たちにとって、特攻を考えるときの要点の一つではありますね。しかし、彼を「特攻に反対した」ということで捉えるだけではやっぱりいけないんだな。美濃部少佐もやっぱり海軍の軍人の一人で、あの時代に選択肢として、森さんの言葉を借りれば「必死隊はダメだ。決死隊でいい」という、その選択の違いがあっただけでしょう。だけど、それはほとんどもう同じ次元まで行っているんですよね。
自分は一〇〇パーセント死ぬという命令は出せない。だけど九〇パーセントならやる。指揮官としてそこを守ったというだけで、特攻に対してちょっとだけ距離を置いた指揮官というふうに、僕は見ているんです。
大西長官の思想転換
森 大西についてはもう一点、彼の大変節を指摘せねばなりませんね。比島で特攻作戦を中止すべきだという意見に反し、同じ二航艦の福留(繁)中将の部隊にまで拡大し、内地に呼びもどされて軍令部次長という要職につくと、こんどは一億総特攻という戦略的な立場に大転換する。
保阪 その点が、大西瀧治郎という人物の謎ですね。大西は、鈴木貫太郎内閣の和平工作に抵抗して徹底抗戦を主張し、「日本は最終的に二千万人の特攻死を実行すべきだ」などと東郷外相に言っている。当時、毎日新聞の記者だった戸川幸夫さんが、「これで勝つんですか?」と聞いたときの答えもしばしば引用されますが、そのときも、「二千万人死ななきゃダメだ」と、答える。
二千万人といったら国民の五人に一人ですよね。そのことはどういうことかというと、アメリカはびっくりするわけです。こんな民族いるのか? こんな戦争あるのか? と言って、向こうのほうがもうこんな戦争は「やめよう」と言うだろう、と。これが大西の最後の考えだったらしい。これは大西だけじゃないんだと思う。
本土決戦派のそういう考え方の傲慢さと、それから、軍人の領域じゃなくて、ある意味での狂気が、やはり特攻作戦に狎れるなと言いながら、どうも最後に大西の中には出てきたのではないでしょうか。
森 この話については海軍の大先輩である小沢治三郎から、「二千万人の男を殺して、だれがこの国を再建できるのか」と叱咤されるんですね。
私もこの大西の思想転換がよくわからない。一億総玉砕、本土決戦といってももはや戦うに兵器なく、食糧も大陸からの日本海輸送ルートが機雷封鎖されて途絶している。戦争の未来展望が何もない状態なんです。ここであくまで戦争を継続すべきというのは、狂気の沙汰です。
当時の国情からいえば、「撃(う)ちてし止まむ」ですから当然なのかもしれないけれども、この狂熱とは何だったのか。
一つのヒントは、大西の比島脱出にあると思うんです。つまり、特攻機が皆無になって全員が山ごもりして上陸した米軍とゲリラ戦をたたかう。「最後の一兵まで比島を死守せよ」と、大西が命令を下すわけです。
ところが、米内海相が「和平交渉を有利にみちびくためには米軍に一矢を報いることが必要だ」として、彼を内地に呼びよせる。このとき、現地に居残る司令から、われわれをおき去りにして逃げるのかというような批判を受けて、内地へ飛び立つ基地の暗がりで「そんなことで、戦(いくさ)ができるか!」と大西が司令を殴りつける。これは実際に起こった出来事で、目撃談もある。
大西長官としては、特攻隊を出した時点から責任をとって自決する覚悟を決めていたと思いますね。その気持をどうしてわかってくれないのか、というのが本当の気持だったでしょう。
その結果、現存部隊一万五千四百名が山ごもりし、生存者四百五十名という惨憺たるゲリラ戦となった。ですから、大西の頭のなかにはたえず彼らの存在があって、いまなおフィリピンの山中にこもって戦っている兵士たちと同様に徹底抗戦せよ、と言いつづけたのではないか。
そこに大西中将の悲劇があり、彼がいまなお和平論者から指弾される理由になるんじゃないですか。
保阪 なるほど。それもわからないではない。ジョン・ダワーの『容赦なき戦争』という、戦時下のアメリカで行なわれた反日キャンペーンの実態を分析した本があります。日本への憎しみの構造は相当な広がりをもったことがわかります。
また、駐日大使だったジョセフ・グルーが戦時下のアメリカを講演して歩いて、「日本というのはそんなに変な国ではない。ある意味でバランスのある国だ」と説いて歩くと、「いい日本人はみんな死んだんじゃないか。残っているのはみんな悪い日本人だ」というような反応があった、ともいわれている。
ダワーやグルーの本を読んでいると、日本とはやっぱりそうなのかなと思う。アッツ島玉砕というのが十八年の五月にあるでしょう。あれは全員死亡ですよ。戦死ですよね。それを「玉砕」と言い換えて、美学的な領域に入っていく。
戦時国際法で捕虜が認められているのだから、戦闘で全員が死ぬという、こんな愚かな戦略はあり得るわけがない。それを大本営で美化し、そして歌までつくり、山崎(保代)隊長を讃え尽くして、みんな玉砕する。その延長が特攻になるわけですよね。そこへ行くまで、全員戦死の場合は「肉弾」「突貫」というのがあったりして、「玉砕」という言葉で美化されて、「特攻」という言葉になるんです。順序があるような感じがするんですよ、日本の戦争には。
それはだんだん、だんだん、正常な判断を失って単純に言えば狂気の世界、領域に入っていく。このことを戦後社会は、大西がいたからなんだ、というような形で問題のすり替えをやっているでしょう。そうではない、という指摘が、特攻に取り組む僕らの共通の基盤にあるべきだと思うんですよね。
僕とか森さんが持っている問題意識というのは、ある意味では歴史的な問題意識だと思うんですよ。この問題意識を次代に継承できるかどうかが僕らの時代的な役割で、森さんのこの本も、『敷島隊の五人』も歴史を継承する力を持っている。だから、次の世代、三十代の人なんかにこういう本を読んでほしいという思いが、僕は常に特攻の問題に関してはあるんですよね。
森 僕自身もまさしくそれを今日的なテーマ、つまり、あの時代だから、戦争中だからではなくて、その同じ歴史を我々はいま繰り返しているわけでね。それは戦争という極限の世界ではあるんですけど、でも、その行なわれていることは今日も繰り返しているんじゃないか。われわれはあの二十年八月十五日になって、すべてを全部遮断してしまっているんだけど、そうじゃないだろう、ということがあって、それはもうぜひ学んでもらいたいと思うんですよ、昭和史からね。