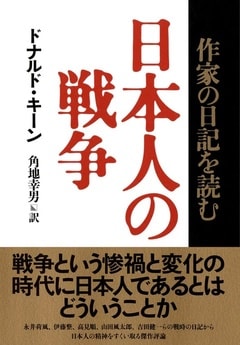太平洋戦争における硫黄島での戦いは、太平洋を巡る日米の戦いの中でも、特に激しく苦痛に満ちたものと言える。
昭和十九年六月、マリアナ諸島、サイパンの線を絶対国防圏として戦った日本軍は、もろくも敗退し、最後の決戦としたレイテ決戦も惨敗し、硫黄島での戦いが始まったときには、すでに日本には戦争継続の力はなかった。
フィリピンを征圧した米軍は、次の目標を、サイパンから日本本土空襲をした場合の援護戦闘機の飛行場と、損傷したB29の不時着飛行場として、東京から南方千二百五十キロの位置にある硫黄島に目標を定めた。日本側としては、硫黄島を占領されれば、それは日本本土空襲の強化であり、直接的には、皇居のある東京への空襲の激化に繋がることである。大本営としては、硫黄島は絶対に守り通す必要があったのである。
本書は、このような状況の中で、圧倒的な兵力の米軍を迎え撃ち、従来の島嶼防衛戦闘とは異なる粘り強い抵抗をし、米軍が、数日で征圧できると予想していた戦闘を、一ヶ月以上に亘る激闘の末、遂に全滅に至った守備隊の指揮官栗林忠道中将と、同じく硫黄島で命を落とした軍人の最期を、生存者、遺族の証言と、数多くの文献で辿った物語となっている。
栗林中将は、昭和十九年六月に硫黄島防衛の指揮官として着任したが、島嶼での防衛戦闘について、独特の考えを持っていた。従来の日本陸軍の島嶼防衛における基本的な戦術は、いわゆる水際撃退を基本とし、敵の一兵も上陸させないという考えが主流であった。ところが、広大な南方戦域における米軍との対決では、この防御戦術はことごとく失敗し、孤島部隊は玉砕を続けていた。栗林は、従来の島嶼防衛の失敗の原因を、米上陸部隊を水際で撃退しようとしたことに原因がある、と判断し、徹底した縦深陣地の構築による、持久戦を想定していた。水際撃退作戦が失敗するのは、米軍側から見れば当然のことなのである。米軍の上陸地点を攻撃できる場所といえば、地形的に想像がつく。当然日本軍の兵力の配備位置は大よそ偵察できるので、日本軍の水際陣地は、猛烈な空爆と、戦艦を含む大規模な艦砲射撃によって、事前に大きな打撃を与える事が出来る。このために、米軍としては、水際防御のための布陣をした日本軍は、実に攻撃しやすい目標だったのである。このような島嶼攻撃は、米軍にとっては一定のスケジュールを立てて作戦に臨む事が可能だった。栗林は、これを排して、米軍を上陸させ、全島内での遊撃戦的な戦いを命じたのだ。
栗林は、まず米軍を水際で叩くが、米軍の上陸阻止に拘ることなく、主作戦は、米軍を島内に引き入れた後の戦闘であるとしていた。こうすると日米の戦線が複雑に交錯し、日米両軍は常に入り混じった形で戦闘することになる。米軍から見れば、味方撃ちの可能性があるために、艦砲射撃や空爆がしにくくなる。このために、米軍の圧倒的な空爆、砲撃能力を発揮して、一気に日本軍を殲滅する事が出来なくなるのである。
このような作戦の実施のために、長期戦を考えた栗林は、全島をトンネルで繋いだ地下要塞の建設を計画した。そして、兵士は、高温で硫黄ガスの噴出する島の地下をひたすら掘り進み、実に総延長十八キロに及ぶ洞窟陣地を建設した。驚くべきことと言わなくてはならない。しかし、この作業には反対も多かった。自分たちは米軍と闘うために来たのであって、穴掘りのために来たのではない、と。
この地下陣地が、いかに優秀であったかは、米軍が上陸前に硫黄島に加えた二万トンに及ぶ砲弾、爆弾の嵐も、ほとんど日本軍を傷つけることは出来なかった事実が証明している。このために、昭和二十年二月十九日の朝、水陸両用装甲車と、上陸用舟艇合わせて七百五十隻で押し寄せた米軍は、ほぼ無傷だった日本軍の激しい攻撃を受けて、海岸で二千四百名もの戦死者を出したのである。米軍にとって予想だにしなかった損害だったが、本当の過酷な戦闘は始まったばかりだった。