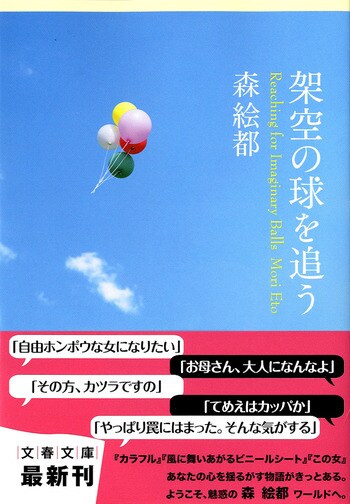収められている十一の物語を読みながら、何度も「あぁ」、と呟(つぶや)いた。切実で、だけど楽しくて、どう言葉に表せばいいのか悩ましく、読み終えたときにもまた「あぁ」とため息が漏れてしまった。
本書に描かれているのは想像に難くない、いかにもありそうな、あるいは実際に見たことや、その場に居たこともあるような気さえする、とても身近な光景ばかりだ。
たとえば表題作は少年野球の練習風景が舞台で、それを見守る母親たち、という構図もこれまで何度も休日のスポーツ公園で目にした覚えがあるし、続く「銀座か、あるいは新宿か」の、学生時代の友人との飲み会というシチュエーションも特に珍しいものではない。「パパイヤと五家宝」の主人公のように、ちょっとした余裕のある日にいつもと違う高級食料品店に足を運んだことは私にもあるし、「あの角を過ぎたところに」の恋人たちと同様に、昔馴染みの店の前を、久し振りにタクシーに乗って通りかかったら違う店に変わっていた、という経験もある。
それはきっと、私だけではないはずで、そうした意味において本書は多くの読者がすんなり物語の世界に入ってゆける、間口の広い作品集に仕上がっている。
でも、だけど。
身近で、親しみやすく、ついつい「あるあるそんなこと!」と無邪気に共感を抱きかけたところで、森絵都は読者にそのもう一足先にある情景を見せるのだ。
表題作で描かれる少年野球の練習は、コーチの気合いが空回り気味で、見学している母親たちは集中できずにいる息子たちに呆れつつも勝手なおしゃべりに興じている。
コーチはまだ初心者レベルの少年たちに、まずはフライの追い方を教えようと見本を示すが、少年らはその姿を笑い、道化的にふるまうことを競いはじめる。見つめる母親たちは〈「結局さ、さんざんユニホームだのグローブだのってお金をかけたあげくに、高校生くらいになったらお母さん、僕はお笑い芸人になりたいんだとか、突拍子もないことを言い出したりするんだろうね」〉〈「だよね。親の気も知らないで、俺は巨人よりも吉本の星になりたいんだ、とかさ」〉〈「ボールよりも夢を追いかけたい、なんてね。マジ許せない」〉〈「勘当もんだよ、勘当」〉などと語りあう。
いかにも「ありそう」な状況で、読んでいてもクスクスと可笑しさが込み上げてくる場面だった。
けれど、この先に続くたった一言で、その空気はがらりと一変するのだ。切なくて愛(いと)しくて「あぁ」とため息を吐(つ)くしかない世界へと。
表題作に限らず、それはどの物語にも共通する感慨で、読み進むうちにどんどん気持ちが落ち着かなくなっていった。
私たちは日頃、様々な場面を見聞きし、時にはその渦中に存在し、けれど、ほとんどのことを適当に「流して」生きている。そうしなければ、心の平穏を保つことなど出来ないし、それが大人の処世術というものだと思い込んでいる。馴染みの店が無くなっていても、その理由を深追いしている暇などないし、ホームレスらしき老人が出勤途中の若い女性にわざと接触し転ぶ場面を目撃しても(「チェリーブロッサム」)、百均で母と息子が言い争っていたとしても(「夏の森」)、少し眉を顰(ひそ)めるだけで深く考えずに通り過ぎ、たちまち記憶の中から消去してしまう。
本書はそうした、確かに見ていたはずなのにすぐに消えてしまう、消してしまう、日常の中に確かに存在したはずの「想い」を、読み手の心の中に鮮やかに浮かびあがらせてゆく。
と、同時に「巧い」と唸るのは、にもかかわらず、すべての物語を短編小説として綺麗に落とすために動かしていくあざとさが皆無である点。
書き方によっては全編を感涙必至の「いい話」としてまとめることも可能なはずなのに、随所に「えっ、そうくるの!?」と驚愕し、吹き出さずにはいられない主人公たちの強(したた)かさや変わり身の早さが挟み込まれているのだ。個人的に最も意外性が高く、印象的だった「二人姉妹」は、主人公が温泉旅行先で年下の従妹に姉妹関係が上手くいかないことを相談される話なのだが、そのぎくしゃくしてしまった「原因」に心が震え、聞かされた主人公同様に考えさせられ、このシリアスな状況にどんな結末を用意するのかとハラハラしながら読み進めた結果、思いがけず爆笑してしまった。
こうしたちょっと毒の効いた、けれどある意味リアルな人間らしさが、本書の親しみ易さに繋がっているのは明白で、著者の長編小説とは一味違う魅力となっている。
見ていたはずの光景、消したつもりでいた記憶、深く知ろうとしなかった物事の意味。そんなものを現実社会で誰かに思い出せ、考えろ、と突きつけられたとしたら、正直、余計なお世話だと思うだろう。
でも、それが小説なら、森絵都の描く物語なら、すんなり胸に沁(し)みてくるこの不思議。「あぁ」とため息を漏らすしかない、という読書の幸福を、ぜひ体感して下さい。