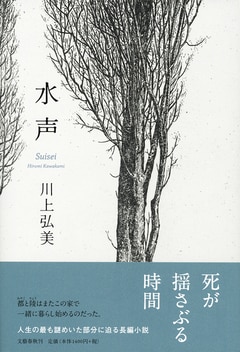十代の頃、いわゆるホームドラマが嫌いでした。
「嫌い」というとやや強い言い方になってしまいますが、否定的な感情を抱いていたのは事実。
当時の私はホラーやSF、ミステリーといったエンターテイメント要素の強い作品に夢中でした。不可解な謎を解き明かす名探偵の推理に興奮し、非日常な異形の世界にページをめくるのももどかしいほど魅了されました。
それに対し、家族とは私にとって大切な反面、面倒くさくてうっとうしい日常そのものでした。
物語の中ではどこにだって行けるのに、何にだってなれるのに、どうしてそこでまでわざわざつまらない現実に寄り添わなきゃいけないんだろう。そんなふうに思ってどこか敬遠していました。
異世界や現実離れした犯罪の出てくる小説は「そんなものを読んで」と眉をひそめられるのに、いじめや家族愛など日常生活におけるそうした題材を取り扱った作品は高尚なもののように薦められる傾向にも微かに反発を覚えていたのかもしれません。
大学生のとき、一人暮らしをしている先輩のアパートに遊びに行きました。
クイーンの国名シリーズについてとうとうと私に語っていた先輩が、ふと時計を目にして「あ、『サザエさん』観なきゃ」と呟きテレビのリモコンを手に取りました。
知的で大人びたイメージの先輩がその国民的アニメ番組を当り前のようにつけたことをやや意外に思っていると、彼女がはにかんで「なんか落ち着くっていうか。つい観ちゃわない?」と言い訳するような口調で言いました。
画面の中でカツオは終わらない夏休みの宿題と格闘し、サザエさんは財布を忘れて家に走る。登場人物は決して年を取らず、決定的な不幸は起こらない。変わらない家族の風景。それはなぜかひどく懐かしい感情を喚起しました。
先日、戦争で母親を亡くした幼い子供が、地面にチョークでお母さんの絵を描いてその上に横たわり眠る写真を見ました。
まるで母親に抱かれるかのように、胎児みたいに身体を丸めて。
拙いシンプルな点と線。誰が見てもただの絵だけれど、いま、この子にとってこれは絵じゃなくてお母さんなんだ。そう強く思いました。
愛情をかけてくれた祖父母が亡くなったとき、どちらの死に目にも会えませんでした。駆けつけたけれど、間に合わなかった。家族はいつまでもそのままの形でそこにいてはくれないんだな、とあらためて感じたこと。
いつも冷静で論理的な担当さんがお子さんの写真を見せてくれて、かわいいですね、と言ったら「はい!」とこちらが面食らうほど勢いよく即答したこと。「僕の子、世界一かわいいんです」って、無条件にまっすぐに。