《おれたちって、生まれてこのかたずっと、だだっぴろくて白っぽい野に投げだされているみたいだよね》
息をつめるように読み進めていたこの物語の中で、ふいにつぶやかれたこの一言が、一瞬すべてを真っ白にした。主人公の都の弟、陵が都に言った言葉である。この「白っぽい野」には、見覚えがある気がする。なにもない、白い場所に放り出された不安感と、なにもないからこその、豊かな感じ。それは、孤独という言葉が一番近いようで、大きく違うようにも思う。いずれにしても、繊細な感覚をつみ重ねた世界にふいに開ける、白くて明るい、さびしい野は、あらゆる人が共通して持っている感覚でもあるのではないかと思う。その存在に気付いているか、いないかの違いがあるだけで。
母と娘、母と息子、姉と弟、兄と妹、いとこ、伯父と姪、伯父と甥……といった、様々な血のつながりを持つ者同士の複雑な関わりが、長い年月を通じて描かれていく。その関係は、一見淡いようで、磁石が自然に引きあうようにその人の根本的な何かの力で引きあい、ときに濃密になる。その瞬間のあやうさと美しさに、震えた。
血の繋がりとはなんだろうか。家族とはなんだろうか。震えののちに胸に去来したのは、そうした素朴な問いだった。
東日本大震災ののち、家族が目の前で命を落とす経験をした多くの人の証言を背景に家族の絆が強調された。自分の家族を一番大事に思うことは、すばらしいことであると同時に当然のこと、という強制力が入ったようで、なんだか違和感があった。そのことを思い出しながら、この小説は、そうした強制的な家族像から逃れながらも強く意識しあう家族の、特異で不定形の愛情を新しく提示しようとしたのではないか、と考えた。
複雑で巨大な社会構造を作り出した人間だが、たった一人に立ち戻ってみると、やわらかくてもろく、死んだら二度と生き返ることのできない、とても不安な存在である。自分たちが不安な存在であることに気付いた、あるいは気付かされた人々が、小説の中で、その不安を共有し、確認し、あたため、味わい、ときに楽しんでいるようだった。
物語の時間は、現在五十代半ばとなった都の実人生におけるいくつかの時期と、都の母親である「ママ」の昔語りによって語られる想像の時間とが交錯しながら、立体的にからまる。
いろいろな人を惹きつけてしまう魅力的な「ママ」のことを、目の前にいるときも、いないときも、さらに死んでしまってからも《ママはとうに死んでしまったのに、まだわたしの中にいる。だから、わたしは一人でいても一人にはなれない。いつだって、ママはどこかにいてわたしを眺めている》と、都はずっと考え、思い続けている。
その心を追いながら、「インナーマザー」という言葉を思い出していた。強すぎるその影響力に苦しむアダルトチルドレンらの心の中に内在している母親像のことを示す心理学用語だが、都の場合は、心の中に常に「ママ」がいることで苦しんでいるわけではない。なにしろ「ママ」のことが大好きなのである。内なる母の存在は、多かれ少なかれ誰の心にもあるだろう。なんらかの事情で母親の記憶を持てなかった人も、想像上の母を心に住わせるという。生まれてきたことと、今生きていることの意味を、内なる母と対話することで得ているのではないだろうか。

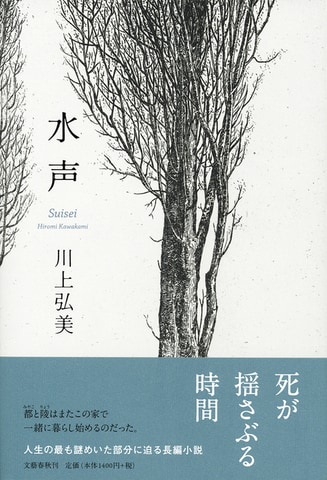
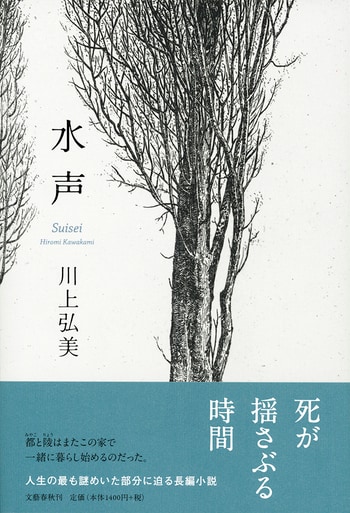

![[選者対談]小池真理子・川上弘美作家の全随筆を読んで見えてくるもの](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/9/9/480wm/img_99dfda8f29ff2d71bb2819048258a0de47962.jpg)












