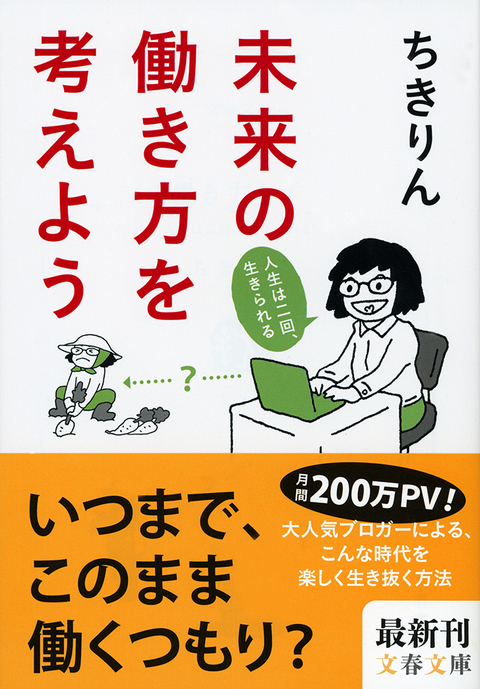
本書が単行本で出たときのことは、とても鮮明に覚えています。同じころに出した拙著と、問題意識や提言がかなり共通していたからです。その後、ちきりんさんとは、トークイベント等で直接お会いする機会もありました。その際、考えていることがとても似ていることを再認識して、意気投合。その後に出した私の新書では、帯の言葉まで書いて頂きました。
ちきりんさんといえば、あのイラストがすぐ思い浮かびます。実物のちきりんさんもイラスト通りの飾らない人柄と気配りのきいた話しぶりで、人をひきつける魅力にあふれた人です。その魅力はどこから来ているのだろうと考えてみると、やはりご本人が「楽しいことだけして暮らす」ことに徹しているからなんだろうなと思います。
その辺りのことは、本書を手に取られているちきりんファンの皆さんのほうが、きっとずっとお分かりなのだと思いますが、そういう潔さや清々しさみたいなものが、話しぶりやしぐさにも、そして本の語り口にも、にじみ出ている気がします。
そんな、ちきりんさんが、未来の働き方を真剣に考えたのが本書。IT化やグローバリゼーションなどによっておこる未来の変化を予測して、その激動の中で幸せに生きていくための働き方を提案しています。具体的には、職業人生を、前半、後半の2回に分けて考え、1度目は横並びの働き方しかできなかったとしても、40代からは自由でオリジナルな働き方に移行することを薦めています。
この将来予測と、それにどう対応していったらよいかという考え方が、私とちきりんさんとで、かなり共通していたのです。もちろん、二人の見ている視点はかなり違いました。ちきりんさんの場合は、個人の立場にたって、激変する社会をどう生き抜くかという問題意識から出発しています。一方、私のほうは、日本社会を何とか持続・発展させていくには、どんな仕組みが必要かという問題意識が出発点でした。にもかかわらず、その両方が、ほぼ同じ結論にたどり着いていたというのは、とても興味深いことだと思います。
本書が単行本で出版されてから、既に2年以上経過しています。この間の世の中の動きはとても速く、経済環境も大きく変化しました。けれども世の中は、ちきりんさんが本書で予想していた方向に確実に向っているようにみえます。ちきりんさんの将来を見通す目は確かだったのです。
この間起こった大きな動きとしては、人工知能の発達がマスコミ等で大きく報じられるようになって、コンピュータに仕事を奪われてしまうのではないか、という漠然とした不安感をもつ人が増えてきたことが挙げられます。
しかしそれは、本書の主題でもある、未来の働き方を自分で考えることの大切さが依然として、いや、当時よりもさらに重要度が増していることを意味しています。本書がますます世の中に必要になっているのです。
しかも、その「革命的変化」は“大きい”ばかりでなく、いまだかつてなく“速い”ことに、私自身は注目しています。大きい変化でもそれがゆっくりであれば、働き方にはそれほどのインパクトは与えなくてすみます。変化には、次の世代が対応してくれればよいからです。変化が速いとそういうわけにはいきません。一人のライフサイクルよりも速く技術が変わっていき、社会が変わっていくので、それに合わせて一人ひとりが大きく変化していく必要が出てくるからです。本書にも指摘されているように「一生ひとつの仕事が非現実的」になっていくのです。
現状を見ても、その兆候はあちこちに表れているように思います。大企業をみれば、一見、終身雇用が機能しているようにも見えます。しかし、有名な大企業ですら中高年を大リストラせざるを得ない時代になっています。これは、経営の失敗の結果という面もあるでしょうが、やはり時代の大きな波を受けた結果でもあります。今や残念ながら、どんな大企業であっても、リストラや倒産のリスクを抱えている時代です。それは、技術や産業の実態が大きく変化しているからです。
リストラには至らなくても、実質的に社内で仕事がない“社内失業者”も、全国で何百万人にも上っています。そういう人たちも、実は決してやる気がないわけではないのだと思います。会社を取り巻く環境が大きく変化してしまったために、自分の能力を生かす場所がその会社の中になくなってしまった場合がほとんどでしょう。これも、世の中が大きく変化した結果です。
とはいえ、能力を生かす場所がない、生きがいを感じて働ける場所がないというのは、個人にとっても会社にとっても、不幸なことです。そんな状態から抜け出して、もっと楽しく自分らしく働きませんか、というちきりんさんのメッセージが、だからこそ、とても大切になってくるのです。
一方では、働く期間はどんどん長期化しています。年金給付開始年齢は、このままいけば、70歳近くにしないと財政がもたなくなるのはほぼ確定でしょう。一方で、寿命は昔に比べて延びています。最近の私が関与している研究によれば、単に寿命が延びているだけではなくて、高齢者の体力は確実に伸びています。今の60代、70代は昔の60代、70代とは違うのです。元気に楽しく働ける期間は長くなっています。
70歳まで、同じ職場でやりたくもない仕事をお金のために続けるのか、それとも、自分の喜びとなるような、楽しくやる気のでる仕事をずっと打ち込んでいけるようにするか。どちらが良いかと聞かれれば、答えは火を見るよりも明らかでしょう。そして、どちらを選ぶかは、本書の後半部分でも書かれているように、人生後半で、自らのキャリアや仕事を見直すことができるかどうかにかかっています。
こんなことをいうと、「会社を辞められるのは、能力や経済力のある特別な人だけじゃないのか?」と言われることも多いです。でも、実はそんなことはないのです。ちきりんさんも書いている通り、そういう心配をする人は、一度も転職経験のない人がほとんどです。転職経験のある人は、外に出さえすれば、なんとかなることを経験的に知っているのです。
私個人としては、第二、第三の人生をより生き生きとしたベターなものにしたいなら、やはりある程度の能力開発は、いくつになっても必要ではないかと考えています。変化の速い世の中では、残念ながら、個人がもっているスキルが陳腐化しやすいのも事実です。専門学校で実践的な知識や新たな知識を身につけたりして、常にスキルをアップデートしておくことは、今後ますます重要になってくるでしょう。
社会の政策や制度といった側面を考えると、まだまだこのようなスキルアップが容易にできるような教育機関が少ないように感じます。大学といえば、若者が行くところと考えられていて、たとえば中高年の大学生や大学院生は、どこのキャンパスでもかなりの少数派でしょう。でも、世界的にみれば、中高年になって大学で学んでいる人はたくさんいるのです。
もちろん、日本でも社会人大学や生涯学習等の取組みがずいぶん進められていて、社会人が学ぶ機会は増えてきています。けれども、第2の人生のために新しい技能を身につけたり、スキルアップ実現のための知識を吸収したりできる教育プログラムはまだまだ不足しているように思うのです。大学でなくても専門学校でもどんな名前の教育機関でも良いのですが、中高年がきちんとスキルアップできるような場所がもっとあるべきですし、そのための政策を考える必要もあると考えています。
最近は、インターネットを通じたオンライン教育も盛んになりつつあります。これは時間のない社会人にとっては、大きな武器になる可能性をもっています。この面でも、技術の変化は世の中を大きく変えるかもしれません。
とはいえ、あまり難しく考える必要もないのです。転職に成功した人たちの事例をみていても、まったく新しいスキルを身につける必要があったというよりも、自分の能力を今いる会社だけでなく、新しい場所で生かせるように再整理するだけで、それがスキルアップになり、大きな武器になったケースは多いです。
結局のところ、大事なのは、企業に与えられるままに働き方、生き方を選ぶのではなく、自分で主体的にキャリアを設計し、スキルを獲得していくことでしょう。そして、それこそが本書の大きな主題であり、そのための実践的なステップがふんだんに書かれているのです。
本書を読んで実際に、40代で新しい働き方・生き方に移行する人が増えてくれば、日本経済もきっと大きく変化すると思うのです。40代以降の人たちがもっと生き生きと働くことができれば、経済全体の生産性もあがり、今よりもさらに経済が活性化することでしょう。
本書の内容を実践することで、いやいや働かされるのではなく、自分がやりたいと思うことができる人が沢山現れてほしいと思っています。そうすれば、より明るい働き方ができる人が世の中に増えてくることでしょう。そう、ちきりんさんのように。


















