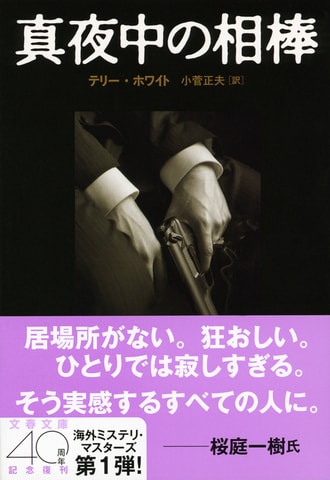ああ、いい小説だなあと率直に思った。三十年ぶりの再読であるが、三十年前に読んだときよりも印象が深い。こんなにいい小説だったのかとさえ思った。
三十年前、本書が上梓されたとき、女性作家が書いたハードボイルドとしてかなりの話題をよび、当時ミステリ・ベストテンでも上位に入ったし、一九八〇年以降の名作ガイドの決定版『ミステリ・ベスト201』(瀬戸川猛資編、新書館)でもとりあげられたし、いまだに多くの人が熱い思いで語る作品なのだが(そのわりに品切れが続いていて今回の復刊の運びとなったのだが)、個人的なことをいうなら、三十年前、この同性愛的な雰囲気の強い作品にやや距離を覚えたのも事実である。海外ミステリ史的にはゲイ・ミステリの走りとして、九〇年代以降にどっと出てくる本格的な(つまり同性愛をカミングアウトした主人公たちの)ゲイ・ミステリの先鞭をつけた作品であり、現在から見ればいささか描写が淡いかもしれないけれど、それでも三十年前は、この男同士の会話にしろ、仕種にしろ、ずいぶん濃いイメージがあり、それで多少の戸惑いを覚えたのである。
しかしどうだろう。いま、くもりなく自然に読めば、違う景色が見えてくるのではないか。作者が同性愛的な文脈を巧みに作り上げていることは事実だが、はたしてどこまでゲイ・ミステリを意識したかはわからない。作者が描きたいのが同性愛ではなく、もちろん異性愛でもなく、むしろ同性愛・異性愛を超えた愛であることは、予想もしない結末を見ればわかるだろう。人を精神的に愛することとは何なのか、庇護すべきものは何なのか、僕らがいま生きている現代社会において、精神の脆い者たちを守り、ともに生きるとは何なのかをとことん追求している。だからこそいつまでも語り継がれているのである。
さて、物語を紹介しよう。まず、プロローグから読者を引きつける。
その殺しの仕事はいつもと変わらないはずだった。マックの運転する車からジョニーが降りてビルに侵入し、数分後、標的を仕留めて帰って来た。だが、様子が違っていた。部屋には組織を牛耳る男しかいないはずだったが、もう一人いて、その男も殺してきたという。組織の男ならたいして問題はなかった。しかしそうではなかった。
マックとジョニーは、ヴェトナムの戦場で出会った。住民を虐殺した村のなかで、ひとり虚脱した青年兵のジョニーがいた。精神を病み、だれかそばにいないと生きていけないほどだった。マックはジョニーの面倒を見、除隊したあとも、ニューヨークで一緒に生活をはじめるが、窮乏から殺し屋稼業に乗り出す。マックが仕事をとり、ジョニーが殺す役割だった。腕利きの評判を勝ち得ていたが、招かざる客を射殺して運命が変わる。
射殺事件を捜査するのは、刑事のサイモンだった。サイモンは事件に入れ込み、家族をかえりみなくなり、ひたすら顔の見えない殺し屋を追い求めていく。
物語は三部構成で、第一部はマックとジョニーと殺し屋稼業、第二部は殺人事件捜査にのめりこむサイモン、第三部は追う者と追われる者の対決が描かれる。一九八三年のアメリカ探偵作家クラブ賞最優秀ペイパーバック賞を受賞した作品であるが、意外と普通小説的な拡がりがある。ペイパーバック・オリジナルは娯楽色が強いものだが、作者は丹念にヴェトナムの戦場を描き、サイモンの妄執に近い捜査と壊れていく家庭生活を綴る。テリー・ホワイトがいいのは、何よりも繊細な感覚と、それを捉える文章である。
たとえば、冒頭の戦場の場面で、マックが“目を覚ましたときはあたりは真っ暗だった。淡い月の光はあまりにも脆すぎて、彼らを包んでる闇を貫き通せないかのようだ”(二九頁)と、出会ってすぐのもどかしく不安定な心理を月の光に託して見事に描いている。無垢で純粋なジョニーは青色を好み、車もブルーのを買うのだが、その青ははじめから使われていたのだし、二人の関係が安定した第三部の冒頭では、ジョニーの視点から“月の光を浴びた静けさのなかに坐り、マックが眠るのを見つめ、夜の闇が褥のように自分たちをくるむのに任せることに満足していた”(三四八頁)と表現する。
この描写を見てもわかるが、数はすくないものの、気取りなく自然に風景を描き、そこに心情を投影させている。この自然との感応は、四季が豊かで、短詩型の長い伝統のある日本文学の得意とするところであるが、テリー・ホワイトも、たんたんとたくまずに感情をうたいあげている(だからこそ日本人の読者にうけるのだろう)。その感情は、いうまでもなく、同性に対するシンパシーであり、精神的な愛である。
作品が発表された時代はまだ同性愛に対する忌避感は少なからずあった。古典的なハードボイルド探偵に対抗して、一九七〇年代には新ハードボイルド探偵が続々生まれて、そのなかにはジョゼフ・ハンセンのゲイの保険調査員デイヴ・ブランドステッターもいたけれど、正面から同性愛を描くことよりもゲイの探偵が事件を調査するというニュアンスが強かった。それだけでも充分にセンセーショナルな出来事であったのだが。
そういう時代的な制約のなかで、いかにして同性愛的な繋がりを描くのかという戦略が、作者のなかにあっただろうと思う。たとえばマックもサイモンも、女性と積極的に性的な関係をもつけれど、その最中に去来するのはジョニーである。性的な対象としてではなく、心にひっかかる存在としてジョニーを思い出しているのだが、性的昂奮のなかで同性の存在を喚起させる点には意味があるし、それに関してマックが決定的な問いかけをして己が欲望のありかをまさぐる場面もある。
ただ矛盾するようだが、作者が同性愛の文脈を作りあげていることは事実としても、前述したように作者の狙いはもっと広い無償の愛にあるだろう。マックとジョニーが出会ったころ、マック(本名アレグザンダー・マッカーシー)は三十五歳で、ジョニー(本名ジョン・ポール・グリフィス)は二十七歳。八歳しか違わないのに、兄と弟というより父と息子のような関係である。小説ではその六年間が描かれるのだが、読んでいくうちにマックの母親が精神病院で亡くなったことが語られ、精神障害を疑われるジョニーを病院送りにすることを拒絶する理由もわかってくる。意外に華々しいジョニーのハイスクール時代のことも語られて、逆に戦争で傷ついたジョニーが痛々しく見えてくる。
ジョニーがささいなことで警察につかまったとき、被害を訴えた男に向かって隣室に住む老女が、ジョニーは“あんたのために戦っていた兵隊さんだったんだよ。戦争にいって頭が少し病気になったからって、あの子が悪いのかい?”(九二頁)といい、マックも“適当に戦争をやり過すことのできる人間もいます。できない人間もいる。ジョニーは不向きだったんです”(九四頁)と弁護する。悲惨きわまりないヴェトナム戦争での後遺症、それはアメリカ人ひとりひとりの罪と悔恨と許しを求めるものであるが、この避けがたい人の精神を破壊する出来事は、東日本大震災を体験した日本人にも近しいだろう。未曾有の悲劇を経験して心を深く閉ざしたジョニーは決して他人ではないのである。