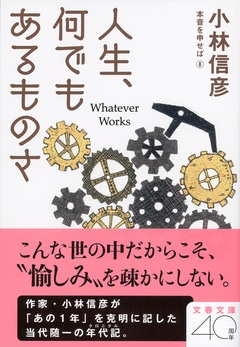一例を挙げよう。
《あいかわらず、〈悩ましい〉というコトバが、ふしぎな使われ方をしている》
《スラングがスラングであるうちはいいのだが、最近〈がっつり〉という俗語(スラング)が出てきて、テレビでは番組のタイトルにしている》(ともに『気になる日本語 1』)
という指摘につづけて、小林さんは嫌な言葉をいくつか俎上に載せる。《なにげに》とか《カミングアウトする》とか《こだわる》とか《ひもとく》とかいった、妙に若ぶった言葉や、語釈を勝手にねじ曲げた言葉だ。
私もこの手の言葉を嫌う。小林さんの尻馬に乗っていわせていただくと、「ハンパない」とか「ぼく的に」とかいった類いの言葉も背筋がぞっとする。「なにげなく」とか「半端じゃない」とか、本来の形をほんのちょっと端折るだけで時代の先端を行く気分になれる、という浅薄さが私には耐えがたい。いつかも地下鉄のなかで、表参道を「オモサン」と略称しているOLを見かけて苦笑したことがあったが、要するに「気になる日本語」とは「ダサい日本語」なのだ。言葉をケチるなよ、変なところで。
ただ、急いで付け加えておきたいことがある。
小林信彦さんは、この本のなかで「言葉の憲兵」を演じたりはしていない。慨嘆することや顰蹙することはあっても、指弾とか摘発とかいった野暮で粗暴な行為は、小林さんとは無縁なのだ。むしろ、小林さんはわれとわが身を振り返って苦笑することさえある。たとえば、こんな一節。
《スラングを使うくせが、若いころにあった。二十代から三十代にかけてである。今にして思えば、つまらないことなのだが。(改行)一九六〇年代――三十代なかばのことだ。(改行)某社の非常にすぐれた編集者(純文学の)と話をしていて、(改行)「そいつはヤバいですね」と言ってしまった。(改行)はっとすると、相手は困ったような苦笑するような目をしている。(改行)〈ヤバい〉は犯罪者の隠語である。(中略)無意識に、ではなく、わざとそういうスラングを使うくせがあることを、ひどく恥じた》(『気になる日本語 2』)
しまった、やっちゃったか――そのときの小林さんの表情を想像すると、思わず頬がゆるむ。大島渚監督『白昼の通り魔』(一九六六)に出演していた小林信彦をご覧になった方ならお気づきだろうが、当時の小林さんには、石部金吉とは正反対の、見るからにすばしっこい町っ子の印象があった(映画のなかでは佐久の中学校の教師役だったはずだが)。そう、喩えていうなら、よく切れる飛び出しナイフ。遊び好きで、冗談好きで、どこかクレイジーで、いっそ道楽者といってよいくらいの旺盛な好奇心の持ち主。
その好奇心が、役者の技芸を見きわめる眼に結びつく。世評にとらわれない眼。食わず嫌いに従わない眼。隅々まで行き届く眼。急所を射抜く眼。