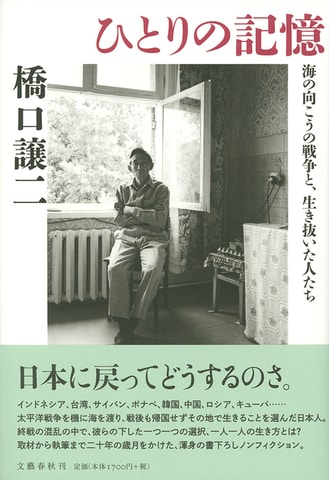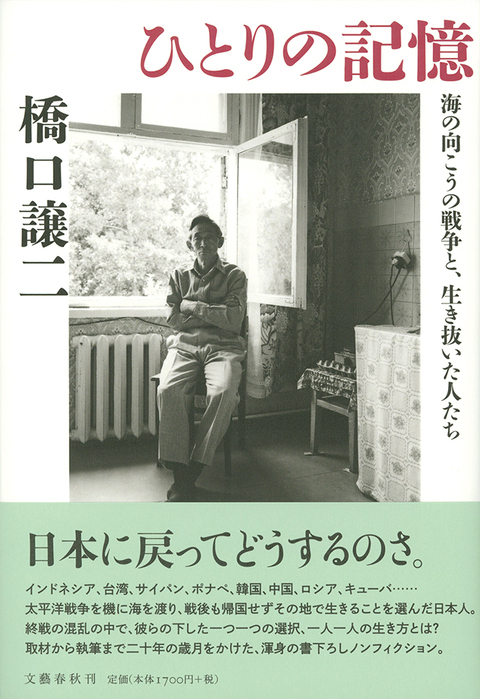自分の人生をふり返っているこの十人もまた、わからないのだ。あれが岐路だったと思い出すことはできる、でも、ではなぜこちらに一歩踏み出したのかは、足を踏み出した彼ら自身にもわからない。つまりそれは、人生の終焉の見えはじめた自分が、なぜ、今ここにいるのかわからない、ということだ。こう気づいて、私は動揺するほどの衝撃を受けた。そして納得した。ここに描かれる「わからなさ」こそが、私の知りたかったものの正体だ。

今朝の朝食 コーヒー一杯
今現在、私たちの多くは、自分の人生は自分で決められると思っている。なんでも思うままになる、という意味ではない、ままならぬ人生でも、人生は自分の手中にあると信じている。だから私たちはごくふつうに、しあわせになると言う。夢をあきらめないと言う。がんばれば報われると言う。けれど七十年前に、そんなふうに考えていた人がいただろうか。それを私たちはすぐに戦争のせいだと片づけてしまうが、戦前はどうか。そのもっと前は。この本に登場する人たちは、みな、人生を自分のものだとは思っていない。まして国家や天皇のものでもない。天候のように、季節のように、身をゆだねるしかない、従うしかないもののようにとらえている。だからわからない。岐路と思える場所で、彼らはみずからの意志で選択をしていないから。そのように人生をとらえていないから。彼らそれぞれの壮絶な人生を、なぜ引き受けて今ここに在るのか、彼ら自身にもわからないのに違いない。それは決して絶望ではない。ひとつの真実だ。
ときどき彼らは、きれいごとに聞こえかねないことをごく自然に口にする。だれか他人のために生きる、とか、他人(日本)に迷惑をかけられない、といったことだ。それは戦争教育のせいだと思いがちだけれど、人生が自分のものではないからこそ、出てくる考えではないだろうか。あまりにも巨大で凶悪な「戦争」のせいで、見えなくなっているものを、この作品はそんなふうに垣間見せてくれる。
そして私は静かに思う。人生が自分のものであるという今の私たちの考えは、あたらしいというよりはめずらしい、少々いびつなものなのではないか。
他人の家に居候している八十六歳の男性。所持金が二万円に満たない八十五歳の男性。日本の写真で部屋を埋め尽くしている七十一歳の男性。文字だけでこうして書けば、彼らの人生は紛れもない戦争の犠牲であり、絶望的で、悲痛だ。けれども私にはどうしても彼らが不幸だと思えない。というよりも、このなかに登場するだれも彼も、幸福だとか、不幸だとか、私には思えない。彼らの人生はそんな分類を超越している。人生というものが、彼らの手中におさまるようなちいさなものでないのと同様、幸福や、不幸なんて概念は、その人生の前になんの意味もなさない。まっすぐこちらを向いた写真のなかの姿を見て、私はそう確信するのである。