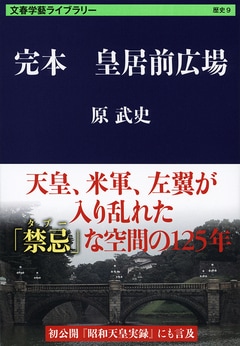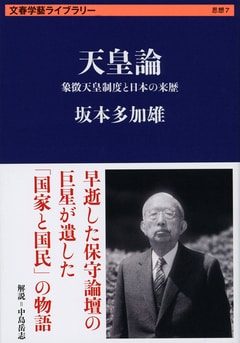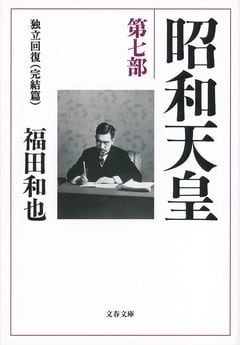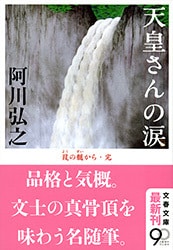『昭和天皇実録』が各メディアによって一斉に公開されたのは、二〇一四年九月九日のことである。前月の八月二十二日、宮内記者会には、その全体を収めた電子記録のチップが渡されていて、記者たちはそれを読みつつ、どのような形で紹介するかを考えていた。
たまたま私は幾つかの社からその解析を頼まれていたので、『実録』の全体図を早めに読む機会が与えられた。一読しての率直な感想をいうなら、次の二点を強く意識することになった。第一は、宮内庁書陵部が編んだだけあって、さすがに多くの史料・資料が使われているという驚きであった。天皇側近が公務として日々書きこむ記録、文書がふんだんに使われているので、「民(アカデミズムやジャーナリズム)」の描いてきた昭和天皇像とは異なるとの実感である。もとより、「官(国)」が描く天皇像が「民」と同じということはありえない。昭和天皇の姿を「国家」といった枠組みで捉える以上、そこに憶測や推量を持ち込むわけにはいかないからだ。
その点で、この『実録』は抑制が効いているし、相応の配慮をしていることは否めない。
第二は、奇妙な表現になるが、「昭和天皇は生きている」との感がしてならなかったという点だ。この『実録』のさりげない描写や行間から、昭和天皇の息づかいや生身の肉声が聞こえてくるように思えた。宮内庁書陵部の発表によれば、『実録』は、「平成二年度より書陵部編修課において編修を開始。同二十五年度に編修を終了」という経緯を辿った。編修課には、「宮内庁組織令の第21条に編修課所掌事務として『天皇及び皇族の実録の編修に関すること』」との役割があった。
その役割に沿って二十四年以上にわたり、この『実録』の編纂に勤めてきたということである。その時間と密度が、全体で一万二千頁という中に凝縮されているように思う。
「昭和天皇は生きている」との実感は、太平洋戦争の開戦に至るプロセス、敗戦にまでの終戦工作、アメリカを中心とする連合国の占領支配などを通じて、昭和天皇の〈歴史に向き合う姿〉から得られる。そういう姿を確認するたびに、天皇が自らの時代を超えて教訓や智恵を日本国民に伝えているように思う。私たちは、書陵部の執筆者との間で、「昭和天皇は生きている」との感情を共有することが大切ではないか。
『実録』から感じた二つの視点をもとに、私は半藤一利氏、御厨貴氏、そして磯田道史氏らと談を交わす機会を得た。いずれも深く読みこなしているために、改めて私は知識を得たのだが、とくに痛感したのはこの『実録』が、これまで編まれた『明治天皇紀』や『大正天皇実録』とは異なり、口語体で書かれているうえに、用いる史料も一般の雑誌も参考にしているために、解釈する側にも狭隘な権威主義とは一線を劃する幅広い人間性が必要だという意味になる。
三氏はそのような人間性をもってアカデミズムに、あるいはジャーナリズムに地歩を築いている。本書では、それぞれの視点で『実録』の読み方を披瀝している。私は三氏に遅れまいと、私なりの意見を語ったのだが、本書は現段階で『実録』が読まれる立場を各人が代弁しているように思う。その点を汲みとっていただければ四人に満足感はあると思う。
あえてつけ加えておきたいのだが、昭和天皇の在位期間(昭和元年十二月二十五日から昭和六十四年一月七日)は、六十二年と二週間に及び、西暦では一九二六年から一九八九年までとなる。国内にあっての六十二年と二週間という在位年数は、歴代天皇の中でももっとも長い。この間には、人類が体験した歴史的事件・事象(戦争、占領、敗戦、革命騒動、餓えから飽食まで)が詰まっている。その時代に存在した昭和天皇は、ときに国の主権者として、ときに象徴としての役割が課せられた。
このような時代にあって、天皇は主体的にどのような君主であろうとしたのか、が最大の関心事である。
昭和天皇の在位期間は二十世紀の三分の二弱を占める。二十世紀には、科学技術の異様な進歩、市民の誕生、ナショナリズムの昂揚など幾つかのベクトルを想定することができる。こういうベクトルの中で、日本はどう位置づけられるのか、そこで昭和天皇はどのような君主だったのか、が問われることになるだろう。あるいは他国からはどう見られていたか。そのこともまた、国際社会で確かめられるであろう。
私たちは、国の内外で問われる昭和天皇像について、同時代史の中から答えをつくりだす必要がある。そのことが歴史的責務でもある。もしその労を惜しんだなら、次代の人たちから、私たちは〈歴史感覚欠如の時代の人なり〉と謗(そし)られるだろう。もとより「民(アカデミズムやジャーナリズム)」の側の書はあるにしても、第一級の史料は公開されていないがゆえの限界もあった。
今回の『実録』について、私は、五十年、百年、あるいは二百年先の世代の人たちに、この時代の役割を果たしたとの感想を持っている。「官(国)」の側が可能な限り史料を用いて編纂したという意味では、この時代の総力がこめられていることにもなる。歴史的責任を果たしたとの思いを、同時代人としても味わうことができたが、肩の荷がおりたという人も多いのではないか。大仰な言い方になるが、読み解いていった私たちにも同じような思いがあり、その点を理解していただければと思う。
本書は、『実録』の公開にあたり、「文藝春秋」(二〇一四年十月号)での鼎談(半藤一利氏、磯田道史氏、保阪正康)、さらに続編としての同誌(同年十一月号)での鼎談(半藤一利氏、御厨貴氏、保阪正康)に加えて、半藤一利氏と私の対談(その一部は「文藝春秋SPECIAL」二〇一五年季刊冬号に収録)を収めている。誰もが歴史的記録に触れることができたことを喜んでいたと付記しておきたい。
(本書「おわりに」より抜粋)