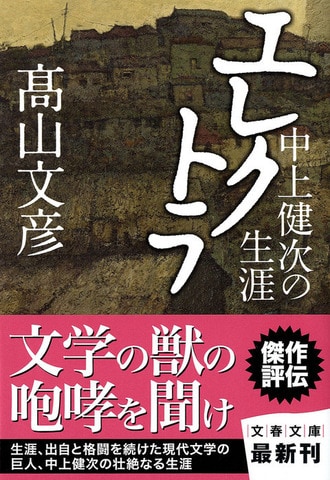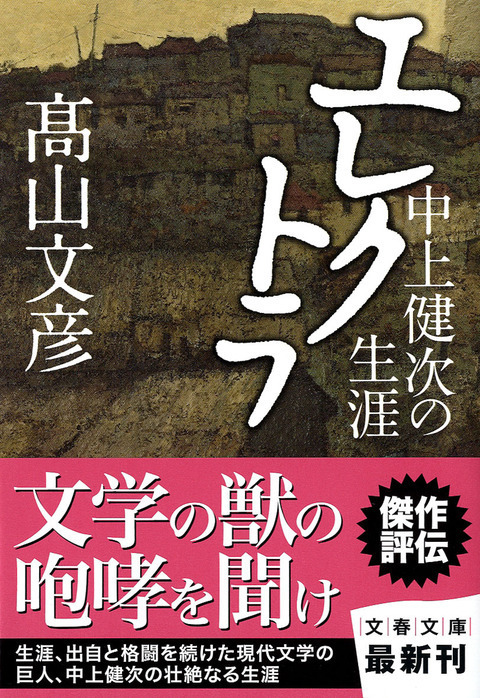これほどものを書きたいと飢えた子のように渇望する人間を、私は知らなかった。彼の生まれた被差別部落、私生児としての生い立ち、複雑な家庭環境、自殺する兄、君臨する女王蜂のような母。陽炎のようにゆらめき騒ぐ実父。彼は「父殺し」「母殺し」という文学上の重大なテーマを、生まれながらにその身をもって経験してきた人であった。
これを書かなければ生きていけないというほどのいくつもの物語の束をその血のなかに受けとめて作家になった者がどれほどいるだろうか。
今年五月、ソウルの画廊で一枚の絵に出会った。それは「タルトンネ」と呼ばれる、かつて市内の丘という丘にその頂までびっしりと軒を連ねていた貧しい集落を描いたものだ。子供らの遊ぶ声が聞こえてくるようだった。白菜を刻みながら昔語りをするアジュマ(おばさん)やオモニ(お母さん)たちの声も。
私は金正浩(キムジヨンホ)という画家のアトリエを訪ね、何作か見せてもらった。どれもタルトンネを描いたものだったが、そのなかの一枚に胸を射抜かれてしまった。丘の下から見上げるタルトンネだった。油絵ではなくて、廃材を張ってつくった板面に、セメントの粉やコーヒーの粉を塗りつけてざらざらした質感を出している。
一軒一軒小さな家が頂上までひしめいている。それはたしかに一軒ごと丁寧に描かれているが、全体を見渡すとひと山が城のようで、私は金正浩に「貧者の王宮」と言った。ガルシア・マルケスの『族長の秋』の宮殿も、このようではないかと思われた。エレクトラの宮殿も、このようではないかと思われた。
なんという巡り合わせだろう。中上の路地は、とうに消滅してしまった。タルトンネもいまや高層アパート群にとって代わられている。しかし、まさしくいま自分が目のあたりにしているのは、息をし、ドクドクと脈を打っている物語の王宮なのだ。
初校ゲラと向き合っているとき、このような絵に出会ったことは、天の導きとしか考えられなかった。私は金正浩にお願いして、装画に使わせてもらうことにした。緒方修一がすばらしい装幀をしてくれた。
ずいぶんながくかかったが、ひとつの作品を世に送り出すためには、その作品が帯びた運命を無視しては良いものは生まれないようだ。
読者のこころにこの新作の主題が届いてほしいと、いまは願うばかりだ。