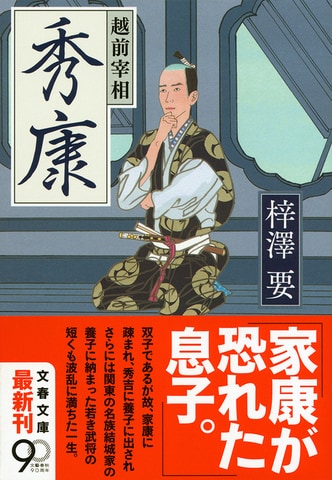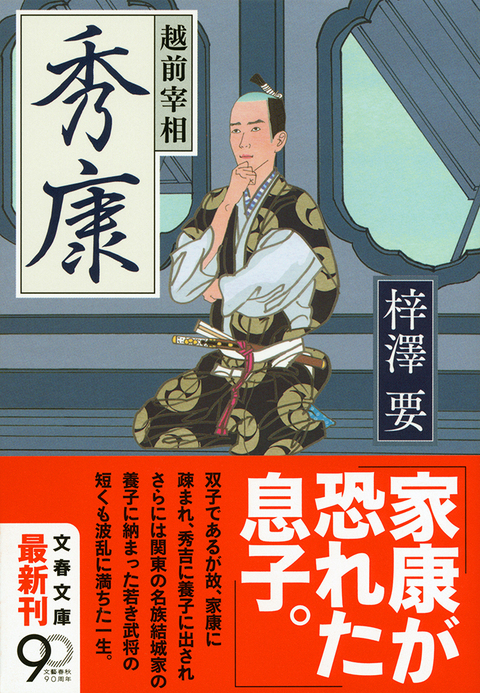「武家の高野。男たちの新天地」。それを、秀康は越前に樹立しようとした。それが、三十四歳で死んだ秀康の最後の願いだった。彼はそこまで、自分自身を高めることができた。六分の一の存在からスタートした秀康は、一でも二でもなく、無限大でもない、数字を超越した世界観と人間観に到達した。それが、永遠に昇華したということである。
人間には、有限な命しかない。だが人間の認識次第で、死すべき人間も、ここまで無限へと到達できる。終章が「滅びざるもの」と名づけられたのは、まことに感慨深い。ここにおいて、秀康は、叙事詩の主人公としての悲劇を全うしたのである。
ところで、秀康の世界認識と人間認識は、どのようにして鍛えられていったのだろうか。彼の幸運は、二人の天下人を「父」に持ったことである。アイデンティティの分裂という点では不幸だが、人間を見る目を鍛えることができた点では幸福だった。
歴史の激流の中でもがき苦しむ秀康は、天下人たちに対する人間観が深まってゆく。人間を見る眼の確かさは、歴史を客観的に俯瞰する歴史観の深化につながる。 たとえば、第七章「北の関ヶ原」。秀康は、石田三成という人物と身近に接する機会があった。
《そう考えると、秀康はまだ自分が若いがゆえに見えていない三成の真の姿、真の価値があるのではないかという気がする。それが何なのか、見極めたい気持と、懼(おそ)れと、その両方が秀康の中でせめぎあっている。》
三成の真実を見極める眼を持つことができれば、父である家康の真実も、家康と確執がある自分自身の真実も、はっきりと見えてくる。その時、人間たちを操って歴史を作り出そうとする「天」の正体が、明瞭に見えてくる。
関ヶ原の決戦の前夜、秀康は北関東に残って、会津の上杉氏の動きを押さえ込んだ。東軍勝利の報を宇都宮で聞いた秀康は、「そうか。天は、父上を選ばれたか」とつぶやいた。
秀康は、石田三成の人間性を知っている。また、自分が対峙した敵である上杉景勝と直江兼続の人間性も高く評価している。しかるに、自分を愛さず、自分も愛せない父の家康の方が、天から愛されたのはなぜなのか。人間として家康よりも上の三成・景勝・兼続が、天から愛されなかったのはなぜか。秀康の悩みは、深い。
だが、天と人間との永遠の相剋という悩みを解決する力は、三十四歳で死去した秀康本人にはない。彼を暖かく包み込んできた母や妻たちにもない。彼らの生と死を叙事詩として織り成してきた作者にさえもない。
だからこそ叙事詩は、国民の共有財産である。苦悩も救済も読者の側に委ねられた。さらには、現在の読者だけでなく、次の世代の読者にも手渡される。それが、読み継がれる叙事詩としての歴史小説の真価である。秀康の無念と、彼の澄み切った祈りは、こうして長く語り継がれゆく。