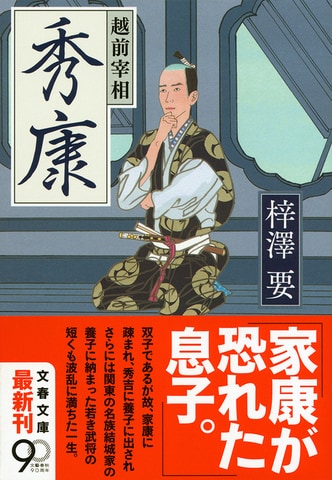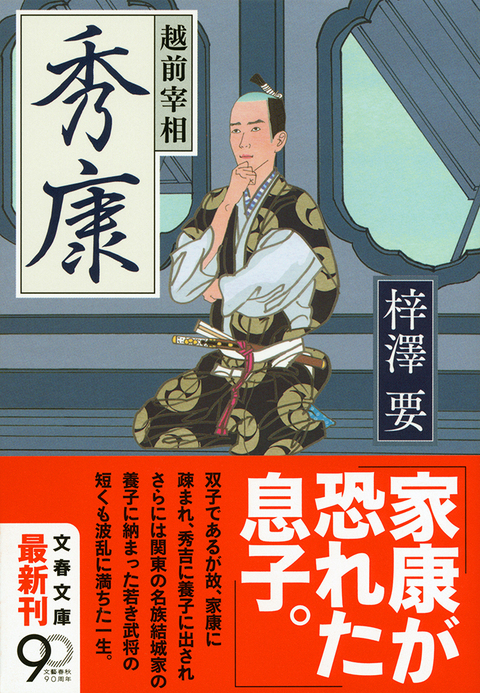梓澤要は、この『越前宰相秀康』で、歴史小説の沃野に、新しい道を切り拓くことに成功したのではないか。そう思わせるほどに本格的で、読みごたえのある小説である。
序章「高野の石廟」は、作者が結城秀康の母親である「お万」の心の中へ入り込むための儀式を描いている。シャーマンは、梓弓に、呼び出した死者の霊を宿らせるという。梓澤要は、自らの文章の中に歴史上の人物の魂を呼び出し、語らせる。そして、終章「滅びざるもの」で、歴史の真実を語り終えた霊は去る。作者も、梓弓としてのペンを置いて、「お万」の心から出る。そして、現代の日常世界へと戻ってくる。
作者は、母親の視点から、結城秀康という男の心の中をのぞき込もうとする。類い稀な苦しみを経験し、若くして死んだ秀康の人生には、どんな「生きる意味」があったというのか。そして秀康は、「秀康」に生まれなければ、どのような人生が生きられたのか。
母の視点は、妻の視点とも重なる。秀康の妻の鶴子も、側室のおゆきも、母のお万に似て、強い女性である。ひたぶるに生きる女たちの力が、どんなに秀康の心を癒してくれたことか。「妹(いも)の力」を感じさせる彼女たちは、まさに「水の女」である。
これまでも梓澤要は、女性に視点を据えて歴史を語ることに、定評があった。だが『越前宰相秀康』は、単なる「女性の視点」ではない。なぜならば、全編が女性である語り手の一人語りではないからである。苦しみ続ける男性主人公の一生を、強い女性が暖かく包み込んでいる、という関係なのだ。
男の命を女が包み込んでいることを、女が書く。この時、女性作者は、男を愛する女の心だけでなく、女に包み込まれている男の心の中へも入り込んでいる。女と男の異なる目と心が、一つに溶け合う。そして、男でもなければ女でもない、「人間」という存在の素裸の本質が見届けられる。たとえて言えば、女たちの愛に包まれた光源氏という男の一生を、女性作者である紫式部が書き記したのと同じなのだ。
男と女が攪拌され、「人間」そのものの真実を写し取る小説。そのためには、男性の強さと、女性の優しさとを合わせ持つ、独自の文体が必要である。この小説を読み進める読者は、梓澤要の文体に最初は突き放したような冷たさを感じるかもしれない。けれども、読み終わる頃には、作者の大いなる愛を実感することができよう。この小説の読みどころの一つは、文体そのものなのである。