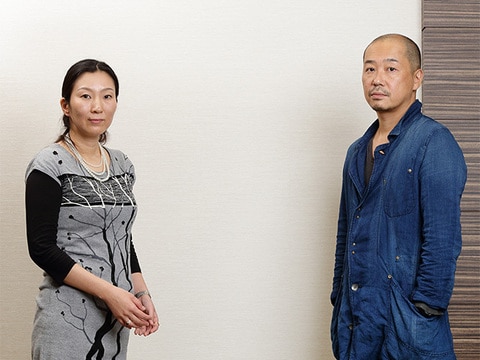――新刊『まほろ駅前狂騒曲』は、直木賞を受賞した『まほろ駅前多田便利軒』、そして『まほろ駅前番外地』に続くシリーズ3作目です。続編は最初から考えていたのですか?
三浦 いえ、1作目の『便利軒』を書いた時は、シリーズ化はあまり考えていませんでした。2作目の『まほろ駅前番外地』を書いているときに「週刊文春」連載のお話を頂いたので、次作につながる伏線を『番外地』の中で張るよう意識しました。週刊誌連載では毎回締切ぎりぎりになってしまって、本当に大変でした。でも折角の週刊誌なんだから、原稿のストックを作るより、毎週書いたほうがいいと思ったんです。そうじゃないと月刊誌に書くのと同じになってしまいますから。次がどうなるか自分でもわからないまま書くのもいいんじゃないかと思ってやってみたんですが、辛かったですね(笑)。
――今回は、多田が4歳の女の子、実は行天の実の娘「はる」を預かることになります。多田は子供を亡くした過去があり、行天も理由は明かされていませんが、子供を大の苦手としている。この2人と「はる」が一緒にいてはたして大丈夫なのか、はらはらしました。
三浦 私も3人の関係がどうなるかわからないまま書いていました。でも一作目の『多田便利軒』で、多田は自分で自分の心に、ある意味救済のような落とし前をつけています。じゃあ行天にとって、自分の心と向き合えたと思えることは何なのか――それは苦手な子供とうまく向き合えたときなんじゃないかと思ったんです。遺伝子的にも自分の娘である「はる」と行天がちゃんと向き合えるように今回「はる」を登場させたのですが、結果的にこのような展開になりました。
――「はる」と行天が2人だけで向き合う一方で、多田が新しい恋に踏み出す、ある夜のシーンがあります。それぞれの新しい関係の始まりが対照的に描かれ、とても感動的でした。
三浦 多田がちょっといい気になって朝帰りをするシーンですね(笑)。あのシーンは特に意識的にパラレルに描こうとしたわけではなくて、多田が新しい人間関係に踏み出せるのか、行天が子供時代の心の傷を克服できるのか、と考えながら書いてきたことの偶然の結果です。
――子供といえば、後半から登場する小学6年生の松原裕弥も重要ですね。彼はある活動に夢中な母親に従うしかない状況に、とても複雑な思いを抱いています。
三浦 裕弥はダークサイドに落ちるかどうかの瀬戸際にいます。落ちてしまえば、行天のように傷を抱えながら生きていかなければならない。行天は自分と同じ轍を踏まないよう裕弥を導きますが、おそらくあり得たかもしれない自分の姿を、まだ子供の裕弥に見たのだと思います。一度つらい出来事が起こってしまったら、その傷は消すことはできない。けれど既に傷を抱えて生きている人間は、これから傷を負ってしまいそうな他者に対して、「進む方向はそっちじゃないと思うんだよね」と言うことができる。それが行天の今回の役割だったと思います。意識していないでしょうが、裕弥が救われることによって、行天も救われたのではないでしょうか。
――今回は横浜中央交通(横中)の「バスの間引き運転」に固執する岡老人が抗議のバスジャックを起こします。これにより生ずる人間関係の変化が、物語全体を加速させますね。
三浦 岡さんは1作目から横中への不信感をあからさまにしています。ならば横中の言い分も聞いてやらないといけない、とずっと思っていて、今回ようやくそのことを含め書くことができました。バス絡みの映画『スピード』のようなものが書ければよかったんですけど、無理でした(笑)。書けていたら今頃、ハリウッド映画の売れっ子脚本家になってます(笑)。
――第1作から共通しますが、物語の中では単純に「家族」「友達」という言葉で言い表せない、いろいろな人間関係が示されています。だからこそこの物語は老若男女を問わず、様々な視点から読めるようになっているのではないでしょうか。
三浦 世の中には「家族」や「友達」のような言葉では絶対に言い表せない人間関係が無数に存在していると思うんですよ。言葉からこぼれおちるものが、必ずある。少なくとも私にはそう見える。でも言葉がないがゆえに、ひとつとして同じではない人間関係が、安心できるすでにある言葉に簡単にあてはめられてしまう。本当は存在しているけれど、まだ命名されていない無数の関係性、それを物語の中で描いてみたいと思っています。命名されていないものを言葉で定義するのではなく、「炙りだす」には、物語はとても適した方法だと思います。
――本作はシリーズ中、最も長い作品となりました。
三浦 本当に連載中は大変でした。24時間常に多田や行天と一緒にいるという感じでした。だから自分で書いていて2人の動きに驚かされることがありました。「こんなことするのか!」と(笑)。物語が終わっても多田や行天たちは相変わらずの調子でまほろで暮らしています。彼らのこれからを想像して頂けたら、作者としてとてもうれしいですね。