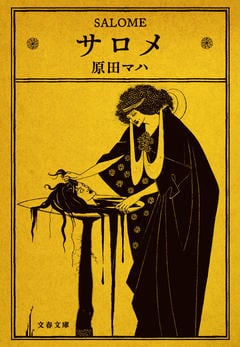※書籍刊行時の記事(2008/12/20公開)です。
長いあいだ書きたかった物語をようやく書き上げた。
作家になって三年足らずだが、六年まえ、会社を辞めてフリーランスの身になってからずっと、心の中で「いつかこのことを書く」と決めていた。「このこと」というのは、自分が当時抱えていた家族の問題、そして会社を理由あって辞職したこと。ただし、その頃、作家になるという意志が特にあったわけではない。それなのに「書く」と決めていたのだから、考えてみると、この物語の礎(いしずえ)になった家族と自分の体験こそが、私を文章の道へと導いてくれたようにも思う。
そんなわけで、この物語は限りなく私小説に近い。もっと細かく言うと、導入部から三分の一はほぼ自分の体験に基づいて描いている。けれど、残りの三分の二は完全なファンタジーだ。「私の人生も、こんなことになればいいな」という、夢を託した感もある。正確に言えば、「私の人生」というよりは、「私の父の人生」に、こんなあたたかい奇跡が起きればいい、という願いをこめた。
『キネマの神様』は、神に見放されたささやかな家族が主人公だ。「後期高齢者」になっても、ギャンブル依存症で借金を繰り返し、家族に迷惑をかけ通しの父。父のせいで人生を台無しにされたと嘆く母。そして、課長に昇進するも会社内部のいざこざに巻きこまれ、四十歳手前にして職を失ってしまった娘。極端に不幸ではないかもしれないが、平凡な幸せを手に入れられずにいる家族。かつて私の家族がそうであったように、このような家族は日本中にたくさんいることと思う。夫婦、親子というもっとも身近な者同士、いちばんわかっているからこそ、家族に問題があれば「どうにもならない」と、あきらめてしまっている人もいるだろう。それが凄惨な事件に発展してしまうことさえある。そんなニュースを目にするたびに、家族が心を通い合わせるきっかけが何かなかったのだろうか、と考えてしまう。
私の父は現在八十二歳だが、かつては大変なギャンブル好きで、そのためにいつも借金を重ねていた(最近は年のせいもあって、さすがに身を引いたようでほっとしている)。家族、特に母はさんざん苦労をさせられ通しだった。幸か不幸か、作家である兄が父のことを繰り返し小説に書き続けてきたこともあって、私が作家になってからは、誰にも隠しだてせずにこの父のことを話せる土台がすでにできていた。普通に聞けば、どうしようもない、やんちゃの度が過ぎた人である。けれど不思議なことに、兄も私も、この父の存在を創作の原動力にしてきた感がある。小説の中でイタい目に遭わせて苦労させられたカタキをとる、などという物騒なことはちっとも考えない。確かにどうしようもない、けれどどうしようもなく愛すべき存在として、この父の人となりを書き留めておきたい。そんな思いがあった。ギャンブル好きで借金体質というネガティブなキャラ以上に、父なりに輝いている素質もある。人情が厚く、大変な読書家。そして、五歳の頃から今日まで、膨大な数の映画を日々観続けていることだ。
私の父をそっくりに写し取った登場人物、円山郷直(まるやまさとなお)は、七十九歳でギャンブル依存症。まともなもので興味があるのは映画だけだ。郷直のひとり娘・歩(あゆみ)は、不当な理由で長年勤めた会社を退職せざるを得なくなり、いったんは絶望するものの、父が病気をしたり借金を重ねたりする不幸が重なって、むしろこうしてばかりはいられない、と立ち上がる。父を再生させるにはギャンブル以外の好きなことに熱中させるのがいい、と悟った歩は、映画で父の人生を変えようと思いつく。そして結局、歩は自分自身が、映画に、そして父に救われることになる。
マンションの管理人を務める父が入院しているあいだの留守を預かった歩は、父が膨大な映画評をノートに書き付けているのをみつける。それに刺激されて、自分も名画座の存続に関する雑感を書き付けておくのだが、父はこれを勝手に老舗映画雑誌「映友」のブログに投稿してしまう。それがきっかけで、歩は「映友」の編集部にライターとして起用され、やがて父も「キネマの神様」と題した映画ブログを展開することになる。知らず知らずのうちに、父と娘は助け合い、思い合いながら、映画の世界へどんどん踏み込んでいく。そしてとうとう、奇跡が起こる。
作中には、歩の家族以外にも、「映友」編集長・高峰と引きこもりの息子、歩の元後輩で父親と確執する清音(きよね)などが出てくる。そして父が通う名画座の支配人・寺林と、歩の同僚・新村が、それぞれに父や歩と映画を通じて友情を育んでいく。加えて、これは秘密にしておきたいのだが、もうひとり、「ローズ・バッド」と名乗る謎のブロガーが、奇跡を起こすきっかけを作る。さて、涙のエンディングはいかに?
などと書けばまさしく映画そのもののようだが、この小説を書きながら、実際に私はたくさんのことを学んだ。
私は普段、父ほどには映画を観ないのだが、この小説のために実に多くの映画を観た。そしてたくさんの映画評を読んだ。そのおかげで、物語の構成、プロットの作り方、泣かせる場面の盛りこみ方、オープニングとエンディングの盛り上げ方などなど、思いがけない副産物がもたらされたように思う。作中、いくつか映画評を書いたのだが、これが思いのほか楽しく、上手下手は別として、今後もこっそり映画評を書き続けようかと思ったくらいだ。
作中で、老いた父がネットと格闘する場面が出てくる。そして、ネットを通じて、誰にも相手にされなかった孤独な老人が真実の友に出会う、という、誰にでも起こりうる奇跡を描いた。ネットを使えれば、年配者だって、見しらぬ誰かと心を通い合わせることができるかもしれない。ネットの功罪はさまざまだろうが、その議論はよそに預けるとして、シニアの方々もネットを利用してもっと世界を広げてもらいたい、との願いもこめたつもりだ。
物語の終盤まぢかで、謎のブロガー、ローズ・バッドが「タイトルの前に出てくる名前(The Name above the Title)」について触れる箇所がある。かつてハリウッドの多くの映画人は、映画のオープニングで、スクリーンにタイトルより先に自分の名前が出てくるような大物になりたい、と憧れた。けれどいま、コンピュータスクリーンに現れる無数のブログの上で、映画について熱く語る名もなき人々こそが、映画を支えているのだ、と指摘する。この言葉を、本作のサブタイトルに据えた。
この小説を書き終わってから、父と映画館へ出かけた。父は頼みもしないのに、熱心に解説をしてくれた。小説に出てくるような奇跡は、もちろん私たち家族には訪れなかった。けれどこうして、父が元気でいてくれて、一緒に肩を並べて映画を観られることこそが、キネマの神様が与えてくれた奇跡なんじゃないか、と思う。
映画を愛する人も、そうでない人も、この小説を読んで映画が観たくなったとしたら嬉しい。そして家族であれ友人であれ、いちばん好きな人と映画館に出かけてくれたとしたら、もっと嬉しい。