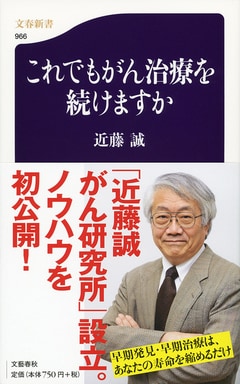「ばあば神」の語り手である母子家庭の母親の、息は浅い。読点がなく、スペースが無数に挿入される文章は、不安で浅くなる呼吸のままに東京での地震後の混乱を語る。電話を通じて登場する北九州の母が、語り手の子供である樹里にとっては「ばあば」だが、ここで「ばあば神」と呼ばれるのは、どうやら「ばあば」の母、つまり語り手のひいばあば、あるいはその母のひいひいばあばらしい。
ひいばあばもピンポイントの放射線治療を受けている。しかも一日2シーベルトを五日と聞けば、フクシマの人々も腰を抜かすだろう。先の大戦の空襲の最中に「ばあば」を産み、しかも曇っていた北九州を避けて長崎に原爆が落ちたことを、ひいばあばは「げんし ばくだんも おっぱらった」と思っている。強運のばあばが「だいじょ ぶよ」と呟き、かみほとけ、せんぞ、そしてみなみなさまがまもりなさる、と言うとき、ひいばあばは、ほとんど神と同化している。しかしここで作者は、どうもそのような安寧をもたらす神を書きたいのではないらしい。ほとんどゴジラのように、巨大化した白髪の老婆が大暴れし、ビルを壊し、電線を引きちぎる。その怒れる老婆こそ「ばあば神」なのである。
怒りが何に向けられているのか、どうしてそれが「ばあば」なのか、理解しきれたとは思えないが、だからこそ鮮烈である。
この「ばあば」を巨大化させ、大暴れさせるような人間内部の暗闇は、他の作品でも随所に感じられる。
「関門」では海峡の向こうの半島からの脅威に、異様なほど怯える男が描かれる。空には偵察機、海には巡視艇という環境も環境だが、タモちゃんという男の怯えようは神経症めいている。しかし作者の筆は、神経症で片付けるのではなく、むしろ怯えに同化していくように感じられる。ここでも我々は、光の背後の深い暗闇のようなものに向き合わされるのだ。
もしかすると、人はそのような不思議を求めているのだろうか。「海のサイレン」ではそうも思えてしまう。富山湾に春先、けっこうな頻度で現れる蜃気楼、魚津ではそれが現れるとサイレンが鳴るらしい。蜃気楼は単なる自然現象だし、瑞兆ともされるのに、筆者はサイレンの音に不吉なイメージを喚起され、蜃気楼の周辺に警戒警報、空襲、硝煙の臭いまで絡めていく。
ラストでは震災のあった三月十一日、その日にも蜃気楼を求めて海岸を歩く人々がいたことが描かれ、一見暢気そうにも思える。しかし人は、摂氏五度という寒さのなかで、いったい何を求めて彷徨うのか。そして日本列島を挟んだ背中合わせの東北で、そのとき期待を遥かに超えた自然の霊異が現れるのである。