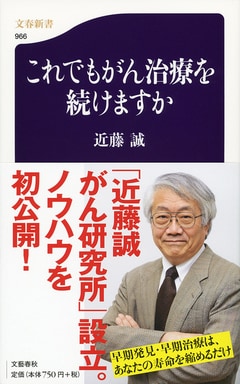私は以前、自分なりに「地霊」という隠しテーマをもって、『四雁川流景』(文春文庫)という短編集を上梓したことがある。それはある想像上の町の、古代から積み重なった大地の記憶を覗く程度の、ささやかな物語であった。
今回、村田喜代子さんの『光線』を読み、いつもながらその手際に感服すると同時に、スケールの大きさにも驚嘆した。
同じく「地霊」をテーマに据えながら、途中、東日本大震災が起こり、またご本人のガン治療もあって、「地霊はどこかに吹っ飛んでいる。いや、『地』はすでにずたずたになっている」と、「あとがき」に書かれるのだが、それでも、なのか、それゆえ、と言うべきか、とにかくそこには人間の体内から月や太陽まで、空の彼方から大地の底の暗闇まで、そうして果ては人間の精神の中の底知れぬ暗闇へと、不分明な意識は分裂するように広がり龍のように世界を覆っていく。密やかにしかも自在に蠢く地霊が、この地球のあちこちに跋扈しているように思えた。
震災から三年半が経ち、私の住む福島県では、ようやく「計画的避難区域の人々」というような括り方の無理を、感じる人々が多くなってきた。もとより人は、個別の歴史を踏まえ、個別の事情のなかで暮らしているのであり、行政にすればやむを得ないにしても、一般の人々までがたとえば放射線量などでそこに住む人々を区分けするなど、通常は考えられないことだ。最も大雑把で迷惑な括り方が「フクシマの人々」だが、そんな人はどこにもいないと、知らせることが今や文学の仕事かもしれない。一つの出来事が、千差万別の体験になることはどこでも変わらない、当たり前のことだ。
震災後まもない三月十三日、自らのガン治療のために遥か鹿児島まで出向き、活気を帯びた桜島の麓で放射線治療を受ける女性にとって、放射能とはいったい何だろう。東日本大震災とは何だろう。
「原子海岸」では、そうして四次元ピンポイント放射線の治療を受け、留年生の気分で過ごす人々が、同窓会のような旅行をする。
そこで交わされる彼らの会話を、私は多くの人々に読んでほしくなった。
「東日本では沢山亡くなったじゃないですか。元気な人たちが、一瞬に。病気もないのに……」
「ええ、ええ。ガンでもないのにね」
「だから私たちガンが消えても、あんまり大きな声でバンザイって叫べませんものね」
「ええ、そりゃあ叫べないですよねえ」
ああ、なんということか。これほどに、放射線治療を受けた人々に気を遣わせていたなんて、いったい誰が想像できただろう。どうか遠慮なくバンザイしてくださいよと、言いたくなってしまう。