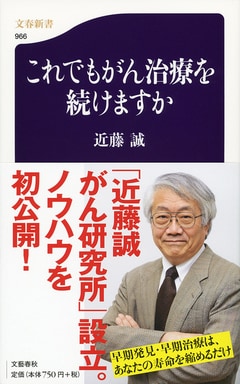それにしても「ばあば神」といい「爺捨て」といい、日常を逸脱した高齢者は神の領域に入るのではないか。それは大地に居ながら大地を超えた存在かもしれない。嫌々行くのであれ進んで行くのであれ、山に入った爺は地霊だけに従って自由に暮らし、自由に死んでいくのだろう。この国の山林はまだ国土の六割以上あるから、地霊への期待もしずかに膨らむ。
さて最後に置かれた「楽園」。私はさっき「安心して楽しめた」などと書いてしまったが、これはとんでもない誤解を生みかねない表現だった。
設定や構成の妙により、安心して読めてしまうのは間違いないが、私にはこれほど恐ろしい物語はなかった。
地上が「楽園」なのだと言えるその人は、地下八百メートルにある地底湖をさらに洞窟潜水で進んでいく。洞窟潜水の恐ろしさは、浮上してきてもそこに水面はなく、岩に覆われているということだ。
それは暗闇体験であるばかりでなく、底知れぬ未知の世界の体験である。実際私は、読みながらジェットコースターで下りていくときのような、下腹の疼きを感じた。学生たちのディスカッションの形で話は進むからすんなり読めるものの、地底を彷徨った恐怖の七時間をまともに書かれたら堪らない。本人もその後睡眠剤と抗うつ剤の常用者になり、心臓発作を起こして床についたまま、一時は廃人同様であったらしい。
自ら「探検家」と称する瀧山氏の言葉が興味深い。まだ誰も入っていない洞窟の探検には、精神的にきわめて危険なエクスタシーがあるというのだ。第七超新洞を発見した瀧山氏だが、自分が発見するまでその洞窟は存在しなかったわけだから、発見という「存在の確認」は造物主に近づく体験だというのだ。
造物主としての神、それは「ばあば神」や山の神などとは根本的に違う。しかし私の中では、不思議な霊異とそれを待ち望む心がここにおいて合流する。
「光線」も蜃気楼も「ばあば神」も、あるいは大地の絶頂での出逢いさえも、そこには霊異を待ち望む自己が潜んでいなかったか。そんなに巨きなものまでは……、などと言い訳してもそれは通じない。
瀧山氏の次の言葉が象徴的である。
「闇は人間の精神の中にあり、洞窟の闇は簡単に光を持ち込める軽い種類の闇と感じます」
洞窟の中でライトが消え、二度と点かないとしても、洞窟の闇は軽いと瀧山氏は言う。正直なところ、その感性は私には理解できない。しかしもしかしたら、それより遥かに重いという精神の闇こそが、地霊の霊異霊験を待ち望んでいるのだろうか。
「ばあば神」、いや、造物主の造り賜いし如き、見事で恐ろしい村田喜代子作品群である。